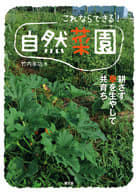
本日、 。
。
今週は雪が多いです。今年は溶けると、降り積もるの繰り返しですね。
雪の多い年は、豊作と言われたり、雪と農業は関係があります。
今年も公開講座を来月2日間で行います。今年の7回目です。
公開講座「無農薬・自然菜園のコツを学ぶ」 ~ 土づくり&菜園プランの立て方 ~
今度、3 月 3 日(日)、3 月 10 日(日)※両日同じ内容で、
時間:13:30~16:00(開場 13:00~)
会場:三郷農村環境改善センター2F(長野県安曇野市三郷温 2267-2)
会場費:500 円
参加方法:予約不要(当日、直接お越しください)
今まで多くの先生たちに自然農・自然農法をおしみなく教えていただき今の私があります。
そのため、年に一度は、公開講座という形で還元できればと思います。
野良仕事が始めると菜園を持っている方は忙しくてなかなか参加できないのでまだ本格化しない3月に行っております。
当時の私は、自然農法といいながら、自然が見えず、野菜の声も聴こえず、ただ自然農法だといって好き勝手やっていました。
そのため、自然農法をやり始めた当初は、失敗の連続。
なぜうまくいかないのかさえわかりませんでした。
そこで、全国の自然農、自然農法、有機農業、循環農業の実践者の農地を見学させていただいたり、研修まがいのお手伝いをさせていただき実地を通して多くを学ばせていただきました。
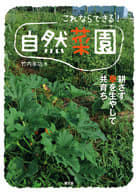
十数年経ってもまだまだわからないことだらけですが、おぼろげながら一つの道筋が立ってきたところ、
執筆のご依頼があり、意気揚々と引き受けたものの、一向に筆が進まず3年半、ベテラン編集者の力を借り何とか1冊まとめたのが
『これならできる!自然菜園』(農文協)でした。
この1冊は、多くの師匠たちの教えと叡智をまとめたものになっています。
始めた当初の自分のような自然農・自然農法を始める方、始めている方を想定し、Azumino自給農スクール、あずみの自然農塾など、菜園教室で質問される具体的な内容を中心にしています。
今回、1冊の本にまとめる機会が得れたお蔭で、頭の中がとても整理されました。
今回の公開講座では、菜園を始める際にもっとも気になる土づくりと菜園プランに関して、はじめて1本の講座にまとめました。
まとめてみて、気づいたのですが、自然菜園では、土づくりも菜園プランも違う内容ではなく、「野菜が自然に育つ」という同じテーマの内容で、切っても切り離せない密接な内容でした。
土づくりといえば、土に何かを投入して、野菜が育つ土を作ること。
菜園プランといえば、菜園が連作障害がでないように、ローテーションなどを野菜の配置を考えること。
と一見すれば違う手段でしたが、どうもこれは従来の化学肥料を使った栽培の話でした。
化学肥料や農薬の代替として、有機肥料、自然農薬を使えば無農薬栽培ができるかというと、そうでもないということがわかってきました。
最近では、自然菜園と化学肥料や農薬を使った栽培では、コンセプトが違うだけでなく、野菜が育つ仕組みそのものが違うような気がします。
化学肥料や農薬を使った栽培では、野菜は作りもの。管理するもの。
一方、自然菜園では、野菜が自然に育つような環境を整えていくこと。自然に沿うこと。
ずいぶんと違う感じがします。
その違いを認識することが、大切だと思います。
不自然な土づくりや菜園プランもありますし、自然に叶っていく土づくりと菜園プランもあります。
自然に育てることは、自然に放置することではなく、自然に沿って野菜を育てることです。
その手助けになる講座になればいいなーと思っております。
今年は、この公開講座もそうですが、1年間自然菜園的な菜園教室について言及し、行っていこうと思います。
自然菜園という切り口で、私自身勉強していこうと思います。
これからもよろしくお願いたします。
**************************
2013年度の自然菜園講座の一つ「あずみの自然農塾2013(第7期)」の募集が始まりました!(12/25~2月末)

2012年12月の講座での集合写真
「あずみの自然農塾2013(第7期)」の募集が始まりました!(12/25~2月末)
先着24名。耕さず、草と虫を敵としない川口由一さんのはじめた自然農に特化したシャロムヒュッテに1泊2日しながら、全10回の体験型ワークショップです。
耕さない田んぼに、畑で実際に、自然の理を学び、実践できます。
しかも、自分の小さな菜園区画が付いているので、3~12月の間自然農で野菜を育てることができます。
半農半Xの暮らし、自然農にご興味がある方にお奨めの講座です。
只今準備中ですが、
自然農法で自給自足の農園が学べる「Azumino自給農スクール2013」
穂高養生園で、日帰りも食事、宿泊もできる自然菜園入門講座も間もなく募集がはじまります。
お好みでお選びください。
【お迷いの方へ】
・耕さない自然農を学びたいなら→「あずみの自然農塾2013(第7期)」
・無農薬栽培の基本から応用を学び、我が家の自給率をアップしたいなら→「Azumino自給農スクール2013」
【拙著のご紹介】
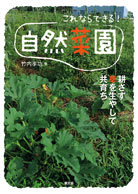
『これならできる!自然菜園』

『コンパニオンプランツで失敗しらずのコンテナ菜園』
好評発売中~

自然農・自然農法で家庭菜園をはじめたい、無農薬栽培の基本を教えてほしい方に、
2回に分けて、基本的な考え方と実際に行う方法を学べます。
前半は講座、後半は日頃疑問な点などを質疑応答を行います。
次回は、第2回菜園プランの立て方です。詳しくは↓
この春から畑を始める方、自然農法、無農薬栽培に興味のある方、
おもしろい野菜の話を聞きたい方などなど、お気軽にお越し下さい。
 『これならできる!自然菜園』(農文協)の著者が教える!!!
『これならできる!自然菜園』(農文協)の著者が教える!!!
『これからはじめる!自然菜園入門』
日程 ①2月 8日 (金)土づくり編
②月22日(金)菜園プラン編
会場 蕎麦とりい(穂高神社)
時間 15:30~17:00講座(15:00開場)
17:00~17:30質問応答
講師 竹内孝功(自給自足Life代表)
参加費 各1,500円(玄米いなり、お茶付き)+500円(テキスト代)
持ち物 筆記用具 、
お持ちであれば『これならできる!自然菜園』
■予約、問い合わせ 蕎麦とりい 0263-82-3039
(安曇野市穂高の穂高神社の北の鳥居のすぐそば、お船会館内です。)
 。
。今週は雪が多いです。今年は溶けると、降り積もるの繰り返しですね。
雪の多い年は、豊作と言われたり、雪と農業は関係があります。
今年も公開講座を来月2日間で行います。今年の7回目です。
公開講座「無農薬・自然菜園のコツを学ぶ」 ~ 土づくり&菜園プランの立て方 ~
今度、3 月 3 日(日)、3 月 10 日(日)※両日同じ内容で、
時間:13:30~16:00(開場 13:00~)
会場:三郷農村環境改善センター2F(長野県安曇野市三郷温 2267-2)
会場費:500 円
参加方法:予約不要(当日、直接お越しください)
今まで多くの先生たちに自然農・自然農法をおしみなく教えていただき今の私があります。
そのため、年に一度は、公開講座という形で還元できればと思います。
野良仕事が始めると菜園を持っている方は忙しくてなかなか参加できないのでまだ本格化しない3月に行っております。
当時の私は、自然農法といいながら、自然が見えず、野菜の声も聴こえず、ただ自然農法だといって好き勝手やっていました。
そのため、自然農法をやり始めた当初は、失敗の連続。
なぜうまくいかないのかさえわかりませんでした。
そこで、全国の自然農、自然農法、有機農業、循環農業の実践者の農地を見学させていただいたり、研修まがいのお手伝いをさせていただき実地を通して多くを学ばせていただきました。
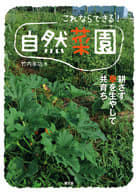
十数年経ってもまだまだわからないことだらけですが、おぼろげながら一つの道筋が立ってきたところ、
執筆のご依頼があり、意気揚々と引き受けたものの、一向に筆が進まず3年半、ベテラン編集者の力を借り何とか1冊まとめたのが
『これならできる!自然菜園』(農文協)でした。
この1冊は、多くの師匠たちの教えと叡智をまとめたものになっています。
始めた当初の自分のような自然農・自然農法を始める方、始めている方を想定し、Azumino自給農スクール、あずみの自然農塾など、菜園教室で質問される具体的な内容を中心にしています。
今回、1冊の本にまとめる機会が得れたお蔭で、頭の中がとても整理されました。
今回の公開講座では、菜園を始める際にもっとも気になる土づくりと菜園プランに関して、はじめて1本の講座にまとめました。
まとめてみて、気づいたのですが、自然菜園では、土づくりも菜園プランも違う内容ではなく、「野菜が自然に育つ」という同じテーマの内容で、切っても切り離せない密接な内容でした。
土づくりといえば、土に何かを投入して、野菜が育つ土を作ること。
菜園プランといえば、菜園が連作障害がでないように、ローテーションなどを野菜の配置を考えること。
と一見すれば違う手段でしたが、どうもこれは従来の化学肥料を使った栽培の話でした。
化学肥料や農薬の代替として、有機肥料、自然農薬を使えば無農薬栽培ができるかというと、そうでもないということがわかってきました。
最近では、自然菜園と化学肥料や農薬を使った栽培では、コンセプトが違うだけでなく、野菜が育つ仕組みそのものが違うような気がします。
化学肥料や農薬を使った栽培では、野菜は作りもの。管理するもの。
一方、自然菜園では、野菜が自然に育つような環境を整えていくこと。自然に沿うこと。
ずいぶんと違う感じがします。
その違いを認識することが、大切だと思います。
不自然な土づくりや菜園プランもありますし、自然に叶っていく土づくりと菜園プランもあります。
自然に育てることは、自然に放置することではなく、自然に沿って野菜を育てることです。
その手助けになる講座になればいいなーと思っております。
今年は、この公開講座もそうですが、1年間自然菜園的な菜園教室について言及し、行っていこうと思います。
自然菜園という切り口で、私自身勉強していこうと思います。
これからもよろしくお願いたします。

**************************
2013年度の自然菜園講座の一つ「あずみの自然農塾2013(第7期)」の募集が始まりました!(12/25~2月末)

2012年12月の講座での集合写真
「あずみの自然農塾2013(第7期)」の募集が始まりました!(12/25~2月末)
先着24名。耕さず、草と虫を敵としない川口由一さんのはじめた自然農に特化したシャロムヒュッテに1泊2日しながら、全10回の体験型ワークショップです。
耕さない田んぼに、畑で実際に、自然の理を学び、実践できます。
しかも、自分の小さな菜園区画が付いているので、3~12月の間自然農で野菜を育てることができます。
半農半Xの暮らし、自然農にご興味がある方にお奨めの講座です。
只今準備中ですが、
自然農法で自給自足の農園が学べる「Azumino自給農スクール2013」
穂高養生園で、日帰りも食事、宿泊もできる自然菜園入門講座も間もなく募集がはじまります。
お好みでお選びください。
【お迷いの方へ】
・耕さない自然農を学びたいなら→「あずみの自然農塾2013(第7期)」
・無農薬栽培の基本から応用を学び、我が家の自給率をアップしたいなら→「Azumino自給農スクール2013」
【拙著のご紹介】
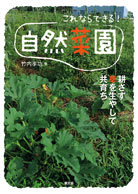
『これならできる!自然菜園』

『コンパニオンプランツで失敗しらずのコンテナ菜園』
好評発売中~

自然農・自然農法で家庭菜園をはじめたい、無農薬栽培の基本を教えてほしい方に、
2回に分けて、基本的な考え方と実際に行う方法を学べます。
前半は講座、後半は日頃疑問な点などを質疑応答を行います。
次回は、第2回菜園プランの立て方です。詳しくは↓
この春から畑を始める方、自然農法、無農薬栽培に興味のある方、
おもしろい野菜の話を聞きたい方などなど、お気軽にお越し下さい。
 『これならできる!自然菜園』(農文協)の著者が教える!!!
『これならできる!自然菜園』(農文協)の著者が教える!!!『これからはじめる!自然菜園入門』
日程 ①2月 8日 (金)土づくり編
②月22日(金)菜園プラン編
会場 蕎麦とりい(穂高神社)
時間 15:30~17:00講座(15:00開場)
17:00~17:30質問応答
講師 竹内孝功(自給自足Life代表)
参加費 各1,500円(玄米いなり、お茶付き)+500円(テキスト代)
持ち物 筆記用具 、
お持ちであれば『これならできる!自然菜園』
■予約、問い合わせ 蕎麦とりい 0263-82-3039
(安曇野市穂高の穂高神社の北の鳥居のすぐそば、お船会館内です。)































そうですね。
まず、緑肥作物ミックスでヒントになったのが、福岡正信さんの粘土団子です。無為自然にするために、これがいいからという人間の理屈だけでなく、自然に選んでもらい一番その場に合ったものが優先するという点からも4種類以上の緑肥作物を混ぜて、通路などに播いております。
ご質問のエンバクとライムギは、夏の草としてエンバク、冬の草としてライムギで蒔く時期や播く畑の環境によってブレンドの割合が変えております。
どちらも品種によって期待できる効果や機能性があるので、畑や時期に合ったものを選ぶようにはしております。
ただし、原点でお話ししたように、均一な整備された畑以外では、生えてくる草が多様なように、個々の緑肥作物の機能に特化するのではなく、なるべく多様なタネが相性良くその場その場にあって生えてこれることを一番大切にしております。
ライ麦とエンバクはどのように使わけされ、どのような考え方で播かれていますか。
ライ麦の方が背が高く根が深い=有機物資材を多く確保でき、土を耕す と思ったのですが、野菜が陰になるほど背を高くすることはないので、背の高さよりも生長速度の方が問題になるか?とか、寒さに強いライ麦は暑さに若干弱めなら、播種時期によってはエンバクを使うべき?とか、エンバクは機能性(○○病や○○線虫に効果がある)が優れているものが多い、等考えています。
実際に播いてみようと思いますが、竹内さんのお考えを教えていただいて指針にしたいと思います。
よろしくお願いします。
お野菜にも、旬が3つあります。「走り→盛り→名残り」です。カツオでいえば、初鰹→鰹→戻り鰹です。
本当に美味しい野菜は、ただ甘いだけでなく風味がよく、火が通りやすく調理時間も少なく美味しいです。
促成栽培が主な市販ではなかなかお目にかかれないものです。
自給菜園の醍醐味を見つけて味わってください。
そんなに美味しい野菜が食べれるのならやってみます。
また 分からない事がありましたら質問させてください。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。鵜のみではなく、比較実験することがとても大切だと日々の菜園教室でも言っているので、以下の点を考慮してみてください。
・マメ科同士は品種によっては根粒菌が喧嘩するのでダメかも。→こちらでは喧嘩はなく、お互いに異なる根粒菌の御蔭でうまく言っております。
・白クローバーは畑ではなく畦で使う。→正解です。白クローバーは菜園内で使うと野菜と喧嘩してしまいます。
私が緑肥作物を混播するのは、多年草緑肥作物を単一で使うよりも効果的だからです。もう一つは、畑の中で一番合う緑肥作物を無為自然に選びたかったからです。つまり多様性における自然選択です。
そこで、
多年草のアカクローバーのみを播いたところと、一年草のエンバク、クリムソンクローバーと混ぜて播いたところで、翌年のアカクローバーの生育を比較刷るとわかりやすいと思います。
「これならできる~」に記載されていた緑肥の混播ですが、ライムギ、エンバク、イタリアン、オーチャード、赤、白、クリムソンクローバーを買ってみました。
混播の効果を調べようと思い、単播と混播、マメ科とイネ科の混播等を検討していましたが、組み合わせで注意すべき点などあるのでしょうか。
・マメ科同士は品種によっては根粒菌が喧嘩するのでダメかも。
・白クローバーは畑ではなく畦で使う。
くらいしか思いつかず、あとは実験次第と考えていますが、組み合わせは相当数になります。
土が違えば緑肥の育ち方も違うと思いますが、比較実験の参考になる指針を教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
旬限定+αでいいと私は思っております。
旬も走り、盛り、名残りと3回風味が異なり食べきれないほどです。
本当に美味しい野菜に出会うと、その他の時期に食べたいと思わなくなるから不思議です。
うちでは、1~4月はほぼ野菜は採れませんが、保存方法やプランターを使って他の時期でも食べるには困りません。
すべて自然菜園にする必要はありません。今までの栽培方法プラスで、一部不耕起にしてみてください。
不耕起もベストではなく、ベターだと思っております。いろいろお試しください。
ご想像のように春が遅く、秋は早い風土でありますので、2毛作の段取りには悩まされます。
那須の露地栽培では、枝豆の播種適期は5月下旬からで、何回かに分けようとすると収穫時期が伸びて、秋物の播種に影響してしまいます。
不耕起ならば育苗し植付すれば多少の調整はできるかとも思いますが、旬の時期限定となりそうです。
何か良い知恵がございましたらご教授お願いします。
那須山麓の標高700mですか。私も安曇野の750mですから似たような風土かもしれませんね。
栽培を早めたいのであれば、ポリマルチはとても有効だと思いますが、有機物マルチと異なり、消費一方の栽培になるので、自然耕は難しいかと思われます。
私でしたら、菜園の半分は、今まで通りでポリマルチで早く採れる栽培をし、半分は草マルチで育てるゆっくり型の露地栽培にします。
そうすることで、長期間収穫できるのでいいところどりができると思います。いかがでしょうか。
僅かばかりの家庭菜園ではありますが、加齢と共に人力で耕す事がきつくなって、不耕起は大変魅力的です。
草の根で耕す、有機物マルチの効果等は経験上認める所ですが、菜園は那須山麓の標高700mにあり、保温材としてポリマルチやビニールトンネルは必需品としてました。(土ステージは3あると思います)
ポリフィルムを使い、有機・無農薬で満足の栽培でしたので、なかなか踏み出せずにいます。よろしくご教授お願いします。
沖縄でもやっている方が多いのですね。
沖縄の播き時を守れば、もっと収穫できるかもしれませんね。
まずは、今あるソバを収穫し、種にもしてみてくださいね。
そうなんです。沖縄本島南部の、海まで数十メートルの場所に、トランジションタウン活動の仲間と自然農の小さな畑をつくって蕎麦と小麦をまきました。
蕎麦は沖縄の友人からもらったもので、宮古島で育てられているもののようです。沖縄本島でも北部(大宜味村)では栽培されていたりするのですが、蒔くべき時期などもよくわからないままに、とりあえず蒔いてみよう!と蒔いちゃった次第です^^;
風が強い場所なせいか、蕎麦は高さ20センチくらいにしかならず、でも強風に耐えて可愛い花をたくさんつけてくれました。
アドバイスいただいたとおり、「一番実がついていそうな時期」を見計らって、刈り取りと乾燥、チャレンジしてみます。ありがとうございましたー!
アバサー汁食べにいらっしゃる際にはぜひご連絡くださいね♪
今ソバ?とブログを拝見して納得しました。
島でしたか。それは今になりますね。
私も沖縄が好きで、数回おじゃまさせていただいており、
いつか嫁さんにアバサー汁をご馳走したいと思っております。
「もうつぼみがないかどうかを確認し、黒い実を割って粉っぽいかどうか見てみる」で概ねOKですが。
島ですと、長日のため、短日植物の蕎麦の花の開花がなかなか終わらず、最後の花を待っていては、落ちる実の方が多くなってしまうかもしれません。
花が咲き終わっていいないものは、刈り取って島立てしても実には至りませんので、落ちるものとまだ実にならない部分を計りながら、一番実がついていそうな時期を狙って、島立てしてゆっくり乾燥させることで、実を充実させてから脱穀してみてください。
島の場合、台風など風が強くなると身が落ちやすくなるので、風が強くなって落ちてしまう前に刈り取るのも重要です。
また、これは提案ですが、昔から島で栽培している蕎麦の品種があれば一番いいのですが、倭(本島)でいう「春ソバ」がむいているかもしれません。ソバは日が短くなっていく際に花を咲かせて実をつける植物なので、倭では春の日が長くなる時期は、春播きの春ソバでないと実をつけません。風味は、秋そばには劣りますが、年中春のような沖縄では、春ソバがむいているかもしれないからです。
FBのコミュではありがとうございます。ブログ、とてもわかりやすくて勉強になります。お言葉に甘え、蕎麦の収穫のタイミングと方法について質問させてください^^
いま、花と実が両方ついていて、葉は綺麗な緑、
こちらの写真よりは花がまだかなり多い状態です。
http://blog.goo.ne.jp/taotao39/e/02f85b6df20374dd444bde6b39d76d58
文中には「一番最後の花が咲き終わり、最初に実った実が粉質が出てきたら収穫する目安です」とあるのは、「もうつぼみがないかどうかを確認し、黒い実を割って粉っぽいかどうか見てみる、という理解で合っていますか?
すでに実の一部が落ち始めていることもあり、タイミング的に刈り取りをした方が良いのか、落ちた分だけを拾いつつ少し待った方がよいのか、教えていただけたらありがたいです。
よろしくお願いします。
営業ウーマン、助かります。ありがとうございます。
橋本・西村両先生のあの講座私も受けました。
いろいろな堆肥の造り方ありますが、橋本式が一番高品質にでき、お気に入りです。
セスバニアは、専用の菌をつけること、5~6月に播くことがとても大切で特殊な緑肥作物なので、難しいと思います。
私もいろいろな先生に教わってきたので、いろいろやってみてください。
教わったやり方をミックスする場合のコツは、比較試験しながら、何が悪かったのかわかるように栽培することです。
本もたまに持ち歩いては、興味のありそうな友人に勧めています。営業マンさせて頂いています(笑)
先日、愛農会での橋本先生の堆肥の講座に参加してきて、有機質肥料の概念の疑問が少し解けた様な気がしました。堆肥を作る段階からの、マメな温度管理と観察眼が丈夫な作物を作る厳しさも感じました。
昨年、畝間にセスバニアをまいたのですが、時期はずれといい加減さで、5cm位にしか成長しませんでした(ToT)
今年は実質一年目の畑となりますので、私も竹内さん始めいろんな先生方に教わった事を実践していきたいと思います。
そうですね。私も草が育つといつ刈って敷くのが、いいのか欲をかいてしまうことがあります。
菜園教室では、敷く草が欲しいとみんなで刈り合う場面も見られるほど、草の認識が変わる方が多く見られます。
お気軽に、これからもどしどしご質問ください。
なるほどー。よく分かりました。
育てる野菜の量と相談で決めたいと思います。
昨日も草刈をしていたのですが、カラスノエンドウのような
草の根に根粒菌がついているのを発見して感動したり、
牧草の根の量の多さに驚いたりしてました。
この本を読んでからというもの、草を刈る時にもったいない
とさえ思うようになりました。
野菜を育てることも楽しいですが、何より草や土、虫などの
自然の循環を感じられる作業がとても楽しく生きがいになっています。
質問にもお答えいただきありがとうございました。
またくだらない質問をすると思いますがよろしくお願いします。
緑肥作物も最初は弱いので、大切に育てて、30cmを超すようになったら、下10cm以上残して刈り、刈った緑肥作物で野菜を草マルチしながら育てていきます。
今度出る雑誌『現代農業』(農文協で)で自然菜園の畝が紹介されると思います。
畝を活かすか、通路を広くするかは、草刈りの便だけでなく、菜園プランや菜園の規模にもよりますのでお好みで。
通路を広めの80cmにした場合、私は緑肥作物ミックスを2条に播きます。もちろん、1条でもいいのですが、その場合播き幅を18cmよりも広く25cmくらい広くする方法でもいいです。
通路を広くした分、緑肥作物の播く面積を多少広げて、草刈りを楽にし、草マルチの材料を多めに育てることができます。
早速の返信ありがとうございます。
やはりまたぐのですね。
もしかしたら自分が本を読み違えているのかと
不安になったものですから質問させていただきました。
実際、畝をひとつ潰せば50センチから80センチにできるのですが、
そうすると草刈が大変でしょうか。
ありがとうございます。
ハコベが生えている畑であれば、余程肥えていて野菜が育ちやすい環境になっている目安です。本でいえばステージ3の野菜が育つ目安です。ハコベの育つ大きさによって差はありますが、良い畑になっている証拠です。
肥料を入れ、耕すかどうかは好みです。
入れればいれただけ大きくなりますが、偏った肥料分は病虫害を招き、野菜の風味を損ね保存性を低下させるので私の場合、無肥料で育て、野菜の状態をみながら追肥のような形で補っていきます。
一番大切なことは耕す場合、草は根を残して刈り耕す両脇に避けてから、耕したい場所のみに留めて、土と枯れ草、ハコベなどすき込まないことです。
肥料があってもなくても、土と枯れ草、生きた草を混ぜてしまうと、すぐに種まき、植え付けはできません。
通信菜園教室については他の方からも要望があります。以前不手際でメルマガが休刊した経緯から、皆様に迷惑にならない内容でまた4月位からはじめられればと思っております。パソコンスキルがないものですから、技術的にどのようにやったらいいのかわからないといった感じで、後手後手になっていて申し訳ございません。
ステージ2でしたか。今まで畑として働いていた菜園だったのでしょうか。ステージ2のミニトマトやダイコンなどがスムーズに育って安いと思いますが、
ステージ3の野菜によっては、1~3年くらいクラツキなどした方が育ちやすいものもあるかと思います。
通路は、50cmであれば中央に上幅18cm程度に緑肥作物のブレンドを播きます。そうすると、両脇に15㎝合わせて30cmの歩くスペースができます。
つまり、中央に1条生えてくる緑肥ミックスをまたぐ様に歩きます。またいで歩くことで、踏まずに歩くことができます。
いかがでしょうか。
春の準備を始めていますが、畝の上においていた枯れ草をとったら、下にハコベなどの草が生えていました。枯れ草と共に取ってから浅く起こして肥料を入れた方がよいのでしょうか?それとも枯れ草はそのままにして種をまくところだけ枯れ草を取り除いたらよいのでしょうか?
教室に参加したくても距離的なこと・時間のことままなりません。
週末菜園ですので毎週写真を取っていますが、
通信を利用したお教室の開催予定はありますか?
本購入しました。どの内容もすんなりと納得できて
実践できそうです。
早速、レベル2と思われる土地の畝たてから
始めているのですが、
畝間の幅について疑問に思ったので質問させてください。
本にあるとおり、畝間に緑肥を撒きたいと思います。
通常より広めに通路幅を50センチとり、
鍬の幅で軽く起こして種を撒くとありますが
畝を立ててみた所、大きくなるまで踏まないようにすると、
手入れなどの作業の際に歩けるスペースはほとんど無いように感じました。
実際はどのようにされているかを教えていただければ
嬉しいです。
どういたしまして。
私も本にまとめる機会を得て、頭の中がすっきりしました。
まだまだ駆け出しなので、今読みかすともう少しシンプルな入門書が欲しい感じがしております。
このブログのコメント欄には菜園のご質問大歓迎です。
質問は勉強になります。これからもよろしくお願いいたします。
私は竹さんのご著書を常に手元においている毎日です。
読めば読むほど、今の自分には今さらながら気づかされること多々あります。 今年のテーマとして根性のある「根」に注目しつつ昨年の教訓を生かしながらもっともっと自然の声に耳を傾けていきたいと思います。
いろいろ質問などさせていただくこともあるかと思いますがよろしくご教授願います。