今日は着物関係のイベントで 琵琶のレクチャーコンサートが某所にて開かれた。

着物の先生の源氏物語の中で琵琶の出てくる場面のレクチャー。明石の場面や 宇治十帖の中など 琵琶が奏せられる場面というのは多い。実際にその頃にどんな旋律が奏でられていたのか実際に聞くことができるというなかなか興味深いレクチャーコンサート(こういうことがなければ自らはチケット買ってまで行かないような気もいたしますが・・・)だからいい機会と思い着物を着てでかけた。
奏者は須O誠舟先生 Oは田です。元々薩摩琵琶がご専門で大河ドラマや歌舞伎の世界でも活躍され、琵琶の普及につとめていらっしゃる方
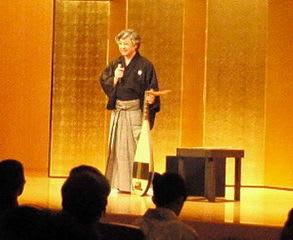
薩摩琵琶では 城山っていう西郷隆盛の最後を歌った勝海舟が作った曲を演奏された。薩摩琵琶は大きさは楽琵琶や平家琵琶より小さいがバチは大きく鋭い音も出る。朗々とした語りの伴奏と 中に入る手事が聞き応えあった。
上の写真で先生が持っているのは 楽琵琶 これが源氏物語などに登場する古来の琵琶らしい。音は薩摩琵琶より柔らかい気がした。
これで 「ばんかそう」 という曲を演奏された。正倉院で保存されていた古文書の中から見つかった楽譜を元に復元した曲だそうだ。
はっきり言って のんびりゆったりはしているが これがメロディ?って感じの音楽。こういう曲が紫式部の時代には実際に演奏されていたのでしょうね。優雅ではあったがしっかり眠りに誘われてしまった。
その後 平家物語の有名な導入部 祇園精舎の鐘の声・・の一説を弾き語りされたが 祇園精舎っていう単語一つ語るのに ぎ~~~お~~~ん~~~しょ~~~お~~~じゃ~~~お~~~~~ って感じで たっぷり一分はかかりましたね。一段語るのにいったい何時間かかるのだろうか? 昔の人は気が長かったのねと変な感心をしてしまった。
だいぶ時代は下がるけど 蕪村(だったよね?)の 「行く春や 重たき琵琶の抱き心」っていう句が好きだ。 春の終わりのまったりしたけだるい雰囲気がよく表されてると昔から思っていた。
今日 実際の楽琵琶の大きさと(思ったより大きい)眠気を誘われる音と旋律を聴いて、この句に改めて納得できた。
今日は若葉色の色無地にグレイ地にローズピンクの利いた帯を合わせ 帯揚げと帯締めもローズにしてみた。この色無地は初めて着た着物だけど色無地って無地のワンピース感覚で着られるのねって今更だけど新発見してしまった。

実は仕立てておいて3年くらい寝かしておいた着物だけど着てみたら案外着やすく、帯の合わせ方如何で色々に着られそうである。晩春の一枚になったわねとちょっと嬉しい。

着物の先生の源氏物語の中で琵琶の出てくる場面のレクチャー。明石の場面や 宇治十帖の中など 琵琶が奏せられる場面というのは多い。実際にその頃にどんな旋律が奏でられていたのか実際に聞くことができるというなかなか興味深いレクチャーコンサート(こういうことがなければ自らはチケット買ってまで行かないような気もいたしますが・・・)だからいい機会と思い着物を着てでかけた。
奏者は須O誠舟先生 Oは田です。元々薩摩琵琶がご専門で大河ドラマや歌舞伎の世界でも活躍され、琵琶の普及につとめていらっしゃる方
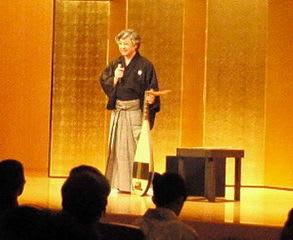
薩摩琵琶では 城山っていう西郷隆盛の最後を歌った勝海舟が作った曲を演奏された。薩摩琵琶は大きさは楽琵琶や平家琵琶より小さいがバチは大きく鋭い音も出る。朗々とした語りの伴奏と 中に入る手事が聞き応えあった。
上の写真で先生が持っているのは 楽琵琶 これが源氏物語などに登場する古来の琵琶らしい。音は薩摩琵琶より柔らかい気がした。
これで 「ばんかそう」 という曲を演奏された。正倉院で保存されていた古文書の中から見つかった楽譜を元に復元した曲だそうだ。
はっきり言って のんびりゆったりはしているが これがメロディ?って感じの音楽。こういう曲が紫式部の時代には実際に演奏されていたのでしょうね。優雅ではあったがしっかり眠りに誘われてしまった。
その後 平家物語の有名な導入部 祇園精舎の鐘の声・・の一説を弾き語りされたが 祇園精舎っていう単語一つ語るのに ぎ~~~お~~~ん~~~しょ~~~お~~~じゃ~~~お~~~~~ って感じで たっぷり一分はかかりましたね。一段語るのにいったい何時間かかるのだろうか? 昔の人は気が長かったのねと変な感心をしてしまった。
だいぶ時代は下がるけど 蕪村(だったよね?)の 「行く春や 重たき琵琶の抱き心」っていう句が好きだ。 春の終わりのまったりしたけだるい雰囲気がよく表されてると昔から思っていた。
今日 実際の楽琵琶の大きさと(思ったより大きい)眠気を誘われる音と旋律を聴いて、この句に改めて納得できた。
今日は若葉色の色無地にグレイ地にローズピンクの利いた帯を合わせ 帯揚げと帯締めもローズにしてみた。この色無地は初めて着た着物だけど色無地って無地のワンピース感覚で着られるのねって今更だけど新発見してしまった。

実は仕立てておいて3年くらい寝かしておいた着物だけど着てみたら案外着やすく、帯の合わせ方如何で色々に着られそうである。晩春の一枚になったわねとちょっと嬉しい。















