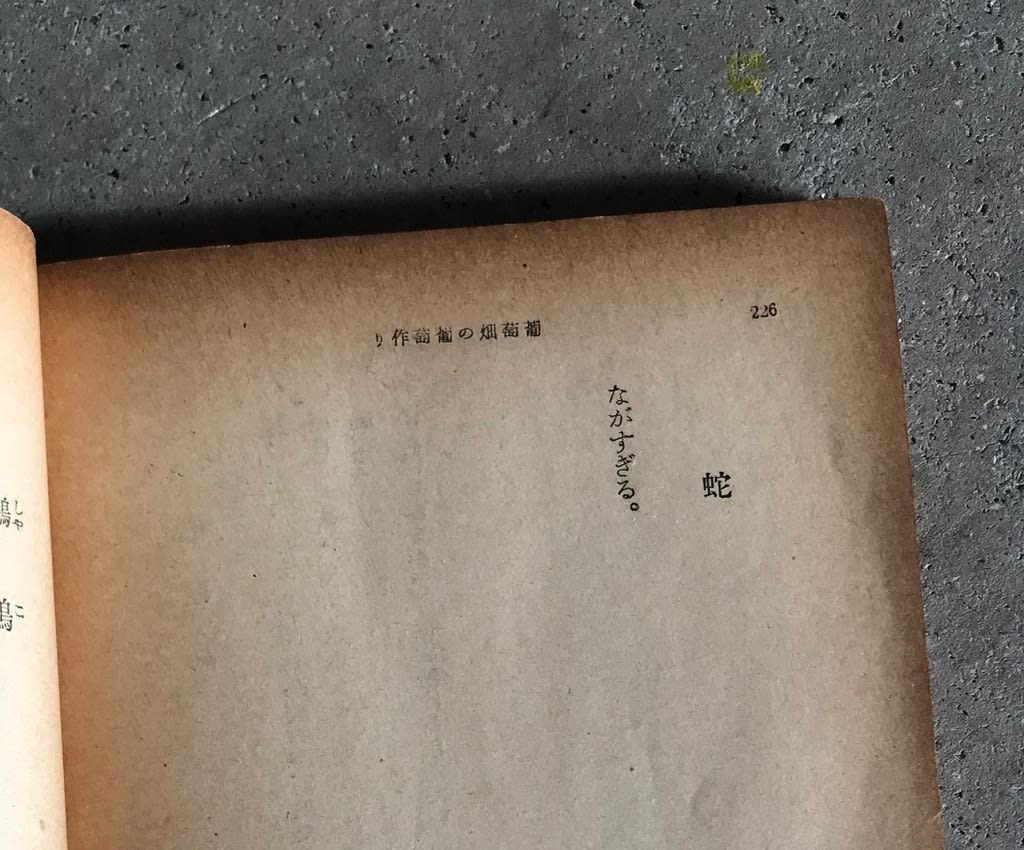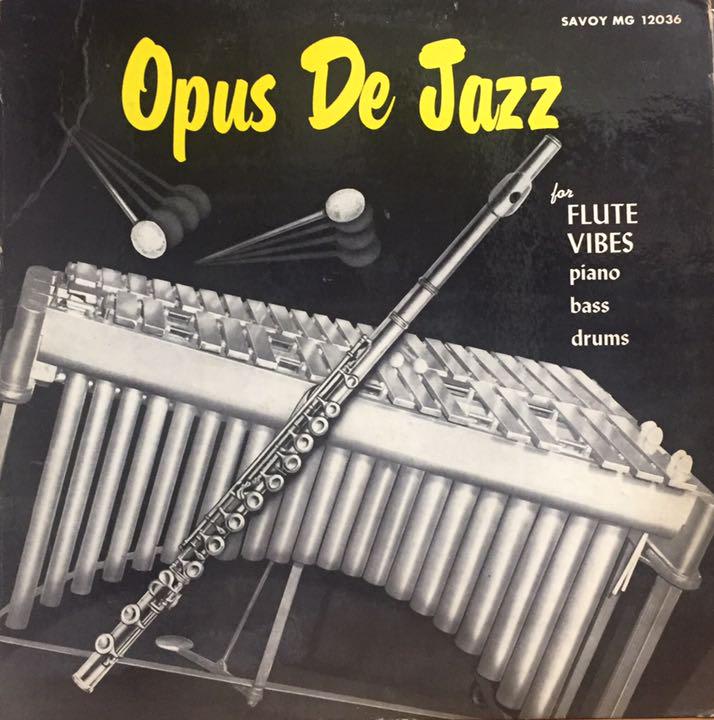藤田 祐樹,岩波科学ライブラリー (2019/8).
タイトルに惹かれて図書館で借用.人類学者の研究という,自分には想像がつかない世界が描かれている.出版社による内容紹介は
*****
日本の人類史でもっとも古く,長く,そして謎の多い旧石器時代.何万年もの間,人々はいかに暮らしていたのか.えっ,カニですか……!? ウナギを釣り,貝のビーズでおしゃれして,旬のカニをたらふく食べる.沖縄の洞窟遺跡の膨大な遺物から見えてきた,旧石器人のなんとも優雅な生活を,見てきたかのようにいきいきと描く.
*****
秋,カニがまるまると太る時期になると旧石器人はどこからかサキタリ洞にやってきて,カニをたらふく食べ,またどこかに去っていくのだそうで,まだまだわからないことが多い.
全6章のうちの第5章は,消えたリュウキュウジカの謎.島に暮らすうちに,資源と面積が限られ,敵がいない状況で小型化し,長寿を楽しんでいたシカたちが,後からやってきた旧石器人にあっという間に食べ尽くされてしまった...という推測.
その旧石器人はどこかに消えてしまった.旧石器人は遺伝的には現在の沖縄人とは無関係,ということは,われわれの祖先ではないのだそうだ.
巻末の著者紹介には「近ごろは,旧石器人を真似て貝の釣り針で魚釣りに挑戦中.好きな食べ物はカニとウナギと焼き鳥」とある.焼き鳥以外は旧石器人そのもの.世界最古の貝の釣り針が著者たちによって発見された過程もこの本に書いてある.