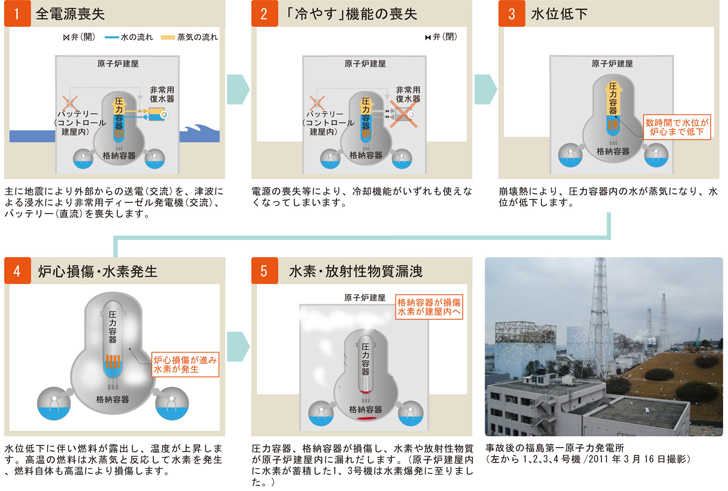【僭越ながら論】:「未曾有」とメディア
『漂流する日本の羅針盤を目指して』: 【僭越ながら論】:「未曾有」とメディア
東日本大震災の発生以来、改めて認識させられた単位や固有名詞、そして言葉がある。
例えば「シーベルト」「ベクレル」といった放射能に関する単位や、「原子力安全・保安院」「原子力安全委員会」などの政府組織、放射性物質の「セシウム」「ヨウ素」「ストロンチウム」などだ。
事故や事件の報道で頻繁に使われ、定着する言葉は少なくない。アメリカにおける同時多発テロでの「アルカイダ」などはその最たる例だ。
そうした言葉の"ひとつ"が気になっている。
■「未曾有」
3月11日以来、連日のようにテレビや新聞の紙面でお目にかかるようになった言葉のひとつに「未曾有」がある。震災について語られる(あるいは報じられる)時、必ずと言っていいほど冒頭にこの言葉が振られる。「東日本大震災という未曾有の事態に・・・」、「未曾有の国難の前に・・・」といった具合だ。最近の国会論戦でも頻繁に聞かれるが、元首相が「みぞうゆう」と誤読し、一躍有名になったことは記憶に新しい。
その「未曾有」である。
■語源
語源をたどると、「未曾有」とは梵語すなわちサンスクリット(サンスクリットは古代インドの言語)の「アドブダ」(adbhuta)が中国で漢訳されたものだという。もとは仏陀の功徳を褒め称えた時の仏教用語で、"非常に珍しいこと""これまでなかったこと"を指すとされ、仏典にも登場する。
梵語の「アドブダ」(adbhuta)を日本語に直訳すると「奇跡」となるそうだが、日本に入ってきたのは漢訳された「未曾有」。そのため、"未(いま)だ・曾(かつ)て・有(あ)らず"、つまり 「これまで一度もなかったこと」の意味だけがこの言葉に対する一般的な解釈となったものらしい。
「未曾有の好景気」「未曾有の災害」といったように、善にも悪にも用いられてきた。ただし、世相を反映してか現在はもっぱら悪い事象を形容する言葉になっている。
■「未曾有」の数々
東日本大震災による死者・行方不明者の数は明治29年の「明治三陸地震」のそれを上回っており、一般家屋やライフラインを含めた都市基盤も平成7年の「阪神・淡路大震災」以上に失われた。地震の規模は"マグニチュード9"という世界最大級(正確には観測史上4番目)で、人的にも経済的にも、まさに「戦後最大」の災禍である。
この国は、これまでにも多くの「災禍」「惨禍」「国難」を経験してきた。
近代に限って言えば、前述の「明治三陸地震」。大正12年の「関東大震災」。そして平成7年には「阪神・淡路大震災」が発生した。
広島、長崎で一瞬にして数十万人の未来を奪った「原爆」や、さらには「太平洋戦争」自体がもたらしたものもそれに違いない。日清、日露の戦役も同じことだ。
経済的な問題としては平成20年のリーマンショックが引き起こした金融危機もしかり。
これらすべてが、当時において「未曾有」と表現されてきたことは疑う余地がない。
■「未曾有」とは?
それでは、何をもって「未曾有」とするのか。被害者の数か、震度の大きさか、津波の高さか、被災地の範囲か、経済を含めた全体へのダメージの深刻さか・・・。
東日本大震災と比較すれば、犠牲者の数や建物被害では関東大震災の方が上回っているし、津波をともなう巨大な地震として今回の規模が「未曾有」だったかといえば、地震の歴史に詳しい人は「明治三陸地震」のほかに「平安時代の『貞観地震』の事例だってあるじゃないか」と反論するだろう。
終戦から65年を経ても、なお苦しみの種を残していることでは原爆や戦争によるダメージの方が際立っている。
もちろん、それぞれの地震が起きた当時と現在では人口や建造物の数が違っており、簡単に比較することは難しい。
戦争は国家指導者による「人災」の側面が強く、地震や津波と同列で論じることには違和感がぬぐえない。
「未曾有」を規定することは、ことほどさように難しい。だからこそ、"未曾有の安売り"は危険であり、「原発安全神話」を崩壊させた大震災をその一語で片付けていいのか、という懸念がつきまとう。
■「未曾有」乱発のあやうさ
「未曾有」の3文字が乱発されることに"あやうさ"を感じるのは、延長線上に「想定外」という言い訳があるからにほかならない。
「想定外」とは知識や経験のなさを隠すための言葉に過ぎず、これを軽々しく口にする人間は「自分ほどの者でも見通せなかった」と言っているだけのこと。つまりは人を見下しているということで、驕りの証明でもある。
とくに、政治や行政にたずさわる人間にとっては禁句だと思うが、残念なことに首相をはじめ政府関係者は、「想定外」あるいは同義の「想像を超えた」などという発言を重ねてきた。
もちろん、裏には「『想定外』だから仕方がない。自分は悪くない」=「責任は取らない。取る必要がない」とのメッセージが潜んでいる。
政府や東京電力は、東日本大震災がもたらした津波や原発事故は「想定外」だったという姿勢を崩していない(こうした姿勢には多くの批判が出ているが・・・)。その根拠は、今回の震災の規模があらゆる意味で「いまだかつて一度もなかったこと」すなわち「未曾有」の事態だったからというところにある。
見方を変えれば、為政者にとって「未曾有」こそ「想定外」の証明というわけだ。だが、これはいけない。
前述したが、過去の大地震の歴史を検証すれば、東日本大震災の被害の大きさは決して「初めて」とは言い切れない可能性があることが分かる。
原発についても、米国・スリーマイル島や旧ソ連のチェルノブイリで実際に事故が起きているうえ、国内の原発でも数え切れないほどの事故や「事故隠し」が明らかとなっている。
そうすると、東日本大震災の規模や福島第一原発の事故に「未曾有」は当てはまらないことになる。決して「未だ曾(かつ)て有らず」ではないからだ。
政府や東京電力が発すべきは、「対策を怠った」か「間違いを犯した」、あるいは「高をくくっていた」という真摯な反省の言葉だったはずだが、「未曾有」であることを盾に「想定外」でことを終わらせようとしている。
心配なのは、「未曾有」の乱発が為政者の逃げ道になり、誰も責任を取らないまま"増税"などの国民への"つけ回し"が行なわれることであり、メディアまでがこれに組する形になりはしないか、その事である。
■原発に関する疑問
戦後、原発は「国策」として建設が進められてきた。自民党政権下ではもちろん、政権交代を果たした民主党も原発推進の立場であったことに変わりはない。そこで、いくつかの疑問が生じる。
・スリーマイル、チェルノブイリの事故を経て、阪神淡路大震災が「地震」というこの国が抱える最大の問題点を突きつけていたにもかかわらず、「日本では事故はあり得ない」との立場を崩さなかった国や電力会社、御用学者の責任は問われないのだろうか。
・「原発安全神話」を作り上げるため、巨額な税金をつぎ込んで国民を欺いてきた者たちは謝罪しないのか。
・そして何より、為政者たち以上に「未曾有」を乱発するメディアに、そうした問いかけを担う資格があるのかということだ。
■創作された「原発安全神話」
これまで、国や電力会社は、膨大な予算を使って原子力発電の必要性、安全性を広報して来た。そうして作り上げられた「安全神話」が虚構だったことは、福島第一原発の事故が証明済みだ。
新聞紙上で原子力発電の広告記事を読んだ経験は誰もが共有しているだろうし、テレビはタレントや文化人を起用した原発の広報番組やCMをたれ流してきた。
潤ったのは新聞社でありテレビ局だったわけで、多くのメディアが原発は安全だという神話「創作」の片棒を担いできたのは事実だろう。
新聞社やテレビ局が経営重視であることは論を待たないが、そのことがジレンマとなって大切な視点を欠いてはいないだろうか。
■メディアに求められる「覚悟」
復興に向けて動きが始まったいま、報ずべきことは、被害を拡大させた原因の究明であり、不十分だった対策にかけられた予算の額や内容であり、原発や公共事業利権からもたらされた利益を政治家や官がどれほど食いつぶしてきたかの検証であろう。
そうでなければ、多くの国民は何も知らされないまま、ただ利権集団のつけ回しに追われるはめになる。
メディア側にも「原発安全神話」の創作に加担したことに対する反省が求められているのは言うまでもない。
性根を据えてこの国の未来を語るのなら、メディア側にも相応の「覚悟」が必要なのではないのか。
電力会社による自民党の政治資金団体への寄附や原発の広報。ゼネコンから政治家への献金。本来の目的を果さなかった放射能拡散予測システムや役に立たなかった防災モニタリングロボット。そうした「無用の長物」に多額の税金を投じ続けてきた官僚組織・・・。
すべてを支えてきたのは、被災者を含めた国民が支払った電気料金や税金なのだ。もちろんメディア側に流れ込んだ巨額な原発広報費も原資は同じである。
こうした事実を脇に置いたまま、復興はもちろん、増税や国債発行などの政治課題についてまともな批評ができるとは思えない。
大半のメディアが政府や東電の「想定外」という逃げ口上について批判しているが、ならばなおさら、「未曾有」という言葉の使い方を誤ってはいけない。
正確をもって旨とする大手メディアが、あやふやな「未曾有」を乱発することは、「原発安全神話創作」に加担した事実を覆い隠すため伏線を張ったとしか見られかねない。
被災地の悲劇や美談、震災がもたらしている社会状況を報じることも大切だ。しかし、何が事態を悪化させたかの"覚悟を持った検証"がなければ、国民はメディアへの信頼を失うだろう。
これまで、そうした自己批判も含めた姿勢の報道があったのか?
寡聞にして、私は知らない。
元稿:HUNTER 主要ニュース 【僭越ながら論】 2011年05月09日 11:20:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。