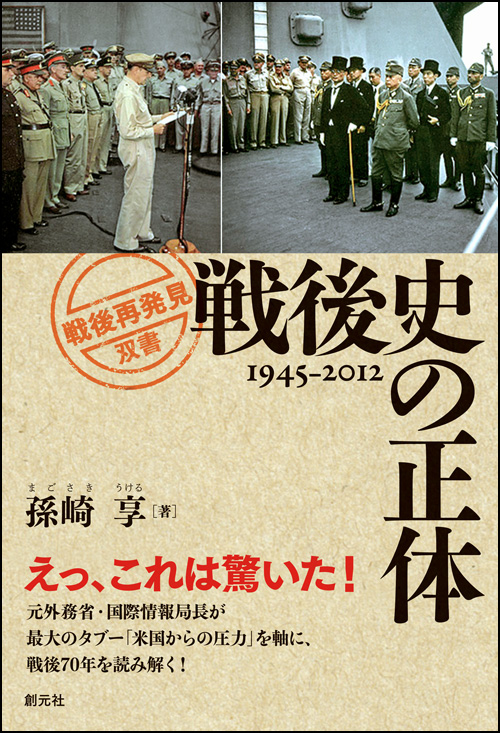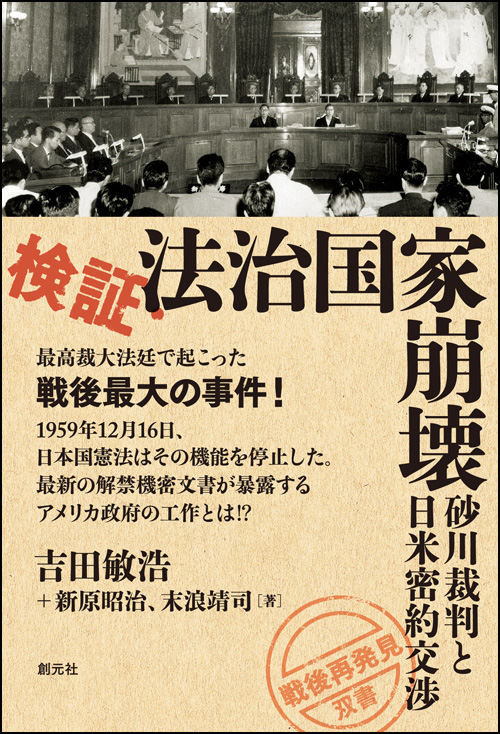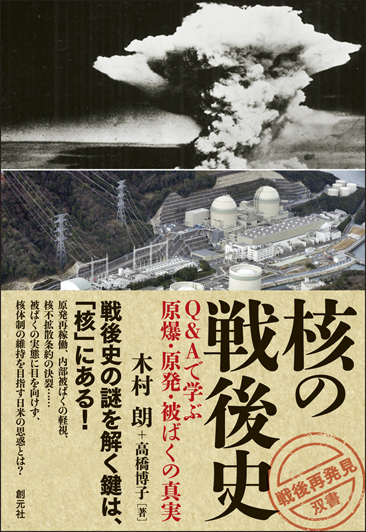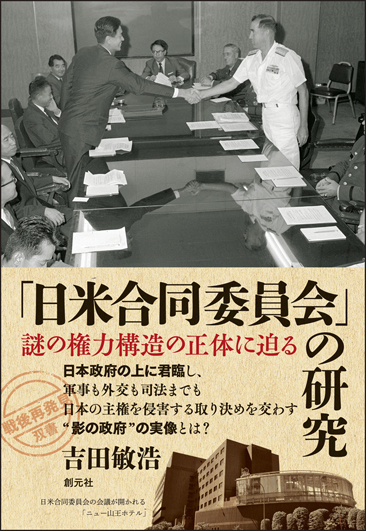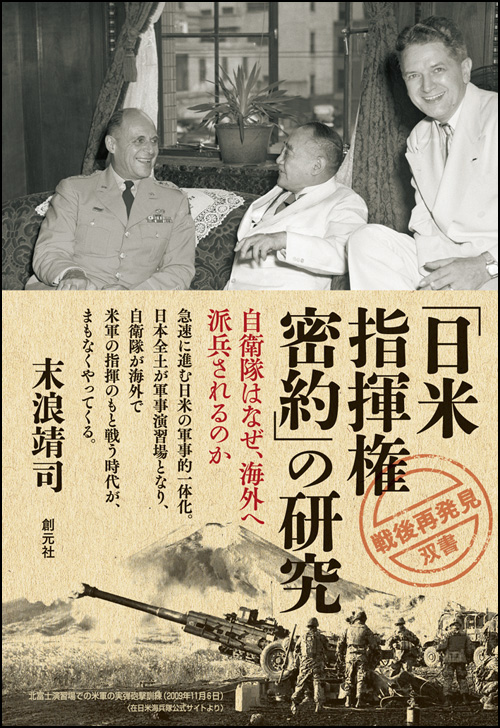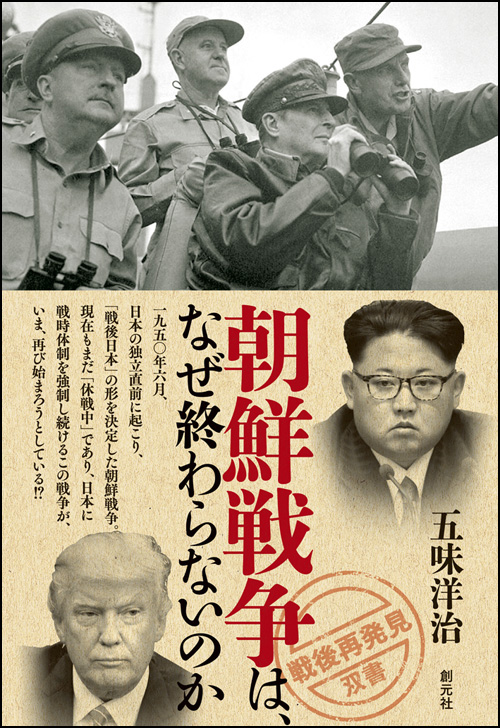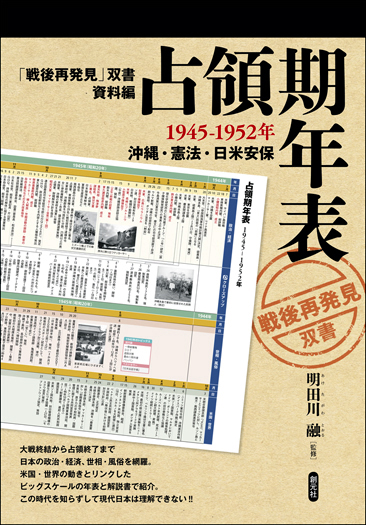【社説①】:能登半島で震度7 命守る行動を最優先に
『漂流する日本の羅針盤を目指して』:【社説①】:能登半島で震度7 命守る行動を最優先に
マグニチュード(M)7・6、最大震度7を観測した能登半島地震。石川県の能登地方を中心に家屋の倒壊、大規模火災、津波など甚大な被害をもたらした。余震はなお続き、死傷者がさらに増える可能性もある。人命救助と被災者の支援に全力を挙げたい。

【地震】富山県内で震度1 能登半島沖を震源とする最大震度1の地震が発生 津波の心配なし© 富山テレビ
M7・6は阪神大震災(M7・3)を大きく上回る。気象庁の記録によると、内陸部を震源とする地震では、過去100年間で関東大震災(M7・9)に次ぐ規模の歴史的な大地震といえる。
能登半島の群発地震でこれまで最も大きかったのは2023年5月のM6・5。今回はその30倍以上のエネルギーだ。
震度6弱以上の極めて強い揺れがこれまでにない広い範囲に及んだため、ビルや住宅など建物の倒壊が相次ぎ、下敷きになった人らが亡くなった。震源の近い地震の恐ろしさを物語る。
輪島市中心部では1日夕に出火し、十数時間燃え続けた。一大観光地である朝市通り周辺がほとんど焼失した。
輪島市への道路が寸断され、現地に入りにくい状況も続いているという。行方不明者の捜索や救出を最優先に、人員や重機の投入には海上輸送を含むあらゆる手だてを尽くしてほしい。
地震発生と同時に大津波警報や津波警報が発令された。能登地方の広範囲で漁港内の漁船が転覆したり、周辺道路に流れ込んだりしたことはあったが、人的被害は今のところ報告されていない。
多くの住民らが警報と同時に高台や山の手へと逃げた。東日本大震災の教訓が生かされた形だ。
◆揺れ感じたらすぐ避難
津波は、震源がたとえ内陸でも地下の断層が海底にまでつながっていれば起こる可能性がある。その場合、津波は陸地近くで起こるため、すぐに海岸に押し寄せる。輪島では地震発生の約10分後に1・2メートル以上の津波を観測した。
太平洋岸だけではなく日本海沿岸でも、揺れを感じたらすぐに避難することが大切だと、あらためて心に刻みたい。
今回の地震では、停止中の志賀原発(石川県志賀町)で、核燃料貯蔵プールの水が揺れによってあふれ、冷却装置がおよそ40分も止まるなどのトラブルが起こった。変電装置では油が漏れたり消火装置が働いたりしたという。
停止中であっても原発の安全を維持する重要な機器である。
07年の新潟県中越沖地震でも柏崎刈羽原発の変電装置が燃え、プールの水があふれた。その教訓は生かされていたのか。トラブルの詳しい調査と結果の公表が欠かせない。
能登地方では20年12月から群発地震が続き、震度1以上は3年間で500回余を数える。
今回は本震の規模が大きく、震源も浅いため、その後も断続的に余震が起きている。今後1週間程度は震度7規模の地震と津波が発生する恐れがあるという。今回の群発地震がいつまで続くのかは見通せない状況だ。
政府の地震調査委員会は地下深くから上昇してくる地下水が原因との見解を示したが、これが能登半島沖を走る活断層を刺激したのかどうかは分かっていない。
1965年から約5年間続いた松代群発地震も、能登での群発地震同様、地下水が原因とされ、大量の水が地上に噴き出し、収まった経緯がある。
ただ松代は最大の地震がM5・4と規模が小さく、今回の群発地震が松代と同様の経過をたどるかどうかは見通せない。詳しいメカニズムの解析が待たれる。
今回の震度7の地震では、関東や中部地方でも緊急地震速報が出され大きな揺れを感じた。地震への備えが日ごろから必要だと感じた人は多かったのではないか。
◆個人や家族での備えも
水や食料など最低限の備蓄や、避難場所や家族との連絡方法の共有など、個人でできる備えをあらためて確認しておきたい。
現地では、遮断された交通網や停電、断水などライフラインの復旧が待たれる。被災者に必要物資を届けるために、政府や自治体などによるプッシュ型支援も強化してほしい。
緊急地震速報が頻繁に鳴り、精神的に疲れたり、怖くて眠れない夜を過ごしたりする人も多いだろう。心のケアも必要となる。
現地は3日にかけて雨が降る予報だという。揺れで地盤が軟らかくなっており、土砂崩れなどへの警戒も必要だ。自らの命を守ることを最優先に行動することを心掛けてほしい。
元稿:東京新聞社 朝刊 主要ニュース 社説・解説・コラム 【社説】 2024年01月03日 07:41:00 これは参考資料です。 転載等は各自で判断下さい。