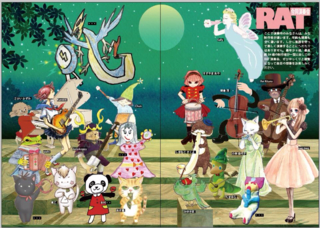Revive
娘さんを自転車に乗せてあげたい。
その思いは娘が4歳の頃から
いろいろ調べ、いろんな人にご迷惑をおかけして。結果離散してしまっていた その話。
今年に入り、再検討をしてくださっているタイミング。
なので、少しでもお勉強。
しておかなければ。
この自転車
歩くように自転車にのる
がコンセプトらしい。
身体に合わせて様々な合わせこみが可能な設計がなされているようにみえる。そんな自転車。
娘さんか漕ぎやすいような形を模索するのにいいのかも。
いろんなことを考えますね。
高齢化社会に合わせて、さまざまなものが開発されてくる。
アンテナを高くして、その中で義肢装具使用者にとり、活用できそうなものがないか考える。
習慣になりつつありますね。
これまた川村義肢の慶社長からのご紹介。やはりアンテナが高いですね。叶わないながらもついていかなければと 日々反省です。
こうした自転車をお借りして、義肢製作所さんやメーカーさんと協力できれば、「義足でも乗れる自転車」が作れないかしら。
そうした思いをもちますね。
遠藤さんや佐野さんなど、工学の分野からさまざまなアプローチが行われつつある今。考えていけないかしら。
一患者からの意見は、小さいかもしれないけれど。たぶんその後ろには同じような状況を当たり前だと思わされている患者がいる。患者家族がいる。
私のように声を上げるのは 珍しいよね。だって、それより日常に大変なことが山積みだもの。
でもだからこそ。
今私にできること。たくさんあるかもしれないから。
気力が続く限り、いろんなことを真剣に考え続けていきたい。
まぁ。仕事の内容よりも、娘さんのことを考えている時間がもしかしたら長いかもしれないのは内緒。
でもまぁ。
その経験は不思議と仕事にも生きるんですけれどね。
以下、参考リンクより
http://www.giant.co.jp/revive/
『歩くように、自転車に乗る』ため、ちょっと おせっかいします。?
?我々が二本足で歩きはじめてから、ずいぶん長い時間が経ちました。ですがそんな期間を経た現在でも、歩く以上に、カラダに良い運動は生まれていないのです。歩くのは、カラダの胸から下にあるほとんどの筋肉を使用し、体軸バランスを調整しながら進む運動。走る動作のような衝撃も少ないので、ストレスなく長時間運動するのに最適です。問題なのは、エンターテイメント感のなさ。そのスピードの遅さのため、楽しい気持ちになかなかならないのです。
?一方、人力での最速の動作である自転車に乗る行為は、そのスピード自体が心とカラダのストレスを癒してくれます。その移動のラクチンさのおかげで、長時間長距離、歩くよりもラクに楽しく有酸素運動できます。
ただ、これまでの自転車のつくりには、競技用自転車の思想が伝統的に反映されています。つまりスピードを出しやすく、うまくなればウィリーなどもしやすいのですが、使う筋肉のバランスは、歩きに比べてバラバラ。自転車に乗るとももや腰など、部分的に疲れてしまうのはこのためです。
?「歩くように、自転車に乗れたら」。そんな相反する理想を実現したのが、全く新しいコンセプトの乗り物、リバイブです。『MTBワールドカップ』や『ツール・ド・フランス』など、世界最高のスポーツバイシクルシーンを走るトップブランドが、そこからフィードバックしたデータ&技術を使いました。できあがったのは、カラダと心に気持ちいい、というコンセプトの、これまでにない乗り物です。
アナタの姿勢が良くなるように、ちょっと おせっかいします。?
『歩くように自転車に乗る』ためには、リバイブの寝そべるような乗車姿勢が大切です。これまで太ももの筋肉(大腿四頭筋)だけが受け持っていたペダリングでの負担を、下半身全体の筋肉、歩く時に使うのと同様の筋肉へと分配します。それが、長い時間気持ちよく乗れる理由です。
もう一つ大きいのが背もたれの効果。これまでは腰の筋肉が受け止めていた上半身の重みと下半身が作った踏み出しの力。リバイブはこの応力を背中全体からおシリ、太ももの裏側で分配し、受け止めます。現代病とも言える腰痛のほとんどは、体幹のコア筋肉と呼ばれる腹筋群、広背筋、腸腰筋などが運動不足やストレスなどにより硬化し、疲労しやすくなることで起こります。
リバイブは、これらコア筋肉を動かしほぐすことで、コア筋肉の硬化を、ひいては腰痛の予防にもなります。医学博士、筑波大学運動生化学研究室征矢英昭助教授によると、体幹から下半身の筋肉がバランスよく使えるようになれば、日常生活での姿勢も確実に良くなり、余計な筋肉の緊張が取れるそうです。おまけにこの寝そべった姿勢は、精神の緊張をほぐすのにも最適だそう。運動生化学的にもストレスを癒してくれる乗り物、なんですね。
?一般サイクル車ではペダリングで太ももの表側を多く使い、上体の重さをサドルと腰で支えています。リバイブでは上体の重さを背もたれで分散し、下半身全体でペダリングすることで筋肉への負担も分散させているのです。上体が起きた姿勢は目線が高く、安心感を生み、楽しいライディングが可能になるのです。?
アナタ専用の乗り心地になるよう、ちょっと おせっかいします。?
?身長や腕、脚の長さ。ヒトのカラダはそれぞれ違います。だから最適な乗り位置=ポジションも、一つとして同じものはないんです。ところがこれまでの自転車は、そんな基本調整すら一大事。新たに部品を買わなければいけなかったり、あるいは調整なんかできなかったり。
そこで、リバイブは、自転車とアナタの接点である3ポイントの調整を簡単にできるようにしました。それが、サドル位置、ハンドル位置、ペダルとの距離。アナタだけに最適なポジションになれば、オーダーメイドのような走り心地になります。そして、全体に低めの乗車位置のおかげで自然と足つき性も良くなり、安全に。スポーツバイクブランドとしての、おせっかいです。