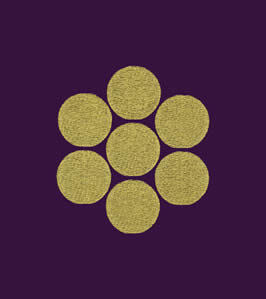◇IT(1990年 アメリカ 187分)
原題 IT
監督 トミー・リー・ウォーレス
出演 オリビア・ハッセー、アネット・オトゥール、エミリー・パーキンス、リチャード・トーマス
◇27年も経ってしまった
この間、ぼくはなにをしていたんだろう?
1990年当時、ぼくはとにかくスティーブン・キングが大好きで、普段から本を読まない僕にしてはほんとうに珍しいことに、出る本出る本つぎつぎに買い込んでは読んでた。どれもこれもおもしろくて、でも、どうしても読めない本があった。それが『IT』だった。まあとにかく分厚くて、あ、キングはいつもどれも分厚いけどね、その中でもこの本はかくべつに厚かった。
まあそんなことはいいし『水晶島奇譚』も似たようなものだとおもうんだけど、とにかく『IT』は読み終えることができなかった。このテレビ映画がレンタルビデオ屋に列んだのはそんなころだ。テレビでも『スティーブン・キングのイット』とかってタイトルで放送されたらしいけどそちらは観てない。それはともかく『IT』が読めなくなって、でもなんとかこの作品は観たものの、それ以来、ぼくはキングの読者ではなくなった。
で、それから27年経っちゃった。ペニー・ワイズが蠢き出す頃だ。
さて、こちらのピエロ=ペニー・ワイズはティム・カリーだ。う~ん、当時もおもったことなんだけど、テレビというのは照明がベタなんだよな。だから怖さよりも滑稽さの方が先走っちゃってて、マクドナルドにでも行こうかしらって気になったりもした。ただ、給水塔はどっちもどっちながら、大井戸はリメイクされた映画よりも断然こちらの1990年版が好い。ロケーションで、あ、こっちの方が雰囲気あるじゃんってところは随処にある。あるものの、どうしても平板で、ぼくの個人的な感覚からすると187分観続けるのはちょいと辛いかな。