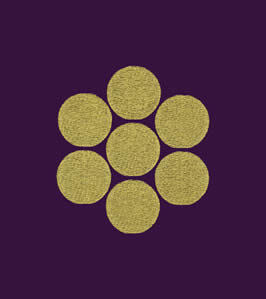◎暗殺の森(1971年 イタリア、フランス、西ドイツ 115分)
原題/Il conformista
英題/THE CONFORMIST
仏題/LE CONFORMISTE
監督・脚本/ベルナルド・ベルトルッチ 音楽/ジョルジュ・ドルリュー
出演/ジャン=ルイ・トランティニャン ドミニク・サンダ ステファニア・サンドレッリ
◎アルベルト・モラヴィア『孤独な青年』
Il conformistaの意味は順応主義者。では、ジャン=ルイ・トランティニャンは何に順応したんだろ?
1928~43年にかけて、ひとつの時代があった。ファシズムだ。イタリアのファシズムがローマで終わりを告げたのは、1943年7月25日。映画の佳境でもあるんだけど、時代の終焉と、それまでの自我の崩壊とが重なる。で、原題Il conformistaが浮かびあがってくる。
トランティニャンがなんでファシズムに順応したのか。
むろん、少年時代に、元牧師に悪戯をされそうになった際、
「ぼくは、拳銃で撃ち殺してしまった」
というトラウマを抱えている事実はあるにせよ、ほんとのところは、よくわからない。
でも、さしたる主張もないまま、暗殺に巻き込まれていくわけだけど、自分が生きようとした生き方ではない、与えられた生き方、つまり、自分の意識とは無縁な生き方に順応せざるを得なかった、っていう青年を演じてる。
トランティニャンは性的にいえば特異な洗礼を受けてしまったためか、なんの悩みもないお嬢さんで、処女としかおもえないような妻には興味がなく、彼女ステファニア・サンドレッリが、実は、幼い頃に還暦も過ぎた老い耄れに手籠にされ、その後10年間もその爺さんの性的な処理道具にされていたというような、どうにもしがたい事実を聞かされた途端、彼女に欲情して交合するというのは、つまり、同類相哀れむのではなく、彼女をようやく情欲の対象にできたということなんだろう。
それだけ、トランティニャンの人格形成は、過去の事実に順応してしまってるんだね。
ただ、かれはかれなりに悩める若き青年で、やがて暗殺の対象となってしまう教授との間に、プラトンを引用した問答が持たれる。
洞窟の影は所詮は幻影であり、光が満ちれば消えてしまう。しかし、一方向からしか光が当たっていなければ、恐ろしいほどの現実味を持っている。自身の過去の呪縛にしても、ファシズムの呪縛にしても同じ事だ…と。
けど、それは所詮、理屈の為の理屈でしかなく、ふたりの関係はもっと生々しい。
トランティニャンは、教授の若き妻ドミニク・サンダを関係を持つんだけど、それは、かれを順応させた教授の最愛の対象を汚すことになり、つまりは、自分を育て、かつ順応させていたものに対する抵抗と復讐になる。
けれど、教授が暗殺される段にいたり、トランティニャンは、仲間の暗殺者たちが暗殺を実行に移しながらも、車から森の中へ出ようとはせず、結局のところ、暗殺には加担しない。教授を殺すことが、順応させていた者からの脱出になるはずなのに、加担しない。
なぜなら、それは、トランティニャンを否応なく順応させていたファシズムへの抵抗だからだ。もっとも、それは同時に、愛してしまったドミニク・サンダを助けないという行為にもなる。
ドミニク・サンダは如何ともし難い葛藤に包まれるわけだけど、その間に、彼女は森の中で、教授に殉ずるように暗殺されてしまう。
ただ、ドミニク・サンダとステファニア・サンドレッリは、ふたりでタンゴを踊る場面が象徴しているように、トランティニャンの表の性衝動と裏の性衝動の具現化になっているから、どちらが死んでも、トランティニャンの性は崩壊してゆくしかなくなってしまう。
要するに、左右対称の調和のとれた極上の画面が、手持ち撮影になった途端に崩壊するように、順応主義者は順応できなくなってしまったときに自己崩壊してしまうんだね。
順応している自分が許せず、順応している環境から脱出しようともがきながらも、結局のところ、その呪縛から解き放たれることはないっていう辛さを、早熟の天才ベルナルド・ベルトルッチは、ヴィットリオ・ストラーロの極上の画面をもって、表現してるんじゃないだろか?
ただ、この映画があまりに残酷なのは、少年時代にトラウマとなっていた殺人が、実は殺人未遂で、すべては自分の思い込みによって、自己を順応主義者にしてしまっていたという、それまでの人生を木っ端微塵に打ち砕いてしまうような事実が用意されてることで、トランティニャンに当たっていた光は、自分が引き金をひいて作り出した光にもかかわらず、その光そのものがまがい物に過ぎなかったっていう徹底ぶりで締めくくられる。
身が引き裂かれそうになる映画じゃない?