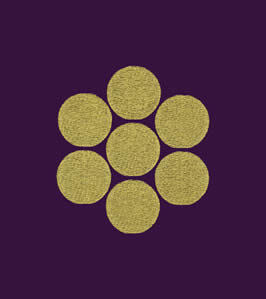◇アンナ・カレーニナ(2012年 イギリス・フランス 130分)
原題 Anna Karenina
staff 原作/レフ・トルストイ『アンナ・ カレーニナ』
監督/ジョー・ライト 脚本/トム・ストッパード 撮影/シェイマス・マクガーヴェイ
美術/サラ・グリーンウッド 音楽/ダリオ・マリアネッリ 衣装/ジャクリーン・デュラン
cast キーラ・ナイトレイ ジュード・ロウ ケリー・マクドナルド エミリー・ワトソン
◇1832年、マリア・アルトゥング、サンクトペテルブルクに生まれる
マリアっていうのは、アンナのモデルになった女性のことで、
詩人のプーシキンの娘だそうだけど、これは余談。
さて。
人生は回り舞台とかって台詞は、誰がいったんだっけ?
なんとも奇抜な発想っていうか、舞台が映画になっているという不思議な演出。
もちろん、戸外でのロケーションもあるにはある。
でも、駅も馬場も、夏も冬も、すべて舞台の上で展開し、それを観客が観るのだけれど、
その観客も劇中の観客にすぎないっていう多重構造の映画になってる。
なんで、そんな構造にしたんだろ?
ロシアの貴族社会が虚飾と虚栄に満ち溢れているから、
そんな嘘っぱちの社会を端的に象徴するには舞台がいい、
とでもいう結論に行きついたんだろうか?
ま、そうした構造が好かったかどうかは、観る人が考えることだ。
並はずれた発想だと褒める人もいれば、
舞台というクッションのせいで映画に入り込めないと不満を漏らす人もいるだろう。
ぼくは、こういう斬新さは好きだから、いいんじゃないかな~とおもうけど。
それはそれとして、
衣装は、ものすごく綺麗だった。
美術と衣装の凄い映画は、ほんと、観ていて気持ちがいい。
あと、ジュード・ロウがいい。
なんたって、役作りのために頭を剃り上げ、
保身に尽くし、体裁ばかりを気にし、波風の立つのを嫌がるという、
時代を超えてどこにでもいそうな没落貴族の役柄をじっくり演じてる。
ま、役者根性についてはともかく、ジュウド・ロウの役どころは、
恐妻家で知られるトルストイ自身がモデルになったような夫役だけど、
かれとケリー・マクドナルドの役だけが、やけにリアルな印象を持った。
それと、アンナの兄嫁の役を演じてるケリーが、
「不倫を嫌がっているわけではなく、相手がいれば自分だってする」
というようなことをぽろりと口にするところなんざ、リアルですわ。
それはともかく、
アンナが、暗示的に幾度も登場する列車に飛び込むのは、
ちっぽけでつまらない虚栄心が崩壊してしまうからなんだろなって見えてしまう。
なぜって?
だって、他のご婦人方は、
アンナの行為と行動と姿勢と態度には眉をひそめて陰口は叩くものの、
「あなたのしていることは、汚らわしく、神もまたあなたを見捨てるでしょう」
てなことを面と向かっていっているわけではないし、もしかしたら本心は、
「あんたたちはふたりとも蓮っ葉な感じだけど羨ましいわ。悔しいから陰口叩いてやるの」
てなことだったのかもしれず、そうした劣等感や嫉妬をアンナが見抜いていれば、
みずから命を断つような真似はしなくて済んだかもしれない。
アンナは、
自分が、誰よりも美しく貞淑な人妻であり、かつ理知的な母親であると自惚れていた。
ところが、
「真実の愛に目覚めたのよ」
などと嘯いて背徳の恋に身を焦がしているのを周りが勘づいたのでは?
と疑心暗鬼になり、また、道ならぬ恋がもとになって自分が嫌悪され、
かつ軽蔑の対象にされているかもしれないと妄想するようになり、
くわえて、
愛人が母親の選んだ小娘に興味を示しているのを目撃したことで、
もう自分は愛されていないんだ、棄てられるんだと勝手におもいこみ、
さらに絶望し、
自分が悲劇のヒロインになるためには死を選ぶしかないとでもいうような、
いわば、いびつな自己陶酔の末、衝動的に線路に飛び込んでしまった。
つまりは、虚栄心が粉々に砕かれたことによる自己崩壊なんじゃない?
と、下司の勘繰りしかできないぼくは、ついついおもってしまう。
でも、こうした自殺の動機はやっぱり前の世代の感覚で、
現代の冷めた観客たちは、
「なんだかボルテージ高過ぎでしょ」
とか、いいかねない。
だから、斬新な演出を持ち込んで、役者たちをおもいきり着飾らせることで、
現代とやや異なる感覚だけど舞台の中でならまだまだ十分に輝くだろう、
とでもいっているようにおもえてならないんだけど、うがち過ぎかしら?