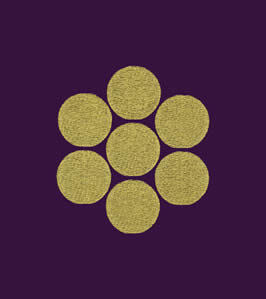◎大怪獣バラン(1958年 日本 82分)
英題 Varan the Unbelievable
staff 監督/本多猪四郎 特技監督/圓谷英二(円谷英二)
原案/黒沼健 脚本/関沢新一
撮影/小泉一 美術/清水喜代志 特技美術/渡辺明
造形/利光貞三、八木寛寿、八木康栄、村瀬継蔵
合成作画/石井義雄 光学作画/飯塚定雄、茂田江津子
音響効果/三縄一郎 音楽/伊福部昭
cast 野村浩三 園田あゆみ 千田是也 平田昭彦 土屋嘉男 本間文子 熊谷二良
◎特撮とボク、その39
ぼくがこの作品を初めて観たのは、テレビだった。
当時の白黒テレビは画像も悪ければ音も悪く、
カラーの怪獣映画に慣れてたぼくには、ちっともおもしろくなかったんだけど、
もうずいぶんと大きくなってから、伊福部昭のBGMを聴いた。
そのときの衝撃たるや、なんでこの映画が劇場で観られないんだ!てなもので、
以来、ぼくは『大怪獣バラン』の再上映を待ち焦がれてたんだけど、
まったく再上映されることはなかった。
でもまあ、劇場では今のところ観られずにいるものの、充分におもしろかった。
いや、すごかった。
バランの飛んでくところはちょっとばかりお粗末ではあるけれど、
そんなことは、物語と映像と音楽による全体の出来栄えからすればたいしことじゃない。
自衛隊の記録映像と上手にミックスされた戦闘場面の迫力は、
特撮映画中の白眉じゃないかっておもえるし、
合成されてる作画の見事さといったらないし、ミニチュアの湖がまたいい。
もちろん、
日本のチベットといわれる北上川の上流岩屋に残る婆羅陀魏山神の伝承とか、
なんとも超古代オタクの心をそそるような設定もいいし、
祠に祀られた婆羅護吽の像もまたいい。
けど、なんといっても凄いのが、伊福部昭の音楽だ。
『婆羅陀魏』は伊福部昭の傑作じゃないかっておもえるし、
『兵士の序曲』をもとにする行進曲のオンパレードには鳥肌が立つ。
鳴き声がゴジラほどの哀愁がないのと、
照明弾につけられたメガトン爆弾を呑み込んでの体内爆発という設定が、
もうちょっとなんとかならなかったんだろかとはおもうけど、ま、仕方ない。
あ、そうそう。
特技助監督のチーフとして出目昌伸さんが参加しているのには、
ちょっと意外な感じがしたけど、これは余談。