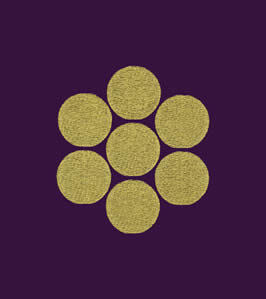◎山猫(1963年 イタリア、フランス 187分)
伊題 Il gattopardo
仏題 Le Guepard
staff 原作/ジュゼッペ・トマージ・ディ・ランペドゥーサ『山猫』
監督/ルキノ・ヴィスコンティ
脚本/ルキノ・ヴィスコンティ スーゾ・チェッキ・ダミーコ エンリコ・メディオーリ
パスクァーレ・フェスタ・カンパニーレ、マッシモ・フランチオーザ
撮影/ジュゼッペ・ロトゥンノ 美術/マリオ・ガルブリア
音楽/ニーノ・ロータ ジュゼッペ・ヴェルディ
cast バート・ランカスター アラン・ドロン クラウディア・カルディナーレ ジュリアーノ・ジェンマ
◎1860年、赤シャツ隊、シチリア上陸
なにが凄いって、もちろん、舞踏会の場面なんだけど、
ふたつ、疑問がある。
ひとつは、舞踏会に参加している面々で、
当時、なにごとにも完璧を期したいヴィスコンティは、
シチリア島に代々命脈を保ってきた貴族の末裔たちが出演者として招き、
ほんものの舞踏会であるかのように撮影したという。
でも、ほんとうだろうか?
こんなに大勢の人達が、ひとり残らず貴族の末裔なんだろうか?
一般の民衆とどんなふうに違うんだろう?
って、貴族の血が一滴も流れていないとおもわれる僕なんぞは、
疑いのまなこで観ちゃうんだよね、まったく困ったもんだ。
疑問のふたつめは、照明だ。
ヴィスコンティは、本物の貴族の舘を借り切って撮影したものだから、
大掛かりな照明を持ち込むような無作法をせず、
無数の蝋燭を立てて撮影したらしい。
たしかにおびただしい蝋燭のせいで、室内はむせかえるような暑さになり、
貴族の末裔たちはみんなが扇子を開いて風をおくってる。
アラン・ドロンの額も汗だらだらで、
「こりゃ、まじに暑いんだろな~」
ってことは一目瞭然なんだけど、
ほんとに、蝋燭の灯かりだけで撮影できたんだろうか?
キューブリックの『バリー・リンドン』は特別なレンズを用いたから、
たしかに蝋燭の灯かりだけで撮影も可能だったんだろうけど、
ヴィスコンティがいくらこだわりの王者であっても、可能だったんだろうか?
だって、天井ちかくまでくっきりと映ってるし、
蝋燭のシャンデリアの上部がまるで影になっていないのは、
かれらの頭の上に、巨大な照明が置かれているからじゃないのかしら?
ってことだ。
蝋燭がどれだけ明るくても、天井ぎりぎりの明るさはかなり乏しいはずだし、
当然、炎のかすかなゆらめきが影をつくるんじゃないのかな~と。
ま、そんな重箱の隅をつつくことはないんだけど、
それくらいしか突っ込みどころのないほど、
完璧な映画に仕上がってるっていうことだろう。
バート・ランカスターは落魄してゆく貴族を堂々と演じていたし、
村娘の気の強い美人を演じたクラウディア・カルディナーレも強烈な個性美だったし、
なんといっても、天下の2枚目アラン・ドロンのぎらぎらした美しさは比類がない。
野心と情熱の塊で、名と実をあげることに躍起になっている若き貴族という役は、
おそらく、当時、アラン・ドロンをおいてほかに演じられるような役者はいなかったろう。
このあともヴィスコンティと組んで欲しかったけど、
そのあたりのことは、ふたりにしかわからない微妙な話だろうから、
地球の裏側の庶民がなにをどう願ったところで仕方がない。
ちなみに、今回観たのは、
製作後30年経った2003年に、
当時の撮影監督ジュゼッペ・ロトゥンノが監修して、
ようやく完成させた『イタリア語・完全復元版』だったんだけど、
最後にもうひとつだけ疑問がある。
緑の色だ。
陽光に満ちたシチリア島は、そこらじゅうが輝き、乾燥しきっているから、
たしかに緑は日焼けし、色褪せてしまっているかもしれないんだけど、
それでも、みずみずしい緑が撮られていたんじゃないだろうか?
フィルムはどうしても寒色系から色が抜けていくから、
もしかしたら、青や緑の退色はもはや修復できないほどになっちゃったんだろうか?
てなことも、なんとなくおもってしまったのでした。