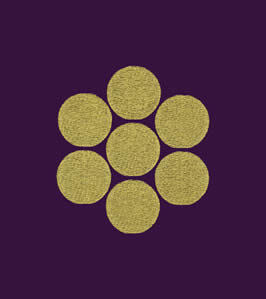◎桐島、部活やめるってよ(2012年 日本 103分)
staff 原作/朝井リョウ『桐島、部活やめるってよ』
監督/吉田大八 脚本/喜安浩平、吉田大八
撮影/近藤龍人 美術/樫山智恵子 装飾/山田好男
衣装/遠藤良樹 ヘアメイク/大野真二郎 音楽/近藤達郎
主題歌/高橋優『陽はまた昇る~桐島、部活やめるってよバージョン~』
製作/映画「桐島」映画部
cast 神木隆之介 橋本愛 山本美月 大後寿々花 東出昌大 清水くるみ 松岡茉優
◎僕たちはこの世界で生きていかなければならないのだから
綺麗な絵だった。
自然な光と自然な構図と自然な演技が好印象だ。
で、内容についてなんだけど、
その綺麗な絵に、孤独があふれてた。
もっとも、あらすじはあってないようなもので、
すくなくとも、桐嶋が部活をやめるっていう情報が流れたことで、
すこしずつなにかが狂い始めるっていうのは、どうなんだろう?
ほんとうだろうか?
桐嶋っていうのは、かれらの同級生なんだけど、
母親が長期欠席を届けるために学校には来たらしい。
でも、欠席の理由は、教師たちからは語られない。
だから、桐嶋が病気だとしても、
それが身体の病なのか心の病なのかはわからないし、
事故に遭ったのかどうか、まさか自殺したとかいうことはあるのかどうか、
まあ、ちょっとそれをほのめかす幻を観るような場面は後で出てくるけど、
ともかく、
理由が曖昧なまま桐嶋が不在になってしまったために、
かれに依存していた一部の生徒が狼狽するというだけのことだ。
もちろん、その狼狽が波及して、一部の生徒と親しい生徒に、
自分の抱えていた漠然とした不安を意識し、
行動させちゃうっていうこともあるんだけどね。
ただ、
それを「なにかが狂い始める」とかいうもったいぶったいいまわしで、
表現するのが正しいのかどうかよくわからないんだけど、
まあ、そんな生徒達の描き方が「さすが、吉田大八」なんだよね。
つまり、簡単にいってしまうと、
この話は、少年や少女がいかにして自立を意識するかってのが主題だ。
桐嶋がいないと試合に勝てないバレーの連中は、
桐嶋に依存していた自分たちが腹立たしく、中でもアタッカーのゴリラ久保は、
その怒りを桐嶋の代わりの部員にあたるんだけど、それが意識できない。
桐嶋を大好きな学校で一番の美少女(山本美月、ええわ~)は、
桐嶋に依存していたために学校生活が灰色になり、
自分がおもうほど桐嶋は自分を好きではなかったという事実にうちのめされ、
学校の誰もが、桐嶋について自分に質問してくることになにも答えられないことで、
自他ともに認めている美しさのプライドががらがらと音を立てて崩れていく。
桐嶋の親友だと勝手におもいこんでいて学校の帰り道や塾を共にすることで、
なんとなく安心していた運動神経抜群ながら気力の足りない美男子は、
実は吹奏楽部の部長から慕われていることに気づいているのかいないのか、
つきあっている意地悪な女子から、
見せびらかしキスを迫られるままにしてしまうという流され続けの自分に、
どうにもやるせない嫌気がさし始め、
野球部主将の3年生が、
ドラフトの候補について歯牙の端にも掛けられていないのに、
ドラフト会議のその日までバットを振り続けるという、
野球バカぶりをまのあたりにしたことで、
自分はいったいなにを目指しているんだろうという疑問もまた自覚し始めている。
そうしたゴリラ久保、美少女、美男子といった3人の回りで、
3人の情緒が不安定になったために影響されてしまうのが、
吹奏楽の部長、性格ブス、桐嶋に依存してたもうひとりの帰宅部男子、
桐嶋の代用リベロ、代用リベロに惚れながら性格ブスと行動を共にしてるバト部女子、
ということになるんだけど、かれらについて分析するのは長くなるから、擱く。
以上の8人が、桐嶋がやめることで心の中に化学反応が起きてしまうわけだけど、
かれらに共通していることは、桐嶋がいなくなることで狼狽しながらも、
所詮、自分が大事で、自分のことだけ心配してて、
桐嶋自身がどうなってしまうのかという心配はほとんどしない。
つまり、かれらにとって桐嶋は、自分を不安定にさせないモノでしかない。
そんな連中とほぼ一緒に行動しながらも、かれらとは明らかに一線を画し、
かれらについて客観的に眺めているもうひとりの美少女がいる。
橋本愛だ。
橋本愛は、帰宅部男子とつきあってるんだけど、
それを公表することで余計な波紋を投げかけるのと共に、
周りと自分たちの間に余計な一線をひかれてしまうのをあらかじめ回避している。
おそらくバドミントンの腕もそれなりだろうし、成績も常に上位に位置しているんだろう。
つまり均整のとれた生徒というわけで、たぶん入試も推薦で合格したりするんだろう。
だから、桐嶋がいようがいまいが、彼女にとってはどうでもよく、
でも、物事があらかた見えてしまう大人びた性格のせいで、
見なくたっていいモノまで、見ちゃう。
神木隆之介だ。
かれが妙な存在感で登場してきたとき、
ぼくたちはようやく「ああ、主役はこのシネフィルか~」と納得する。
と、同時に、この映画の構造が、
舞台劇『ゴドーを待ちながら』の主題を持ってきて、
桐嶋が自殺したのではないかというほのめかしも入れ込みつつ、
展開と構成については『バンテージ・ポイント』とほぼ同じ作り方なんじゃないか、
ていうような感覚を覚え始める。
ぼくは活字嫌いのぱーぷりんだから、原作は読んでいない。
だから、勝手な想像で、
もしも、視点が多様されているんだとすれば、
おそらく数人の生徒のモノローグかなんかで、
オムニバス形式の小説になってるんじゃないかっておもうんだけど、
それを映画で表現するためには、同じシークエンスを順に並べるしか方法がない。
当然『バンテージ・ポイント』的な作り方にせざるをえないだろう。
ただし、
英西合作の『バンテージ・ポイント』は強烈な暗殺劇で疾走感のみの映画だから、
そこに深遠なテーマ性を求めることはできないんだけど、
8つの視点から30分間の暗殺劇を観た後、主役のボディガードに集約される。
ボディガードの視点は8つの視点の中のひとつだったら、観客に唐突感はない。
ところが、本作だと、前半の視点が多用されているところでは神木の視点はない。
にもかかわらず、
神木隆之介がなんで主役になるのかっていうと、かれだけが自立しているからだ。
でも、自立しているっていう意識はかれにはないし、
そもそも自立したくて自立しているわけじゃない。
自立せざるをえない立場に追い込まれてしまっているから自立してしまっただけだ。
どういうことかっていうと、かれとかれの友達つまり映画部はゾンビだからだ。
ゾンビっていうのは、なにも最初からゾンビになりたかったわけじゃない。
死んだり殺されたりして魂を失いながらもまだ生きていたいっていう強烈な意識が、
死体を動かし、起き上がらせ、歩かせ、要するにゾンビ化させる。
神木隆之介たち映画部の連中は、
生徒達にとっていようがいまいがどうでもいい存在で、死人とおんなじだ。
透明人間といってもいいんだけど、要するにかれらを覚える必要はない。
ところが、この顔を覚えなくても、橋本愛のように覚えてしまう子もいる。
橋本愛は好い子でいることが唯一、彼女のアイデンティティを肯定できる。
好い子でいれば回りから無視されることもないし、嫌われて敬遠されることもない。
そういうことからすれば自分大好き少女であることに変わりはないんだけど、
好い子でいなくてはいけないがゆえに、周りをすべて平等に見てしまう。
つまり、彼女にとっては、桐嶋も神木隆之介もおんなじなのだ。
こういう平等意識は、ときとして罪つくりなものになる。
相手を、ここでは神木隆之介のことだけど、勘違いさせちゃんだよね。
もしかしたら自分を意識してっていうか、自分に気があるんじゃないか、と。
けれど、そんなものはただの錯覚で、自分は所詮ゾンビでしかないと思い知らされる。
これほど虚しいものはなくて、いったい自分はどうしたらいいんだろうと。
学校はたくさんの生徒があふれてるのに、
自分だけが、どうしようもない孤独に叩き落とされてる。
ただ、神木隆之介にかぎらず、映画部はそういう連中のあつまりで、
剣道部の部室の奥にある陽もささないような物置におしこまれてる。
でも、かれらには映画という、現実逃避かもしれないけど、共通した興味がある。
映画を製作することは自分たちを別な世界の主役にすることで、
そこにはさまざまなかたちの自分がいて、誰もが自分を肯定してくれる。
もちろん、うだつのあがらない映画オタクに女子生徒が興味をもってくれるはずはなく、
女高生の役が必要な場合はカツラをつけて女装するしか手立てはない。
こんな淋しくも悲しい高校生活がほかにあるだろうかっておもうけど、
かれらの半径1メートル以内には、そういうゾンビ的世界しか存在していない。
熱い涙を拭いてくれるような友達なんているはずがない。
それを認識しているのかいないのか、神木隆之介は役者にこう台詞を吐かせるんだ。
「僕たちはこの世界で生きていかなければならないのだから」
そしてまた、かれのレンズはこう撮らえている。
ゾンビ化した映画部の連中が周りのくそったれ生徒どもを次々に噛み殺していくんだと。
これが、熱い涙でなくてなんだろう。
ちなみに、神木隆之介が構えて、美男子にインタビューして、
自分の不安定な気持ちを涙でもって表現させてしまうカメラは、
日本が生んだ8ミリカメラの名機「フジカZC1000」だ。
このカメラは、
アニメ『あの夏で待ってる』(主人公の名前は霧島海人)で、
ヒロインのひとりである山乃檸檬の愛用してるカメラでもある。
これも余談だけど、
大学の映画制作グループを扱った映画『虹の女神』では、
この名機がフィルムを一本すべて多重露光できることから、
コダックのコダクロウムを、フジのカートリッジに詰め込み撮影するという、
ぼくらの大学時代には誰も気づかなかった技を披露してくれてる。
ともかく、そんなZC1000なんだけど、
吉田大八が高校時代と大学時代にどんな部活動をしてたのかぼくは知らないけど、
ZC1000が手に入ってたんだろうか?
だとしたら羨ましいかぎりで、でもできれば、ぼくとしては、
キャノン1014XLSをベルボンPH701Bに搭載してほしかった。
で、1014を構えながら、やや仰ぎ見た角度のショットで、
「いや、たぶん、監督にはならないな」
という、自分の才能を冷静に分析するのと共に、
孤独なんかに負けてたまるもんかっていう気概のこもった台詞をいってほしかった。
まあ、余談はさておき、
吉田大八は、ほんとうに好きな世界を作り上げたんだろうな~。
そんな気がした。
もし、吉田大八に遭うようなことがあったら、訊いてみたいことがある。
「みんなに頼られてる桐嶋が、いちばん孤独だったんだろうか?」って。