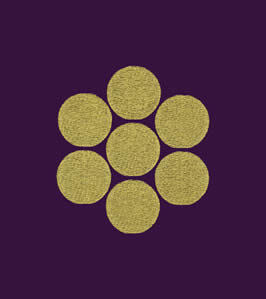☆千利休 本覺坊遺文(1989年 日本 107分)
監督/熊井啓 音楽/松村禎三
出演/三船敏郎 萬屋錦之介 奥田瑛士 加藤剛 芦田伸介 上條恒彦 東野英治郎
☆井上靖『本覺坊遺文』より
天正19年2月28日、利休切腹。
「死ではなくなる。無ではなくならん」
これはいったいどういう意味か、ということが主題だといっていい。
実は簡単な謎解きなんだけど、映画で結論は出していない。
まるで、利休が本覺坊をつきはなすように、
「その答えは、おのれひとりで出すものだ」
とでもいわれているような気分になる。
師として、また、矜持を持ち続けたひとりと男として、利休は描かれている。利休の死についての謎は、もちろん、わからないままだ。けれど、そこに断固たる意地のようなものがあったであろうと、井上靖と熊井啓はいっている。
それを三船敏郎は、茶の手前だけでなく、茶掛けに榊で水を飛ばすさまで、たしかなものとして表現した。おそらく、三船敏郎を除けば、日本映画界には誰もできなかっただろう。
加藤剛の古田織部はちょっとばかり生真面目すぎて、たしかに死の盟約を交わす者のひとりとしては上出来だけれど、織部という偏屈な人間をおしだすにはちょっと出来がよすぎる。
萬屋錦之介は、この映画が遺作になった。佳境、床の上で、まるで前田利家の最期のように、まぼろしの脇差を手にして切腹の見立てをし、そして死を迎える。
利休の死の謎を解き明かしたのか、それともそれは幻想だったのか、おそらく本人にもわからないまま死を迎えることになるけれども、
「わしは切腹はせぬよ。切腹はせぬが、茶人だよ」
枯れた風情ながら、やはり得意の台詞まわしでいいきった錦之助の、東映で時代劇の若として君臨した錦之助の、遺作にふさわしいものだった。
やけにものわかりのいい知的で文化的な秀吉を演じた芦田伸介も、東野英治郎も、上條恒彦も、奥田瑛二も、誰もが与えられた役をしっかりと演じているのがひしひしとわかり、それに競うようにもっていった熊井啓の演出も好い。
画面は芸術的というより枯れた佇まいをしっかりと捉えながら、利休の切腹を表現する桜吹雪は一挙に幻想的な芸術性を見せつける。
音楽も、安土桃山時代の音とはおもえない現代的な印象ながら、結局のところ、登場人物たちの内面の音を奏でている。
80年代の傑作のひとつといっていいかもしれないね。