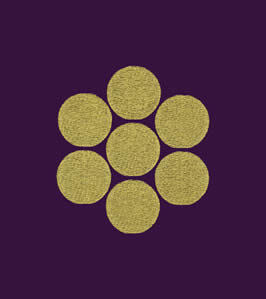◇幸せへのキセキ(2011年 アメリカ 124分)
原題 We Bought a Zoo
staff 原作/ベンジャミン・ミー『幸せへのキセキ~動物園を買った家族の物語』
監督/キャメロン・クロウ 脚本/アライン・ブロシュ・マッケンナ キャメロン・クロウ
撮影/ロドリゴ・プリエト 美術/クレイ・エイ・グリフィス 音楽/ヨンシー
cast マット・デイモン スカーレット・ヨハンソン エル・ファニング パトリック・フュジット
◇2007年7月7日、ダートムーア動物学公園、開園
鮭、鯨、そして動物園と、
なんだか、生き物の映画ばかりが連続してるけど、
この映画は、どちらかといえば『世界にひとつのプレイブック』に似ている。
なぜって?
人の再生の物語だからだ。
人はいろんなことで傷つき、壊れ、立ち直れないような痛手を受けるけれども、
いつかかならず新たな人生に踏み出す機会が訪れるから、
そのときにこそ、勇気をもって立ち向かっていこうじゃないか、
っていう主題になってるからだ。
妻そして母を亡くした家族に訪れる機会が、たまたま動物園だっただけの話だ。
それがハリウッドの定番だろうっていわれれば、それまでだけどね。
まあ、それはさておき、
原作のある映画、実話をもとにした映画、どちらにもいえることだけど、
映画がなにかに影響されたり感銘を受けたりして製作されるのは当たり前で、
その原作や実話の持っている主題は損なわないようにしなければならないけれど、
作品の内容は、別に原作や事実に忠実である必要は、これっぽちもない。
ただ、この映画の場合、かなり原作に沿ったもののようで、
原作者の英コラムニスト、ベンジャミン・ミーもずいぶん嬉しそうに取材を受けていた。
いちばん大きく異なっているのは、奥さんを脳腫瘍で亡くす時期だ。
動物園を買う前か、買ってからか、という違いで、でもそれは主題を決して損ねていない。
2006年10月、ダートムーア野生動物公園を購入したベンジャミンは、
翌年の7月に、ダートムーア動物学公園をオープンしたんだけど、
実際の奥さんキャサリンは、2007年3月31日に40歳で亡くなっている。
けど、映像化される際、奥さんの亡くなった時期にこだわる必要はない。
愛する者を亡くした家族にとって動物園をふたたび開園することは、
動物によるセラピーを受けているようにも感じられるけど、
それ以上に、
動物を愛している人達とのふれあいが大切な癒しになっているっていう図式は、
しっかりと主題に則したものになっているっておもうから。
にしても、たくさんの動物を使っての撮影は大変だったろうし、
なにより動物園を作らなくちゃいけない美術さんたちもたいそう苦労しただろう。
話はがらりと変わるんだけど、
小学生の頃、ぼくは、動物が好きだった。
ただし、動物そのものではなく、動物のフィギュアが好きで、たくさん集めていた。
ぼくの田舎には、山の上の公園に鹿と猿と鳥と小動物の檻があり、
とても動物園とはいえないような小さなものながら、いまだに飼育されている。
誰が動物たちの面倒を見ているのか知らないけれど、
もしかしたら、戦後まもない頃から何代にもわたって飼育されているのかもしれない。
ま、それはいいとして、そんなしょぼいものしかない田舎に育った僕は、
都会に出なければ、大々的な動物園なんて見ることも叶わなかった。
当然、動物に興味はなかったんだけど、ただ、手塚治虫の『ジャングル大帝』が好きだった。
そのせいで、動物のフィギュアを集め始めたんじゃないのかな、自信はないけど。
ともかく、そのフィギュアは何百匹にもおよび、それを並べると畳3畳分はゆうにあった。
このフィギュアは、当時、デパートでしか売ってなかったから、
母親の買い物についていくと、かならず数匹ずつ買ってもらった。
イギリスのブリテン社というところが作っていたもので、
まじまじと見惚れるほど正確な縮尺で出来ていた…ような気がしてた。
ところが、ある時期からマガイ物が出回るようになった。
デパートでは売られず、田舎のおもちゃ屋や夜店で扱われるもので、
動物のお腹を見ると、Hong Kong とあった。
これじゃダメなんだ、とおもっていたら、ときどき、また別なフィギュアが混じり始めた。
アメリカのサファリ社というところだった。
そこの頃には徐々に動物フィギュアへの興味も薄れてしまったんだけど、
おとなになってから海洋堂の動物フィギュアが登場したとき、
「ああ、懐かしい」
とおもって、あらためて動物フィギュアの世界を覗いた。
そしたら、ブリテン社は1999年に40年の歴史を閉じていたようで、
サファリ社とドイツのシュライヒ社をはじめ、いろんな国で製作されているのを知った。
けど、どの動物もなんだか顔が大きくて、やけに可愛らしくなっていた。
「ちがうんだよな~、これは」
もちろん、当時の動物とは比べ物にならないくらい精巧に出来てるんだけど、
1960年代の少年からすれば、なんだかしっくりこない。
ときどき、おもうんだ。
どこかの町の、時の流れに置き忘れられたような古ぼけた百貨店に、
あの日のようにガラスのショウケースに入れられた動物が並んでないかな~と。
そしたら、ぼくはまたこつこつと買い漁り、ぼくだけの動物園をつくりたいな~と。
なんてまあ、ちんまりした夢なんだろうね。