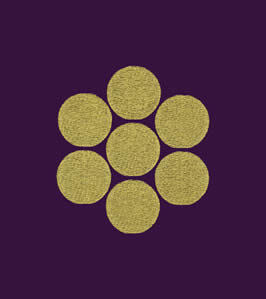☆危険なメソッド(2011年 イギリス、ドイツ、カナダ、スイス 99分)
原題 A Dangerous Method
staff 原作/クリストファー・ハンプトン『The Talking Cure』
舞台劇『A Most Dangerous Method』
監督/デイヴィッド・クローネンバーグ 脚本/クリストファー・ハンプトン
撮影/ピーター・サシツキー 美術/ジェームズ・マカティア キャロル・スピア
衣裳デザイン/デニス・クローネンバーグ 音楽/ハワード・ショア
cast キーラ・ナイトレイ マイケル・ファスベンダー ヴィゴ・モーテンセン
☆第一次世界大戦、前夜。
ほぼ、実話らしい。
父の子のような師弟関係あるいは信頼かつ尊敬しあえる精神科医同士だった、
カール・グスタフ・ユングとジークムント・フロイトの間に亀裂を走らせたのは、
患者であり、かつ新たな論文の起草者となるザビーナ・シュピールラインで、
この作品は、その常軌をやや逸した観にある三角関係を描いてる。
なんといっても、
キーラ・ナイトレイの顎突き出し分裂絶叫演技が凄いんだけど、
彼女の演じるザビーナが、
幼児期の父親による厳格な躾のせいで、性的な抑圧を抱え、
それによって総合失語症を患い、治癒させるためには性衝動の解放しかなく、
簡単にいってしまえば、
臀部をスパンキングされながらセックスにいたるという、マゾヒズムの解放しかなく、
このメソッドを行うのが、サディズムを目覚めさせてしまうユングだったって設定だ。
つまり、もともとユングも精神疾患を抱えてて、これを治癒させるには、
異常な性愛に溺れ、それで抑圧されてきた自我を解放させるしかなく、
要するに、ザビーナとの異常な関係を保ち続けなくちゃいけないわけだ。
もちろん、そういう診療と行為が事実かどうかは、このふたりにしかわからない。
でも、
貞淑な妻を愛しているユングはこの魅惑的なザビーナに溺れつつも葛藤し、
やがて見栄も外聞もかなぐりすててザビーナに関係の継続を哀願するんだけど、
ザビーナはフロイトのもとへ向かい、性的抑圧の解放について語るようになる。
このザビーナの行動が、ユングとフロイトを決裂させるわけだ。
本編の前後、タイトル部分は、流麗な筆致の手紙が拡大されたもので、
それはおそらく、ユングとフロイトが遣り取りした尊敬と罵倒とは想像できるものの、
映画が終わっても、明かされない。
明かされるのは、ザビーナがナチスの虐殺によって世を去ることくらいで、
こうしたところ、きわめて奥ゆかしい良識と節度を保った映画っていえる。
ただ、あれだよね、
ユングやフロイトがいかにも紳士然とした学者として登場し、
重厚な室内で会話を交わしているから、難解な議論に見えてしまうけど、
これが、都内のセルフサービスのカフェなんぞで、
TシャツにGパンみたいなラフな格好で、
「極度のストレスや小さい時からの呪縛を解放させるには、
自分がほんとはエッチが好きで、変態セックスにもちょっと興味があるんなら、
恥とか誇りとか、そんなものは棄てて、好きな相手とセックスすりゃいいじゃん。
幸せな人生を送りたいんだったら、自分に正直になるしかないんだよな~」
とかいってたら、きわめて下品で低俗な人間におもわれちゃうかもしれない。
ほんと、世の中ってのは虚飾に満ちてる。
それは、クローネンバーグもよくわかってて、
脇に、そういう人間像を配置してる。
たとえば、ユングの妻を演じたサラ・ガドンは、
湖のように青い目で、黄金のような長い髪をした、アーリア系の見本のようで、
夫の浮気も黙って堪えるという、いかにも貞淑な妻を演じているんだけど、
彼女による匿名の手紙が悲劇の引き金になっていることをおもえば、
心の中にはどすぐろい憎悪と嫉妬が渦巻いていることはよくわかるし、
それこそが人間なのだと断言されてる気もするし、
精神医にして患者のヴァンサン・カッセルが、
ユングに対して「自分に正直になれ」というのも、
一見、悪魔のささやきのようにも聞こえるけど、天使のみちびきのようでもあるのは、
人間にとって性欲というか情欲は死ぬまでつきまとって離れない存在で、
これを薄っぺらな紳士然あるいは淑女然として否定するから、
大なり小なりストレスという名の精神疾患に陥るわけで、
「くそったれ男やつまらない女に堕したくなければ、自己を解放することだな」
と、真正面から突きつけられるからだ。
まったく、クローネンバーグは正直に生きてる。
ちょっと、おぞましいけどね。