今年のノーベル文学賞は中国の莫言が受賞しました。欧米のメディアからも本命視されていた村上春樹が、ノーベル文学賞を逸した理由(わけ)とは何だったのでしょう? いや、そうした問いは違うのではないか。10月12日付の朝日新聞は、村上春樹がノーベル文学賞を逃した理由(わけ)ではなく、中国の莫言が受賞した理由(わけ)について、3面に大きく紙面を割いています。
莫言(ばく げん モー イェン)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8E%AB%E8%A8%80

ただし、莫言の受賞が意外だったとしているのではありません。莫言も最有力候補の一人と目されていたし、ほかにも大物は目白押し。ミラン・クンデラ(81)・ウンベルト・エーコ(78)・フィリップ・ロス(77)・コーマック・マッカーシー(77)・トマス・ピンチョン(73)・ジョイス・キャロル・オーツ(72)、そうそうボブ・ディラン(71)の名前も挙がってびっくりしましたが、誰が受賞してもおかしくありません。
失礼ながら存命中に顕彰されるべき「巨匠」たちに比べれば、莫言57歳に村上春樹61歳と、二人ともまだじゅうぶんに若いといえます(ノーベル賞は物故者に授与されません)。これからいくらでもチャンスがあるはずの二人に、最終候補は絞られたのはなぜか? 一言でいえば、中国の影響力がその背景にあった。朝日新聞記事はそう読むことができます(実際の選考過程がどうであったかは別にして)。
いや、中国が世界第二位の経済力を背景に、国際社会への発言力の大きさをノーベル賞の選考に及ぼした、というのではありません。オリンピックのメダル獲得競争と同様に、中国が国威発揚の一環として、ノーベル賞受賞に躍起となってロビー活動をしたというなら、国際社会にとってはむしろ慶賀すべきニュースでしょう。その反対のネガティブな影響力を中国は行使してきたようです。
朝日新聞の見出しは次のようでした。「文学賞 莫言氏受賞に歓喜」「中国、快挙どうアピール」。これがいわゆる大見出しです。中見出しで大きいのは、「天災と人災が出発点」。莫氏が子ども時代に体験した、農村の飢餓などの天災や文化大革命という人災が、氏の文学の出発点だったという履歴の紹介です。中間の小見出しには、「体制内作家との声も」とあります。
文化大革命や一人っ子政策など体制批判を含む作品もあるが、政府公認の中国作家協会の副主席の地位にあり、2年前にノーベル平和賞を授与されながら、いまも刑務所に閉じこめられたままの民主活動家の劉暁波について沈黙を続ける莫言に対して、「体制内作家」という批判があることを指摘するものです。
劉暁波(りゅう ぎょうは リュウ シャオボー)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%89%E6%9A%81%E6%B3%A2
ちょっと唐突な流れです。莫言の作品や文学観より、彼の政治的な立場を気にしています。つまり、この朝日の記事は、「中国、快挙どうアピール」という大見出しが語るように、中国の反ノーベル賞ともいえる姿勢を解説する国際政治記事でした。
1980年にチベット仏教会の最高指導者ダライ・ラマ14世にノーベル平和賞、2000年には文化大革命をきっかけにフランス国籍を取って出国した高行健にノーベル文学賞、そして2010年には民主活動家の劉暁波にノーベル平和賞。中国にとっては、「賞がよこしまな政治目的に使われていることをあらためて示した」(高行健受賞に対する中国政府談話)という受賞が続いたことになります。
高行健(こう こうけん ガオ シンジェン)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E8%A1%8C%E5%81%A5
したがって、中国はほとんど、アンチノーベル賞といえるほど、敵視に近い冷淡な態度をとってきました。その具体例を検証したのが、すぐ横に並んだ、「平和賞 2年前の授与に反発」「ノルウェーと亀裂、今も」との見出しの記事です。前記の劉暁波にノーベル平和賞を授与したノルウェーに対する、ほとんど国交断絶に近い中国の姿勢をまとめたものです(文学賞はスウェーデン・アカデミーが授与しますが、平和賞はノルウェーのノーベル賞委員会が決めるのですね)。
ノルウェーの前首相に入国ビザを発行しなかったり、ノルウェー産サーモンの通関規制を強化してその輸出を6割減にしたり、中国の報復と嫌がらせは現在も続いていて、対話の機会がないために改善の糸口さえ見えないそうです。中国からいえば、ダライ・ラマ14世と劉暁波にノーベル平和賞を授与するなど、政治的な攻撃を受けたのだから、報復するのはあたりまえということでしょう。
さて、そのように読んでいくと、この朝日新聞記事の意図は明らかです。莫言のノーベル文学賞受賞は、国際社会が中国へ配慮したもの、中国の人権や平和に対する強圧的な姿勢にある譲歩を示した、欧米の宥和政策のひとつではないか。そんなことは一言も書いていないけれど、あながちうがった読み方ではないはずです。この「ノルウェー記事」の最後は、こう締めくくられています。
中国の外交に対しては、在北京の外交官の間に「世論の弱腰批判を恐れるあまり、相手国が譲歩しないと緊張関係を変えられな」と硬直化の懸念も広がる。
とすれば皮肉なことに、やはり中国が批判するとおり、ノーベル賞は政治目的によって決定されることを裏づけたことになります。もちろん、欧米を中心とする国際社会には、人権や平和を普遍的な価値とする民主政を批判される理由(いわれ)はないでしょう。しかし、尖閣諸島をめぐり日中間に緊張が高まっているこの時期に、村上春樹を対抗馬として莫言に受賞させるのは、あまりにも政治目的と思えるのは、日本人のやっかみでしょうか。
言い遅れましたが、莫言はもちろん、村上春樹もその長編小説は一冊も読んだことはありません(村上春樹の短編は何篇か読みました。エッセイや翻訳はよいと思っています)。読んだことはありませんが、村上春樹がノーベル賞をとれない理由として、その非政治的な非社会問題的なテーマを取りざたされていることには、少し疑問を感じます。農村の飢餓や文化大革命を扱えば政治的な小説で、缶ビールを片手にビートルズを聴きながら彼女について考える小説をミーハー小説というなら、そりゃ政治の位相が違うだろうと思うのです。
最後に。莫言というペンネームは、「言う莫(なか)れ」からきているそうです。人権と平和を弾圧する体制内にとどまり創作活動を続けていることは、その作品が村上春樹のいう「壁」にぶつかって潰れる「卵」側に立つ限り、尊敬に値するものでしょう。国家権力によって、若い同志を幾人も無残に殺され、幾たびも命の危険にさらされた魯迅も、国を出ることはなく、出ようとしたこともなかったのでした。莫言と中国の皆さん、ノーベル文学賞の受賞おめでとうございます。
(敬称略)
莫言(ばく げん モー イェン)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%8E%AB%E8%A8%80

ただし、莫言の受賞が意外だったとしているのではありません。莫言も最有力候補の一人と目されていたし、ほかにも大物は目白押し。ミラン・クンデラ(81)・ウンベルト・エーコ(78)・フィリップ・ロス(77)・コーマック・マッカーシー(77)・トマス・ピンチョン(73)・ジョイス・キャロル・オーツ(72)、そうそうボブ・ディラン(71)の名前も挙がってびっくりしましたが、誰が受賞してもおかしくありません。
失礼ながら存命中に顕彰されるべき「巨匠」たちに比べれば、莫言57歳に村上春樹61歳と、二人ともまだじゅうぶんに若いといえます(ノーベル賞は物故者に授与されません)。これからいくらでもチャンスがあるはずの二人に、最終候補は絞られたのはなぜか? 一言でいえば、中国の影響力がその背景にあった。朝日新聞記事はそう読むことができます(実際の選考過程がどうであったかは別にして)。
いや、中国が世界第二位の経済力を背景に、国際社会への発言力の大きさをノーベル賞の選考に及ぼした、というのではありません。オリンピックのメダル獲得競争と同様に、中国が国威発揚の一環として、ノーベル賞受賞に躍起となってロビー活動をしたというなら、国際社会にとってはむしろ慶賀すべきニュースでしょう。その反対のネガティブな影響力を中国は行使してきたようです。
朝日新聞の見出しは次のようでした。「文学賞 莫言氏受賞に歓喜」「中国、快挙どうアピール」。これがいわゆる大見出しです。中見出しで大きいのは、「天災と人災が出発点」。莫氏が子ども時代に体験した、農村の飢餓などの天災や文化大革命という人災が、氏の文学の出発点だったという履歴の紹介です。中間の小見出しには、「体制内作家との声も」とあります。
文化大革命や一人っ子政策など体制批判を含む作品もあるが、政府公認の中国作家協会の副主席の地位にあり、2年前にノーベル平和賞を授与されながら、いまも刑務所に閉じこめられたままの民主活動家の劉暁波について沈黙を続ける莫言に対して、「体制内作家」という批判があることを指摘するものです。
劉暁波(りゅう ぎょうは リュウ シャオボー)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8A%89%E6%9A%81%E6%B3%A2
ちょっと唐突な流れです。莫言の作品や文学観より、彼の政治的な立場を気にしています。つまり、この朝日の記事は、「中国、快挙どうアピール」という大見出しが語るように、中国の反ノーベル賞ともいえる姿勢を解説する国際政治記事でした。
1980年にチベット仏教会の最高指導者ダライ・ラマ14世にノーベル平和賞、2000年には文化大革命をきっかけにフランス国籍を取って出国した高行健にノーベル文学賞、そして2010年には民主活動家の劉暁波にノーベル平和賞。中国にとっては、「賞がよこしまな政治目的に使われていることをあらためて示した」(高行健受賞に対する中国政府談話)という受賞が続いたことになります。
高行健(こう こうけん ガオ シンジェン)
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E8%A1%8C%E5%81%A5
したがって、中国はほとんど、アンチノーベル賞といえるほど、敵視に近い冷淡な態度をとってきました。その具体例を検証したのが、すぐ横に並んだ、「平和賞 2年前の授与に反発」「ノルウェーと亀裂、今も」との見出しの記事です。前記の劉暁波にノーベル平和賞を授与したノルウェーに対する、ほとんど国交断絶に近い中国の姿勢をまとめたものです(文学賞はスウェーデン・アカデミーが授与しますが、平和賞はノルウェーのノーベル賞委員会が決めるのですね)。
ノルウェーの前首相に入国ビザを発行しなかったり、ノルウェー産サーモンの通関規制を強化してその輸出を6割減にしたり、中国の報復と嫌がらせは現在も続いていて、対話の機会がないために改善の糸口さえ見えないそうです。中国からいえば、ダライ・ラマ14世と劉暁波にノーベル平和賞を授与するなど、政治的な攻撃を受けたのだから、報復するのはあたりまえということでしょう。
さて、そのように読んでいくと、この朝日新聞記事の意図は明らかです。莫言のノーベル文学賞受賞は、国際社会が中国へ配慮したもの、中国の人権や平和に対する強圧的な姿勢にある譲歩を示した、欧米の宥和政策のひとつではないか。そんなことは一言も書いていないけれど、あながちうがった読み方ではないはずです。この「ノルウェー記事」の最後は、こう締めくくられています。
中国の外交に対しては、在北京の外交官の間に「世論の弱腰批判を恐れるあまり、相手国が譲歩しないと緊張関係を変えられな」と硬直化の懸念も広がる。
とすれば皮肉なことに、やはり中国が批判するとおり、ノーベル賞は政治目的によって決定されることを裏づけたことになります。もちろん、欧米を中心とする国際社会には、人権や平和を普遍的な価値とする民主政を批判される理由(いわれ)はないでしょう。しかし、尖閣諸島をめぐり日中間に緊張が高まっているこの時期に、村上春樹を対抗馬として莫言に受賞させるのは、あまりにも政治目的と思えるのは、日本人のやっかみでしょうか。
言い遅れましたが、莫言はもちろん、村上春樹もその長編小説は一冊も読んだことはありません(村上春樹の短編は何篇か読みました。エッセイや翻訳はよいと思っています)。読んだことはありませんが、村上春樹がノーベル賞をとれない理由として、その非政治的な非社会問題的なテーマを取りざたされていることには、少し疑問を感じます。農村の飢餓や文化大革命を扱えば政治的な小説で、缶ビールを片手にビートルズを聴きながら彼女について考える小説をミーハー小説というなら、そりゃ政治の位相が違うだろうと思うのです。
最後に。莫言というペンネームは、「言う莫(なか)れ」からきているそうです。人権と平和を弾圧する体制内にとどまり創作活動を続けていることは、その作品が村上春樹のいう「壁」にぶつかって潰れる「卵」側に立つ限り、尊敬に値するものでしょう。国家権力によって、若い同志を幾人も無残に殺され、幾たびも命の危険にさらされた魯迅も、国を出ることはなく、出ようとしたこともなかったのでした。莫言と中国の皆さん、ノーベル文学賞の受賞おめでとうございます。
(敬称略)











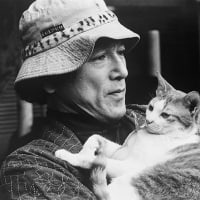

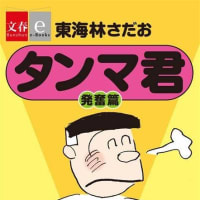












」で検索すればトップで出ると思います。
http://business.nikkeibp.co.jp/article/world/20121014/238029/?rt=nocnt
ノーベル賞の選考に政治的意図があるのは明らかですが、そして宥和政策という面だってあるのかもしれないけど、それだけで勝たれるような単純な意図ではなさそうですね。
語れる → 勝たれる