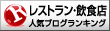「天璋院篤姫」では篤姫の視点からの和宮降嫁の様子が描かれていたので、では和宮の側から見るとどうなるのだろうと「和宮様御留」を読んでみました。
しかしこれは、和宮が実は身代わりだったという物語でした。
フキはみなしごだが明るく働き者の、京都の武家屋敷に勤める下女であった。
ある日、和宮の母の観行院の目にとまり、おそらく年頃と背格好が同じ位という理由で京都御所に連れて行かれる。
何の説明もなく綺麗な着物を着せられ、和宮と同じ部屋で寝起きすることになり、戸惑いながらも和宮の所作を覚えていく。
突然、和宮がいなくなったことに気が付いたフキは、自分の世話係の省進に尋ねる。
”「宮さん何処へ行かはったん」
(省進は)フキを肩から抱き寄せて、自分の胸の中にフキの顔を押し付け、しばらく背中を撫でていたが、やがて身を離すと、一語一語ゆっくりとフキに向かって話し出した。
「宮さん、どうぞどうぞ、お心沈めて頂かされ。なんのなんのご心配さんもあらしゃりませぬ。この省進が、お傍から片時離れませぬよって、ご安心遊ばされ」(中略)
「それで、宮さんは」
「冗談仰せ遊ばされるものではござりませぬ。省進がこうしてお傍にお付きしている御方が、宮さんであらしゃりますのに」”
フキはこうして和宮の身代わりとなるが、読み書きもできず、お茶の手前どころか食事の作法もなってない。
不安でたまらないうちに江戸へ出発することになり、四六時中いつも傍にいた省進が10日間ほどいなくなる。
フキは食べられなくなり眠れなくなり、遂に発狂する。
慌てた周りの者がしたことは…
攘夷か開国か、幕府か朝廷かに揺れる国情を納めるために、公武合体という大義の元に、将軍の元に降嫁を決められる和宮、何の説明もなく替え玉にされる下女フキ。
明るくクルクルと働いていたフキが御所の奥に押し込められ、人格どころか存在そのものを無視され、次第に精神の均衡を失っていく様が、克明に書かれています。
あとがきで著者が、この作品を平洋戦争と重ね合わせたと言っているのに驚きました。
「みな犠牲者だった。フキは赤紙一枚で招集され、何も知らされないまま軍隊に叩き込まれ、適性をもたぬままに狂死した若者たちと変わらない」と。
徳川14代将軍家茂に嫁ぐ皇女和宮「降嫁」の大行列は、50Kmの長さになったと。
先頭が江戸城に到着しても、尻尾はまだ八王子にいたということになります。
公家や護衛の武士、荷物を運ぶ人足など2万人の大行列が、京都から江戸まで25日間かけて中山道を進んだということです。
なんという無駄な贅沢をしたことか。
「天璋院篤姫」も「和宮様御留」も、この時代の女性たちが「道具」でしかなかったことを描いている点は同じでした。