足らざるを 補うことが なによりも 先に補う ことこそ常道
■ 伊東清
伊東清
【金融資本原理主義の幕引き】
「価格のわからない金融商品を、価格のわかっ
ている金融商品で複製する。それによって元の
金融商品の価格が無裁定原理によって求まる」
というのが数理ファイナンスの基本的な考え方
が裁定されようとしている。
米証券取引委員会(SEC)とニューヨーク証券
取引所(NYSE)などを運営するNYSEユーロネ
クストの規制部門は4日、米金融大手ゴールド
マン・サックス・グループの一部門ゴールドマ
ン・サックス・アンド・カンパニーの証券部門
に対して株式の空売り規則に違反したとして罰
金を科したという。NYSE規制部門からの通達に
よると、2008年12月から2009年1月の間、ゴール
ドマンの株式執行決済部門が、顧客が保有して
いた空売りのポジションを買い戻すための十分
な株式を調達していなかった、とされている。
ゴールドマンが何百件もの株式の空売り注文を
継続して受けたことで事態が深刻化したという。
派生商品の価格などを考えるときに何故この理
論が使えるのかの理由は「派生商品というもの
は基本的に原資産との関係で価格、あるいはキ
ャッシュ・フローが決まる資産であり、一般に
原資産とその他の金利系の資産等を組合わせて
保有することにより複製(実質的に同じもの)
が可能と考えられるからである」による。![]()
裁定取引は原理的に言って、2つの資産の組合
わせとして行われるので、基本的にこれが可能
になるためには、将来同じキャッシュ・フロー
を生む現在価値の異なる資産、あるいは現在価
値が同じで将来の同一時点で異なるキャッシュ・
フローが確実に発生する資産が必要になる。派
生商品の上記のような性質から、複製ポートフ
ォリオとの間でこのような裁定取引のスキーム
を考えることができ、よってその現在価値は複
製ポートフォリオの価値と一致しなければなら
ない、という考え方が適用できることになると
されるが、通常の金融資産(株式)などは、そ
れと同じキャッシュ・フローを生む複製ポート
フォリオを考えることは難しい。よってプライ
シング原理として無裁定理論は基本的に使いに
くいとされる。 Wiener process
Wiener process
A demonstration of Brownian scaling, showing ![]()
for decreasing c. Note that the average features of
the function do not change while zooming in,
and note that it zooms in quadratically faster
horizontally than vertically.![]()
つまるところ、確率微分方程式を原理主義の拠
り所とした「無裁定永久機関」の誘導的な夢は
水泡に帰そうとしている現場に、曲げれもなく
立ち会っていることだ。そのことは、「ギリシ
ャの危機を扇動しているのが、ゴールドマンサ
ックスやJPモルガンといった米国の投資銀行
的な勢力と、S&Pなど米英の格付け機関である
ことだ。彼らは、ドルやポンドの危機を回避す
るために、ドルやポンドより先にユーロを潰そ
うとしている。ギリシャ国債を売ってギリシャ
の危機がひどくなっているように演出しつつ、
英米などのマスコミも動員して投資家の不安を
煽り、時機を見てS&Pがギリシャ国債を格下げし、
危機を激化させている」とする田中宇好みの機
能主義的帰結(「ユーロ危機はギリシャでなく
ドイツの問題」2010/04/30)(“Goldman role in
Greek crisis probed”)(“Special relationship between
UK and US is over, MPs say”)(“Euro Sales Extend
as Morgan Stanley Mulls EU Breakup (Update3)”)
の陰謀説はやがて『ダビンチ・コード』と一緒
くたにされるとしても、汲み取る<事実>対象は
明確だ。
つまり、「毎晩1本二百万円もするワインをの
み干しながら、デリバティブ商品を開発し拡販
する行動」の根っ子を問うてみても虚しい。世
界の総GDPが5,400兆円(2007年)、過剰流動総額
が66,940兆円(デリバティブ総額51,640兆円、77%)
で約8%に過ぎない(残りは債権、株式、先物商
品)からだ(※「国際投資顧問」)。寧ろ、米
証券取引委員会( SEC )が要求する「開示性」
に対する英米金融資本運営企業集団が「隠匿性」
に拘る<保守性>にある。その最後の拠り所の完
全放棄が「市場の停滞」を招くのであれば、市
場調整機構の過剰を解かねばならぬが、運用方
法や技術が問題というのであればやりようがあ
るというものだ。その意味において、従来の英
米の金融・市場原理主義の幕引きと、IMF改
革や世界銀行機構改革は最優先課題と考える。
■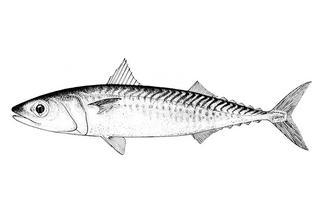
【ゴマサバは元祖寿司】
ゴマサバ(胡麻鯖)、学名 Scomber australasicus
は、スズキ目・サバ科に分類される魚の一種。
太平洋の熱帯・亜熱帯海域に分布する海水魚で
ある。日本では食用魚として重要で、近縁のマ
サバ、グルクマ等と共に「サバ」と総称される。
地方名としてマルサバ(各地)、ホシグロ(新
潟)、ゴマ(千葉)、コモンサバ(島根)、ド
ンサバ(福岡)などがある。日本近海を含む、
太平洋の暖流に面した熱帯・亜熱帯海域に広く
分布する。マサバより高温を好み、日本近海で
も夏に漁獲量が増える。沿岸域の表層で大群を
作り遊泳する。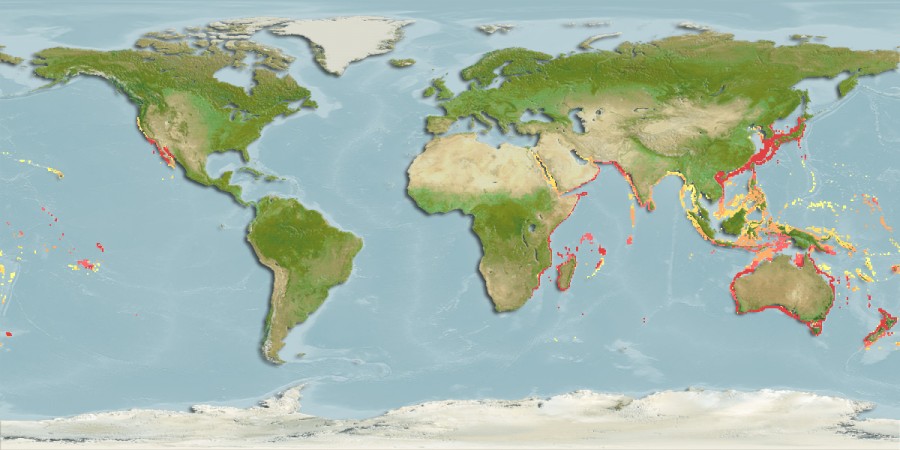
食性は肉食性で、動物プランクトン、小魚、頭
足類など小動物を捕食する。産卵期は春で、マ
サバより産卵期が早い。マサバより脂肪が少な
いが、季節的な味の変化が少ないとされている。
夏はマサバの味が落ちるがゴマサバの味は落ち
ず、漁獲量も増える。鯖節への利用が多いが、
他にもマサバと同様に〆鯖(きずし)、鯖寿司、
焼き魚、煮付け、唐揚げ、缶詰など幅広い用途
に利用される。新鮮なものは刺身でも食べられ
るが傷みが早いので要注意。高知県土佐清水市
の清水サバ、鹿児島県屋久島の首折れ鯖など、
各地に地域ブランドがある。
真鯖より脂が少ないく上品な胡麻鯖の棒寿司は日
本一だろう。畜養から完全養殖にはもう少し時間
がかかるかも知れないが、工夫次第では健康食品
として世界に『寿司の王様』として普及していく
だろう。
■

















