朝早く 怯える母の 横顔を 見送る朝の ショートスティ
■![]() 北本宏子
北本宏子
【バイオエタノールのその後】
特許:特開2009-213440「アルコールの製造方法」
試験菜園の二年目となり、玉蜀黍(1品種)、
ゴーヤ(1品種)、ナスビ(4品種)、トマ
ト(3品種)の4種類に日照時間を4時間に
絞り『セカンド・ランド農法』の観察を開始
した。ところで、去年の旧聞だが独立行政法
人「農業環境技術研究所」が、セルロース系
バイオマスを収穫後、貯蔵しながら糖化・エ
タノール発酵をする、今までにないバイオエ
タノール「固体発酵法」を開発したという。
これによると、酵素や微生物が持つ自然な力
を利用する日本古来の醸造技術と、国産飼料
の生産利用技術を応用した「農業・醸造型バ
イオエタノール生産技術」。加熱処理等の工
程が少ないため、使用するエネルギーを低く
抑えることができるとのこと。.jpg)
この手法では通常のバイオエタノール生産濃
度の1.6倍の8%の収量で酵素量を抑え、百円
/Lでエタノールを生産する目標値だというが
酵素購入費が結構するので使用量を1/10に抑
えたという。やはり酵素製造費用のコストダ
ウンが隘路になっている。 臭化メチル
臭化メチル
もう1つアルコール纏わる興味深い情報があ
った。それは、人間が作り出したフロンガス
などでオゾン破壊されるが、臭化メチルとい
う農薬 (土壌消毒剤) にも同様な性質があ
ることがわかり、「モントリオール議定書」
でよって使用が規制された。この代替薬品と
してエタノールが有効だと、農業環境技術研
究所の研究だ分かったという(「農業と環境
」No.119、(2010年3月1日)。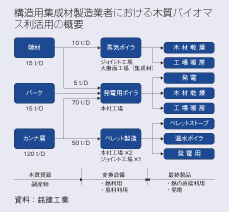
それによると、消毒液としてのアルコールは、
約80%の濃さで効果が一番高いが、濃いアル
コールは霧状にするとすぐに蒸発し、費用が
嵩む。通常の殺菌効果が得られない薄いアル
コール(濃度1%以下)を散布し蒸発防ぐた
めに農業用ポリエチレンシートで覆うことで、
2週間置いただけで、病原性の細菌、糸状菌
(カビ)、線虫、土壌害虫、雑草の発生が抑
えられたという。
低濃度のアルコールに防除効果がある理由は
わかっていないが、薄いアルコールで浸され
ることで土壌中の環境が酸素の多い好気的な
状態から酸素のない嫌気的な状態に変化し、
有機酸が増加するのが理由の一つだろうと推
察されている。除菌などの消毒にエタノール
が使えるならバイオエタノールの濃縮は不要
(搬送費が嵩むが)となる。
ところで、『セカンド・ランド農法』での消
毒はオゾン及びオゾン水を基本に考えている
(消毒効果と空気即ち土壌への酸素・窒素注
入による好気処理による土壌改質を兼ねてい
る)が、土壌の中の微生物 (細菌やカビなど
)が、土壌有機物を分解して二酸化炭素を出
し、植物の根から二酸化炭素が放出され、こ
れを土壌呼吸と呼ぶ。つまり、土壌呼吸を含
む農耕地の炭素循環は、大気中の炭素 (二酸
化炭素)は光合成によって作物に取り込まれ、
作物の呼吸により大気に戻り、残りは作物内
に蓄積される。収穫後の茎や葉、あるいは根
などの作物残渣がそのまますき込まれたり、
あるいは堆肥として施用されると、作物中に
あった炭素は土壌有機物として土の中に蓄積
されます。この土壌有機物が土壌微生物によ
って分解されると、炭素は二酸化炭素として
大気へ放出される。このようにして炭素は大
気、作物、土壌の間を循環している。.jpg)
温暖化が進んだ場合、温度の上昇によって農
耕地土壌の微生物が活発に働き、土壌呼吸に
より二酸化炭素が大量に放出される心配があ
り、土壌は地球上で海洋に次いで2番目に大
きい炭素貯留庫で、大気中の約2倍、森林な
ど植物バイオマスの約3倍もの炭素を蓄積し
土壌がたくわえている炭素の約10%が農耕地
土壌にあるという。
もう少し言うと、この土壌には自然界の衝撃
(ストレス)をやわらげる緩衝作用があり、
作物の生育を守っている。薄い塩酸(酸性)
または水酸化ナトリウム(アルカリ性)をほ
んの少し入れると、水のpH値は大きく変化す
るが、前もって水の中に土を混ぜておくと、
pH値はほとんど変わらない。これは土にイオ
ンを吸着するはたらきがあり、化学的な緩衝
作用を持ち、例え酸性雨が降っても、土のpH
値が大きく酸性に傾くことなく、作物の根が
守られている。
また、保水性や空気含有性を有し、大雨で土
が水びたしになっても、土の中の水は一定の
量に落ち着き、空気と水のバランスが保たれ
る。逆に、しばらく雨が降らなくても土はあ
る程度の水分量を維持して、作物の根に水を
供給し、土に植えた作物は枯れず、土壌には
物理的な緩衝作用がある。
さらに、土の中にはカビやバクテリアなど数
千から1万種類の土壌微生物が住み、1グラ
ムの土の中には1億個体以上の微生物がひし
めき合って、これらの微生物のうち特定の種
類だけが増えすぎたり、またいくつかの種が
絶滅したりすることはほとんどなく、一定の
バランスが保たれ、個々の微生物が、自らの
住み心地に合った場所を選択するという生物
的な緩衝作用としてはたらくといわれている。
■
【鮪と鰹と須磨】
スマ(須萬)、学名 Euthynnus affinis は、スズ
キ目・サバ科に分類される海水魚の一種。イ
ンド太平洋の熱帯・亜熱帯域に広く分布する
大型肉食魚で、食用にもなる。地方名として
ワタナベ(千葉)、スマガツオ(東京)、キ
ュウテン(八丈島)、ヤイト(西日本各地)、
ヤイトマス(和歌山)、ヤイトバラ(近畿)
などがある。成魚は全長1m・体重10kgに達す
る。体型はカツオなどと同様の紡錘形で、鱗
は目の後部・胸鰭周辺・側線周辺にしかない。
カツオと違って腹側に縞模様は出ず、背中後
半部に斜めの黒い帯模様が多数走る。また、
生体では胸鰭の下に1~7個の黒い点が出るの
が特徴で、西日本での呼称「ヤイト」はこの
黒点を灸の跡になぞらえたものである。ただ
しこの黒点は死ぬと消えてしまう。
全長10cm程度の幼魚は細長い体型で、黒っぽ
い横帯模様が約12条ある。他の類似種にはヒ
ラソウダ、マルソウダ、ハガツオなどがいる
が、スマの成魚はこれらより体高が高い。日
本の本州中部以南からハワイ、オーストラリ
ア北部、アフリカ東岸まで、インド洋と西太
平洋の熱帯海域に広く分布する。カツオほど
の大群は作らず、単独か小さな群れで行動す
る。また、沿岸性が強く、若魚は内湾に入る
こともある。
図 世界の漁獲高
食性は肉食性で、魚、甲殻類、頭足類などを
捕食する。カツオ、マグロ、シイラ等を狙っ
た釣りや延縄で漁獲される他、定置網などの
沿岸漁業でも獲れる。身はカツオに似た赤身
で、刺身、焼き魚などで食べられる。食用以
外にマグロやカジキ等の釣り餌として使われ
ることもある。刺身は鮪や鰹と遜色なく美味
いといわれるが、鰹と間違えられやすい。養
殖の情報は知らない。
■

















