都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「日本画の挑戦者たち―大観・春草・古径・御舟―」 山種美術館
山種美術館
「日本美術院創立120年記念 日本画の挑戦者たち―大観・春草・古径・御舟―」
9/15~11/11

山種美術館で開催中の「日本画の挑戦者たち―大観・春草・古径・御舟―」の特別内覧会に参加してきました。
1898年、東京美術学校を辞職した岡倉天心は、新たな時代の日本画を探求すべく、大観をはじめとした画家とともに、日本美術院を創立しました。
その日本美術院の120年を祝して行われているのが、「日本画の挑戦者たち」で、草創期の横山大観、菱田春草、小林古径、速水御舟をはじめ、戦後の小倉遊亀や片岡球子、それに現代の田渕俊夫や宮𢌞正明などの作品を網羅し、同院の長きに渡る制作の歴史を辿っていました。

小林古径「猫」 昭和21年 山種美術館
冒頭は猫がお出迎えです。それが古径の「猫」で、やや畏まった様子で座る猫を、真正面から描いていました。白く身体は美しく、気品があり、確かに「仏画のような荘厳さ」(解説より)が感じられるかもしれません。古径は、大正後期に渡欧した際、エジプトのバステト神の猫を写生しましたが、四肢を揃えて座る姿が、この作品と共通するとも指摘されています。

横山大観「燕山の巻」(部分) 明治43年 山種美術館
大観の画巻に力作がありました。横へ長く連なるのが「燕山の巻」で、明治43年の中国旅行の体験をもとに、同地の風景を「燕山・楚水の巻」の2巻1組に表しました。「燕山の巻」は、北京の城壁や万里の長城などを描いていて、瑞々しい水墨によって、中国の山々や樹々、そして建物の並ぶ風景を、牧歌的に表現していました。

下村観山「不動明王」 明治37年頃 山種美術館
下村観山の「不動明王」も興味深い作品でした。ちょうど明王が直線上に飛来する様子を表していますが、よく目を凝らすと、隆々とした筋肉で、陰影があり、西洋絵画の描法を思わせるものがありました。

菱田春草「雨後」 明治40年頃 山種美術館
春草の「雨後」に魅せられました。山の裾から下方で落ちる滝の光景を表していて、全てはぼんやりとしていて、全体を捉えきれません。いわゆる朦朧体による作品で、水の冷ややかな質感や、湿潤に満ちた大気などを表していました。また山の際が、樹木の連なる様子を示すためか、細かい斑点のような筆触で描かれているのも、目を引くかもしれません。

小林古径「清姫」(一部) 昭和5年 山種美術館
古径の「清姫」が1つのハイライトかもしれません。紀州の道明寺伝説に取材した連作で、物語を8面にして表しました。全8点が一度に公開されるのは、約5年ぶりのことでもあります。

速水御舟「牡丹花(墨牡丹)」 昭和9年 山種美術館
御舟では「牡丹花(墨牡丹)」が絶品でした。黒い花弁を幾重にも重ねた牡丹を、たっぷりと墨を含んだ筆で描いていて、花の柔らかい質感までが伝わってくるかのようでした。また蕊は金で描き込まれていて、仄かに輝いていました。これほどはかなく見える花の絵も、そう滅多にないかもしれません。

小茂田青樹「春庭」 大正7年 山種美術館
小茂田青樹の「春庭」も美しい作品でした。縦長の画面の左右に、桜と椿を描いていて、その合間に小道が奥へと続いていました。桜は既に見頃を終えたのか、花びらを落とし、小道に積もっていました。何気ない戸外の景色ながらも、幻想的な雰囲気も漂っていて、フランスの画家、シダネルを風景画を思い起こしました。

田渕俊夫「輪中の村」 昭和54年 山種美術館
この風景画に思いがけないほど引かれた作品がありました。それが、現在、日本美術院の代表理事を務める田渕俊夫の「輪中の村」で、木曽川と長良川に囲まれた輪中の農村を描きました。
家々や田畑、それに高圧線の鉄塔などは、ほぼ一面のモノトーンで覆われている一方、中央の白いビニールハウスと、その周囲のエメラルドグリーンの田畑のみ、色彩を伴って描かれていました。いずれも写実的でありながら、何やら白昼夢を前にしているかのようで、不思議と風景にのまれるような感覚に陥りました。なお空は、くしゃくしゃにしたアルミ箔を紙に貼って表しているそうです。

岩橋英遠「瑛」 昭和52年 山種美術館
まばゆい陽の光が大地に降り注ぐ、岩橋英遠の「瑛」も魅惑的ではないでしょうか。一羽の鳥が横切っていて、朱色に染まる棚田は、神々しいほどに輝いていました。

速水御舟「名樹散椿」 昭和4年 山種美術館
さて会期も中盤を過ぎました。10月16日に御舟の一部の作品が入れ替わり、重要文化財の「名樹散椿」の公開がはじまりました。私も改めて見てきました。

速水御舟「名樹散椿」(部分) 昭和4年 山種美術館
「名樹散椿」は、当時で樹齢400年に達した、京都の昆陽山地蔵院の椿を金地に描いた作品で、枝の屈曲を強調し、図像的に表した葉などは、琳派的なデザインを思わせるものがありました。とはいえ、花はかなり写実的で、一時、質感表現を追求した、御舟の1つの到達点としても知られています。昭和52年には、昭和以降の日本画として初めて重要文化財に指定されました。
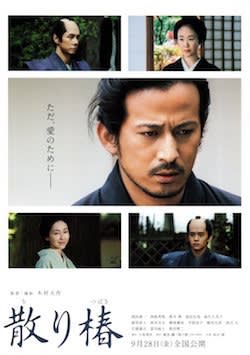
映画「散り椿」@chiritsubaki928
http://chiritsubaki.jp
最近、改めて「名樹散椿」が注目される機会がありました。それが、9月28日より公開中の映画、「散り椿」(木村大作監督)で、葉室麟の原作の表紙に、「名樹散椿」が使われました。
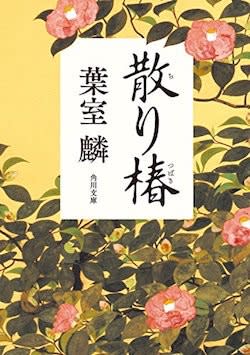 「散り椿/葉室麟/角川文庫」
「散り椿/葉室麟/角川文庫」
実際のところ、本作も、映画「散り椿」の公開に合わせ、特別に出品されました。またこの「名樹散椿」のみ、一般会期中も撮影が出来ます。(動画、フラッシュ、自撮り棒や三脚は不可。)
11月11日まで開催されています。
「企画展 日本美術院創立120年記念 日本画の挑戦者たち ―大観・春草・古径・御舟―」 山種美術館(@yamatanemuseum)
会期:9月15日(土)~11月11日(日)
休館:月曜日。但し9/17(月)、24(月)、10/8(月)は開館。9/18(火)、25(火)、10/9(火)は休館。
時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。
料金:一般1000(800)円、大・高生800(700)円、中学生以下無料。
*( )内は20名以上の団体料金。
*きもの割引:きもので来館すると団体割引料金を適用。
*リピーター割:使用済み有料入場券を提示すると団体割引料金を適用。
住所:渋谷区広尾3-12-36
交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。渋谷駅東口より都バス学03番「日赤医療センター前」行きに乗車、「東4丁目」下車、徒歩2分。
注)写真は特別内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。
「日本美術院創立120年記念 日本画の挑戦者たち―大観・春草・古径・御舟―」
9/15~11/11

山種美術館で開催中の「日本画の挑戦者たち―大観・春草・古径・御舟―」の特別内覧会に参加してきました。
1898年、東京美術学校を辞職した岡倉天心は、新たな時代の日本画を探求すべく、大観をはじめとした画家とともに、日本美術院を創立しました。
その日本美術院の120年を祝して行われているのが、「日本画の挑戦者たち」で、草創期の横山大観、菱田春草、小林古径、速水御舟をはじめ、戦後の小倉遊亀や片岡球子、それに現代の田渕俊夫や宮𢌞正明などの作品を網羅し、同院の長きに渡る制作の歴史を辿っていました。

小林古径「猫」 昭和21年 山種美術館
冒頭は猫がお出迎えです。それが古径の「猫」で、やや畏まった様子で座る猫を、真正面から描いていました。白く身体は美しく、気品があり、確かに「仏画のような荘厳さ」(解説より)が感じられるかもしれません。古径は、大正後期に渡欧した際、エジプトのバステト神の猫を写生しましたが、四肢を揃えて座る姿が、この作品と共通するとも指摘されています。

横山大観「燕山の巻」(部分) 明治43年 山種美術館
大観の画巻に力作がありました。横へ長く連なるのが「燕山の巻」で、明治43年の中国旅行の体験をもとに、同地の風景を「燕山・楚水の巻」の2巻1組に表しました。「燕山の巻」は、北京の城壁や万里の長城などを描いていて、瑞々しい水墨によって、中国の山々や樹々、そして建物の並ぶ風景を、牧歌的に表現していました。

下村観山「不動明王」 明治37年頃 山種美術館
下村観山の「不動明王」も興味深い作品でした。ちょうど明王が直線上に飛来する様子を表していますが、よく目を凝らすと、隆々とした筋肉で、陰影があり、西洋絵画の描法を思わせるものがありました。

菱田春草「雨後」 明治40年頃 山種美術館
春草の「雨後」に魅せられました。山の裾から下方で落ちる滝の光景を表していて、全てはぼんやりとしていて、全体を捉えきれません。いわゆる朦朧体による作品で、水の冷ややかな質感や、湿潤に満ちた大気などを表していました。また山の際が、樹木の連なる様子を示すためか、細かい斑点のような筆触で描かれているのも、目を引くかもしれません。

小林古径「清姫」(一部) 昭和5年 山種美術館
古径の「清姫」が1つのハイライトかもしれません。紀州の道明寺伝説に取材した連作で、物語を8面にして表しました。全8点が一度に公開されるのは、約5年ぶりのことでもあります。

速水御舟「牡丹花(墨牡丹)」 昭和9年 山種美術館
御舟では「牡丹花(墨牡丹)」が絶品でした。黒い花弁を幾重にも重ねた牡丹を、たっぷりと墨を含んだ筆で描いていて、花の柔らかい質感までが伝わってくるかのようでした。また蕊は金で描き込まれていて、仄かに輝いていました。これほどはかなく見える花の絵も、そう滅多にないかもしれません。

小茂田青樹「春庭」 大正7年 山種美術館
小茂田青樹の「春庭」も美しい作品でした。縦長の画面の左右に、桜と椿を描いていて、その合間に小道が奥へと続いていました。桜は既に見頃を終えたのか、花びらを落とし、小道に積もっていました。何気ない戸外の景色ながらも、幻想的な雰囲気も漂っていて、フランスの画家、シダネルを風景画を思い起こしました。

田渕俊夫「輪中の村」 昭和54年 山種美術館
この風景画に思いがけないほど引かれた作品がありました。それが、現在、日本美術院の代表理事を務める田渕俊夫の「輪中の村」で、木曽川と長良川に囲まれた輪中の農村を描きました。
家々や田畑、それに高圧線の鉄塔などは、ほぼ一面のモノトーンで覆われている一方、中央の白いビニールハウスと、その周囲のエメラルドグリーンの田畑のみ、色彩を伴って描かれていました。いずれも写実的でありながら、何やら白昼夢を前にしているかのようで、不思議と風景にのまれるような感覚に陥りました。なお空は、くしゃくしゃにしたアルミ箔を紙に貼って表しているそうです。

岩橋英遠「瑛」 昭和52年 山種美術館
まばゆい陽の光が大地に降り注ぐ、岩橋英遠の「瑛」も魅惑的ではないでしょうか。一羽の鳥が横切っていて、朱色に染まる棚田は、神々しいほどに輝いていました。

速水御舟「名樹散椿」 昭和4年 山種美術館
さて会期も中盤を過ぎました。10月16日に御舟の一部の作品が入れ替わり、重要文化財の「名樹散椿」の公開がはじまりました。私も改めて見てきました。

速水御舟「名樹散椿」(部分) 昭和4年 山種美術館
「名樹散椿」は、当時で樹齢400年に達した、京都の昆陽山地蔵院の椿を金地に描いた作品で、枝の屈曲を強調し、図像的に表した葉などは、琳派的なデザインを思わせるものがありました。とはいえ、花はかなり写実的で、一時、質感表現を追求した、御舟の1つの到達点としても知られています。昭和52年には、昭和以降の日本画として初めて重要文化財に指定されました。
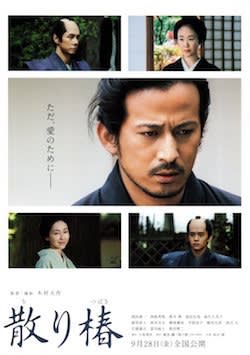
映画「散り椿」@chiritsubaki928
http://chiritsubaki.jp
最近、改めて「名樹散椿」が注目される機会がありました。それが、9月28日より公開中の映画、「散り椿」(木村大作監督)で、葉室麟の原作の表紙に、「名樹散椿」が使われました。
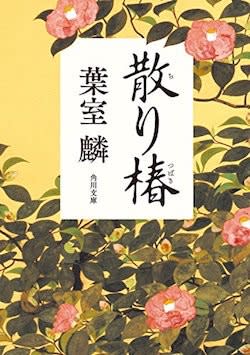 「散り椿/葉室麟/角川文庫」
「散り椿/葉室麟/角川文庫」実際のところ、本作も、映画「散り椿」の公開に合わせ、特別に出品されました。またこの「名樹散椿」のみ、一般会期中も撮影が出来ます。(動画、フラッシュ、自撮り棒や三脚は不可。)
映画「#散り椿」大ヒット上映中!! 原作小説の表紙を飾った《名樹散椿》が、山種美術館にて特別公開開始。 | カドブン https://t.co/2AasgPAzRC #カドブン
— 山種美術館 (@yamatanemuseum) 2018年10月15日
11月11日まで開催されています。
「企画展 日本美術院創立120年記念 日本画の挑戦者たち ―大観・春草・古径・御舟―」 山種美術館(@yamatanemuseum)
会期:9月15日(土)~11月11日(日)
休館:月曜日。但し9/17(月)、24(月)、10/8(月)は開館。9/18(火)、25(火)、10/9(火)は休館。
時間:10:00~17:00 *入館は16時半まで。
料金:一般1000(800)円、大・高生800(700)円、中学生以下無料。
*( )内は20名以上の団体料金。
*きもの割引:きもので来館すると団体割引料金を適用。
*リピーター割:使用済み有料入場券を提示すると団体割引料金を適用。
住所:渋谷区広尾3-12-36
交通:JR恵比寿駅西口・東京メトロ日比谷線恵比寿駅2番出口より徒歩約10分。恵比寿駅前より都バス学06番「日赤医療センター前」行きに乗車、「広尾高校前」下車。渋谷駅東口より都バス学03番「日赤医療センター前」行きに乗車、「東4丁目」下車、徒歩2分。
注)写真は特別内覧会時に主催者の許可を得て撮影したものです。
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )










