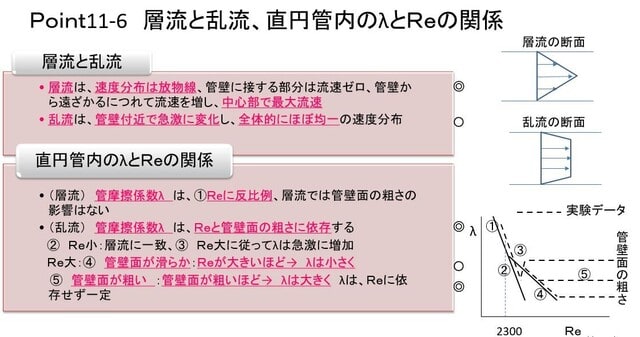長瀞の宝登山(ほとさん)に蝋梅(ろうばい)を見に登山した。登山というよりはハイキングだ。この季節、もう何度も登っている。いい天気だ。秩父鉄道野上駅がスタート、しばらく平地を歩き、そのうち登り。標高5百㍍足らずの山で、大した登りではない。
しかし、この山で一昨年の秋、死亡事故が発生したそうだ。風の強い日で、帽子が飛ばされそうになり、追っかけているうちに滑落、死亡した。ネットの記事にもなってる。事実はここまでだが、私が推測するに、風が強いのは尾根歩き、尾根から転落してもこの山なら途中の樹木に引っかかりそうなもんだが、運が悪かったんだろう、そして打ちどころも悪かったんだろう。山は甘く見てはいけない、怖いな。
以下、写真でこの日の登山の模様を解説します。
(長瀞アルプス、尾根に登っても、こんなに樹木がある)

(民有林があり、寄付金箱、百円を寄付)

(氷池の分岐、いつもここで休憩する)

(小鳥峠、かわいい名前だ)

(いよいよ宝登山への急登、登り口)

(長い長い階段、写真はたいしたことないように見えるが、実際はきつい登り)

(そして宝登山山頂、平日のせいか登山者はわずか)

(右の近くは城峰山、左遠くには百名山の両神山)

(秩父盆地と武甲山、左に二子山が見える)

(蝋梅園、日当たりのいい場所で咲き始め)

(蝋梅、美しい花とほのかな香り、冬に咲くのはうれしい)

(下山して、長瀞神社へ参拝)

下山して、おでん🍢と甘酒をいただく。秩父駅前で秩父鉄道の方から、蝋梅の苗木を戴く、無料だ。ちょっと良かった。この日は、かんぽの宿寄居へ。