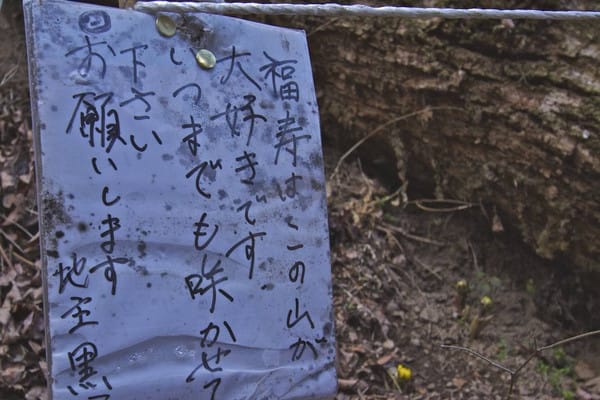カタクリの群生地は自分達が住んでいる街の近くにもある。また、自宅近くの里山ではカタクリの花が盛りのときを迎えている。それにもかかわらず、私達は2時間半ほどドライブをして、カタクリ山公園(栃木県那珂川町)に向かった(4月5日)。
*****
私達が公園に着いたとき、残りの駐車スペースは2、3台分と、駐車場が混んでいた。那珂川町(なかがわ)の案内(パンフレットやホームページ)では、関東最大規模の群生地、3ヘクタールの広さ、100万株のカタクリ、今は見頃、などのフレーズが目立つ。そして、平坦な木道、階段、登り坂、下り坂と、園内は歩く上でも変化に富んでいる。
この日、青空が見えたものの雲が多かった。陽射しは雲によってたびたび遮られた。しかし、雲の切れ間からの陽光によって、赤紫色の彩りが帯状となって見えることがあるだろう。そのような場面を見逃したくない。中腰になったり座ったりして、私達は視線の位置を何度か変えた。
雲間からのスポットライトは期待したようにならなかったが、ある程度は赤紫色の帯が見える瞬間があった。陽射しが斜めとなる時間帯では、どのようが場面があらわれるだろうか。
群生地には、里山の雰囲気が漂っていた。
花を開こうとしているカタクリの群れ、落葉樹林、そして落ち葉
色が濃い花を選んでクローズアップすると。
前日の悪天候(降、雹、風)に負けることなく、花は生き生きとしていた。

*****
群生地には、キクザキイチゲの花が咲いているスポットがあった。 キクザキイチゲ(菊咲一華、別名はキクザキイチリンソウ)はキンポウゲ科イチリンソウ属の多年草であり、山地の落葉樹林を好むと言われている。花名は花が菊のそれに似ていることに由来する。
カタクリとアズマイチゲ
*****
ショウジョウバカマの群生地(猩猩袴、山地の谷沿いや林野の湿った場所を好むユリ科の多年草)。花の多さは圧巻であった。私達はこれほどの群生を見たことがなかった(感動と唖然)。
ショウジョウバカマでは、花の色に変化が多いとされている。例えば、谷川岳では濃色系(紅)から淡色系(白)の花に出会う。ここでは、花々が優しい印象の色を帯びていた(淡色系)。
群生地においてだからこそと、花を上から眺めてみる。
******
公園の出口にて。フキ(蕗)の畑。那珂川町では、蕗が特産品として栽培されている。私達はこのような蕗畑を初めて見た。
*****
この群生地を、私達が訪れたのは、ブログ「花の詩山の詩(http://blog.goo.ne.jp/kurikoma7 )」を書かれている「minoさん」のお蔭である。深謝。
公園を出てから、私達は国道293号を経てイワウチワの群生地(那珂川町)に向かった。途中、道の駅(ばとう、馬頭)で眺めた高原山(釈迦ヶ岳、鶏頂山など、1600-1800 m、旧火山)。対称的に見える山容が魅力的であった。
*****
インポート「こつなぎの写真ノート」から