最近めっきり教育問題を書かなくなっている。もう現場を離れて長くなったし、特にコロナ禍の教育事情はよく判らない。大変なんだろうなあと傍から想像するだけである。そんな中でも、時事的に考えることはあるので、二つのテーマに関して書いてみたい。一つは「部活動改革」で、いままさに大きく動き出そうとしている。マスコミでも紹介されることが増えてきて、この前は「4時半で全員下校」という取り組みを進めている地域が紹介されていた。検索すると「部活動改革」のケースがいろいろと出て来る。
 (スポーツ庁の取り組み)
(スポーツ庁の取り組み)
その中身も重要なんだけど、その前に最近になって気付いた問題を最初に考えてみたい。5月のゴールデンウィークが終わったところだが、学校の正教員に採用された年からゴールデンウィークがなくなった。僕は1980年にフレンズ国際ワークキャンプ(FIWC)の韓国キャンプに参加した。その後で関東でもやってると教えられ、1981、82年の2年間のゴールデンウィークは群馬県渋川市に泊まりがけで出掛けた。83年も行こうかなと思っていたら、就職とともに祝日は部活の試合引率になって行けなくなったのである。
職場では一番下っ端だから、○部の副顧問だと言われて、5月3日、5日は試合だから引率だということになった。部活引率手当もなく、もちろん代休もなかったが、そのことの法的な説明もなかった。ただそういう現場だったわけで、今から考えてみれば、これでは確かに「ブラック企業」と言うしかない。何の報酬もなく、事実上強制されるわけだから、「アンペイド・ワーク」(unpaid work)だったわけである。しかし、そのような概念は知らなかったし、僕にも最初は「ただ言われるままに動く」以外の働き方は出来なかったわけである。それは何故だったのだろうか。
幾つか理由があるが、そもそもどんな仕事でも内部から改革するのは難しい。理由があってそうなっているので、新米教員がすぐに改善は出来ない。勉強は嫌いでも部活なら出て来る生徒も多い。教員の中にも「部活イノチ」みたいな人が結構いる。一生懸命やっている生徒や同僚に対して、おかしいとはなかなか言いにくい。それに実は当時はあまり「アンペイド」という意識が薄かった。学校だけではなく民間も含めて、その頃は「ユルい職場慣行」がいっぱいあったからだ。(例えば、学校行事の後では管理職が率先して校内で豪快な飲み会をやっていた。今なら処分ものだ。)早く帰れる日もあって相殺された感じだったのだ。
もう一つ、学校には「アンペイドな領域」が必要だとも思っていたのである。あらゆる仕事には「共同体」的な部分があって、特に学校のような人と人が関わる仕事、「教育」という領域には、単に「契約で結ばれた労働」だけでは収まりきらない部分がある。水田農耕の共同体では、一年に一度村人が集まって水路を掃除するといった仕事が必要だ。同じように、日本の学校には宿泊行事や生徒会活動、掃除など、それも「広義の勉強」だけど、教科書のないような狭間の領域がある。部活動は中でも生徒にとって非常に大きい。そういう狭間の領域は「アンペイド」になりやすい。
「バブル崩壊」期頃から、公務員バッシングが横行するようになり、「慣行」はどんどん法規に則ったギチギチの運用に変えられていった。しかし、法律で規定されていない「ブラック」な部分はそのままだから、負担感が半端なくなったのも当然だ。もう戻ってこない昔を懐かしんでも仕方ない。教師の半分以上はもう「昔」を知らないんだし、これからは新しいやり方を作らなければと思いつつ、僕はなかなか「学校の中のアンペイドワーク」という問題意識は持たなかった。その一番の理由は、学校の共同体的な部分をなくしてしまって良いのかと思っていたからだ。
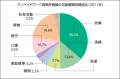 (アンペイド・ワークの内容)
(アンペイド・ワークの内容)
「アンペイドワーク」という概念はフェミニズムの中で登場した。資本主義社会で「賃金」として評価されない「労働」がある。最近「アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か?」(カトリーン・マルサル著、河出書房新社)という本が刊行されたが、まさにそういうことである。資本主義を理論化したようなアダム・スミスにも、見えてない問題があったのである。そもそも「労働」と呼ぶときには、第2次、第3次産業で雇われて働き、労働の対価として「賃金」を受け取るというイメージが強かった。「社会主義の祖国」ソ連邦の国旗は「槌と鎌」で、それは「労働者と農民の連帯」だと言われたが、では「農民」は「労働者」ではないのだろうか。
我々の生命としての持続を支える仕事、つまり「家事」や「育児」は、多くの場合は「家庭」の中で行われる。そして、その担い手が誰であっても(多くは「妻」、場合によっては「夫」や「親」など)、大体は賃金は支払われない。(富裕層では、家事や育児を金銭で「外部化」する場合もある。)そして、企業の定年退職後も「長い老後」が存在するようになると、「介護」という問題が発生した。それらが実は世の中を支えている「隠れた仕事」(シャドウ・ワーク)であり、「支払われない仕事」(アンペイド・ワーク)だという「発見」が、フェミニズムの発想の中で見えてきたわけである。
今の事例で判るように「アンペイド・ワーク」は大体が「家庭」の中で発生している。話を部活動に戻すと、労働契約に基づかない部活動は「家族関係」なのだろうか。そういうことになってくる。そうか、とそこで思ったわけである。まるで部員を家族扱いしている顧問が多かった理由がわかった気がしたのである。よく女子スポーツの部活では、顧問が部員を名前で呼びつけている。ミスを注意するときなども、「マユミ、何してるんだ」とか「ユカ、そんなんでどうする」とかである。そうか、これは「家族意識」だったのかと初めて気付いた気がした。
部活動で体罰や行き過ぎた勝利至上主義が起きるのも、アンペイド・ワークがもたらす家族意識が間違った方向に行き着くことから来るのではないか。やはり、学校の労働はきちんと労働法に合致し、ワークとペイが正当に対応するようなものでないと、歪んだ部分が出て来るのではないか。段々そう思うようになってきたわけである。では、どのように変わってゆくべきなのかは次回に。
 (スポーツ庁の取り組み)
(スポーツ庁の取り組み)その中身も重要なんだけど、その前に最近になって気付いた問題を最初に考えてみたい。5月のゴールデンウィークが終わったところだが、学校の正教員に採用された年からゴールデンウィークがなくなった。僕は1980年にフレンズ国際ワークキャンプ(FIWC)の韓国キャンプに参加した。その後で関東でもやってると教えられ、1981、82年の2年間のゴールデンウィークは群馬県渋川市に泊まりがけで出掛けた。83年も行こうかなと思っていたら、就職とともに祝日は部活の試合引率になって行けなくなったのである。
職場では一番下っ端だから、○部の副顧問だと言われて、5月3日、5日は試合だから引率だということになった。部活引率手当もなく、もちろん代休もなかったが、そのことの法的な説明もなかった。ただそういう現場だったわけで、今から考えてみれば、これでは確かに「ブラック企業」と言うしかない。何の報酬もなく、事実上強制されるわけだから、「アンペイド・ワーク」(unpaid work)だったわけである。しかし、そのような概念は知らなかったし、僕にも最初は「ただ言われるままに動く」以外の働き方は出来なかったわけである。それは何故だったのだろうか。
幾つか理由があるが、そもそもどんな仕事でも内部から改革するのは難しい。理由があってそうなっているので、新米教員がすぐに改善は出来ない。勉強は嫌いでも部活なら出て来る生徒も多い。教員の中にも「部活イノチ」みたいな人が結構いる。一生懸命やっている生徒や同僚に対して、おかしいとはなかなか言いにくい。それに実は当時はあまり「アンペイド」という意識が薄かった。学校だけではなく民間も含めて、その頃は「ユルい職場慣行」がいっぱいあったからだ。(例えば、学校行事の後では管理職が率先して校内で豪快な飲み会をやっていた。今なら処分ものだ。)早く帰れる日もあって相殺された感じだったのだ。
もう一つ、学校には「アンペイドな領域」が必要だとも思っていたのである。あらゆる仕事には「共同体」的な部分があって、特に学校のような人と人が関わる仕事、「教育」という領域には、単に「契約で結ばれた労働」だけでは収まりきらない部分がある。水田農耕の共同体では、一年に一度村人が集まって水路を掃除するといった仕事が必要だ。同じように、日本の学校には宿泊行事や生徒会活動、掃除など、それも「広義の勉強」だけど、教科書のないような狭間の領域がある。部活動は中でも生徒にとって非常に大きい。そういう狭間の領域は「アンペイド」になりやすい。
「バブル崩壊」期頃から、公務員バッシングが横行するようになり、「慣行」はどんどん法規に則ったギチギチの運用に変えられていった。しかし、法律で規定されていない「ブラック」な部分はそのままだから、負担感が半端なくなったのも当然だ。もう戻ってこない昔を懐かしんでも仕方ない。教師の半分以上はもう「昔」を知らないんだし、これからは新しいやり方を作らなければと思いつつ、僕はなかなか「学校の中のアンペイドワーク」という問題意識は持たなかった。その一番の理由は、学校の共同体的な部分をなくしてしまって良いのかと思っていたからだ。
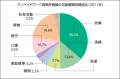 (アンペイド・ワークの内容)
(アンペイド・ワークの内容)「アンペイドワーク」という概念はフェミニズムの中で登場した。資本主義社会で「賃金」として評価されない「労働」がある。最近「アダム・スミスの夕食を作ったのは誰か?」(カトリーン・マルサル著、河出書房新社)という本が刊行されたが、まさにそういうことである。資本主義を理論化したようなアダム・スミスにも、見えてない問題があったのである。そもそも「労働」と呼ぶときには、第2次、第3次産業で雇われて働き、労働の対価として「賃金」を受け取るというイメージが強かった。「社会主義の祖国」ソ連邦の国旗は「槌と鎌」で、それは「労働者と農民の連帯」だと言われたが、では「農民」は「労働者」ではないのだろうか。
我々の生命としての持続を支える仕事、つまり「家事」や「育児」は、多くの場合は「家庭」の中で行われる。そして、その担い手が誰であっても(多くは「妻」、場合によっては「夫」や「親」など)、大体は賃金は支払われない。(富裕層では、家事や育児を金銭で「外部化」する場合もある。)そして、企業の定年退職後も「長い老後」が存在するようになると、「介護」という問題が発生した。それらが実は世の中を支えている「隠れた仕事」(シャドウ・ワーク)であり、「支払われない仕事」(アンペイド・ワーク)だという「発見」が、フェミニズムの発想の中で見えてきたわけである。
今の事例で判るように「アンペイド・ワーク」は大体が「家庭」の中で発生している。話を部活動に戻すと、労働契約に基づかない部活動は「家族関係」なのだろうか。そういうことになってくる。そうか、とそこで思ったわけである。まるで部員を家族扱いしている顧問が多かった理由がわかった気がしたのである。よく女子スポーツの部活では、顧問が部員を名前で呼びつけている。ミスを注意するときなども、「マユミ、何してるんだ」とか「ユカ、そんなんでどうする」とかである。そうか、これは「家族意識」だったのかと初めて気付いた気がした。
部活動で体罰や行き過ぎた勝利至上主義が起きるのも、アンペイド・ワークがもたらす家族意識が間違った方向に行き着くことから来るのではないか。やはり、学校の労働はきちんと労働法に合致し、ワークとペイが正当に対応するようなものでないと、歪んだ部分が出て来るのではないか。段々そう思うようになってきたわけである。では、どのように変わってゆくべきなのかは次回に。
















