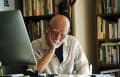2011年2月からこのブログを書いている。細かく言うと、今日(2021年4月12日)でブログ開設から3695日だという。それは「早期退職」を前にした時期だった。ちょうど10年経ったことになる。3月31日とか4月1日とかの「キリがいい日」に記念の記事を書こうかと思ったんだけど、自分の気持ちがまとまらない気がした。だから他の記事を書いていたんだけど、やっぱり「10年目のまとめ」も書いておこうかなと思って。時期が遅れたけど書いている次第。
今も毎日のように書いているけれど、無理して書き続ける気は無い。書くのが大変になったら辞めればいいと思っているけれど、当面書きたいことは絶えない感じだ。去年のコロナ「ホームステイ」で判ったけれど、自分は本があれば生きていけるようだ。そして読めば感想を書きたくなる。もう本や映画の感想専門にしてしまおうかと思うときもある。でもやはり、社会問題、国際情勢なども書きたくなってくるのである。「今を生きる」人間の一人としての義務感のようなものだ。
 (昨日の記事をスクリーンショット)
(昨日の記事をスクリーンショット)
自分なりに何か文章を書くことは昔から好きだった。学生時代にはハガキ版の通信を出したことがある。それは「緑の五月通信」と名付けていた。その後21世紀になった頃から「電子メール版緑の五月通信」を書くようになった。それがブログに移行した感じかもしれない。当初は両立を考えていたのだが、多忙もあるけど「メールの一斉送信」が難しくなって止めてしまった。ブログ開設時は「教員免許更新制反対日記」と名付けていた。突然教員を辞めてしまったので、その理由や今やってることを報告することに意味があるかと思ったのである。
5年経って、勤めていても定年の歳になったので「紫陽花通信」に変更した。教育関係の記事もおおよそ書いてしまったし、教員免許更新制度という愚策がなくても退職している年齢になったからだ。その時に書いたけれど、改めて書いておくと「紫陽花通信」というのは、奈良の「大倭紫陽花邑」という共同体から来ている。FIWC(フレンズ国際労働キャンプ)関西委員会がハンセン病回復者施設「交流(むすび)の家」を建てた場所である。僕は1980年にFIWCの日韓合同ワークキャンプに参加して、韓国のハンセン病定着村を訪れた。その時に事前キャンプで「交流の家」に泊まった。その後も何度も行っている。
その前に真木悠介「気流の鳴る音」を読んでいた。共同体のあり方として、同書はモチ型とオムスビ型という概念を提出していた。「お米」という素材を完全につぶして一つにする「モチ」と米粒のままつながっている「オムスビ」の違いである。前者がヤマギシ会、後者が紫陽花邑だったと思う。僕は「個が個のまままとまる」「アジサイの花」を「クラスの目指すもの」と思ったから、時々思い出したように作る「クラス通信」は「紫陽花通信」と名付けていた。
だから書くこと自体には何の苦労もないんだけど、それでも昔は一日に2つ書くことが時々あった。今はもう無理だと思う。書きためた記事も整理が必要だが、なかなかまとまった時間が取れない。時々そういう日があると、休憩したり読書に時間を使いたくなる。政治の記事はその時点では読まれるが賞味期限が短い。今となっては意味が無いものはどんどん削除しようと思ってるんだけど…。映画監督や作家などを長目にまとめる記事は、その時には読者が少ないけど数年経って読まれ始めることがある。面白いもんだと思う。政治や国際情勢に関しては、自分があらゆる問題をきちんと書けるわけではない。そういう必要もないと思う。
誰に向けて書いているかというと、あまり意識しないでいるけれど特定層ではない「抽象的な固定層」かと思う。今さら「炎上」もしたくないので、あまり悪口は書きたくない。映画なんか人それぞれの好みで見ればいいので、僕が今ひとつと思った映画を大々的に批判記事を書く必要もないと思う。しかし、政治・社会などの記事では批判を避けることは出来ない。避ける気もない。誰かの気を損じるとしても、書くべきことを書くのは義務だと思っている。僕が社会科の教師になったのは、知っていること、学んだことを伝えていくためだ。僕がある程度知っているけれど、一般の理解は今ひとつだと思える問題には、書くべきだと思っているのである。
そのためにはある程度の文章量が必要となる。だから「ブログ」が最適になる。「ツイッター」では誤解を招きやすい。それに僕の日々のあれこれを同時的に知りたい人は特にいないだろう。写真や動画を撮るのは面倒くさいから、そういうSNSもやらない。ただし、知り合いとつながっているため「Facebook」はやっている。今じゃブログへのリンクぐらいしか書かないことが多いが。でもブログに「尾形修一の」なんてどうでもいい個人名を入れ続けているのは、昔の知り合い(生徒など)が見つけやすくするためだ。もし良かったらFacebookで連絡を貰えればと思う。
今後年齢をどんどん重ねるわけで、毎日書くことは少なくなるだろう。定期的に何曜日休みと決めてもいいけど、僕の場合見に行く映画(演劇、寄席)などの日程に左右されるので、将来にわたって何曜日休みとは決めにくい。それでもしばらくは週に6日ぐらいは書くと思う。どうでもいいこともあるが、自分の中に書きたいことが溜まりすぎないようにしているわけ。今後ともお付き合い願えればありがたいと思っています。なお、昨日は、3007829ブログ中635位だった。712人の訪問者。別にあまり気にしてないけど。最近は500位位内はほとんどなく、600~800代が多い。
今も毎日のように書いているけれど、無理して書き続ける気は無い。書くのが大変になったら辞めればいいと思っているけれど、当面書きたいことは絶えない感じだ。去年のコロナ「ホームステイ」で判ったけれど、自分は本があれば生きていけるようだ。そして読めば感想を書きたくなる。もう本や映画の感想専門にしてしまおうかと思うときもある。でもやはり、社会問題、国際情勢なども書きたくなってくるのである。「今を生きる」人間の一人としての義務感のようなものだ。
 (昨日の記事をスクリーンショット)
(昨日の記事をスクリーンショット)自分なりに何か文章を書くことは昔から好きだった。学生時代にはハガキ版の通信を出したことがある。それは「緑の五月通信」と名付けていた。その後21世紀になった頃から「電子メール版緑の五月通信」を書くようになった。それがブログに移行した感じかもしれない。当初は両立を考えていたのだが、多忙もあるけど「メールの一斉送信」が難しくなって止めてしまった。ブログ開設時は「教員免許更新制反対日記」と名付けていた。突然教員を辞めてしまったので、その理由や今やってることを報告することに意味があるかと思ったのである。
5年経って、勤めていても定年の歳になったので「紫陽花通信」に変更した。教育関係の記事もおおよそ書いてしまったし、教員免許更新制度という愚策がなくても退職している年齢になったからだ。その時に書いたけれど、改めて書いておくと「紫陽花通信」というのは、奈良の「大倭紫陽花邑」という共同体から来ている。FIWC(フレンズ国際労働キャンプ)関西委員会がハンセン病回復者施設「交流(むすび)の家」を建てた場所である。僕は1980年にFIWCの日韓合同ワークキャンプに参加して、韓国のハンセン病定着村を訪れた。その時に事前キャンプで「交流の家」に泊まった。その後も何度も行っている。
その前に真木悠介「気流の鳴る音」を読んでいた。共同体のあり方として、同書はモチ型とオムスビ型という概念を提出していた。「お米」という素材を完全につぶして一つにする「モチ」と米粒のままつながっている「オムスビ」の違いである。前者がヤマギシ会、後者が紫陽花邑だったと思う。僕は「個が個のまままとまる」「アジサイの花」を「クラスの目指すもの」と思ったから、時々思い出したように作る「クラス通信」は「紫陽花通信」と名付けていた。
だから書くこと自体には何の苦労もないんだけど、それでも昔は一日に2つ書くことが時々あった。今はもう無理だと思う。書きためた記事も整理が必要だが、なかなかまとまった時間が取れない。時々そういう日があると、休憩したり読書に時間を使いたくなる。政治の記事はその時点では読まれるが賞味期限が短い。今となっては意味が無いものはどんどん削除しようと思ってるんだけど…。映画監督や作家などを長目にまとめる記事は、その時には読者が少ないけど数年経って読まれ始めることがある。面白いもんだと思う。政治や国際情勢に関しては、自分があらゆる問題をきちんと書けるわけではない。そういう必要もないと思う。
誰に向けて書いているかというと、あまり意識しないでいるけれど特定層ではない「抽象的な固定層」かと思う。今さら「炎上」もしたくないので、あまり悪口は書きたくない。映画なんか人それぞれの好みで見ればいいので、僕が今ひとつと思った映画を大々的に批判記事を書く必要もないと思う。しかし、政治・社会などの記事では批判を避けることは出来ない。避ける気もない。誰かの気を損じるとしても、書くべきことを書くのは義務だと思っている。僕が社会科の教師になったのは、知っていること、学んだことを伝えていくためだ。僕がある程度知っているけれど、一般の理解は今ひとつだと思える問題には、書くべきだと思っているのである。
そのためにはある程度の文章量が必要となる。だから「ブログ」が最適になる。「ツイッター」では誤解を招きやすい。それに僕の日々のあれこれを同時的に知りたい人は特にいないだろう。写真や動画を撮るのは面倒くさいから、そういうSNSもやらない。ただし、知り合いとつながっているため「Facebook」はやっている。今じゃブログへのリンクぐらいしか書かないことが多いが。でもブログに「尾形修一の」なんてどうでもいい個人名を入れ続けているのは、昔の知り合い(生徒など)が見つけやすくするためだ。もし良かったらFacebookで連絡を貰えればと思う。
今後年齢をどんどん重ねるわけで、毎日書くことは少なくなるだろう。定期的に何曜日休みと決めてもいいけど、僕の場合見に行く映画(演劇、寄席)などの日程に左右されるので、将来にわたって何曜日休みとは決めにくい。それでもしばらくは週に6日ぐらいは書くと思う。どうでもいいこともあるが、自分の中に書きたいことが溜まりすぎないようにしているわけ。今後ともお付き合い願えればありがたいと思っています。なお、昨日は、3007829ブログ中635位だった。712人の訪問者。別にあまり気にしてないけど。最近は500位位内はほとんどなく、600~800代が多い。