こんにちわ。
地元、鎌倉が舞台の大河ドラマ、”鎌倉殿の13人”を毎回、楽しみに見ている。先週の第8回、”いざ鎌倉”編で、いよいよ頼朝は、石橋山の敗戦から逃れたあと、真鶴から船で房総半島に渡り、そこの有力豪族、上総広常(佐藤浩市)らを味方につけ、大軍を引き連れ、意気揚々と鎌倉に入る。ようやく、ぼくの馴染みの散歩道に入ってくれた(笑)。
今回は、鎌倉入りした頼朝が何処に御所を設けるかも一つのテーマになっているので、ぼくのいつもの散歩道を絡めて紹介したい。現在、療養中で散歩も思うようにならない状況なので、ちょうどいいテーマかも(笑)。
当時、北側(大船側)から鎌倉に入る道は、現在の長寿寺脇から入る亀ヶ谷坂(かめがやつさか)しかなかったようだ。亀でさえ引き返すほど急な坂道だったことからその名が付いたともいわれている。こんなふうな坂道。ぼくの大好きな散歩道。この坂を頼朝らは登って行ったはず。


そして、坂を登り終え、そこからから下ると、扇ヶ谷(おうぎやつ)に通じる。

坂を下ったところに、岩船地蔵堂がある。頼朝と政子の長女、20歳の若さで夭折した大姫を供養するお堂だ。中に白い地蔵尊が安置されている。ドラマではまだ幼児の大姫が政子に抱かれている。

大姫は、のちに木曽義仲の嫡男、義高(染五郎)と婚約するが、義仲の敗北に伴い、頼朝の命で処刑され、大姫は心を病み、早世する。

横須賀線のガードをくぐると、鎌倉駅と海蔵寺方面を結ぶ、現・線路沿いの街道(今大路)が目の前に現れる。右へ行くと、海蔵寺。左へ10分も歩くと寿福寺である。ここに、頼朝の父、義朝の屋敷があった。政子が栄西を招いて跡地に寿福寺を創建、三代将軍、実朝もしばしば訪ね、発展を遂げた。政子と実朝の墓所もある。鎌倉五山第三位の寺院である。

政子と実朝の墓所(やぐら)が並んである。

ドラマでは、地元の豪族、岡崎義実が義朝旧居の付近に頼朝の御所を置くように勧める。この裏手が無量寺谷(むりょうじがやつ)と呼ばれた谷戸で、鎌倉幕府の御家人、安達盛長ゆかりの無量寿院という大規模な寺院があったと言われている。邸宅もここにあったようだ。現在、この地には鎌倉歴史文化交流館が建っている。

しかし、頼朝はこれを断り、実弟の僧侶、阿野全成の意見を聞く。真っ先に材木座にある現在の元八幡を参拝し、この八幡宮を現在の場所に遷した。ここを平安京の天皇の内裏に見立て、鎌倉の中心として、新しい武家政治の町、鎌倉の都市計画を実施した。
現在の元八幡・由比若宮。これを遷した。芥川龍之介はこの近所で新婚時代を過ごしている。

現在の鶴岡八幡宮

八幡宮の造成予定地から由比ガ浜を望む頼朝たち。

2016年段葛の桜。頼朝が政子の二代将軍源頼家を懐妊したときに安産祈願で造成した。段葛は第二鳥居でおわるが、参道(若宮大路)は由比ガ浜近くの第一鳥居までつづく。

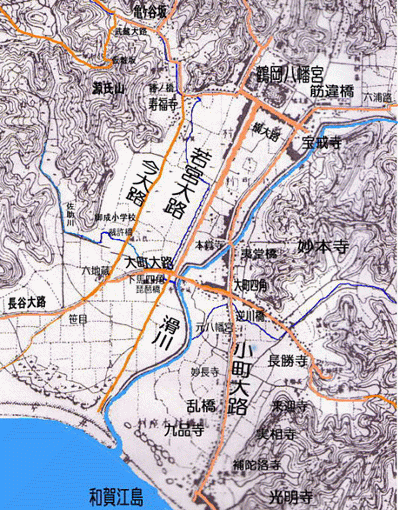
さて、頼朝は何処に御所を建てたか。頼朝と義時が鎌倉入りした当時は、鶴岡八幡宮の前を東西に走る六浦路・横大路がメインストリートだった。方角も良いということで、この道を中心に、幕府の重要な施設が建てられていく。八幡宮の東側奥に隠れたような大倉の地で、大倉幕府とも呼ばれる。現在は幕府跡の石碑が清泉小学校の敷地内にある以外は、東西南北に門があったとされる名残で西御門(にしみかど)という地名が残っている程度である。
八幡宮の流鏑馬の行われる馬場の東鳥居を出ると、横浜国大付属中、清泉小学校の敷地がつづく。この小径は桜も紅葉もきれいな通りで、ぼくの好きな散歩道。

東鳥居に隣接する横浜国大付属中学校。

清泉小学校付近の紅葉。

この近くに、大倉幕府旧跡の石碑が建っている。

仮御所

この先に、頼朝が鎌倉幕府開府に当たり、鬼門の位置に創建した荏柄天神社がある。

頼朝の墓と義時の墓(法華堂跡)は大倉幕府を見渡せる小高い山の上にある。今、何を想うか、頼朝と義時。
頼朝の墓


義時

これからも、鎌倉殿の13人をぼくの散歩道をからめて、紹介したいと思っている。
それでは、みなさん、今日も一日、お元気で!















