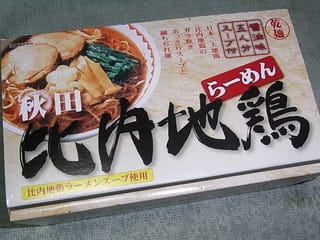かかりつけのいなば内科に行った帰りに、鷺山の自由書房によって、
最新号の『週刊ポスト』を買いました。
この号には、上野さんの記事がのっているという広告を見つけたので、
読みたかったのですが、風邪気味で外出を控えていて、
近くのスーパーはなくなっていたので、ちょっと大き目の本屋さんに行ったのです。
 『週刊ポスト』11/27日号
『週刊ポスト』11/27日号
インフルエンザだったらまっすぐ帰ろうと思っていたのですが、
医者の診断は、「熱もないしインフルエンザじゃないでしょう」。
「対症療法ですが、咳止めを出しておきましょうか」とのことなので、
「新薬は飲んだことがないのですが効きますか」とたずねたら、
「よく効きますよ、人に会うときに飲むとよいですよ」。
咳はさほどひどくないのですが、この時期マスクをして咳をしてると嫌がられるので、
「相手のために飲みます」といったら、「はい。そういうことです(笑)」。
気管支拡張作用のある
フスコデという薬が処方されました。
これで咳発作が起きても安心です。
ということで、マスクをしたまま「自由書房」で本を買って、
帰ってからさっそく『週刊ポスト』の上野千鶴子さん記事を読み始めました。
最新号なので、ちょっとだけ紹介しますね。
 「上野千鶴子が伝授! 「男のおひとりさま力」養成講座」
「上野千鶴子が伝授! 「男のおひとりさま力」養成講座」
次の号が出ると書店から消えるので、もっと読みたい人は本屋に急いでください。
と「週刊ポスト」のピーアールもばっちり。
80万部も発行の、男性によく読まれている週刊誌なので、この記事をきっかけに
『男おひとりさま道』もたくさんの男性に読んでもらえるといいですね。
上野千鶴子さん最新刊『男おひとりさま道』届きました!(2009.10.27)
刊行から一ヶ月足らずで、すでに10万部越え、だそうですから、
『おひとりさまの老後』に追いつくのも夢じゃない。
100万部を越えるミリオンセラーになれば、世の男性に与える影響も大きい、
と思いながら・・・・、
夕方届いた朝日新聞夕刊の「『思想の科学』が映す現代」の記事 を読んでいたら、

こちらにも上野さんが登場されてました。
「思想の科学」が映す現代 ダイジェスト版刊行を機にシンポ
2009年11月19日 朝日新聞
在野の思想をもって時代と対抗し続け、96年に終刊になった雑誌「思想の科学」。50年に及んだ歴史を総覧し、全539冊、約1万件の収録論文・記事から2000件余りのエッセンスを収録した『「思想の科学」ダイジェスト 1946~1996』(思想の科学社)が刊行されたのを機に、このほど東京都内でシンポジウムが開かれた。戦後思想に果たした同誌の役割が改めて討議される中、「今」の抱える問題も見えてきた。
「思想の科学」はどんな雑誌だったか。論者が共通して指摘したのは自由さだった。
社会学者の橋爪大三郎・東京工業大学教授は「体制や党派から距離をとり、一つの枠に収まらない多元性をもっていた」と評価。そのうえで「50年前は別だが、自由に考えることは今や誰でもやっている」と語り、「思想の科学には『(私たちには)考えるべき課題がある』という倫理性を引き受けるまじめさがあった。それが次代に受け継がれていないのではないか」と問題提起した。
動機の問題を問うたのは、高校時代から愛読者だったという上野千鶴子・東京大学教授(社会学)。近年創刊された「ロスジェネ」「フリーターズフリー」などの若者論壇誌を挙げ、「自分の言いたいことを伝えるために、採算性がなくても始まってしまう雑誌がある。終刊するということは、思想の科学が当初持っていたそうした動機が、なくなってしまったということかもしれない」とした。
思想の科学は、戦後間もない46年、当時23歳だった哲学者の鶴見俊輔氏(87)が丸山真男らと7人の同人で創刊した。終刊と創刊を繰り返し、最後の終刊は第8次。会場からは「第9次」の創刊を望む声も上がった。
第8次の編集委員を務めた文芸評論家の加藤典洋氏は「一方に雑誌があって、もう一方に思想の科学研究会という集まりがあり、両者の関係ははっきりしない。だから、どこからでもまた始まる可能性がある」と答えた。
終刊後も研究会は活動を続けている。4年前から会員になっている道場親信・和光大学准教授(社会運動論)はシンポで、思想の科学が各地に読者会を持ち、それが新たな書き手の供給源にもなった点や、中央―支部という関係が内部に持ち込まれなかった点に触れた。「主体(作り手)があって場(雑誌)を作るのではなく、場を作りながら主体が発見されていった。ただ80年代半ば以降は、読者と作り手のフェース・トゥ・フェースの関係性が見えにくくなってきた」
また、中心を持たないという編集方針とは対照的に、創刊メンバーであり半世紀を通じて物心両面で同誌を支え続けた鶴見氏の存在の大きさも、シンポからは見えてきた。上野氏は「鶴見さんが一種のシンボルとして機能し続けた『鶴見雑誌』だった」と述べ、橋爪氏も「創刊の動機の根本にあったのは戦争の経験だろう。それは鶴見さんに体現されてきた」と評した。高齢の鶴見氏に依存できないことが「第9次」の行方にも影を落としている。
96年の終刊時には6人が健在だった創刊同人メンバーだが、今は鶴見氏を除いて鬼籍に入っている。シンポで鶴見氏は、客席に座って議論を見守っていた。会場で発言を求められても固辞したが、閉会後のパーティーではあいさつに立ち、こう述べた。
「思想の科学は六十余年間、除名者なしでやってきた。そういう道を続けていただきたい。『2人になっても続けよう。しかし、2人になっても除名はしない』。お話ししたいのはそれだけです」(樋口大二) |
シンポジウム:『思想の科学』 24日に早大で開催
2009.10.20 毎日新聞
1996年に終刊となった雑誌『思想の科学』の果たした役割などを議論するシンポジウム「『思想の科学』は、まだ続く」が24日、東京都新宿区の早大小野記念講堂で開かれる。同誌(46年創刊)の軌跡をたどる3部作の50年史がこのほど刊行完結したのを記念し、編者らが企画した。
シンポジウムは午後1時からの第1部で、社会学者の橋爪大三郎氏が「戦後日本と『思想の科学』」、評論家の坪内祐三氏が「『思想の科学』という雑誌」、社会学者の上野千鶴子氏が「民間学としての『思想の科学』」と題し、それぞれ講演する。午後3時からの第2部では、講演者3氏に文芸評論家の加藤典洋、作家の黒川創、社会運動史研究者の道場親信の各氏らが加わり、パネルディスカッションを行う。
資料代1000円。申し込みは思想の科学社ホームページ(http://www.shisounokagaku.co.jp/)で。問い合わせも同社(電話03・5389・2101)へ。
|
人気ブログランキング(社会・経済)に参加中 
応援クリック してね
してね 

 本文中の写真をクリックすると拡大します。
本文中の写真をクリックすると拡大します。
週刊ポストといっしょに、
『通販生活』秋冬号も買いました。
この本は、読むだけで注文したことがないのですが、ぱらぱらとめくったら、
別冊に「種子島 蜜芋」の記事が載っていたので、値段も安かったしつい購入。


この「種子島蜜芋」って、今年育てた安納芋と同じものだと思います。
夢百笑 種子島蜜芋
種子島蜜芋のものがたり
1698年
(元禄11年)、領主・種子島久基の命を受けて、島民・大瀬休左衛門が琉球甘藷を栽培したのが始まりで、かの青木昆陽が日本全土に広めたのは、実にその37年後。
現在でも種子島は、国内で最も在来種が豊富な、まさにサツマイモの聖地ともいえる島なのです。
種子島蜜芋」は、その長い歴史の中でこのサツマイモ原種から特に優れた味覚のものを選別し伝承栽培されてきた種で、その名は島内の安納地区が主産地であったことに由来しています。
別名「幻の蜜芋」といわれるように、その形状は唐芋の原種に近い紡錘形丸形で肉色は鮮やかな赤みを帯びた黄金色。そして何よりねっとりした食感でおどろくほど甘味が強いのが特徴です。従来ノサツマイモのイメージとは異なる風味ゆえサツミモ嫌いの人でも食べられるといわれています。
わたしも、さっそく小さい芋を焼き芋にしてみたら、芋が焼けるとともに、
よい香りがして、蜜がじゅわっと流れ出してきました。
。


しっとりとして、焼芋というより、ちょっとたとえようがない甘さです。

こちらは今朝、ホイルに包んでオーブンで焼いたお芋。
竹串がすっと刺さるようになったら取り出して、
ホイルをあけると、なんと、蜜が流れ出しています。

 あまーい。おいーしーい。
あまーい。おいーしーい。
これ今日のお昼ご飯ですが、主食をとばして、いきなりスイーツみたい。
やはり「蜜芋」という名前がぴったりですね。
最後まで読んでくださってありがとう 


 クリックを
クリックを
 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。
明日もまた見に来てね 




















 クリックを
クリックを 記事は毎日アップしています。
記事は毎日アップしています。