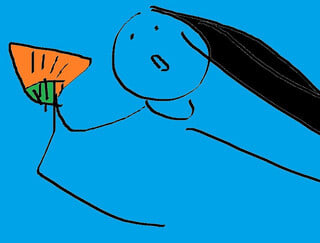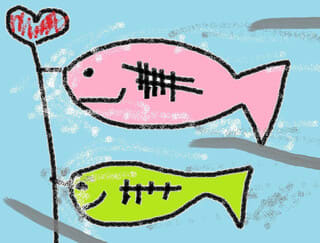つれづれなるまゝに、日くらし硯に向かひて、心にうつりゆくよしなしごとをそこはかとなく書き付くれば、あやしうこそ物狂ほしけれ。
よくあることなのであろうが、徒然草の本文をじゅうぶん読まぬうちから、小林秀雄の「徒然草」(『無常といふ事』)を読んでしまったので、批評家の魂の誕生とか、つい口走りそうになる。
考えてみると、この出だしはすごく異常なことを書いていて、――暇でつれづれなくせに一日中机に向かって、心に移って行く事々を目的もなく書き続けると、その怪しい様は気が狂うほどである、――。意識の流れというより、散漫とした書く動作と書く内容とが狂気の発生をもたらす事態なのであって、これはむしろ、一日中ツイッターをやっている人間のようなものである。ツイッター民のいらいらした感じは、2ちゃんねるのいらいらした感じとは違って、集団行動の狂気というより、そこはかとなく書きつくることによるいらいらが関係しているのではないか。
日記でさえ毎日書いていると、明らかに現実の中になにかゆがんだ空間が出来て、そのなかに意地悪く閉じ込められている様な感覚になるものだが、そんな感覚を言っているのかもしれない。この意地悪い感じが独特で、猜疑心とは違うが、妙にいらいらしたものにとらわれるようになる。
書くことで正気を保つのは結構難しいことなのである。
小林秀雄は兼好は物が見えすぎている、と言っているが、わたくしのような凡人には、見えすぎているという状態は分からない。「過ぎる」という地点ははたして何処なのか。
最近考えているのは、様々な心理的な狂いが悪意を生み出す風景である。どうみても悪意というものが、ある。小林秀雄が「金閣焼亡」で狂人には悪意がある様に見えた、と書いているのは鋭いと思う。小林はどうもそれは勘違いだったと言いたいようにもみえるが、果たしてそうなのか。
雨の降る日の縁端に
わが弟はめんこ打つ
めんこの繪具うす青く
いつもにじめる指のさき
兄も哀しくなりにけり
雨の降る日のつれづれに
客間の隅でひそひそと
わが妹のひとり言
なにが悲しく羽根ぶとん
力いつぱい抱きしめる
兄も泣きたくなりにけり
――朔太郎「雨の降る日(兄のうたへる)」
こういうのを読むと、朔太郎は流石という感じがする。人間にとってつれづれのようなものは感情そのものではなく、他人の感情によって自分の感情が導かれると思わされるからだ。しかしこれはこれで、自分を失うことでもあるわけである。