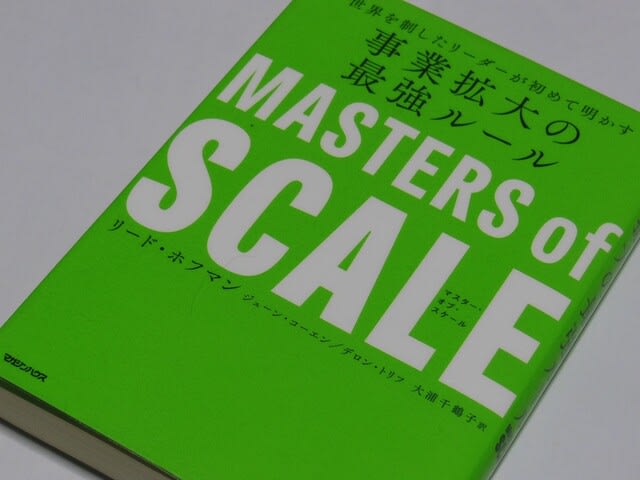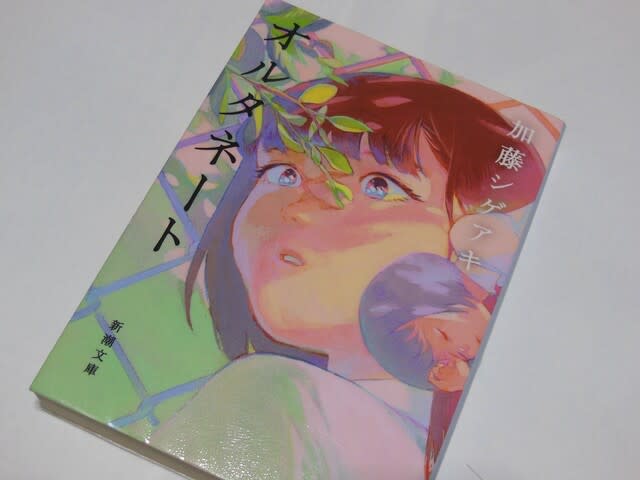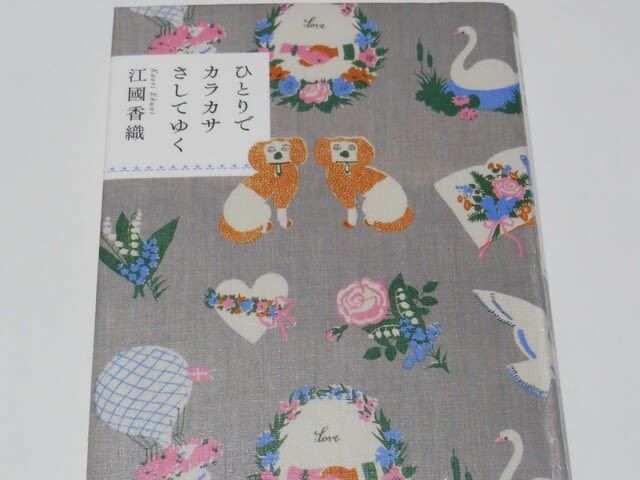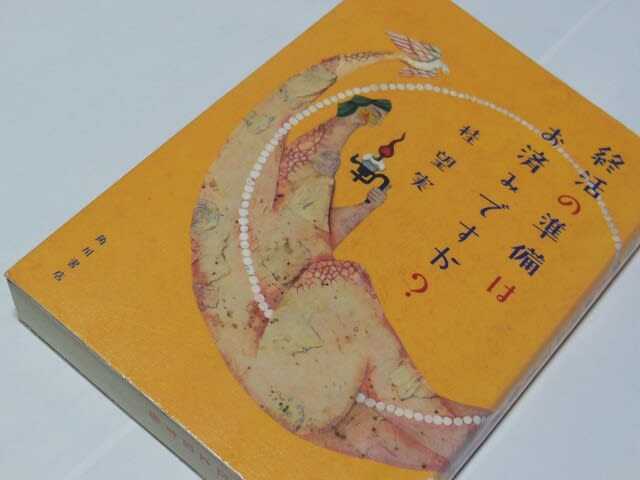過去5年間卒業生から司法試験合格者を出していない底辺のロースクール(法科大学院)の法都大ロースクールになぜか在籍している司法試験合格済の学生結城馨が始めた告発者の主張を書証と証言で判断し有罪なら被告発者に無罪なら告発者に罰を与える「無辜ゲーム」に、過去の自らの犯罪を暴露したチラシを配布された学生久我清義が告発して勝利するが、その後同級生の織本美鈴が過去のことを示した脅迫を受けるなど事件が続き…という法廷ミステリー。
久我と織本の視点で展開するのですが、むしろ結城の刑事司法への絶望と怨念、それでも刑事司法に賭けざるを得ない苦悩に涙します。
弁護士が作者であり、法的・刑事実務的な破綻は特にない(映画化の際に変更されているところでおいおいと思うところはありましたが)と思いましたが、事件での被害者の創傷について2度刺しを示唆する表現はなく(創傷の描写は160ページ、290ページ)発見時に胸元にナイフが突き刺さっていた(119ページ)のに、公判前整理手続で検察官が「犯人は別にいて、被告人はナイフを抜いたに留まる。そんな主張もあり得ると?」と述べ、弁護人が「可能性としては」と言う(160ページ)というのはちゃんと詰めているのだろうかと思ってしまい、終盤で語られる事件の真相が、被害者の創傷の態様やナイフへの指紋の付き方と整合するのか、疑問を感じました。

五十嵐律人 講談社 2020年7月13日発行
メフィスト賞受賞作

久我と織本の視点で展開するのですが、むしろ結城の刑事司法への絶望と怨念、それでも刑事司法に賭けざるを得ない苦悩に涙します。
弁護士が作者であり、法的・刑事実務的な破綻は特にない(映画化の際に変更されているところでおいおいと思うところはありましたが)と思いましたが、事件での被害者の創傷について2度刺しを示唆する表現はなく(創傷の描写は160ページ、290ページ)発見時に胸元にナイフが突き刺さっていた(119ページ)のに、公判前整理手続で検察官が「犯人は別にいて、被告人はナイフを抜いたに留まる。そんな主張もあり得ると?」と述べ、弁護人が「可能性としては」と言う(160ページ)というのはちゃんと詰めているのだろうかと思ってしまい、終盤で語られる事件の真相が、被害者の創傷の態様やナイフへの指紋の付き方と整合するのか、疑問を感じました。

五十嵐律人 講談社 2020年7月13日発行
メフィスト賞受賞作