■『ノーザンライツ』(新潮社)
星野道夫/著
「彼らはオーロラをノーザンライツ(北極光)と呼ぶ。
星野道夫はこの遺作のなかで生きている。」
図書館には1997年発行と、2000年発行の新潮文庫の2冊だったので、古いほうを選んだ。
表紙も上半分が黒いほう。

星野さんの遺作ということで、他の作品を読んでから最後にとっておいた1冊。
星野さんの著書の集大成であると同時に、アラスカに埋もれた伝説を後世に伝える貴重な1冊でもある。
それぞれの人物の伝記はたくさんあるかもしれないけれども、
アラスカという土地にオーロラぐらいしか思い浮かばない日本人の私たちにとっては、
星野さんを通して知る物語はかなり貴重。
シリアとジニー。
2人の怖いもの知らずのパイオニアが、まだまだ未開のアラスカに引き寄せられ、
「キャンプ・デナリ」を建て、そこに無数の伝説的クライマー、ナチュラリストらが集い、
後には部族、土地の権利・保護活動の中心人物にまでなるわけだけれども、
ここでは本書にある通り、サン・テグジュペリが書いた『夜間飛行』の時代が生き生きと描かれていて
無鉄砲な冒険の数々にただただ夢中になってしまう。
その2人の若いパイオニアが女性だというところが、とくに私を強烈にひきつけた。
それらの人物が偉業を成し遂げるつもりなどまったく想像すらせずに、
ただひたすら空を飛びたくて、山に登りたくて、アラスカという土地に惹きつけられて生きていた様子が、
文章とともに所々にはさまれた当時の写真に見られるのも素晴らしい。
過酷なブッシュパイロットの遭難救助の件は『岳』を思いださせる。
他の著書がアラスカに棲むカリブー、グリズリーなどの動物に焦点があてられているのと比べて、
遺作となった本書には、星野さんも含め、アラスカに魅了されて一生を捧げた人々の壮大な物語がたくさん詰まっていた。
同時に、その後、かつてのパイオニアたちは、時代の流れとともに散り散りになり、
油田開発という大事件が起こって西洋文明がなだれこみ、国立公園が指定されたことで原住民や土地に“見えない線”が引かれ、
かつて太古から受け継がれてきた精神文化と消費文化の狭間で悩み、もがく姿も描かれ、居た堪れない思いに囚われる。
先日観た岩合さんの写真展では、広大な国立公園で自然環境に近い状態で野生動物が生きている様子を写真で観て、
「自然が守られている」という安心感を持ったけれども、その自然を糧にして、共存してきた人々にとっては脅威だったんだな・・・
一点から見ると「善」でも、別の視点から見ると「悪」にもなる。この世界の複雑さ。
星野さんは今でもきっと空から時代の流れと、アラスカの人々、動物の暮らし、自然の移り変わりを静かに眺めていることだろう。
【内容抜粋メモ】(ネタバレ注意



「フロンティアというのはね、2つの種類の人間を魅きつけるところなの。
実に魅力的な人々と、悪人たち・・・両方とも、生まれ育った世界に溶け込めず、何かから逃げてきた人間たちだからね」
フェアバンクスの町も、何もない原野に一人の詐欺師が現れたところから始まった。
 1901年 ゴールドラッシュ
1901年 ゴールドラッシュ
一攫千金を夢見てアラスカに来た商人バーネット。
蒸気船の煙を見つけて、何か手に入る物資はないかと、何マイルも山中を走ってきたイタリア人探鉱者・フェリックス・ペドロ。
ペドロは砂金を掘り当て、原野は一夜でブームタウンと化し、バーネットは最初の町長となる。
 1917年 ジニー・ウッド産まれる@オレゴン州モロ
1917年 ジニー・ウッド産まれる@オレゴン州モロ
 1919年 シリア・ハンター産まれる@ワシントン州アーリントン
1919年 シリア・ハンター産まれる@ワシントン州アーリントン
1927年、リンドバーグが大西洋無着陸横断に成功。
1929年、ドイツの飛行船ツェッペリンが世界一周に成功。
******************************シリアとジニー、アラスカへ
シリアもジニーも、初めての飛行機との出会いは「バーンストーマー」。バーン(納屋)ストーマー(嵐)
彼らは空軍からボロボロの練習機を安く買って、アメリカ中の農場に突然現れ、5ドルで5分の空の旅という商売をしていた
シリア「女性パイロットのパイオニア、アメリア・イアハートは私の憧れだった」
製材所の事務員となったシリアは、ある日、なにかに導かれるように小さな飛行場で飛行訓練の申し込みにサインする。
その後、民間の航空学校をトップの成績で卒業した。
ジニーは、大学の飛行クラスを終えて、パイロットライセンスを持っていた。
WASP(約150人の米空軍女性パイロット)


彼女たちは造られた飛行機を戦闘各地に運ぶ仕事をした。
最新鋭戦闘機には、たった一人のパイロット席しかなく、飛行訓練を十分に受けることもなく、
新品の飛行機を、マニュアルを反駁しながら飛ばさなければならず、命を落とした仲間もいた。
第二次世界大戦が終わり、WASPは解体、女性パイロットは職を失う。
彼女らはアメリカ中に飛行機を運んだが、アラスカだけは除外されていた。
フェアバンクスのアラスカ空軍基地には女性用施設が何もなかったため。
ジーン・ジャックという詐欺師が、アラスカに古い飛行機を運ぶ仕事を持ってきて、シリアとジニーは飛びつく。
ジニー「確信していたの。本当にやりたいことを想い続けていれば、いつかその夢は叶うって」
アーチー・フィガーソン:キング・オブ・コッツビューと言われた男。レストランやロードハウス(宿泊所)を経営し仕切っていた。
 1946年12月6日 アラスカに飛び立つ
1946年12月6日 アラスカに飛び立つ


シリアとジニー/小さなイグルー
飛行機があまりにボロくて、それを女性が運ぶというので許可が下りず、どんどん遅れる予定の中、ギリギリで飛び立つ。
ジニーの飛行機“小さなイグルー”とシリアは並んで飛んだが、途中ではぐれ、キンブリングという緊急滑走路で再会する。
気温はマイナス60度。「ウィングオブノース」というラジオ番組は、2人の女性パイロットの様子を毎日のように伝え、
飛行時間27日目、1947年1月1日、2人はフェアバンクスに到着する。
******************************多民族をまとめた「アラスカ核実験場化計画」

エドワード・テラー:「水爆の父」と呼ばれた物理学者。
「プロジェクト・チェリオット(アラスカ核実験場化計画)」
アラスカ北極圏で原爆の実験を目的とした人工港を造ろうとした計画。
1万年以上も個々に散らばって生きてきた先住民(エスキモー、アサバスカンインディアン)をまとめる引き金となった。
シリアとジニーらも、その反対運動の中心人物となる。

環境調査が行われた頃のケープトンプソン
19C。
イギリス人のキャプテン・ビーチェイが率いる探検隊が初めてティキラック地方(現ポイントホープ村)を訪れ、ケープトンプソンと名付けた。
星野さんがアラスカに移住した1978年、最初の旅で行った場所でもある。
1939年。考古学者ルイス・ギディングらが調査し、何万年と手付かずだった600~700戸の壮大な住居跡を発見。
現ポイントホープ村は、人間が暮らし続けてきた北アメリカ最古の場所だった。
1945年。オッペンハイマー率いる「マンハッタン計画」に参加。
同年。ヒロシマ、ナガサキに原爆投下
テラーは、ビキニ環礁での実験で反対を受け、新たな実験場所を求め、“あまり人が住んでいない”という理由から
AEC(アメリカ原子力委員会)がアラスカを選んだ場所は、皮肉にも人間が太古から暮らし続けてきたポイントホープ村だった。
ビル・プルーイット:

環境調査を任された生物学者。シートンを愛読して、北方の自然に憧れ、1953年、初めてアラスカにやってきた。
ビルのフィールドバイオロジストとしての力は圧倒的だった。
物理の専門用語ばかりの話を理解する村人はほとんどいなかったが、
ケープトンプソンの風景が、キノコ雲とともに消えるアニメーションは衝撃を与えた。
「放出された原子灰のほとんどは数時間で無害になります。原爆で生き残った日本の被爆者はすっかり回復に向かっています。
カリブーや海の生物には何の影響もありません」と説明する関係者。
ポイントホープの村人は、委員会の発言を自慢のテープレコーダーにすべて録音した。
計画の環境アセスメントの委託を受けたアラスカ大学は、巨額な予算に酔いしれていた。
アラスカの財政を潤すという魅力に、小さな政界、経済界はすっかり揺さぶられた。
******************************アラスカは誰の土地か?
反対運動の芽は、まずエスキモーの中からはじまった。
村で一番多くカリブーを食べている男が放射能量がもっとも高かった。
カリブーが主食とする地衣類は、放射能を蓄積するもっとも理想的な生物だった。
その関係に気づいたビルは、この計画が生態系に及ぼす未来がはっきり見えたが、こよなく愛したアラスカから去らねばならない未来も見えた。
1960年。ネバダ州はアメリカンインディアンの居留地がある砂漠地帯で、アメリカの最初の核実験場になったばかりだった。
核開発の信奉者だったウィリアム・ウッドがアラスカ大学の学長となり、大学に巨額の予算を引き込もうとしていた。
ビルのレポートは、データのいくつかが大学側によって削除された。
地衣類とカリブーの食物連鎖と放射能の危険性を示唆した箇所はまったく削られ、心配はほぼないという根拠のない安全性が強調されていた。
当時の一般大衆の核への知識は低く、環境保護論者さえ、自然破壊となるダム建設に代わるものとして大きな期待をかけていた。
結果的には、委員会に雇われた3人の研究者が、計画を潰すために立ち上がる。
FBI、CIAエージェントが来て、ドン・フットはその後不慮の死を遂げる。
3人の研究者は解雇されたが、シリアとジニーが送り続けたニュースレターは、アメリカ本土で論争を巻き起こす。
1961年。アメリカ人宇宙飛行士が月面着陸成功、キューバ危機。
ハワード・ロック(当時50歳):一時期は浮浪者だったが、エスキモーの芸術家が故郷のポイントホープに戻り、やがて救世主となる。
ニュースレターは、「アメリカンインディアン協会」(代表:マディガン女史)を大きく動かした。
マディガン女史「アメリカがロシアからアラスカを買った時(約100年前)の土地法「先住民権」で、伝統的な暮らしが保障されています」
ハワードは村の代表として内務省に抗議の手紙を書いた。

白人が来るずっと以前から暮らしてきたエスキモーたち
同じ頃、バロー村では一人の村人がケワタガモを撃って逮捕された。渡り鳥はクジラが捕れない時期、生存に関わる食料となる。
1961年。「国際渡り鳥条約」が施行され、狩猟は営巣が終わる9月以降に限られた。
この条約は白人のスポーツハンティングのために作られた。
同年、バローの集会場にさまざまな村から200人以上のエスキモーが、有史以来初めて1つの目的のために集まった。
モンゴロイドがベーリング海峡を渡って以来、これほど大きな歴史的出来事はなかっただろう。
ニューヨークタイムズの記事は「地衣類を食べるカリブーが核実験の障害となるかもしれない」と見出しを飾った。
1962年。アメリカ原子力委員会の計画に内務省が介入するという通告が届く。
同年。委員会は記者会見を開き「プロジェクト・チェリオット」は中止された。
しかし、ビルはブラックリストに載り、カナダに移住。30年が経つ。
1994年。星野さんはビルを訪ねにウィニペグに行った。
1979年、星野さんが海鳥の調査をしていたある鳥類学者とビルは知人だった。
ビルは、星野さんの愛読書『Animals of the North』『旅をする木』の著者でもある。
3年前の夏、アラスカ大学の図書館員が、古い資料から、当時、計画中止後も、核廃棄物が極秘で実験的に
ケープトンプソンに埋められたままになっている事実を見つけて、周辺のエスキモーの村をパニックにおとしいれた。
2年前、ビルは長年の極北の野生動物の研究業績に対し、カナダ科学アカデミーから最高賞を与えられた。
アラスカ大学も名誉博士号を与えたが、ビルは1週間滞在後、カナダにすぐ帰っていった。

フェアバンクスにあるビルの丸太小屋。30年近く手放さなかったが、2年前に他人に譲った
"Give me a winter
Give me dogs
And you can have the rest"
(私に冬を与えてくれ。私に犬を与えてくれ。あとはすべてお前にあげるから)
ビルが好きなある探検家の言葉。

現在は、マニトバ大学の動物学で教授を務めるビルに、星野さんは核について一切話さなかった
この一連の事件は、後にアラスカを大きく揺るがす「原住民土地請求権」の闘いへとつながる。
******************************マッキンレー山への挑戦


左からウッド、テイラー、レス、ジョージ/空からサポートしたジニー
1954年。4人の若者が誰もなしえなかったマッキンレー山を南面から登るルートを探していた。
エルトン・テイラー、ジョージ・アーガス、レス・ベリック、オートン・ウッド(ジニーの夫)。
4人はむしろこの登山がニュースになるのをとても避けていた。
「登攀(とうはん)」登山で、険しい岩壁などをよじ登ること。とはん。
登山開始から3週間後、最大の難関、巨大な雪庇が立ちはだかっていた。
が、まるで誰かが導いたように、小さな氷のトンネルを見つけて入っていった。
そこを抜けるとサウスバットレスの稜線の上にいた。
翌日パーティは山頂に立ち、すっかり高度順化ができあがっていたため、ハイキングのように下降をはじめた。
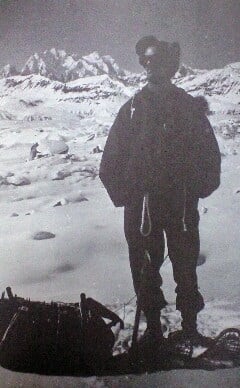
屈強のクライマー、エルトン・テイラー
突然、エルトンが滑り落ちた。雪壁からザイルにぶら下がった彼はすでに息絶えていた。
ジョージは骨盤を外していたため、食料とともにテントに残し、2人は下山し助けを求めた。
この救出行は、南面からの初横断の成功とともに、『タイム』『ライフ』に取り上げられ、全米に報道された。
その後、このルートから登った者は誰もいない。
エルトン遭難後、すでに妊娠していた妻バーニーはアラスカを去った。
バーニーは、幼い頃に両親を亡くし、夫の遭難、不慮の事故で他人の子どもを轢死させたことで、晩年は精神に破綻をきたした。
40年ぶりにアラスカに戻って、キャンプ・デナリでジニーと再会を果す。
バーニー「ひとつだけどうしても悔やまれるのは、エルトンが父親になることを知らずに死んでしまったこと」
ジニー「それは違う。あの日、ルース氷河で最後のフードドロップをして、あなたが妊娠したことを私は確かに伝えたわ」
******************************キャンプ・デナリ~伝説のロッジ


キャンプ・デナリからマッキンレーを見る
シリアとジニーにアラスカの中でもっとも懐かしい場所はどこかと聞くと「マッキンレー国立公園ね」と迷いなく答えた。
ブッシュパイロットの時代が終わり、彼女たちの青春はマッキンレーの山麓に広がっていく。
パイオニア時代からある、アラスカの歴史的なロッジを建てたのが2人だった。
ジニーはレインジャーのウディと結婚して、カトマイ国立公園の初めてのレインジャーに任命された。
レス・ベリック:
マッキンレー登頂の仲間の1人。後にビルとともに「プロジェクト・チェリオット」と闘い、アラスカ大学を追放された植物学者。
晩年、「アラスカの植物学の父」と呼ばれ、フェアバンクスで暮らした。


アコーディオンを弾くウディ
シリア「私たちは大工、水道管工事、医者、ガイド、なんでもやった。キャンバステントからスタートしたのよ」
小さな山小屋は、さまざまな出会いの場所となった。
 ビル・ベリー:アラスカの伝説的な動物画家。キャンプ・デナリの最初のコック。
ビル・ベリー:アラスカの伝説的な動物画家。キャンプ・デナリの最初のコック。
 ミュリー兄弟:『マッキンレー山のオオカミ』の著者。アラスカの生物学のパイオニア。
ミュリー兄弟:『マッキンレー山のオオカミ』の著者。アラスカの生物学のパイオニア。
 ブラフォード・ウォッシュバーン:マッキンレー山域の地図を作成した著名な地理学者。
ブラフォード・ウォッシュバーン:マッキンレー山域の地図を作成した著名な地理学者。
 クレム:フェアバンクスの山道具屋の老主人。ヒッチハイクをしていてジニーに拾われた。そのままドイツに帰らず、アラスカに移住。
クレム:フェアバンクスの山道具屋の老主人。ヒッチハイクをしていてジニーに拾われた。そのままドイツに帰らず、アラスカに移住。
1976年。「私は最初、環境保護論者でも何でもなかった」と言っていたシリアは、のちに
アメリカでもっとも権威のある自然保護団体「ウィルダネスソサエティ」の女性初会長となる。
星野さんは、毎年3月、日本の子どもたち十数人をルース氷河に連れてきて、キャンプをし、星やオーロラを見る体験ツアーをしていた。


ドン・シェルドン/マッキンレーに向かうドン・シェルドンが操縦する飛行機
ドン・シェルドン:マッキンレー山域でひとつの時代を築いた伝説のブッシュパイロット。1975年、53歳で死去。
優れたブッシュパイロットとは、飛行技術だけでなく、さまざまなレベルの客の気持ちや体験を、どれだけ同じ立場に立って、
その苦しみや感動を互いに分かち合うことができるかのような気がする。
客を運ぶために飛ぶだけのパイロットならいくらでもいる。
1972年。ドンは5人の日本女性隊をカヒルトナ氷河に運んだ。
1週間後、最後の頂上アタックに向かった3人が行方不明になり、遺体が見つかるまでドンは10日間、毎日飛び続けた。
その飛行時間の莫大な捜索費用は、妻と相談して、一切請求しなかった。
 ドンとブラフォード・ウォッシュバーンの出会い
ドンとブラフォード・ウォッシュバーンの出会い
ウォッシュバーンは、マッキンレー山域の地図を作成する夢を抱いていた。
空気が究めて薄く、高山での飛行には特別なセンスが要求されるが、ドンはどんな場所にも冷静にランディングした。
ウォッシュバーンは、旧友ボブ・リーブに「あいつはいつか山で命を落とすか、信じられないほど優れたパイロットになるだろう」と語っている。
ボブ・リーブ:氷河への着陸に初成功したアラスカの山岳飛行のパイオニア。
ウォッシュバーンは、あらゆるピークの標高を測り、あらゆる氷河を測量し、現在の地図を作った。
ドン亡き後、彼が愛したルース氷河源流にドン・シェルドンの名前がつけられた。

ドン・シェルドンの飛行機格納庫
星野「アラスカで会ってみたかったが、ぼくは間に合わなかった」
(この著書にも、この「間に合った」「間に合わなかった」という言葉がよく出てくる
が、彼の未亡人ロバータと知り合った。日本の子どもたちの体験にシェルドン小屋を使わせてくれと相談したのがきっかけ。
******************************タクシードライヴァー
コバック川の川沿いには、わずか5つのエスキモーの村がある。
ノルビック、カイアナ、アンブラー、ショグナック、コバック・・・・その人口はきっと1000人にも満たない。
「早春の頃、雪解けとともにこの川が流れはじめるだろ。その時の風景がすさまじいんだ」


セス、白人のステイシー
セス・キャントナー:
アラスカ大学を卒業後、両親は狩猟だけによる原野の生活を求めてコバック川流域に移住した。
10年前、脳腫瘍を患った母アーナのため、両親はハワイ島に移住。
セスは白人でありながら、エスキモーの魂を持つという複雑な境遇にあり、それを著作『タクシードライヴァー』にしたためた。
その最初の一文でセスの立場がよく表れている。白人は、白人女性を決して「白人女性」とは呼ばないからだ。
セスは、老婦人が自分を胡散臭そうに見ているのを感じる。それらしく振る舞おうとするほど、なぜか泥沼に入ってゆく。
老いてゆくことが無用な存在になるアメリカ社会と、それが重要な存在になってゆくエスキモー社会との違いを感じる。
路上で酔い潰れているエスキモーの脇を情けない思いで通り過ぎた後、あれは自分が子どもの頃に世話になった知人ではと気づいたりする。
セスのストーリーには、白人社会とのギャップと、変わりゆくエスキモー社会に対する悲しみが、
どちらにも属することができない自身の想いの中で生き生きと描かれていた。
キャントナー夫妻の長男コールは原野を去り、それまで一度も学校に行った事がなかったのにアラスカ大学に一番の成績入学した。
その時、フェアバンクスの新聞社のインタビューを思い出すと今でも笑ってしまう。
「君は一体、今まで北極圏の山の中で何をしていたのですか?」
「・・・生活をしていました」
コールは大学卒業後、「ピースコア(アメリカの青年海外協力隊)」に参加し、アフリカに渡った。
セスは白人のステイシーと今年結婚し、コッツビューで、セスはエスキモーに野菜の栽培を教え、ステイシーは図書館で働き、
それが終わるとコバック川の原野の家に帰る。
「ミチオ、いつかコバック川の家を失うかもしれない。
国立公園のレインジャーが火をつけて燃やすことができる家のリストにずっと入っているんだ」
アラスカの土地所有権問題は、ゴールドラッシュなど比較にならないほど歴史的な出来事となり、激動の時代になっていった。
アラスカの原野は、アメリカ、アラスカ州、先住民の間で見えない線が引かれ、かつてのフロンティアは終わりを告げた。
セスにとって、国立公園ほど恐ろしい存在はなかったのだ。
(vol.2につづく
星野道夫/著
「彼らはオーロラをノーザンライツ(北極光)と呼ぶ。
星野道夫はこの遺作のなかで生きている。」
図書館には1997年発行と、2000年発行の新潮文庫の2冊だったので、古いほうを選んだ。
表紙も上半分が黒いほう。

星野さんの遺作ということで、他の作品を読んでから最後にとっておいた1冊。
星野さんの著書の集大成であると同時に、アラスカに埋もれた伝説を後世に伝える貴重な1冊でもある。
それぞれの人物の伝記はたくさんあるかもしれないけれども、
アラスカという土地にオーロラぐらいしか思い浮かばない日本人の私たちにとっては、
星野さんを通して知る物語はかなり貴重。
シリアとジニー。
2人の怖いもの知らずのパイオニアが、まだまだ未開のアラスカに引き寄せられ、
「キャンプ・デナリ」を建て、そこに無数の伝説的クライマー、ナチュラリストらが集い、
後には部族、土地の権利・保護活動の中心人物にまでなるわけだけれども、
ここでは本書にある通り、サン・テグジュペリが書いた『夜間飛行』の時代が生き生きと描かれていて
無鉄砲な冒険の数々にただただ夢中になってしまう。
その2人の若いパイオニアが女性だというところが、とくに私を強烈にひきつけた。
それらの人物が偉業を成し遂げるつもりなどまったく想像すらせずに、
ただひたすら空を飛びたくて、山に登りたくて、アラスカという土地に惹きつけられて生きていた様子が、
文章とともに所々にはさまれた当時の写真に見られるのも素晴らしい。
過酷なブッシュパイロットの遭難救助の件は『岳』を思いださせる。
他の著書がアラスカに棲むカリブー、グリズリーなどの動物に焦点があてられているのと比べて、
遺作となった本書には、星野さんも含め、アラスカに魅了されて一生を捧げた人々の壮大な物語がたくさん詰まっていた。
同時に、その後、かつてのパイオニアたちは、時代の流れとともに散り散りになり、
油田開発という大事件が起こって西洋文明がなだれこみ、国立公園が指定されたことで原住民や土地に“見えない線”が引かれ、
かつて太古から受け継がれてきた精神文化と消費文化の狭間で悩み、もがく姿も描かれ、居た堪れない思いに囚われる。
先日観た岩合さんの写真展では、広大な国立公園で自然環境に近い状態で野生動物が生きている様子を写真で観て、
「自然が守られている」という安心感を持ったけれども、その自然を糧にして、共存してきた人々にとっては脅威だったんだな・・・
一点から見ると「善」でも、別の視点から見ると「悪」にもなる。この世界の複雑さ。
星野さんは今でもきっと空から時代の流れと、アラスカの人々、動物の暮らし、自然の移り変わりを静かに眺めていることだろう。
【内容抜粋メモ】(ネタバレ注意



「フロンティアというのはね、2つの種類の人間を魅きつけるところなの。
実に魅力的な人々と、悪人たち・・・両方とも、生まれ育った世界に溶け込めず、何かから逃げてきた人間たちだからね」
フェアバンクスの町も、何もない原野に一人の詐欺師が現れたところから始まった。
 1901年 ゴールドラッシュ
1901年 ゴールドラッシュ一攫千金を夢見てアラスカに来た商人バーネット。
蒸気船の煙を見つけて、何か手に入る物資はないかと、何マイルも山中を走ってきたイタリア人探鉱者・フェリックス・ペドロ。
ペドロは砂金を掘り当て、原野は一夜でブームタウンと化し、バーネットは最初の町長となる。
 1917年 ジニー・ウッド産まれる@オレゴン州モロ
1917年 ジニー・ウッド産まれる@オレゴン州モロ 1919年 シリア・ハンター産まれる@ワシントン州アーリントン
1919年 シリア・ハンター産まれる@ワシントン州アーリントン1927年、リンドバーグが大西洋無着陸横断に成功。
1929年、ドイツの飛行船ツェッペリンが世界一周に成功。
******************************シリアとジニー、アラスカへ
シリアもジニーも、初めての飛行機との出会いは「バーンストーマー」。バーン(納屋)ストーマー(嵐)
彼らは空軍からボロボロの練習機を安く買って、アメリカ中の農場に突然現れ、5ドルで5分の空の旅という商売をしていた

シリア「女性パイロットのパイオニア、アメリア・イアハートは私の憧れだった」
製材所の事務員となったシリアは、ある日、なにかに導かれるように小さな飛行場で飛行訓練の申し込みにサインする。
その後、民間の航空学校をトップの成績で卒業した。
ジニーは、大学の飛行クラスを終えて、パイロットライセンスを持っていた。
WASP(約150人の米空軍女性パイロット)


彼女たちは造られた飛行機を戦闘各地に運ぶ仕事をした。
最新鋭戦闘機には、たった一人のパイロット席しかなく、飛行訓練を十分に受けることもなく、
新品の飛行機を、マニュアルを反駁しながら飛ばさなければならず、命を落とした仲間もいた。
第二次世界大戦が終わり、WASPは解体、女性パイロットは職を失う。
彼女らはアメリカ中に飛行機を運んだが、アラスカだけは除外されていた。
フェアバンクスのアラスカ空軍基地には女性用施設が何もなかったため。
ジーン・ジャックという詐欺師が、アラスカに古い飛行機を運ぶ仕事を持ってきて、シリアとジニーは飛びつく。
ジニー「確信していたの。本当にやりたいことを想い続けていれば、いつかその夢は叶うって」
アーチー・フィガーソン:キング・オブ・コッツビューと言われた男。レストランやロードハウス(宿泊所)を経営し仕切っていた。
 1946年12月6日 アラスカに飛び立つ
1946年12月6日 アラスカに飛び立つ

シリアとジニー/小さなイグルー
飛行機があまりにボロくて、それを女性が運ぶというので許可が下りず、どんどん遅れる予定の中、ギリギリで飛び立つ。
ジニーの飛行機“小さなイグルー”とシリアは並んで飛んだが、途中ではぐれ、キンブリングという緊急滑走路で再会する。
気温はマイナス60度。「ウィングオブノース」というラジオ番組は、2人の女性パイロットの様子を毎日のように伝え、
飛行時間27日目、1947年1月1日、2人はフェアバンクスに到着する。
******************************多民族をまとめた「アラスカ核実験場化計画」

エドワード・テラー:「水爆の父」と呼ばれた物理学者。
「プロジェクト・チェリオット(アラスカ核実験場化計画)」
アラスカ北極圏で原爆の実験を目的とした人工港を造ろうとした計画。
1万年以上も個々に散らばって生きてきた先住民(エスキモー、アサバスカンインディアン)をまとめる引き金となった。
シリアとジニーらも、その反対運動の中心人物となる。

環境調査が行われた頃のケープトンプソン
19C。
イギリス人のキャプテン・ビーチェイが率いる探検隊が初めてティキラック地方(現ポイントホープ村)を訪れ、ケープトンプソンと名付けた。
星野さんがアラスカに移住した1978年、最初の旅で行った場所でもある。
1939年。考古学者ルイス・ギディングらが調査し、何万年と手付かずだった600~700戸の壮大な住居跡を発見。
現ポイントホープ村は、人間が暮らし続けてきた北アメリカ最古の場所だった。
1945年。オッペンハイマー率いる「マンハッタン計画」に参加。
同年。ヒロシマ、ナガサキに原爆投下

テラーは、ビキニ環礁での実験で反対を受け、新たな実験場所を求め、“あまり人が住んでいない”という理由から
AEC(アメリカ原子力委員会)がアラスカを選んだ場所は、皮肉にも人間が太古から暮らし続けてきたポイントホープ村だった。
ビル・プルーイット:

環境調査を任された生物学者。シートンを愛読して、北方の自然に憧れ、1953年、初めてアラスカにやってきた。
ビルのフィールドバイオロジストとしての力は圧倒的だった。
物理の専門用語ばかりの話を理解する村人はほとんどいなかったが、
ケープトンプソンの風景が、キノコ雲とともに消えるアニメーションは衝撃を与えた。
「放出された原子灰のほとんどは数時間で無害になります。原爆で生き残った日本の被爆者はすっかり回復に向かっています。
カリブーや海の生物には何の影響もありません」と説明する関係者。
ポイントホープの村人は、委員会の発言を自慢のテープレコーダーにすべて録音した。
計画の環境アセスメントの委託を受けたアラスカ大学は、巨額な予算に酔いしれていた。
アラスカの財政を潤すという魅力に、小さな政界、経済界はすっかり揺さぶられた。
******************************アラスカは誰の土地か?
反対運動の芽は、まずエスキモーの中からはじまった。
村で一番多くカリブーを食べている男が放射能量がもっとも高かった。
カリブーが主食とする地衣類は、放射能を蓄積するもっとも理想的な生物だった。
その関係に気づいたビルは、この計画が生態系に及ぼす未来がはっきり見えたが、こよなく愛したアラスカから去らねばならない未来も見えた。
1960年。ネバダ州はアメリカンインディアンの居留地がある砂漠地帯で、アメリカの最初の核実験場になったばかりだった。
核開発の信奉者だったウィリアム・ウッドがアラスカ大学の学長となり、大学に巨額の予算を引き込もうとしていた。
ビルのレポートは、データのいくつかが大学側によって削除された。
地衣類とカリブーの食物連鎖と放射能の危険性を示唆した箇所はまったく削られ、心配はほぼないという根拠のない安全性が強調されていた。
当時の一般大衆の核への知識は低く、環境保護論者さえ、自然破壊となるダム建設に代わるものとして大きな期待をかけていた。
結果的には、委員会に雇われた3人の研究者が、計画を潰すために立ち上がる。
FBI、CIAエージェントが来て、ドン・フットはその後不慮の死を遂げる。
3人の研究者は解雇されたが、シリアとジニーが送り続けたニュースレターは、アメリカ本土で論争を巻き起こす。
1961年。アメリカ人宇宙飛行士が月面着陸成功、キューバ危機。
ハワード・ロック(当時50歳):一時期は浮浪者だったが、エスキモーの芸術家が故郷のポイントホープに戻り、やがて救世主となる。
ニュースレターは、「アメリカンインディアン協会」(代表:マディガン女史)を大きく動かした。
マディガン女史「アメリカがロシアからアラスカを買った時(約100年前)の土地法「先住民権」で、伝統的な暮らしが保障されています」
ハワードは村の代表として内務省に抗議の手紙を書いた。

白人が来るずっと以前から暮らしてきたエスキモーたち
同じ頃、バロー村では一人の村人がケワタガモを撃って逮捕された。渡り鳥はクジラが捕れない時期、生存に関わる食料となる。
1961年。「国際渡り鳥条約」が施行され、狩猟は営巣が終わる9月以降に限られた。
この条約は白人のスポーツハンティングのために作られた。
同年、バローの集会場にさまざまな村から200人以上のエスキモーが、有史以来初めて1つの目的のために集まった。
モンゴロイドがベーリング海峡を渡って以来、これほど大きな歴史的出来事はなかっただろう。
ニューヨークタイムズの記事は「地衣類を食べるカリブーが核実験の障害となるかもしれない」と見出しを飾った。
1962年。アメリカ原子力委員会の計画に内務省が介入するという通告が届く。
同年。委員会は記者会見を開き「プロジェクト・チェリオット」は中止された。
しかし、ビルはブラックリストに載り、カナダに移住。30年が経つ。
1994年。星野さんはビルを訪ねにウィニペグに行った。
1979年、星野さんが海鳥の調査をしていたある鳥類学者とビルは知人だった。
ビルは、星野さんの愛読書『Animals of the North』『旅をする木』の著者でもある。
3年前の夏、アラスカ大学の図書館員が、古い資料から、当時、計画中止後も、核廃棄物が極秘で実験的に
ケープトンプソンに埋められたままになっている事実を見つけて、周辺のエスキモーの村をパニックにおとしいれた。
2年前、ビルは長年の極北の野生動物の研究業績に対し、カナダ科学アカデミーから最高賞を与えられた。
アラスカ大学も名誉博士号を与えたが、ビルは1週間滞在後、カナダにすぐ帰っていった。

フェアバンクスにあるビルの丸太小屋。30年近く手放さなかったが、2年前に他人に譲った
"Give me a winter
Give me dogs
And you can have the rest"
(私に冬を与えてくれ。私に犬を与えてくれ。あとはすべてお前にあげるから)
ビルが好きなある探検家の言葉。

現在は、マニトバ大学の動物学で教授を務めるビルに、星野さんは核について一切話さなかった
この一連の事件は、後にアラスカを大きく揺るがす「原住民土地請求権」の闘いへとつながる。
******************************マッキンレー山への挑戦


左からウッド、テイラー、レス、ジョージ/空からサポートしたジニー
1954年。4人の若者が誰もなしえなかったマッキンレー山を南面から登るルートを探していた。
エルトン・テイラー、ジョージ・アーガス、レス・ベリック、オートン・ウッド(ジニーの夫)。
4人はむしろこの登山がニュースになるのをとても避けていた。
「登攀(とうはん)」登山で、険しい岩壁などをよじ登ること。とはん。
登山開始から3週間後、最大の難関、巨大な雪庇が立ちはだかっていた。
が、まるで誰かが導いたように、小さな氷のトンネルを見つけて入っていった。
そこを抜けるとサウスバットレスの稜線の上にいた。
翌日パーティは山頂に立ち、すっかり高度順化ができあがっていたため、ハイキングのように下降をはじめた。
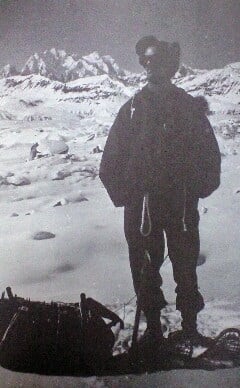
屈強のクライマー、エルトン・テイラー
突然、エルトンが滑り落ちた。雪壁からザイルにぶら下がった彼はすでに息絶えていた。
ジョージは骨盤を外していたため、食料とともにテントに残し、2人は下山し助けを求めた。
この救出行は、南面からの初横断の成功とともに、『タイム』『ライフ』に取り上げられ、全米に報道された。
その後、このルートから登った者は誰もいない。
エルトン遭難後、すでに妊娠していた妻バーニーはアラスカを去った。
バーニーは、幼い頃に両親を亡くし、夫の遭難、不慮の事故で他人の子どもを轢死させたことで、晩年は精神に破綻をきたした。
40年ぶりにアラスカに戻って、キャンプ・デナリでジニーと再会を果す。
バーニー「ひとつだけどうしても悔やまれるのは、エルトンが父親になることを知らずに死んでしまったこと」
ジニー「それは違う。あの日、ルース氷河で最後のフードドロップをして、あなたが妊娠したことを私は確かに伝えたわ」
******************************キャンプ・デナリ~伝説のロッジ


キャンプ・デナリからマッキンレーを見る
シリアとジニーにアラスカの中でもっとも懐かしい場所はどこかと聞くと「マッキンレー国立公園ね」と迷いなく答えた。
ブッシュパイロットの時代が終わり、彼女たちの青春はマッキンレーの山麓に広がっていく。
パイオニア時代からある、アラスカの歴史的なロッジを建てたのが2人だった。
ジニーはレインジャーのウディと結婚して、カトマイ国立公園の初めてのレインジャーに任命された。
レス・ベリック:
マッキンレー登頂の仲間の1人。後にビルとともに「プロジェクト・チェリオット」と闘い、アラスカ大学を追放された植物学者。
晩年、「アラスカの植物学の父」と呼ばれ、フェアバンクスで暮らした。


アコーディオンを弾くウディ
シリア「私たちは大工、水道管工事、医者、ガイド、なんでもやった。キャンバステントからスタートしたのよ」
小さな山小屋は、さまざまな出会いの場所となった。
 ビル・ベリー:アラスカの伝説的な動物画家。キャンプ・デナリの最初のコック。
ビル・ベリー:アラスカの伝説的な動物画家。キャンプ・デナリの最初のコック。 ミュリー兄弟:『マッキンレー山のオオカミ』の著者。アラスカの生物学のパイオニア。
ミュリー兄弟:『マッキンレー山のオオカミ』の著者。アラスカの生物学のパイオニア。 ブラフォード・ウォッシュバーン:マッキンレー山域の地図を作成した著名な地理学者。
ブラフォード・ウォッシュバーン:マッキンレー山域の地図を作成した著名な地理学者。 クレム:フェアバンクスの山道具屋の老主人。ヒッチハイクをしていてジニーに拾われた。そのままドイツに帰らず、アラスカに移住。
クレム:フェアバンクスの山道具屋の老主人。ヒッチハイクをしていてジニーに拾われた。そのままドイツに帰らず、アラスカに移住。1976年。「私は最初、環境保護論者でも何でもなかった」と言っていたシリアは、のちに
アメリカでもっとも権威のある自然保護団体「ウィルダネスソサエティ」の女性初会長となる。
星野さんは、毎年3月、日本の子どもたち十数人をルース氷河に連れてきて、キャンプをし、星やオーロラを見る体験ツアーをしていた。


ドン・シェルドン/マッキンレーに向かうドン・シェルドンが操縦する飛行機
ドン・シェルドン:マッキンレー山域でひとつの時代を築いた伝説のブッシュパイロット。1975年、53歳で死去。
優れたブッシュパイロットとは、飛行技術だけでなく、さまざまなレベルの客の気持ちや体験を、どれだけ同じ立場に立って、
その苦しみや感動を互いに分かち合うことができるかのような気がする。
客を運ぶために飛ぶだけのパイロットならいくらでもいる。
1972年。ドンは5人の日本女性隊をカヒルトナ氷河に運んだ。
1週間後、最後の頂上アタックに向かった3人が行方不明になり、遺体が見つかるまでドンは10日間、毎日飛び続けた。
その飛行時間の莫大な捜索費用は、妻と相談して、一切請求しなかった。
 ドンとブラフォード・ウォッシュバーンの出会い
ドンとブラフォード・ウォッシュバーンの出会いウォッシュバーンは、マッキンレー山域の地図を作成する夢を抱いていた。
空気が究めて薄く、高山での飛行には特別なセンスが要求されるが、ドンはどんな場所にも冷静にランディングした。
ウォッシュバーンは、旧友ボブ・リーブに「あいつはいつか山で命を落とすか、信じられないほど優れたパイロットになるだろう」と語っている。
ボブ・リーブ:氷河への着陸に初成功したアラスカの山岳飛行のパイオニア。
ウォッシュバーンは、あらゆるピークの標高を測り、あらゆる氷河を測量し、現在の地図を作った。
ドン亡き後、彼が愛したルース氷河源流にドン・シェルドンの名前がつけられた。

ドン・シェルドンの飛行機格納庫
星野「アラスカで会ってみたかったが、ぼくは間に合わなかった」
(この著書にも、この「間に合った」「間に合わなかった」という言葉がよく出てくる
が、彼の未亡人ロバータと知り合った。日本の子どもたちの体験にシェルドン小屋を使わせてくれと相談したのがきっかけ。
******************************タクシードライヴァー
コバック川の川沿いには、わずか5つのエスキモーの村がある。
ノルビック、カイアナ、アンブラー、ショグナック、コバック・・・・その人口はきっと1000人にも満たない。
「早春の頃、雪解けとともにこの川が流れはじめるだろ。その時の風景がすさまじいんだ」


セス、白人のステイシー
セス・キャントナー:
アラスカ大学を卒業後、両親は狩猟だけによる原野の生活を求めてコバック川流域に移住した。
10年前、脳腫瘍を患った母アーナのため、両親はハワイ島に移住。
セスは白人でありながら、エスキモーの魂を持つという複雑な境遇にあり、それを著作『タクシードライヴァー』にしたためた。
その最初の一文でセスの立場がよく表れている。白人は、白人女性を決して「白人女性」とは呼ばないからだ。
セスは、老婦人が自分を胡散臭そうに見ているのを感じる。それらしく振る舞おうとするほど、なぜか泥沼に入ってゆく。
老いてゆくことが無用な存在になるアメリカ社会と、それが重要な存在になってゆくエスキモー社会との違いを感じる。
路上で酔い潰れているエスキモーの脇を情けない思いで通り過ぎた後、あれは自分が子どもの頃に世話になった知人ではと気づいたりする。
セスのストーリーには、白人社会とのギャップと、変わりゆくエスキモー社会に対する悲しみが、
どちらにも属することができない自身の想いの中で生き生きと描かれていた。
キャントナー夫妻の長男コールは原野を去り、それまで一度も学校に行った事がなかったのにアラスカ大学に一番の成績入学した。
その時、フェアバンクスの新聞社のインタビューを思い出すと今でも笑ってしまう。
「君は一体、今まで北極圏の山の中で何をしていたのですか?」
「・・・生活をしていました」
コールは大学卒業後、「ピースコア(アメリカの青年海外協力隊)」に参加し、アフリカに渡った。
セスは白人のステイシーと今年結婚し、コッツビューで、セスはエスキモーに野菜の栽培を教え、ステイシーは図書館で働き、
それが終わるとコバック川の原野の家に帰る。
「ミチオ、いつかコバック川の家を失うかもしれない。
国立公園のレインジャーが火をつけて燃やすことができる家のリストにずっと入っているんだ」
アラスカの土地所有権問題は、ゴールドラッシュなど比較にならないほど歴史的な出来事となり、激動の時代になっていった。
アラスカの原野は、アメリカ、アラスカ州、先住民の間で見えない線が引かれ、かつてのフロンティアは終わりを告げた。
セスにとって、国立公園ほど恐ろしい存在はなかったのだ。
(vol.2につづく





























 あとがき:ミチオとの旅~シリア・ハンター
あとがき:ミチオとの旅~シリア・ハンター




