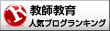『自転車の2人乗りをしたとして、神奈川県警磯子署は11日、横浜市磯子区の無職少女(16)に道交法(乗車積載制限)違反容疑で交通切符(赤切符)を交付した。 自転車の2人乗りでの検挙は県内では2007年11月以来という。 同署幹部によると、少女は8日午後2時半頃、同区杉田の国道16号沿いの歩道で、中学2年の妹(14)を自転車の荷台に乗せ2人乗りをした疑い。 白バイ隊員の2度の警告にもかかわらず走行を続けた。少女は「捕まらないと思った」と話しているという。』 12月12日0時38分配信読売新聞
中学生から大學生まで、自転車に乗るマナーがこの頃悪いので問題になっています。通行人の迷惑も考えずに歩道を無灯火で猛スピートでは知り抜ける高校生やタクシー乗り場で、お年寄りがタクシーに乗ろうとする前を猛スピートで走り抜けたり、当たるか当たらないかのスリルを味わっているらしいですが。猛スピートで、走り抜ける自転車に当たられ怪我をしたり、亡くなられたお年寄りも居ます。この少女自転車の2人乗りで事故を起こさず、怪我をしなくて良かったでずが。いつも2人乗りをしていたのかも分かりません。昔では考えられなかった程自転車に乗る青少年のマナーが悪くなっています。小学校からの自転車の乗り方のマナーや地元警察署による道路交通法の講習会や学校でも自転車で傷害事故を起こさないように交通完全教育教をすべきでは有りませんか。大學で社会常識や自転車の乗り方教えるのでは遅いと思います。警察官や警備員の人に注意されると何が悪いねんと反対に毒付く青少年が多いので困っているらしいですが。自転車に乗るのは自由ですが、自転車に乗る場合マナーも守らないのなら、乗る資格が有りません。自転車の乗るのは自由でも、通行中の人を歩道を歩いている人に怪我をさせ自由は有りません。怪我をさせたのなら責任が有ります。自転車に乗る権利は有りますが、責任と義務が有ります。自由と権利を履き違えた利己主義者が多過ぎるのです。何の為に道路交通法があるのか分かりません。この2人の少女は、道路交通法(乗車又は積載の制限等) 第五十七条 「車両(軽車両を除く。以下この項及び第五十八条の二から第五十八条の五までにおいて同じ。)の運転者は、当該車両について政令で定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方法(以下この条において「積載重量等」という。)の制限を超えて乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。」違反で、交通切符を切られましたが、自転車の2人乗りは危険なので止めましょう。友達を肩に乗せて立って自転車を漕いでいる中学生や高校生もいますね。
◎道路交通法
第十一節 乗車、積載及び牽引(乗車又は積載の方法)
第五十五条 車両の運転者は、当該車両の乗車のために設備された場所以外の場所に乗車させ、又は乗車若しくは積載のために設備された場所以外の場所に積載して車両を運転してはならない。ただし、もつぱら貨物を運搬する構造の自動車(以下次条及び第五十七条において「貨物自動車」という。)で貨物を積載しているものにあつては、当該貨物を看守するため必要な最小限度の人員をその荷台に乗車させて運転することができる。 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。 車両に乗車する者は、当該車両の運転者が前二項の規定に違反することとなるような方法で乗車をしてはならない。 (罰則 第一項及び第二項については第百二十条第一項第十号、第百二十三条 第三項については第百二十一条第一項第六号)
参考資料
自転車の安全利用の促進について
平成19年7月10日
☆警察庁交通局
交通対策本部決定
近年、自転車事故が増加するとともに、自転車が歩道を無秩序に通行している実態を踏まえ、今般、自転車の歩道通行要件の明確化等を内容とする道路交通法の改正が行われたところである。これを機会に、自転車に関する交通秩序の整序化を図り、自転車の安全利用を促進するため、国及び地方公共団体は、次の措置を講ずるものとする。
なお、自転車の通行ルールの広報啓発に当たっては、別添の「自転車安全利用五則」を活用するものとする。
1 自転車通行ルール及び今般の道路交通法の改正内容(以下「自転車通行ルール等」という。)の広報啓発に努めること また、所属職員に対し、自転車通行ルール等の周知を図り、ルールの遵守について指導を徹底すること
2 学校、幼稚園、保育所、福祉施設及び社会教育施設等における交通安全教育、自転車利用者が参加する各種の講習等のあらゆる機会において、自転車通行ルール等の周知徹底を図ること
3 日本自転車普及協会、自転車産業振興協会等の関係団体に協力を要請する等効果的な自転車の通行ルール等の広報啓発を実施すること
4 自転車利用者の悪質・危険な交通法令違反に対する指導及び取締りを強化するとともに、地域交通安全活動推進委員等と連携して自転車の安全利用を促進するための活動を推進すること
5 自転車に係る通行実態・事故実態等を踏まえ、自転車走行空間の整備を推進すること
--------------------------------------------------------------------------------
自転車安全利用五則
1 自転車は、車道が原則、歩道は例外
2 車道は左側を通行
3 歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4 安全ルールを守る
○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○夜間はライトを点灯
○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5 子どもはヘルメットを着用
--------------------------------------------------------------------------------
自転車の通行方法等に関する主なルール
通行場所・方法
◆車道通行の原則
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられ、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側(車両通行帯のない道路では左側端)を通行しなければならない。
著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、路側帯を通行することができるが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第17条第1項及び第4項、第18条第1項/第17条の2
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金/2万円以下の罰金又は科料
◆歩道における通行方法
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行しなければならず、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければならない。
【該当規定】道路交通法第63条の4第2項
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
◆交差点での通行
信号機のある交差点では、信号機の信号に従わなければならない。「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の信号に従う。
【該当規定】道路交通法第7条
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
信号機のない交差点で、一時停止すべきことを示す標識等がある場合は、一時停止しなければならない。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第43条、第36条第3項
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
◆横断
道路や交差点又はその付近に自転車横断帯がある場合は、自転車横断帯を通行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第63条の6,第63条の7第1項
◆自転車道の通行
自転車道が設けられている道路では、やむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければならない。
【該当規定】道路交通法第63条の3
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
自転車の乗り方
◆安全運転の義務
道路及び交通等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
【該当規定】道路交通法第70条
【罰則】3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
◆夜間、前照灯及び尾灯の点灯
夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければならない。
【該当規定】道路交通法第52条第1項、第63条の9第2項、道路交通法施行令第18条 第1項第5号
【罰則】5万円以下の罰金
◆酒気帯び運転の禁止
酒気を帯びて自転車を運転してはならない。
【該当規定】道路交通法第65条第1項
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒に酔った状態で運転した場合)
◆二人乗りの禁止
自転車の二人乗りは、各都道府県公安委員会規則に基づき、6 歳未満の子供を乗せるなどの場合を除き、原則として禁止されて いる。
【該当規定】道路交通法 第57条第2項
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
◆並進の禁止
「並進可」の標識があるところ以外では、並んで走ってはならない。
【該当規定】道路交通法第19条
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
道路交通法の改正による自転車の通行方法等に関するルールの見直し内容
平成19年6月14日に成立した「道路交通法の一部を改正する法律」(平成19年法律第90号)により、次のとおり自転車に関する通行ルール等の規定が見直された。
これらの改正規定は「公布の日から起算して1年を超えない範囲において政令で定める日」から施行されることとなっている。
1.普通自転車の歩道通行に関する規定
(1)普通自転車は、歩道通行可を示す標識等がある場合のほか、
①普通自転車の運転者が児童、幼児又は車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき、
②車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき、 には、歩道を通行することができる。 ただし、警察官等が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
【該当規定】道路交通法第63条の4第1項
(2)普通自転車は、歩道の「普通自転車通行指定部分」(標識等により普通自転車が通行すべき部分)として指定された部分については、当該指定部分を徐行しなければならないが、歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。
【該当規定】道路交通法第63条の4第2項
(3)歩道を通行する歩行者は、標識等により普通自転車通行指定部分があるときは、当該指定部分をできるだけ避けて通行するよう努めなければならない。
【該当規定】道路交通法第10条第3項
2 乗車用ヘルメットに関する規定
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
【該当規定】道路交通法第63条の10
3 地域交通安全活動推進委員に関する規定
道路交通法に規定されている地域交通安全活動推進委員の活動内容に、「自転車の適正な通行方法についての啓発活動」を追加。
【該当規定】道路交通法第108条の29第3項