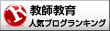同センターは昨年9月、小学生の子供を持つ母親4644人に、子供が夏休みをどう過ごしたか尋ねた。費やした時間が長いのはテレビやゲームだったが、子供の成長につながった体験としては海水浴や図書館通いが挙げられ、同センターは「屋外での体験を増やしてみては」としている。 調査によると、小5と小6が夏休み中にテレビやDVDを観賞した時間は1日2時間17分、ゲーム機での遊びは1時間22分、ごろごろしていたのは1時間7分と、いずれも普段より約30~50分増えていた。 屋外での遊びは普段より51分長い1時間36分、家で勉強した時間は9分短い1時間2分。全体の約30%が塾に通っており、塾での勉強時間は2~3時間だった。 一方、成長につながった活動としては、帰省などの外泊、海水浴や川遊び、昆虫採集、工場などの施設見学、図書館通いが挙がった。 』7月5日5時14分配信 時事通信)
同センターは昨年9月、小学生の子供を持つ母親4644人に、子供が夏休みをどう過ごしたか尋ねた。費やした時間が長いのはテレビやゲームだったが、子供の成長につながった体験としては海水浴や図書館通いが挙げられ、同センターは「屋外での体験を増やしてみては」としている。 調査によると、小5と小6が夏休み中にテレビやDVDを観賞した時間は1日2時間17分、ゲーム機での遊びは1時間22分、ごろごろしていたのは1時間7分と、いずれも普段より約30~50分増えていた。 屋外での遊びは普段より51分長い1時間36分、家で勉強した時間は9分短い1時間2分。全体の約30%が塾に通っており、塾での勉強時間は2~3時間だった。 一方、成長につながった活動としては、帰省などの外泊、海水浴や川遊び、昆虫採集、工場などの施設見学、図書館通いが挙がった。 』7月5日5時14分配信 時事通信)
『神奈川県教育委員会www.pref.kanagawa.jp/osirase/40/<wbr></wbr>4020/index.html )が2010年度の公立小学校教員採用試験の目玉として掲げた、青森、山形、愛媛、沖縄の4県の昨年度の採用試験で1次試験を合格した受験生について1次試験を免除にする試みが、応募者が6人と低調だったことが分かった。 1次試験の免除は、県外の優秀な人材を確保するのが狙いで、全国でも珍しい試み。県の昨年度の倍率は全国都道府県・政令指定市の中で最低の2.4倍。団塊世代の大量退職で採用人数を増やしたため、倍率は低迷していた。 「1次試験はクリアしたが、最終合格しなかった人たちの中に優秀な人材が眠っている可能性がある」。県教委は、昨年度の1次試験競争率が3.5倍以上の県と政令指定市計10自治体に、「採用試験を行う際、1次試験を通過したかどうか確認させてほしい」と打診。そのうち今回の4県から「協力は可能」と打ち返しがあった。4県の倍率は3.7~9倍と高倍率だ。 小学校教員採用試験は、各都道府県で方法は異なるが、神奈川の場合は、1次試験(筆記、論文)と2次試験(面接、実技、模擬授業)の2段階選抜で、今回の免除者は2次試験からのチャレンジとなる。 』 2010年7月2日アサヒコム
神奈川県は、地理的な立地条件も悪くはないと思います。他府県の出身者を採用するよりも地元の地の利、地元の子供達と溶け合い、信頼感を得れるような教員志望者を採用すべきだと思います。神奈川県教育委員会が独自の公立小学校教員採用試験のシステムを構築し、神奈川県の自前で教職に使命感を持った教員採用試験を実施すべきでは有りませんか。地元で育った人にしか、地元の人の気質や習慣、伝統、文化や日常生活は理解出来ないでは有りませんか。神奈川県には、神奈川県内には、教育を背負って立てる有為な教員志望者がいないわけはないと思います。優れた教員採用出来るように採用後の採用条件も魅力有る者に改善すべきでは有りませんか。今や地方分権、地方主権の時代です。各県教育採用試験では、自主性と独自性を発揮しないと各県の教員採用試験に子供好きで教育への情熱と教育への使命感を持った教員志望者が集らないのでは有りませんか。
7月5日7時56分配信 産経新聞
 |
| 拡大写真 |
| 苦情を訴えた保護者の認識(写真:産経新聞sankei.jp.msn.com ) |
■「クラス替え」「アルバム作り直し」…来ない親ほど理不尽
調査は昨年12月下旬から今年1月末に、東京、神奈川などの小中学校計13校に在籍する児童・生徒の保護者2380人に調査を依頼。このうち1752人から回答を得た。 その結果、これまでに学校に苦情などを申し出たことがある保護者は全体の21・6%に上った。苦情・要望の内容は「先生の指導全般について」が断トツ(23%)。教師の指導に口を出す保護者が増えている最近の傾向が表れた。
一方、調査では、苦情・要望を申し立てたことのある保護者の意識を調べるため、「わが子と不仲な子供が同じクラスになったのでクラス替えしてほしい」「わが子の写真が一枚もないのでアルバムを作り直してほしい」といった“極端”な要求について、どのように思うかを質問。
こうした“極端”な要求を「当然」と考える割合が多いのは「あまり学校に行かない」という保護者で、「学校によく行く」という保護者は、こうした要求に否定的な傾向が強かった。
佐藤教授は「保護者ごとにさまざまな事情があるが、学校を頻繁に訪れ、教師とコミュニケーションをとるほうが、学校に対する理解が深まって当事者意識を持つようになり、極端な苦情や要望をしなくなるのではないか」と分析する。 学校に自己中心的な要求を繰り返すモンスターペアレントについては、現場の教師の大きな負担になっており、文部科学省も危機感を強めている。現在議論が進められている少人数学級も、モンスターペアレントに対応する教師の負担を軽減することが目的の一つだ。 モンスターペアレントは教育への悪影響も指摘される。久米井孝夫・大阪市PTA協議会長は「先生を先生とも思わない態度をとる保護者もいる。そういう態度に影響を受けた子供たちは、先生の指導を聞かなくなる」と指摘する。 しかし、モンスターペアレントになるかならないかは保護者自身の意識の問題だけに、問題解決は難しい。久米井会長は「こうした保護者には、PTAの活動に加わってもらうことが大事だと思う。不思議と、身勝手な文句を言うことがなくなる。先生とふれあったり、ほかの保護者と話したりすることで、相手の立場を理解し、身勝手な見方をしなくなるのではないか」と話している。』産経新聞