本日、 。
。
今日は、雪が降る前に落ち葉堆肥を友人と造ってみました。
材料は、落ち葉や鶏の食べ残した野菜残さの他に、

うちのニワトリたちの鶏糞(土とモミガラと混ざっているもの)

米ぬかと油粕を2:1で混ぜたもの

良質な完熟堆肥を使いました。
良質な完熟堆肥には、有用な菌がたくさんいるので、
それを1割ほど入れて造ると失敗が少なく、発酵しやすくなります。
ない場合は、天然菌の宝庫である、山の落ち葉や竹やぶの落ち葉。
もしくは、微生物資材で代用できます。

それらを、落ち葉に均一に混ぜ合わせるために、
軽い順に、落ち葉に撒いていきます。

今回は、さらに壁土を使用しました。
壁土は、ミネラルを含み、堆肥の養分保持力を高めてくれるスーパー素材です。
ただ、手に張りにくいのが難点です。
古い土蔵などの壁は、粘土とワラを発酵させたもので塗っていました。
たまたま去年の暮れに、土蔵を壊していたので、そこで分けてもらったものです。

落ち葉と米ぬかなどが混ざってきたら、壁土も混ぜます。


落ち葉と発酵素材を良く混ぜるために、
スコップと鍬を使い、山にしては崩し、また山にすることを繰り返し行い、
材料が均一に混ざるようにします。

バケツで水を撒きます。
発酵には50~60%の水分量が必要です。
多くても、少なくても失敗します。それぐらい水分量は大切です。

足で踏み込み、水を落ち葉と材料に馴染ませていきます。
その後、山を作り、崩し、切り返しをしながら水分を全体に回します。

水分量は、冬場は50%と少なめにしたいので、
写真のように、両手で強く握った時に、にじんでくる程度が最適です。
ぽたぽた落ちるようでは、水分が多く失敗しやすくなります。

最後に、山に盛り、古いカーペットで覆ってあげます。
古いカーペットは、水分・酸素を適度に調整してくれ堆肥造りをサポートしてくれます。
二日後には、60℃位に発酵し始めます。
2日経っても発酵温度が60℃ない場合には、
そのままにしておくと腐敗し、失敗してしまうので、水分量を調えてあげます。
約30日位の間、切り返ししながら水分量を補い60~70℃位で発酵させると、
草の種や病気が死滅し、良い堆肥になっていきます。
落ち葉堆肥は、完熟に1~2年かかります。
その頃には手でもむと形が崩れ、良い匂いもしくは無臭になります。
それまでは、寝かしておきます。
3年以上寝かした良質な落ち葉堆肥は、樹木医さんが病気の樹に使うような堆肥になっています。
うちでは堆肥はあまり使いませんが、
今回、神社から大量の落ち葉が手に入り、友人の手伝いもあったのでスペシャル堆肥を造ってみました。
****************************
■お知らせ
山形村i-City21のNHKカルチャーセンターで
一押しのお奨めの講座を開きます。
輪作・連作によるの体系化した土作りを学び、自分の菜園プランを見直す方、はじめて菜園を持つ方にお奨めの座学です。
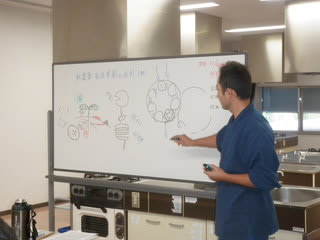
【春準備コース】菜園プランの立て方と土作り
無農薬栽培で家庭菜園のはじめ方や野菜の作付計画を一緒に作ります。
失敗のしない土作りや連作障害しにくい輪作体系を学べます。畑で「困っ た!」をズバリ解決します。
1/12-土作りの考え方(病虫害の少ない畑の特徴、連作障害、輪作体系)
2/9-菜園プランの立て方(1)コンパニオンプランツで菜園プランを作る
3/9-菜園プランの立て方(2)一緒に作った菜園プランを検証する Q&A
詳しくは、
http://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_491207.html
もしよかったら、ご参加ください。たけうち
 。
。今日は、雪が降る前に落ち葉堆肥を友人と造ってみました。
材料は、落ち葉や鶏の食べ残した野菜残さの他に、

うちのニワトリたちの鶏糞(土とモミガラと混ざっているもの)

米ぬかと油粕を2:1で混ぜたもの

良質な完熟堆肥を使いました。
良質な完熟堆肥には、有用な菌がたくさんいるので、
それを1割ほど入れて造ると失敗が少なく、発酵しやすくなります。
ない場合は、天然菌の宝庫である、山の落ち葉や竹やぶの落ち葉。
もしくは、微生物資材で代用できます。

それらを、落ち葉に均一に混ぜ合わせるために、
軽い順に、落ち葉に撒いていきます。

今回は、さらに壁土を使用しました。
壁土は、ミネラルを含み、堆肥の養分保持力を高めてくれるスーパー素材です。
ただ、手に張りにくいのが難点です。
古い土蔵などの壁は、粘土とワラを発酵させたもので塗っていました。
たまたま去年の暮れに、土蔵を壊していたので、そこで分けてもらったものです。

落ち葉と米ぬかなどが混ざってきたら、壁土も混ぜます。


落ち葉と発酵素材を良く混ぜるために、
スコップと鍬を使い、山にしては崩し、また山にすることを繰り返し行い、
材料が均一に混ざるようにします。

バケツで水を撒きます。
発酵には50~60%の水分量が必要です。
多くても、少なくても失敗します。それぐらい水分量は大切です。

足で踏み込み、水を落ち葉と材料に馴染ませていきます。
その後、山を作り、崩し、切り返しをしながら水分を全体に回します。

水分量は、冬場は50%と少なめにしたいので、
写真のように、両手で強く握った時に、にじんでくる程度が最適です。
ぽたぽた落ちるようでは、水分が多く失敗しやすくなります。

最後に、山に盛り、古いカーペットで覆ってあげます。
古いカーペットは、水分・酸素を適度に調整してくれ堆肥造りをサポートしてくれます。
二日後には、60℃位に発酵し始めます。
2日経っても発酵温度が60℃ない場合には、
そのままにしておくと腐敗し、失敗してしまうので、水分量を調えてあげます。
約30日位の間、切り返ししながら水分量を補い60~70℃位で発酵させると、
草の種や病気が死滅し、良い堆肥になっていきます。
落ち葉堆肥は、完熟に1~2年かかります。
その頃には手でもむと形が崩れ、良い匂いもしくは無臭になります。
それまでは、寝かしておきます。
3年以上寝かした良質な落ち葉堆肥は、樹木医さんが病気の樹に使うような堆肥になっています。
うちでは堆肥はあまり使いませんが、
今回、神社から大量の落ち葉が手に入り、友人の手伝いもあったのでスペシャル堆肥を造ってみました。
****************************
■お知らせ

山形村i-City21のNHKカルチャーセンターで
一押しのお奨めの講座を開きます。
輪作・連作によるの体系化した土作りを学び、自分の菜園プランを見直す方、はじめて菜園を持つ方にお奨めの座学です。
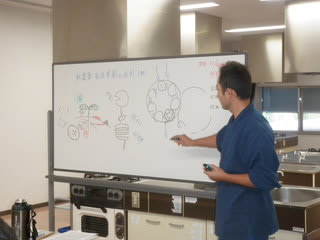
【春準備コース】菜園プランの立て方と土作り
無農薬栽培で家庭菜園のはじめ方や野菜の作付計画を一緒に作ります。
失敗のしない土作りや連作障害しにくい輪作体系を学べます。畑で「困っ た!」をズバリ解決します。
1/12-土作りの考え方(病虫害の少ない畑の特徴、連作障害、輪作体系)
2/9-菜園プランの立て方(1)コンパニオンプランツで菜園プランを作る
3/9-菜園プランの立て方(2)一緒に作った菜園プランを検証する Q&A
詳しくは、
http://www.nhk-cul.co.jp/programs/program_491207.html
もしよかったら、ご参加ください。たけうち





















