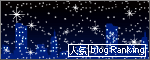レビュー一覧は、こちらから。
ノクドゥは王宮に戻る前に、ファン先生にも協力を依頼していました。
出来る限りの兵を集めようとしたのです。
ドンジュは、ヨン・グンたちと残ることに。
「あなたが誰で私が誰でも、どうでもいい。2人で幸せに暮らしたい。誰かを憎んだり、罪悪感に苦しみたくない。もう、あなたと離れたくない。だから、一緒にいて。それでいい?」
勿論・・・とノクドゥは言い、優しくドンジュを抱きしめました。
そして、ノクドゥは王宮の門を入って行ったのです。
ノクドゥが味方ではなかったと知ったユルム。ま、信じてはいなかったでしょうけど・・・。
ただ、兵曹判書たちがノクドゥと共に戻るとは予想していなかったようです。
ユルムは、ノクドゥは、王位を狙っていると主張。兵曹判書はノクドゥに騙されていると。
「それは違う。」
ユルムを遮ったのは、王妃。
王妃はチョン・ユンジョと共に現れました。
王妃は、光海君が死んだと言いました。
ユルムや反乱軍に動揺が走りました。
王が亡くなった今、嫡子であるノクドゥが次の王になるのは当然ですから。
ユルムはノクドゥが嫡子だという証拠を求めました。
チョン・ユンジョは、自分が証拠だと言いましたが、言葉だけじゃ皆信じるわけはありません。偽者だと言われても、反論できる確証はユンジョにはありません。
でも、王妃は持っていました。あのノリゲです。
周囲の者は、王妃がそのノリゲを常に身に着けていたことを知っていました。
割れたノリゲの片方を、ノクドゥが懐から出しました。
二つはぴったり合いました。
一瞬失敗したかと思ったユルムですが、すぐに反撃に出ました。
20年前、実際は生きていた息子をユンジョが光海君に戻さなかった理由は、光海君が息子の死を望んでいたからだと明らかにしたのです。
ノクドゥもそれを認めました。
父である王から捨てられたのような奴が王位を継げると ・・・とユルム。
・・・とユルム。
幼い頃から王位を狙っていたのは、ユルムでは?とノクドゥ。
「嫡子が王位を継ぐにあたり、先王の愛情など必要ない。確かに私は未熟だが、臣下の補佐があれば問題ない。争わずに済む道があるというのに、敢えて血の流れる謀反を起こす必要があろうか。」
その言葉に納得したユルムの兵の一部が、ノクドゥ側に寝返りました。
それを見たユルムが剣を抜きました。
一気に戦闘となってしまいました。
ノクドゥは王妃を連れて逃げました。まずは安全なところに避難させたかったのです。
王妃はノクドゥをやっと抱きしめることが出来ました。
オモニ・・・と泣きながらノクドゥが言いました。
そう呼ばれ、王妃は本当に嬉しく思いました。
戦の場に戻ろうとするノクドゥを引き留める王妃。次の王となるべき者に何かあっては ・・・と言う事です。
・・・と言う事です。
ユルムたちに王妃が言った言葉は本心でした。
でも、ノクドゥにその気はありません。あの場では、そう言うしかなかったのですが、本心とすると、王座に座ることが怖いのです。
光海君が我が子を殺してまで守ろうとした王座が・・・。
自分もそうなるのではないかと思ったのでしょう。そこまで人を狂わせてしまうモノが王座なのかもしれないと。
それに、ドンジュの元に戻りたかったのです。
王妃は、引き留めようとした手を離しました。
「無傷で戻ると約束して。」
ファン先生はファンテを混乱の中から救い出していました。
ユルムにとってファンテは人質です。逃してはなりません。
すぐさま、ダノに後を追わせました。
ダノとファン先生、互角の勝負です。年のせいで、少しのハンデがファン先生にはあります。
ファン先生はダノに傷を負わされ、倒れてしまいました。
その隙に、ダノはファンテを追いました。
ファンテは父ユンジョを探していました。置いて逃げることはできませんでした。
それはユンジョも同じ。
ユンジョが先にファンテを見つけ、一緒に逃げようとしました。
ところが、ここに至っても、ファンテはまだノクドゥへの反感を捨てきれずにいて、ユルムに付くと言うのです。
親子で言い争っている時、ふいにユルム側の兵が斬りかかって来ました。
ユンジョがファンテを庇って斬られちゃった
ファンテはダノの姿を見て、ユンジョを物陰に隠し、出て行きました。
何事も無かったかのように、ダノについてユルムの元に戻ったのです。
ユルムは遠くにノクドゥの姿を見つけました。
怪我をした兵曹判書を抱えて逃げるノクドゥに矢を向けました。
射ようとした瞬間、目の前に立ちはだかったのは、ドンジュ。
ドンジュは、王宮内で騒動が起こっているという話を聞き、居てもたってもいられず、駆け付けていたのです。
ユルムがノクドゥを狙っていると見るや、死を覚悟して遮ったのです。
驚いたユルム。
でも、もう引き絞っていた弓を止めることは出来ませんでした。
ただ、ドンジュを避けるために、少しだけ方向をずらすことは出来たのです。
お陰で、矢はノクドゥの腕をかすめただけでした。












 余の息子にな
余の息子にな 16代仁祖になるんだよね
16代仁祖になるんだよね