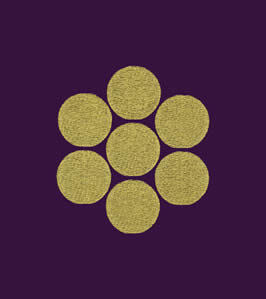◎暗黒街のふたり(1973年 フランス、イタリア 100分)
原題/Deux Hommes Dans La Ville
監督・脚本/ジョゼ・ジョヴァンニ 音楽/フィリップ・サルド
出演/アラン・ドロン ジャン・ギャバン ミムジー・ファーマー イラリア・オッキーニ
◎悪とはなにか?
当時のフランス車はどれもこれも前後ともベンチシートなんだね。首を預けられないのは辛いだろうな。
ポスターに使われてるスチールは後半、ギャバンが印刷所にドロンを訪ねたときのカットだ。この場面、上手にふたりを動かして、両方の表情をうまく捉えてるわ。
しかし、ジョゼ・ジョヴァンニ、剛腕だな。裁判の場面で、ひとりだけ過失傷害致死に居合わせた恋人の証言を音声カットしてギャバンのナレーションだけで処理しちゃうとは。ちからわざだね。
さらにうまいのは、ドロンの最初のカットは印刷所の輪転機の向こうに顔が見えてくるんだけど、それがラストのギロチンの断頭台に見立てられてるところだ。この伏線が上手すぎるのに、ラスト、ギロチンの模型とセットがおそまつなのがなんとも悲しいね。