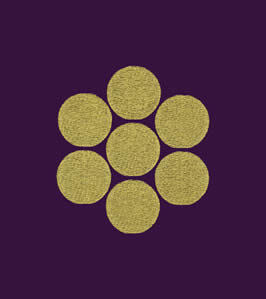◎トールキン 旅のはじまり(Tolkien)
母親(ローラ・ドネリー)の突然死によってバーミンガムのキング・エドワード高校に転入したとき、ラテン語の教師に「トールカイン」と呼ばれ、それを訂正することで鬱陶しがられるが、苗字をまともに呼ばれたことのない僕にはその気持ちはよくわかる。もっとも僕の場合、チョーサーの詩は暗記してなかったけどさ。
友達になったやつがいう。
「もし僕が棒を手にこう言ったら?僕はケーキを食べすぎた、君たちはよせ。これが親の本質だ。われわれは食べたが子供はやめろ。ケーキは愉しいことの比喩だ」
そしてかれらは、会員制の高級カフェで自分にとっての棒とはなにかという談義に入る。なるほど、アタマの良い領家のがきんちょらしい日常だな。僕の高校時代とはまるでちがう。ぼくらは喫茶「杉」に入り浸ってただけだもんなあ。こういう仲間のまじわりが『指輪物語』や『ホビットの冒険』の旅の仲間たちになっていったっていうくくりなんだろうか?
けど、トールキンが貯金する緑の硝子の瓶は、僕がお金を入れてる瓶と同じだ。わお!
本質といえば、トールキンは彼女(リリー・コリンズ)を自分の仲間に紹介する。彼女は水を得た魚のように話をする。ラインの黄金について仲間のひとりと話が弾み始めるが、トールキンは理由をつけて彼女とともに帰る。彼女は怒る。つまらない日常を忘れられそうなのにと。そんなにわたしが恥ずかしいのと。ばかだなあと男の観客はおもうだろう。彼の仲間と親しくするのは、彼に焼き餅を焼かせることだとどうしてわからないんだろう。女の観客はおもうだろう。彼の仲間と話すくらいなんだよと。別にキスするわけでもないのに、彼女は日頃の抑圧から解放されてるんだからそれくらい大したことないじゃん、あ〜嫌だと。男と女はおたがいの沸点が理解できないんだよね。よくわかるわ。
けと、なんで前線で友達を探しに行くんだ?
いくら親友だろうとなんだろうと、戦争中なんだから、尉官が勝手に持ち場を離れるのは無理ってもんじゃないのか?
ま、それはさておき、ニコラス・ホルトはよくやってる。トールキンの青春時代ってこんな感じだったんじゃないかなあって気になる。言語マニアっていう感じだったんだろうか?それでオクスフォード大学の教授になってくんだから、いやあ、趣味は人生を決めるなあ。でも、190センチあるの?背高いなあ。
ところで、トールキン財団はこの作品を認めないそうなんだけど、いったいどこが気に入らなかったんだろう?
トールキンの言語へのこだわりと北欧へのなんともいえない感覚的な憧れが、その後のトールキンの世界観を形作っていったんなら、映画のはしばしにその伏線めいたものがあったりして、途中、ああだから指輪をモチーフにした物語を書いたんだあっておもわず納得しちゃったんだけど、そういうあたりが気に入らなかったんだろうか?