向日葵は 風穏やかに 揺れそよぎ 赤きルージュ 笑い光りぬ 
 Purdue大学
Purdue大学
「透明マント」
【電子噴霧とはなにか?】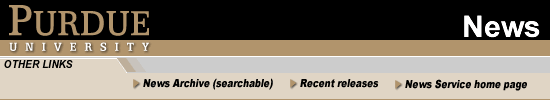
4世紀前、電場によって液体表面が変
形することが初めて観測され、強い電
場が液体界面を不安定にし、周囲気体
から液滴が分離されるが Zeleny が証明
した。この Zeleny の実験は不安定界面
が円錐形状を取ることも明らかにされ
ている(Taylor Corn )。微細ジェット
は、このコーン尖端部から発生し、電
気流体力学的(EHD)尖端流は、エレク
トロスプレーと呼ばれる。
January 7, 2008
'Electrospray' droplet research yields surprising, practical results
バーディユ大学の化学工学部のグルー
プの研究では(「電気流体力学的尖端
流と液体円錐からの荷電液滴の放出」
)、微小導体膜からのEHD尖端流中に
発生するコーン形成→ジェット放出→
ジェット分裂機構の総合的実態解明シ
ミュレーションと実験結果を比較検討
結果(液体をTaylor-Melcher 漏出誘電体
→半絶縁体)、良好な一致が示され尖
端流の動学が軸対称、液体が完全に導
体或いは絶縁体である場合以外のケー
スを前提として、尖端流分裂から生じ
る液滴のサイズを予測するスケーリン
グ則の開発が可能になると報告されて
いる。 Electrospray
Electrospray
「エレクトロスプレー」(電子噴霧)
という文字が目とまり予定が狂った。
しかたがない、ネット検索を始めここ
に至る。昨今、-6千電子ボルトもの
高圧を加え微塵サイズの水分を噴霧す
る‘ナノ・イー’を売りにし空気清浄
装置が販売されている。尤も、ライバ
ル企業は‘プラズマ’方式の空気洗浄
機もそこには入ってくる。話を‘エレ
クトルスプレー’方式に戻す。これは
少量噴霧であり、産業装置ではこれを
電子部品の洗浄装置向けの大量噴霧に
変換ことをテーマに数年、研究開発を
行っていたので興味がそちらに向く。
大量噴霧だけが問題ではない。洗浄後
の排気如何で二次汚染が起きる。例え
ば、残留電荷が大きければ、電荷の作
用力を利用し集塵効率を上げることが
できる(微塵:ミクロンメータ及びナ
ノメータ→尚、微塵工学はこのサイズ
領域を扱う加工技術を指す)。
 Victor Georgievich Veselago
Victor Georgievich Veselago
【透明マント効果】
透明マントの実現に向けて多くの研究
が重ねられる中で「変換光学(トラン
スフォーメーション・オプティクス)」
と呼ばれる新しい分野が誕生し「メタ
マテリアル」や「ナノフォトニクス」、
「プラズモニクス」などのまったく新
しい材料や次世代光技術が生み出され
た。こうした材料や技術は今後、高性
能顕微鏡に向けた高機能レンズなどへ
の活用が期待されている。 ladimir Shalaev
ladimir Shalaev
が、前述のパディユ大学では高性能レ
ンズではなく、透明マントの実現に向
けた技術開発も進められている。これ
まで開発されてきた可視波長域で機能
する透明マント技術と比べて、透明化
できる面積を百倍に高める。メタマテ
リアルを用いた光波長の研究開発では、
同大学が最も進んでいる。新しい設計
手法は、変換光学技術を適用し、金で
作製した導波路とガラス基板という比
較的安価な材料を用いることで、製造
コストをより低く抑えられるという。
同大学のVladimir Shalaev教授は「テーパ
ー導波路の下部へレーザー光を照射す
ると、ある特定の領域で光が屈折する。
曲面レンズで覆った隠したい物体の周
囲で光が屈折すると、光の位相速度が
速くなり、レーザー光はまるで空気中
で拡散したかのように同じ位相を保っ
たまま反対側へ抜ける」という。
今回、同大学が開発した手法では、Au
でコーティングした曲面レンズと同平
面状のシートで透明マントを構成する。
こうした構造を採ることで、広帯域の
マントが実現できるという。つまり、
可視光の全スペクトルに対して透明に
なるよう調整できる。曲面レンズで覆
った領域の周辺でレーザーが屈曲する
ことを実証した。この手法はレーザー
光の波長の百倍もの領域に対しても有
効で対象物の影も見えない。
【スーパーレンズ】
40年前、ロシアの科学者ベセラゴ(
Victor Veselago)は光学の世界を根底か
ら覆す物質を考えつく。これまで知ら
れている物質は、光の折れ曲がり具合
はさまざまだが、屈折率はいずれも正
の値をとるが、奇妙な光の折れ曲がり
方を示す「負の屈折率を持つ物質」が
あると考えた。
2000年、カリフォルニア大学サンディ
エゴ校のグループはマイクロ波に対し
て負の屈折率を示すメタマテリアルを
開発、検証実験に成功した。以来、メ
タマテリアルの不思議な特性を利用し
た技術開発が世界各地で進んでいる。
なかでも最も先端を走るのが「スーパ
ーレンズ」。屈折率が正の物質ででき
た普通のレンズでは,回折限界から光
の波長よりも小さな対象の画像は得ら
れない。
半導体のダウン・サイジングの限界が
なくなり「ムーアの法則」は根底から
覆される?そんな事態も起きるかも知
れない。
----------------------------------
フォトニック結晶(photonic crystal)と
は屈折率が周期的に変化するナノ構造
体であり、その中の光(波長が数100
~数1000nmの電磁波)の伝わりかたは
ナノ構造によって制御できる。基本研
究とともに応用開発が進められ、商業
的な応用も登場している。
---------------------------------- Meta-material
Meta-material
スーパーレンズの実験成功によって電
磁気学がからむほとんどすべての現象
は再検討を迫られている。屈折や回折
限界など、完全に解明されたと考えら
れてきた基本的光学現象でさえ、屈折
率が負の物質の登場で新たな修正が加
えられることになった。「もはや、技
術なし」は覆され、「未体験ゾーンの
‘とばり’が上がる」が、また、改め
て考察することに。

【沈黙の海】
秋刀魚の初競りが行われ、漁獲量が半
数近くまで激減。値段は倍ほど跳ね上
がった。ブログで「魚となれずし」を
シリーズとして取り上げ漁業の有り様
に警鐘をならしてきたつもりでいるが
スウェーデンからも警告を発している。
「私がスウェーデンでこの問題を調べ
始め、行政の担当者たちにインタビュ
ーをしたとき、ものすごくフラストレ
ーションが溜まりました。環境政策と
漁業政策が、ほとんど何もリンクして
いないと気づいたからです」と『沈黙
の海』の著者のイサベラ・ロヴィーン
は話す。
スウェーデン近海のタラの漁獲量は、
1970年代には年間1万5000tだったのが、
昨年は192tに激減。魚を捕り過ぎると
魚が減るだけではなく、生態系全体が
変化する→魚がいなくなると代わりに
貝やエビ、クラゲが増え、食用の魚は
さらに減る→補助金や税の免除で漁師
数を維持→魚群探知機の搭載や船の高
性能化などが進み→さらに魚が足りな
くなり不採算事業化という悪循環には
まると警告する。

















