無理矢理の 蔓茘枝入り ポレンタと 麦酒を含む 汗を拭いつ 
【政府の学習能力】 Peter Schiff
Peter Schiff
ドル、ユーロの信用不安から「円高」
が加速している。いまさら、日本政
府は「洞ヶ峠」じゃないだろうと思
っているが、当たり障りのないコメ
ントの域を超えていない。それじゃ
こちらから質問しよう。「米国経済
を病気に喩えると何の症状?」と。
「口蹄疫?」「まさか?!」。「鬱
病?」「それじゃ、精神安定剤でも
投与する?」。「悪性貧血?」「・
・・」とこんな具合に話しを展開さ
せ考えてみよう。 greenspan
greenspan
グリーンスパン連銀元議長は8月1日
のテレビ出演で「金融システムが壊
れている時には、インフレではなく
デフレになる」と、銀行の貸し渋り
によって超低金利なのに資金流通量
が減る現状について指摘した後「し
かし財政赤字が増え続けているので、
インフレにならないまま長期金利が
高騰するかもしれない」と発言し、
中国などが米国債を買わなくなると
デフレ下の金利高騰という前代未聞
の事態が起こるいう。
また、8月10日、米国の連銀(FRB)
が定例の理事会(FOMC、公開市場
委員会)で「量的緩和」政策の再開
を決定し、市場関係者の多くを驚か
せた。連銀内や金融界では、量的緩
和を復活しても、実体経済への効果
が薄いとの反対する声も強く、リー
マンショック後の米金融は、資金難
ではなく、金融バブル崩壊で巨額の
不良債権の重圧で銀行界が消極的融
資をとり、連銀からの注入や影の銀
行システムの資金調達も、市中に回
らず「貸し渋り」にある。 「インフレ目標4.0%」のすすめ
「インフレ目標4.0%」のすすめ
日本の90年代のバブル崩壊後、日銀
の超低金利策で、不良債権で銀行界
が金を貸さず景気は回復せず、10年
以上のデフレ状態を経験が、米国で
も起きていると懸念している。今の
米経済の問題は、影の銀行システム
で資金を調達できるのが銀行や大企
業だけで、貸し渋りを続ける伝統的
な銀行システムにしか頼れない一般
の米国人の家計や中小企業に資金が
回らないことだ。 Nouriel Roubini
ローン破綻増に失業増が加わって一
般の人々の困窮はひどくなり、米国
の中産階級が階級ごと崩壊し、貧困
層に転落する事態が起きている。米
国では貧困層向けの食糧配給(生活
保護)を受給する人数が1年で19%
も増え、米国民の8人に1人にあた
る4,080万人に達し、来年は4,330万
人になると予測されている。 Bill Gross
Bill Gross
ところで「陰の金融システム」とい
う言葉は、巨大債券運用会社のPIM
COの最高投資責任者(CIO)のビル・
グロースによるものである。ここで
「陰」というのは、取引内容がすべ
てオープンになることを強制されて
いる商業銀行(表の銀行システム)
に対し、取引内容が表に出ないとい
うことを意味した言葉であるが、あ
らゆる規制をくぐり抜け「陰の銀行
システム」を作り出した。それは政
治家に規制緩和政策を採用させるこ
とで実現したシステムである。ニュ
ーヨーク大学スターン・ビジネス・
スクールのヌリエル・ルービニ教授
は「陰の銀行システム」より広く「
陰の金融システム」と言った方がよ
いと主張していた(08年2月5日付R
GEモニター)。
かって、クルーグマンはこれらを評
して、「陰の銀行システム」は複雑
な金融システムを次々に開発し、規
制に縛られている旧金融システムを
凌駕し、規制されていない銀行シス
テムが旧いシステムの銀行より有利
な条件の金融商品を顧客に提供して
きた。その一方で、規制のない自由
なシステムの危険性を危惧する人た
ちを、将来の希望を見ない時代遅れ
のものたちとして馬鹿にしてきたが
いまや陰の銀行システムから現金が
引き出されている。その結果が「金
融収縮の悪循環」であり、3世代前
に生じた金融恐慌の再来であると。
証券の支払い保証を専業とする保険
会社の「モノライン」、会員制投資
クラブの「ヘッジファンド」、証券
を販売する投資目的会社の「SIV」、
銀行ではない金融機関の「ノンバン
ク」なども「陰」の部分だからであ
る。ごまかしであった直接金融礼賛
「陰の金融システム」こそ「私」型
金融システムである。預金者の金を
企業に商業銀行が仲介する「間接金
融システム」よりも、企業が投資銀
行を通じて資本市場から資金を調達
する「直接金融システム」の方が優
れていると金融の専門家や実務家た
ちが声高に語り「金融ビッグバン」
「金融の規制緩和」を実現してきた。 松岡正剛「千夜千冊」
松岡正剛「千夜千冊」
そこには陰のシステムのトリックが
あり、公を理由に規制で縛られて自
由度の小さい「表の金融システム」
に対し「陰の金融システム」の方は
ギャンブル性が高く、金余り社会に
フィットしたのである。そして、上
げ潮の局面では、陰のシステムの方
が魅力的であったが、引き潮局面で
は破滅的な金融収縮を招いたのであ
る。
ここまではお復習い。いますべきは、
実体経済中心経済への回帰→勤労生
活者的側面(所得再配分是正)×生
産者的側面(法人税是正・規制見直
し)×国民的事業的側面(高齢・少
子化)×国際的側面(地球温暖化)
重視→「陰の金融システム」からの
機動的防衛強化(為替差損保険制度
導入・流動性の最適化)のための諸
策実行ということに帰結する。ここ
までくるとおわかりだと思うが、わ
たしは現在の世界経済は「急性悪性
貧血症」という「陰の金融システム」
×「適正を欠いた貨幣増発」のガン
に犯されているのではないかと思っ
ている。これは、7京円もの過剰流
動をコントロールするのが如何に難
儀か素人でもわかる。その意味で今
回の円高は、政府の学習能力の高さ
を計測しているように見えるが如何
に。
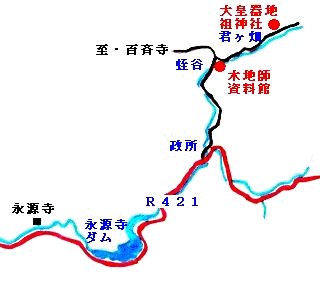
【新しい木地師神話】
木地師(きじし)は、轆轤を用いて
椀や盆等の木工品を加工、製造する
職人。轆轤師とも呼ばれる。9世紀
に近江国蛭谷(現滋賀県東近江市)
で隠棲していた惟喬親王が、周辺の
杣人に木工技術の伝授が始まり全国
に広まった。石川県加賀市山中温泉
(旧、西谷村)真砂(まなご)地区
は惟喬親王を奉じる平家の落人の村
落と伝わり、時代を経て何通かの御
綸旨で森林の伐採を許された主に木
地師達の小村落であったり、山中漆
器の源とされる。朝倉氏の庇護もあ
ったが天正元年の一乗谷城の戦い以
降は庇護も無くなり一部の木地師達
は新天地を求め加賀から飛騨や東北
地方に散って行ったとされる。明治
初期までは、全国各地で朝廷・幕府
の許可を受けた木地師達が、良質な
材木を求めて20~30年単位で山中を
移住していたという。 日本木地師学会
近江の木地師のことは前の職場に地
元出身の後輩がいたので知っていた。
ひょんなことで、イタリアン料理に
大きなプレートをたくさん使うが、
日本の食器はサークルばかりでレク
タングラやスクエアがないことに気
付く。定年後の事業にと関係者に話
かけたがノリが悪く立ち切れに。
「木地師の里を訪ねて」
木工とは、木材に加工をほどこすこ
と。金属加工、金工と対比される。
工作、美術、家具製作などの領域は
もちろんのこと、建築や土木などの
領域でも、木材を加工することを広
くこう呼ぶ。現場によっては「大工
仕事」などと呼ばれることもあるよ
うである。
それから木質バイオマス研究会の仲
間と接触するようになり「木工」の
拡張を考えてみた。つまり、メガフ
ロートの内張や甲板の大きなものか
らねじ、釘は勿論、皿、複雑な日常
品も含めたものを間伐材で機能性、
意匠に優れたものがつくれないかと。
電機自動車や家具、テント、携帯シ
ートカイト等々次々浮かんでくる。
研究開発領域が仕事だったものだか
ら、複合材、含浸材、合板材、エン
ボス材、印刷、塗装など凡そつくれ
ないものはないとの確信はある。い
わばこの東近江に『新木地師集団』
構想を夢見るまでに膨れあがったが、
木工装置の新規考案までは時間がな
いのでまた改めて。

















