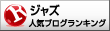高校のブラスバンドでサックスを吹いていた頃に、レジデンツやザ・ポップ・グループやキャプテン・ビーフハートのレコードで聴いたヒステリックなサックスのフリークプレイをきっかけにフリージャズに興味を持った筆者にとって、ことジャズ/フリージャズ/インプロヴィゼーションに関しては、花形の楽器はサックスに他ならない。大抵の場合、レコードを買ったりライヴを観に行く同機は好きなサックス奏者がいるかどうかである。『Sun Ra & his Arkestra / Live at Montreux』で初めてサン・ラのピアノやシンセサイザーを聴いたときは、ひっくり返るほど衝撃を受けたが、一番興奮したのはマーシャル・アレンやジョン・ギルモアやパット・パトリックやダニー・デイヴィス等のサックス隊が入れ替わりに滅茶苦茶なソロを取る瞬間である。
80年代初頭にESP DISKのフリージャズを聴き始めて、アルバート・アイラーをはじめとして、マリオン・ブラウン、チャールズ・タイラー、ジュゼッピ・ローガン、バイロン・アレンといった異能サックス奏者に出会えたことが嬉しかった。しかしESPで一番好きなアルバムは何かと尋ねられて頭に浮かぶ1枚は、ピアニストであるバートン・グリーンのリーダー作『Burton Greene Quartet』である(同時にアルバート・アイラー『Spiritual Unity』とバイロン・アレン『Byron Allen Trio』も浮かぶかもしれないが)。
●Burton Greene Quartet / Burton Greene Quartet (ESP Disk – 1024 / 1966)

『バートン・グリーン・カルテット』の何が好きかと問われれば、まずはジャケットと答える。ミュージシャンのモノクロ肖像写真をメインに使ったESP DISKのアルバム・ジャケットはどれも素晴らしいものばかりだが、バートン・グリーンの映画俳優を思わせるダンディズムと、ピアノ演奏に没頭する俯き加減の表情が、激しい指の動きに応じて微妙にブレている様が、アクションペインティングのような躍動感を伝えている。サウンド面では、ジョン・コルトレーン『Ascension』とアーチー・シェップ『Fire Music』というフリージャズの金字塔作品に参加して気を吐くマリオン・ブラウン(as)の激烈なサックスと並んで、聴きこむほどに凄みを増すバートン・グリーンのアンチノーマルなピアノである。ピアノの音に金属的な異音が重なり、突然パーカッシヴな打撃音になったり、鎖を引きずるノイズに豹変する。当時話でしか知らなかったプリペアド・ピアノを初めて耳にしたのがこのアルバムだった。個人的には特殊奏法ということよりも、ノイズをジャズに融合させたサウンドに魅了されたことが、その後の筆者の嗜好に影響を与えたことは確かである。なお、惜しくも先日コロナ禍で亡くなったヘンリー・グライムス(b)も参加している。
Burton Greene Quartet - Cluster Quartet
●The Burton Greene Trio / On Tour (ESP Disk – 1074 / 1968)

ESP DISKでの2作目のリーダー作はバートン・グリーン・トリオ名義の『On Tour』(1968)。1966年にニューヨーク州芸術評議会 (New York State Council on the Arts)の後援で開催された初のESPアーティスト・カレッジ・ツアーでのライヴ録音。参加したのはサン・ラ&アーケストラ、ジュゼッピ・ローガン・カルテット、パティ・ウォーターズ、ラン・ブレイクと、Steve Tintweiss(b)、Shelly Rustin (ds)とバートン・グリーン(p, piano harp)のトリオ。ちなみにパティ・ウォーターズの2ndアルバム『College Tour』も同じツアーでの録音であり、ラン・ブレイク、バートン・グリーン・トリオ、ジュゼッピ・ローガン・カルテットが曲ごとにバックを務めている。ピアノ・トリオは個人的にはあまり得意ではないが、プリペアド・ピアノや内部奏法を織り交ぜた完全即興演奏は面白く聴ける。セシル・テイラーを思わせる破壊的な演奏もあるが、むしろヨーロッパのジャズに似たクールな実験精神とエレガントな抒情を感じるのは、メンバー全員白人のトリオだからだろうか?正直言って1stアルバムほどのインパクトはないが、後にフランスに移住しヨーロッパで活動する運命を予感させる良作である。
Bloom in the Commune
グリーンの曲は、アルバート・アイラーに象徴されるエモーションの咆哮とは逆の冷静かつ理知的な視点が貫かれていて、得てして感情任せの激情プレイになりがちな自称フリージャズとは一線を画している。それはグリーンが現代音楽を学んだ「白人」であることにも起因するように思える。黒人ミュージシャンが圧倒的に多い当時のニューヨークのフリージャズ・シーンで活動する白人は少数派だった。初期ESPでは、ファグスやザ・ゴッズといったロックは別として、グリーン以外の白人アーティストはボブ・ジェームスとポール・ブレイとパティ・ウォーターズくらいである。そしてパティ・ウォーターズのデビュー作のB面を占める「Black Is the Color of My True Love's Hair」でパティの呪術的な歌を際立たせたのが、バートン・グリーンの空間的なピアノプレイだった。
Patty Waters - Black is the Color of My True Love's Hair
しかしながら、白人であることでバートン・グリーンが攻撃を受けることもあった。今では語られることは少ないが、1967年に詩人、作家のアミリ・バラカ(当時の名義はリロイ・ジョーンズ)が著した『ブラック・ミュージック』に”バートン・グリーン事件(The Burton Greene Affair)”というエピソードが掲載された。1964年にグリーンがマリオン・ブラウンとファロア・サンダースと共演した時、2人のエモーショナル(文中ではスピリチュアル)なサックス演奏に対して、ピアノのボディを叩いたり内部の弦を弾く特殊奏法でコラボするグリーンを揶揄する内容で、冒頭にグリーンのことを”白人でスーパー・ヒップ(MoDErN)なピアニスト”と皮肉っているのを見れば、黒人至上主義者の偏見に満ちた視点で書かれたことは一目瞭然。しかし不幸なことに原書を読んだ日本のジャズ評論家が文字通りの意味で解釈し<黒人ミュージシャンに圧倒され、自己嫌悪に陥り、イライラした気持ちを楽器にぶつけて悔しさを表明し、ついに耐えられなくなり頭を抱えてピアノの下に潜り込んでしまった>と紹介したものだから、日本のジャズファンには”負け犬”のイメージが定着してしまった。ある意味メディアの暴力と言ってもいいだろう。日本に於けるバートン・グリーン像は、圧倒的なマイナスからのスタートであった。
もちろん80年代当時の筆者はバートン・グリーン事件のことなど知る由もなかったが、70年代以降グリーンのレコードの日本盤がほとんどリリースされていない事実は、一度植え付けられたマイナス・イメージを払拭することの難しさを意味しているのかもしれない。しかし一方、バートン・グリーン自身が世界的成功には目もくれず、黙々と自らの音楽を追求し続けたことも事実である。今となっては日本盤・輸入盤の区別どころか、レコードやCDといったフィジカル・メディアが不要とされる時代である。筆者がこうして蒸し返さなければ”バートン・グリーン事件”という黒歴史も忘れら去られる運命だったのかもしれない。しかしながら、歴史を掘り起こすことで過去の嘘や過ちを明らかにして、隠された本当の事実を明らかにすることも大切である。一介の愛好家に過ぎない筆者にそんな大それたことができるか自信はないが、少数であろうと心ある音楽ファンにバートン・グリーンの音楽を知ってもらうことが出来れば本望である。
グリーンの
地球の上に
なる音楽