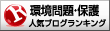この世界のあらゆるものはエネルギーの波動によって干渉しあっており、波形の似たもの同士ほど干渉の度合いは強くなると考えられます。その干渉を感受する能力を進化させることによって、環境変化に適応してきた生物がいます。フランス・ドゥ・ヴァール『共感の時代へ―動物行動学が教えてくれること 』によれば、それは哺乳類だということです。
行動主義が唱える「刺激-反応モデル」と異なり、哺乳類は他者への感受性を発達させることによって社会性を獲得しました。これは子供により手をかけなければならない哺乳類が、進化の中で獲得した能力であり、また大脳辺縁系の発達とも関係しているかもしれません。さらに、霊長類はこの能力を「他者への共感」というレベルにまで発達させ、より高度な社会性を身につけました。つまり、共感は決して人類に特有のものでも、成長過程で獲得するものでもなく、霊長類に本来備わった能力なのです。
それにもかかわらず、近代思想は人間を独立した個人として、また生存や欲求充足のみを目指す利己的な存在と見なしてきました。ホッブスが『リヴァイアサン』で描いたように、近代思想は人間の自然状態を「万人の万人に対する闘争」状態であると考えます。その人間が自身の欲望をある程度抑制してまで社会の形成に合意するのは、自然状態におけるコストがあまりにも大きく、社会を形成した方が「合理的」だからに他ならないというのです。このような社会とは合理的個人の自由意志に基づく契約(これを社会契約といいます)によって成立したものであるという考えは、今日でも私たちをかなりの程度に桎梏しています。
古典物理学と並び、近代思想に大きな影響を与えたものにダーウィンの進化論があります。進化論における適者生存のメタファー(注)は、「完全競争によってパレート最適が達成される」という古典経済学の正当性を裏づける役割を果たしてきました(ところが、ダーウィンに対する誤解と同様、近代経済学の父とされるアダム・スミスも、「神の見えざる手」と同時に市場を制御する「道徳」が必要であると述べており、今日の古典派とは異なった見解を示しています)。最適な種だけが生き残り、そうでない種は排除されるのが自然の摂理であるという誤った認識が、市場競争に勝ち残ったもののみが善であるという、これまた誤った認識に基づく市場原理主義を擁護することになったことは否定できません。これらのような思想的背景の中で、共感の果たす役割は長い間軽視、あるいは無視されてきたのです。
もちろん人間に利己的な面があることは否定できません。しかし、利己的であるのと同時に利他的であるのも事実なのです。人類は独立した合理的個人が闘争の果てにやむなく社会を形成することに合意したのではなく、霊長類が発達させた共感する能力をさらに発達させることによって、社会を形成したのです。
最近、心理学の分野において同調の法則や心理的貸借の関係が研究され、巷にはその手の恋愛マニュアルや消費行動心理の本があふれかえっています。すでに述べましたように、これらの性質は人間特有のものではありません。同書によればチンパンジーにも同様に、同調の法則や心理的貸借の関係が観察されるそうです。そればかりか、チンパンジーは貨幣価値の概念を理解し、「しっぺ返しゲーム」による将来予測までするといいます。こうした性質が、他者と共感することで協調的に行動し、環境に適応してきた霊長類の本能であるというのは興味深い点です。なぜなら、そうした感受性は、決して一部の人間にのみ与えられた特殊能力ではなく、誰もが元々持っている能力であるということ示しているからです。
(注)ダーウィンは「固体の変化が自然選択によって継承された結果、種の多様性が生じた」と述べただけで、現在我々が「進化論」として想起する適者生存や進化=進歩のイメージは19世紀の社会学者、ハーバード・スペンサーによって作られたものだそうです。したがって、実際に古典派経済学に根強い自由放任の思想はむしろスペンサーの影響といえます。有名な「生き残るのは、最も強い種でも最も賢い種でもなく、変化に適応できた種である」という言葉もダーウィンが言ったという証拠もないそうです。
繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした
よろしければクリックおねがいします!
↓
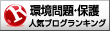
行動主義が唱える「刺激-反応モデル」と異なり、哺乳類は他者への感受性を発達させることによって社会性を獲得しました。これは子供により手をかけなければならない哺乳類が、進化の中で獲得した能力であり、また大脳辺縁系の発達とも関係しているかもしれません。さらに、霊長類はこの能力を「他者への共感」というレベルにまで発達させ、より高度な社会性を身につけました。つまり、共感は決して人類に特有のものでも、成長過程で獲得するものでもなく、霊長類に本来備わった能力なのです。
それにもかかわらず、近代思想は人間を独立した個人として、また生存や欲求充足のみを目指す利己的な存在と見なしてきました。ホッブスが『リヴァイアサン』で描いたように、近代思想は人間の自然状態を「万人の万人に対する闘争」状態であると考えます。その人間が自身の欲望をある程度抑制してまで社会の形成に合意するのは、自然状態におけるコストがあまりにも大きく、社会を形成した方が「合理的」だからに他ならないというのです。このような社会とは合理的個人の自由意志に基づく契約(これを社会契約といいます)によって成立したものであるという考えは、今日でも私たちをかなりの程度に桎梏しています。
古典物理学と並び、近代思想に大きな影響を与えたものにダーウィンの進化論があります。進化論における適者生存のメタファー(注)は、「完全競争によってパレート最適が達成される」という古典経済学の正当性を裏づける役割を果たしてきました(ところが、ダーウィンに対する誤解と同様、近代経済学の父とされるアダム・スミスも、「神の見えざる手」と同時に市場を制御する「道徳」が必要であると述べており、今日の古典派とは異なった見解を示しています)。最適な種だけが生き残り、そうでない種は排除されるのが自然の摂理であるという誤った認識が、市場競争に勝ち残ったもののみが善であるという、これまた誤った認識に基づく市場原理主義を擁護することになったことは否定できません。これらのような思想的背景の中で、共感の果たす役割は長い間軽視、あるいは無視されてきたのです。
もちろん人間に利己的な面があることは否定できません。しかし、利己的であるのと同時に利他的であるのも事実なのです。人類は独立した合理的個人が闘争の果てにやむなく社会を形成することに合意したのではなく、霊長類が発達させた共感する能力をさらに発達させることによって、社会を形成したのです。
最近、心理学の分野において同調の法則や心理的貸借の関係が研究され、巷にはその手の恋愛マニュアルや消費行動心理の本があふれかえっています。すでに述べましたように、これらの性質は人間特有のものではありません。同書によればチンパンジーにも同様に、同調の法則や心理的貸借の関係が観察されるそうです。そればかりか、チンパンジーは貨幣価値の概念を理解し、「しっぺ返しゲーム」による将来予測までするといいます。こうした性質が、他者と共感することで協調的に行動し、環境に適応してきた霊長類の本能であるというのは興味深い点です。なぜなら、そうした感受性は、決して一部の人間にのみ与えられた特殊能力ではなく、誰もが元々持っている能力であるということ示しているからです。
(注)ダーウィンは「固体の変化が自然選択によって継承された結果、種の多様性が生じた」と述べただけで、現在我々が「進化論」として想起する適者生存や進化=進歩のイメージは19世紀の社会学者、ハーバード・スペンサーによって作られたものだそうです。したがって、実際に古典派経済学に根強い自由放任の思想はむしろスペンサーの影響といえます。有名な「生き残るのは、最も強い種でも最も賢い種でもなく、変化に適応できた種である」という言葉もダーウィンが言ったという証拠もないそうです。
 | 共感の時代へ―動物行動学が教えてくれること |
| フランス・ドゥ・ヴァール | |
| 紀伊國屋書店 |
繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした

よろしければクリックおねがいします!
↓