『俵屋の不思議』という本を読みました。京都の老舗旅館「俵屋」を中心に、柱や風呂桶を磨く「洗い屋」、障子屋、畳屋、豆腐屋、湯葉屋、造酒屋、骨董屋などなど、俵屋に関わる職人さんの伝統と仕事へのこだわりが活き活きと描かれています。これら日本の伝統文化を辛うじて繫ぎとめている京都の風土、一方で現代に生きる我々があまりに本物を知らないために偽物が本物になってしまっている現実。
どんなに良い物を追求しても、その良さを理解できる受け手がいなくなれば衰退していかざるを得ません。このことが繊維リサイクルの現状と重なり合って感じられました。
こうした伝統を全て捨て去ってしまった後の日本人には一体何が残るのだろうと考えさせられます。資本主義経済の中に組み込まれた、単なる浪費する単位の集合?既に非日常化している歌舞伎や懐石料理といった断片を拾い集めて「これが日本文化です」と世界に向けて発信したところで、自分たちにその価値を認める下地がなければ不毛なことです。
さらに、ふと先週行ってきた福岡を思い出しました。僕が愛してやまない福岡、10年振りにじっくり歩いた町並みはすっかりその姿を変えていました。しかしただ昔の面影がなくなったということ以上に感じていた寂寞感、あれは一体何だったのだろうと思っていましたが、今こうして考えてみると恐らく福岡の独自性の衰退、東京への同質化のようなものを感じたからではなかったかと思います。
少なくとも10年前は曲がりなりに東京とは違う福岡の独自性みたいなものを感じることができました。しかし今回見た福岡は東京の人がイメージする(あるいはメディアによって作り上げられた)、例えばラーメンやもつ鍋といったものだけが極端にクローズアップされた福岡の姿、その中に福岡自身が埋没しているように感じられました。これは異質というよりむしろ拡大された同質化と言えます。僕が福岡を愛することに変わりはありませんし、10年振りに歩いてみただけで本当のことが分かるわけでもありませんが、直感的にそう感じました。
福岡で感じた寂寞感は世界の中の日本ということについても、リサイクルが直面している現状についても感じられます。我々は我々であることを辛うじて繫ぎとめている艫綱を自らの手で断ち切ろうとしているように見えます。そうならないよいうに少なくとも自分のやっている繊維リサイクルの仕事をもっと掘り下げ、我々が先祖から受け継いできた「将来のためにまだ失ってはならないもの」を発信していきたいと思います。
繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした
よろしければクリックおねがいします!
↓
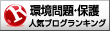
どんなに良い物を追求しても、その良さを理解できる受け手がいなくなれば衰退していかざるを得ません。このことが繊維リサイクルの現状と重なり合って感じられました。
こうした伝統を全て捨て去ってしまった後の日本人には一体何が残るのだろうと考えさせられます。資本主義経済の中に組み込まれた、単なる浪費する単位の集合?既に非日常化している歌舞伎や懐石料理といった断片を拾い集めて「これが日本文化です」と世界に向けて発信したところで、自分たちにその価値を認める下地がなければ不毛なことです。
さらに、ふと先週行ってきた福岡を思い出しました。僕が愛してやまない福岡、10年振りにじっくり歩いた町並みはすっかりその姿を変えていました。しかしただ昔の面影がなくなったということ以上に感じていた寂寞感、あれは一体何だったのだろうと思っていましたが、今こうして考えてみると恐らく福岡の独自性の衰退、東京への同質化のようなものを感じたからではなかったかと思います。
少なくとも10年前は曲がりなりに東京とは違う福岡の独自性みたいなものを感じることができました。しかし今回見た福岡は東京の人がイメージする(あるいはメディアによって作り上げられた)、例えばラーメンやもつ鍋といったものだけが極端にクローズアップされた福岡の姿、その中に福岡自身が埋没しているように感じられました。これは異質というよりむしろ拡大された同質化と言えます。僕が福岡を愛することに変わりはありませんし、10年振りに歩いてみただけで本当のことが分かるわけでもありませんが、直感的にそう感じました。
福岡で感じた寂寞感は世界の中の日本ということについても、リサイクルが直面している現状についても感じられます。我々は我々であることを辛うじて繫ぎとめている艫綱を自らの手で断ち切ろうとしているように見えます。そうならないよいうに少なくとも自分のやっている繊維リサイクルの仕事をもっと掘り下げ、我々が先祖から受け継いできた「将来のためにまだ失ってはならないもの」を発信していきたいと思います。
 | 俵屋の不思議村松 友視世界文化社このアイテムの詳細を見る |
繻るに衣袽あり、ぼろ屋の窪田でした

よろしければクリックおねがいします!
↓



















