都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「酒井抱一 - 200年前の展覧会 - 」 千葉市美術館・市民美術講座(Vol.2)
千葉市美術館(コレクション理解のための市民美術講座)
「酒井抱一 - 200年前の展覧会 - 」
9/29 14:00~
講師 松尾和子(美術館学芸員)
すっかり続きをまとめるのを忘れていました。昨年9月、千葉市美術館にて開催された美術講座、「酒井抱一 - 200年前の展覧会 - 」の講演メモです。Vol.1より続く本エントリは、講座のメイン、つまりは抱一によって行われた「光琳百年忌」について触れたいと思います。講演の流れとしては、はじめに当時の展覧会のあり方を整理した上で、次に百年忌の話に進むというものでした。
江戸時代の展覧会
1、出開帳、見世物:一般向けの展示。現在の展覧会の形態に近い。秘仏公開など。
2、書画会、展観会:サロン的な展示。公開される対象が限定。広い座敷のある、寺社や料理屋などで開催された。
a)古書画を集めて展示する。
b)当代の書画家の新作の発表展示。
例)「陽春桜展観」(1793、高松)中国の書画を展示。
「新書画展観」(1793、京都)皆川堪園主催。
「感応寺雅集の展観」(1794、江戸・感応寺)谷文晁主催。
「秋芳園新書画展観」(1804、江戸・百花園)抱一も出品。
3、追善の会:法要をかねての展観。故人の作とともに、各人の新作も展示する。
例)「池大雅二十五周忌追善会」(1800)
「蘆雪の会」(1810):蘆雪作品を含めた160点が集まった。弟子の寄せ書き入りの「蘆雪像」の展示もあり。
「尾形光琳居士一百週諱展観会」(光琳百年忌。文化12年、1815年。)
1、準備史
a)抱一による光琳作の研究(文化4年頃)
光琳遺族への聞き取り、または谷文晁らとの調査旅行。
b)作品の真贋の鑑定(文化8年頃)
落款の調査。住吉家に作品を持ち込み、その真贋を鑑定させた。
(住吉家古画留帳:光琳作22点を抱一が持ち込んで来たとの記述あり。風神雷神図、宗達の関屋図屏風など。またその中には偽物とされる作品もあった。)
c)「緒方流略印譜」(文化10年)
研究活動の公表。2年後の展観会には出版も行う。
2、文化12年、百回忌に向けて。

a)「観世音像」
百回忌に合わせて制作。光琳の菩提寺に寄進
(=寺の文書には、抱一がこの作とともに金200疋、印譜を寄付して来たとの記述がある。)
故人を偲ぶ意味での立ち葵と百合。彩色を抑えた、穏やかな画風が見られる。
瓶の部分に賛=自らを末弟と記した。
b)「瓶花図」
立ち葵のモチーフ。自ら筆をとり、百回忌の参加者に配った。100枚ほど制作か。
c)「君山君積宛書状」(文化12年5月10日)
君山氏に百回忌の世話人になることを要請。
d)「大田南畝宛書状」
展観の招待状も発送。大田南畝宛。
3、百回忌と「光琳百図」
文化12年6月2日一日限り。
光琳画全42点を展観。(目標の100点には届かず。)
展示作品の多くは当日中に所有者へ返還された。
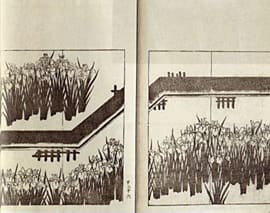
a)「光琳百図」
追善の一環として企画された光琳の画集。実際に出たのは展観後。
展観出品作が多く掲載されているが、「燕子花」など不出品作も載っている。
「必庵宛書状」:百図図版の制作を急がせる内容の書状。弟子其一に宛てたものか。
光琳の作品名、形状、所有者などのリストを提示。光琳画の画集。
住吉家に偽物と判定された作品も載っている。抱一自身の判定か。
原本は焼けている。そのため一部、判別不能な箇所もあり。
当初に上下巻が出版され、さらに増補版も出た。
b)失われた百回忌出品作と抱一
元の光琳画が既に失われているが、出品作を見て、その後抱一が描いた作品。
「三十六歌仙図屏風」、「青楓朱楓図屏風」(其一風)

以上です。この後は、光琳百図が、後世の琳派史にどう影響を与えたのかなどを簡単に説明して幕となりました。
ところで講演の松尾氏によれば、まだ時期は確定出来ないものの、近いうちに、ここ千葉市美において「酒井抱一展」を開催するという話があるそうです。これは、抱一と縁も深い姫路の市立美術館と連動企画(巡回展)になるとのことでしたが、ここ最近、関東で単独の抱一展は殆ど開催されていません。実現すれば、琳派ファンにとっても待望の展示となりそうです。
なお繰り返しになりますが、本エントリは昨年10月の「酒井抱一 - 200年前の展覧会 - 」(Vol.1)の続きにあたります。そちらと合わせてご参照いただければ幸いです。
*関連エントリ
「酒井抱一 - 200年前の展覧会 - 」 千葉市美術館・市民美術講座(Vol.1)
「酒井抱一 - 200年前の展覧会 - 」
9/29 14:00~
講師 松尾和子(美術館学芸員)
すっかり続きをまとめるのを忘れていました。昨年9月、千葉市美術館にて開催された美術講座、「酒井抱一 - 200年前の展覧会 - 」の講演メモです。Vol.1より続く本エントリは、講座のメイン、つまりは抱一によって行われた「光琳百年忌」について触れたいと思います。講演の流れとしては、はじめに当時の展覧会のあり方を整理した上で、次に百年忌の話に進むというものでした。
江戸時代の展覧会
1、出開帳、見世物:一般向けの展示。現在の展覧会の形態に近い。秘仏公開など。
2、書画会、展観会:サロン的な展示。公開される対象が限定。広い座敷のある、寺社や料理屋などで開催された。
a)古書画を集めて展示する。
b)当代の書画家の新作の発表展示。
例)「陽春桜展観」(1793、高松)中国の書画を展示。
「新書画展観」(1793、京都)皆川堪園主催。
「感応寺雅集の展観」(1794、江戸・感応寺)谷文晁主催。
「秋芳園新書画展観」(1804、江戸・百花園)抱一も出品。
3、追善の会:法要をかねての展観。故人の作とともに、各人の新作も展示する。
例)「池大雅二十五周忌追善会」(1800)
「蘆雪の会」(1810):蘆雪作品を含めた160点が集まった。弟子の寄せ書き入りの「蘆雪像」の展示もあり。
「尾形光琳居士一百週諱展観会」(光琳百年忌。文化12年、1815年。)
1、準備史
a)抱一による光琳作の研究(文化4年頃)
光琳遺族への聞き取り、または谷文晁らとの調査旅行。
b)作品の真贋の鑑定(文化8年頃)
落款の調査。住吉家に作品を持ち込み、その真贋を鑑定させた。
(住吉家古画留帳:光琳作22点を抱一が持ち込んで来たとの記述あり。風神雷神図、宗達の関屋図屏風など。またその中には偽物とされる作品もあった。)
c)「緒方流略印譜」(文化10年)
研究活動の公表。2年後の展観会には出版も行う。
2、文化12年、百回忌に向けて。

a)「観世音像」
百回忌に合わせて制作。光琳の菩提寺に寄進
(=寺の文書には、抱一がこの作とともに金200疋、印譜を寄付して来たとの記述がある。)
故人を偲ぶ意味での立ち葵と百合。彩色を抑えた、穏やかな画風が見られる。
瓶の部分に賛=自らを末弟と記した。
b)「瓶花図」
立ち葵のモチーフ。自ら筆をとり、百回忌の参加者に配った。100枚ほど制作か。
c)「君山君積宛書状」(文化12年5月10日)
君山氏に百回忌の世話人になることを要請。
d)「大田南畝宛書状」
展観の招待状も発送。大田南畝宛。
3、百回忌と「光琳百図」
文化12年6月2日一日限り。
光琳画全42点を展観。(目標の100点には届かず。)
展示作品の多くは当日中に所有者へ返還された。
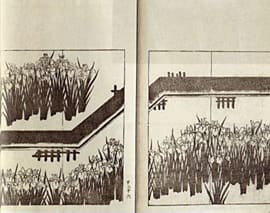
a)「光琳百図」
追善の一環として企画された光琳の画集。実際に出たのは展観後。
展観出品作が多く掲載されているが、「燕子花」など不出品作も載っている。
「必庵宛書状」:百図図版の制作を急がせる内容の書状。弟子其一に宛てたものか。
光琳の作品名、形状、所有者などのリストを提示。光琳画の画集。
住吉家に偽物と判定された作品も載っている。抱一自身の判定か。
原本は焼けている。そのため一部、判別不能な箇所もあり。
当初に上下巻が出版され、さらに増補版も出た。
b)失われた百回忌出品作と抱一
元の光琳画が既に失われているが、出品作を見て、その後抱一が描いた作品。
「三十六歌仙図屏風」、「青楓朱楓図屏風」(其一風)

以上です。この後は、光琳百図が、後世の琳派史にどう影響を与えたのかなどを簡単に説明して幕となりました。
ところで講演の松尾氏によれば、まだ時期は確定出来ないものの、近いうちに、ここ千葉市美において「酒井抱一展」を開催するという話があるそうです。これは、抱一と縁も深い姫路の市立美術館と連動企画(巡回展)になるとのことでしたが、ここ最近、関東で単独の抱一展は殆ど開催されていません。実現すれば、琳派ファンにとっても待望の展示となりそうです。
なお繰り返しになりますが、本エントリは昨年10月の「酒井抱一 - 200年前の展覧会 - 」(Vol.1)の続きにあたります。そちらと合わせてご参照いただければ幸いです。
*関連エントリ
「酒井抱一 - 200年前の展覧会 - 」 千葉市美術館・市民美術講座(Vol.1)
コメント ( 4 ) | Trackback ( 0 )










