都内近郊の美術館や博物館を巡り歩く週末。展覧会の感想などを書いています。
はろるど
「日本の新進作家 vol.6 スティル/アライヴ」 東京都写真美術館
東京都写真美術館(目黒区三田1-13-3 恵比寿ガーデンプレイス内)
「日本の新進作家 vol.6 スティル/アライヴ」
2007/12/22-2008/2/20
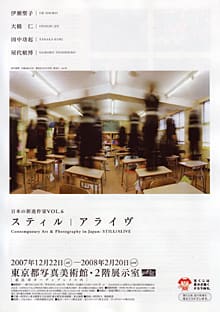
このシリーズを見るのは何年ぶりでしょうか。伊瀬聖子、屋代敏博、大橋仁、田中功起の4名のアーティストが、それぞれ思い思いに独自の表現を突き詰めます。写真美術館で開催中の「スティル/アライヴ」展へ行ってきました。

まず見入ったのは、先日、目黒区美で「銭湯」シリーズの印象深かった、屋代敏博のインスタレーションです。屋代といえば、時に繋がらない光景などを、縦の一線を軸に、左右へパノラマ的におさめてしまう写真が興味深いところですが、今回の「回転回LIVE!」シリーズでは、何とその中へ本人も含めた回転する人物を写し入れています。舞台は全国各地の学校です。これは屋代自身が現地に趣き、約2年ほどかけて学生、生徒の回転する様をフレームにおさめたそうですが、元々、グルリと一周して見やるような屋代の写真にさらなる動き、しかも今回は縦へのベクトルが加わっていて興味深く感じられました。また、回転する生徒たちが、静止した空間から駆け抜けていつの間にやら消えていく(卒業)とでもいえる、堅牢な学校(静止)とそれ(回転)との一種のズレが加わってもいます。それに、実際のプロジェクトを映したビデオも臨場感を高めていました。

美感に優れているという点でベストなのは、伊藤聖子の「スイミング・イン・クオリア」です。前方と左手に配された二枚の大型スクリーンに、同じ素材によりながらもイメージの異なる二つの映像を投影し、そこへさらに二種の音楽をシンクロさせています。異なった速度によって次々と移り変わる映像が、どこか重なりつつもありまた離れていくイメージの揺らぎを生み出し、またそれぞれに呼応するテンポの異なった音楽(一種はヘッドホンでの観賞。)が、時間と空間のリアルな感覚を喪失させていくような、夢見心地で幻想的な場を創出していました。映像と音楽とが半ば対角線上に交わる、明快なコンセプトも魅力の一つです。
最後の田中功起は、それこそ場の重みを解体してくれるような痛快なインスタレーションです。土地の記憶に依りながらも、用いられた素材と現実とのギャップを実にストレートな形で提示しています。ビール工場の映像が、ボーリングのピンを移動させる行程と重なって見えてなりません。映像内の工場より瓶を経由してのボーリング場、そしてさらに土地の記憶を経由しての美術館という空間の全てが、一本の糸で結ばれているような展示でもありました。
今月20日までの開催です。
「日本の新進作家 vol.6 スティル/アライヴ」
2007/12/22-2008/2/20
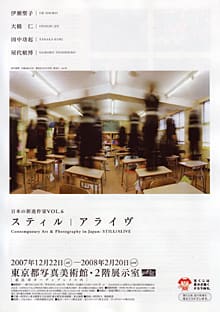
このシリーズを見るのは何年ぶりでしょうか。伊瀬聖子、屋代敏博、大橋仁、田中功起の4名のアーティストが、それぞれ思い思いに独自の表現を突き詰めます。写真美術館で開催中の「スティル/アライヴ」展へ行ってきました。

まず見入ったのは、先日、目黒区美で「銭湯」シリーズの印象深かった、屋代敏博のインスタレーションです。屋代といえば、時に繋がらない光景などを、縦の一線を軸に、左右へパノラマ的におさめてしまう写真が興味深いところですが、今回の「回転回LIVE!」シリーズでは、何とその中へ本人も含めた回転する人物を写し入れています。舞台は全国各地の学校です。これは屋代自身が現地に趣き、約2年ほどかけて学生、生徒の回転する様をフレームにおさめたそうですが、元々、グルリと一周して見やるような屋代の写真にさらなる動き、しかも今回は縦へのベクトルが加わっていて興味深く感じられました。また、回転する生徒たちが、静止した空間から駆け抜けていつの間にやら消えていく(卒業)とでもいえる、堅牢な学校(静止)とそれ(回転)との一種のズレが加わってもいます。それに、実際のプロジェクトを映したビデオも臨場感を高めていました。

美感に優れているという点でベストなのは、伊藤聖子の「スイミング・イン・クオリア」です。前方と左手に配された二枚の大型スクリーンに、同じ素材によりながらもイメージの異なる二つの映像を投影し、そこへさらに二種の音楽をシンクロさせています。異なった速度によって次々と移り変わる映像が、どこか重なりつつもありまた離れていくイメージの揺らぎを生み出し、またそれぞれに呼応するテンポの異なった音楽(一種はヘッドホンでの観賞。)が、時間と空間のリアルな感覚を喪失させていくような、夢見心地で幻想的な場を創出していました。映像と音楽とが半ば対角線上に交わる、明快なコンセプトも魅力の一つです。
最後の田中功起は、それこそ場の重みを解体してくれるような痛快なインスタレーションです。土地の記憶に依りながらも、用いられた素材と現実とのギャップを実にストレートな形で提示しています。ビール工場の映像が、ボーリングのピンを移動させる行程と重なって見えてなりません。映像内の工場より瓶を経由してのボーリング場、そしてさらに土地の記憶を経由しての美術館という空間の全てが、一本の糸で結ばれているような展示でもありました。
今月20日までの開催です。
コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )










