〇兵庫県立歴史博物館 特別展『ひょうごの美ほとけ-五国を照らす仏像-』(2017年4月22~6月4日)
兵庫県内各地の文化財調査や市町史関係の調査で確認された注目すべき仏像と関連資料、約50件を展示する。会場の兵庫県立歴史博物館は姫路城の北側にある。何度か来たことがあるように思っていたが、いつも素通りしていたようで、初訪問だった。
冒頭には朝来市円龍寺の銅造菩薩立像(白鳳時代)。頭部が大きくて子供のようにかわいい。薄くて細い体をかすかにS字にねじっている。このほか、白鳳時代の仏像が全部で4点並ぶ。そうそう、この一帯は白鳳の金銅仏が多いんだよなあ、鶴林寺とか一乗寺とか…と思い出して悦に入る。
展示は大雑把に時代順で、奈良時代の仏像として金蔵寺(多可町)の阿弥陀如来坐像が展示されていた。そのとなりに「参考」として掲げられた菩薩坐像の写真に見覚えがある。近年、横浜市の龍華寺で発見された脱活乾漆像ではないか(金沢文庫で見た)。実は、顔かたちの類似から見て、この菩薩像は、金蔵寺の像の右脇侍であった可能性が高いのだという。金蔵寺の像は、首から下の肉付きのいい体は候補で、頭部には細かい螺髪がびっしり植えられているが、確かに顔だけに意識を集中してみると似ている。なお金蔵寺の像は、もとは摂津に伝来したことが分かっている。
本展には、ほかにも「移動する仏像」の例がいくつかあって、興味深かった。以下は全て、参考写真パネルで展示されていたものだが、いちばん驚いたのは、朝光寺(加東市)の千手観音立像。京都の蓮華王院(三十三間堂)の千体仏の一躯が、あるとき持ち出されたもので、現在の千体仏には室町時代の作が一躯だけ混じっているそうだ。室町幕府の要職にあった播磨守護赤松氏の関わりがあったのではないかという。
また、舎那院(長浜市)の薬師如来坐像は、底面の朱書と円教寺(姫路市)の記録によって、もと円教寺にあったが、長浜城主・羽柴秀吉が毛利攻めで円教寺に布陣したとき、長浜に持ち出されたものと推定されている。現在、円教寺に伝わる小さな如意輪観音坐像は、チョコレート色の肌に衣の截金文様が映える美仏だが、やはり羽柴秀吉に持ち出され、戻ったものであるらしい。まったく武士は無茶なことをする。
快慶(または快慶工房)の「安阿弥陀様」の阿弥陀如来立像、運慶の作風に近い毘沙門天立像も出ていた。私は、善光寺(多可町)の阿弥陀如来立像(平安前期)など、古い姿が好みである。丹波市山南町の薬師如来坐像(平安後期)は、表情のかたい素朴な像だが、墨で描かれた文様がはっきり残る板光背が面白かった。33年に一度ご開帳の秘仏を拝ませていただき、感謝に耐えない。会場で唯一、ケースなしで展示されていたのは、随願寺(姫路市)の毘沙門天立像(平安中期)で、2メートルを超す堂々とした体躯、腰高でスタイルもいいのだが、顔が農民顔で、少し困った様子なのが微笑ましい。
兵庫のいろいろな仏像を知ることができて嬉しかったが、写真パネルの「参考展示」が多かった(18例)のは、得をしたような損をしたような、微妙な気分。安養寺(猪名川町)の阿弥陀如来立像は、いわゆる「逆手来迎印」で、一目見て腕のきれいな伸ばし方が(仏画の)高麗仏っぽいと感じた。 いちばんの「美仏」だと思ったのは、観音寺(朝来市)の聖観音立像で、これはぜひ本物を拝観に行きたいと思ったら、秘仏なのだそうだ。
あとで知ったのだが、同館は、昭和59年(1984)と平成3年(1991)にも「ふるさとのみほとけ」展を開催しており、これが三度目の仏像展になる。博物館の仕事は展示だけではないので、二度目の仏像展以降、地域の仏像について丁寧な調査を重ね、貴重なデータを蓄積してきたことが、しみじみ感じられた。図録の解説は、仏像の来歴、記録、様式、構造(後補や転用の跡など)がしっかり記述されていて、安心感がある。今後も、この地方の仏像が愛され、守り伝えられていきますように。

姫路城は、2009~2015年に行われた「平成の大修理」が終わって、初めて見たと思う。「白くなりすぎでは?」という感想を見た記憶があるが、なるほど、本当に白くなった。いまネットで画像検索すると、屋根瓦の黒と壁の白のコントラストがはっきりした「改修前」の姿と、全体に白くなった「改修後」の姿が混じってヒットする。だんだん前者は忘れられていくのかな…と思い、ここに記憶を書きとどめておく。まあしかし、このくらい白いと、最上階の天守には、いかにもこの世ならぬあやしく美しいものたちが住んでいそうなのは、大変いいと思う。
兵庫県内各地の文化財調査や市町史関係の調査で確認された注目すべき仏像と関連資料、約50件を展示する。会場の兵庫県立歴史博物館は姫路城の北側にある。何度か来たことがあるように思っていたが、いつも素通りしていたようで、初訪問だった。
冒頭には朝来市円龍寺の銅造菩薩立像(白鳳時代)。頭部が大きくて子供のようにかわいい。薄くて細い体をかすかにS字にねじっている。このほか、白鳳時代の仏像が全部で4点並ぶ。そうそう、この一帯は白鳳の金銅仏が多いんだよなあ、鶴林寺とか一乗寺とか…と思い出して悦に入る。
展示は大雑把に時代順で、奈良時代の仏像として金蔵寺(多可町)の阿弥陀如来坐像が展示されていた。そのとなりに「参考」として掲げられた菩薩坐像の写真に見覚えがある。近年、横浜市の龍華寺で発見された脱活乾漆像ではないか(金沢文庫で見た)。実は、顔かたちの類似から見て、この菩薩像は、金蔵寺の像の右脇侍であった可能性が高いのだという。金蔵寺の像は、首から下の肉付きのいい体は候補で、頭部には細かい螺髪がびっしり植えられているが、確かに顔だけに意識を集中してみると似ている。なお金蔵寺の像は、もとは摂津に伝来したことが分かっている。
本展には、ほかにも「移動する仏像」の例がいくつかあって、興味深かった。以下は全て、参考写真パネルで展示されていたものだが、いちばん驚いたのは、朝光寺(加東市)の千手観音立像。京都の蓮華王院(三十三間堂)の千体仏の一躯が、あるとき持ち出されたもので、現在の千体仏には室町時代の作が一躯だけ混じっているそうだ。室町幕府の要職にあった播磨守護赤松氏の関わりがあったのではないかという。
また、舎那院(長浜市)の薬師如来坐像は、底面の朱書と円教寺(姫路市)の記録によって、もと円教寺にあったが、長浜城主・羽柴秀吉が毛利攻めで円教寺に布陣したとき、長浜に持ち出されたものと推定されている。現在、円教寺に伝わる小さな如意輪観音坐像は、チョコレート色の肌に衣の截金文様が映える美仏だが、やはり羽柴秀吉に持ち出され、戻ったものであるらしい。まったく武士は無茶なことをする。
快慶(または快慶工房)の「安阿弥陀様」の阿弥陀如来立像、運慶の作風に近い毘沙門天立像も出ていた。私は、善光寺(多可町)の阿弥陀如来立像(平安前期)など、古い姿が好みである。丹波市山南町の薬師如来坐像(平安後期)は、表情のかたい素朴な像だが、墨で描かれた文様がはっきり残る板光背が面白かった。33年に一度ご開帳の秘仏を拝ませていただき、感謝に耐えない。会場で唯一、ケースなしで展示されていたのは、随願寺(姫路市)の毘沙門天立像(平安中期)で、2メートルを超す堂々とした体躯、腰高でスタイルもいいのだが、顔が農民顔で、少し困った様子なのが微笑ましい。
兵庫のいろいろな仏像を知ることができて嬉しかったが、写真パネルの「参考展示」が多かった(18例)のは、得をしたような損をしたような、微妙な気分。安養寺(猪名川町)の阿弥陀如来立像は、いわゆる「逆手来迎印」で、一目見て腕のきれいな伸ばし方が(仏画の)高麗仏っぽいと感じた。 いちばんの「美仏」だと思ったのは、観音寺(朝来市)の聖観音立像で、これはぜひ本物を拝観に行きたいと思ったら、秘仏なのだそうだ。
あとで知ったのだが、同館は、昭和59年(1984)と平成3年(1991)にも「ふるさとのみほとけ」展を開催しており、これが三度目の仏像展になる。博物館の仕事は展示だけではないので、二度目の仏像展以降、地域の仏像について丁寧な調査を重ね、貴重なデータを蓄積してきたことが、しみじみ感じられた。図録の解説は、仏像の来歴、記録、様式、構造(後補や転用の跡など)がしっかり記述されていて、安心感がある。今後も、この地方の仏像が愛され、守り伝えられていきますように。

姫路城は、2009~2015年に行われた「平成の大修理」が終わって、初めて見たと思う。「白くなりすぎでは?」という感想を見た記憶があるが、なるほど、本当に白くなった。いまネットで画像検索すると、屋根瓦の黒と壁の白のコントラストがはっきりした「改修前」の姿と、全体に白くなった「改修後」の姿が混じってヒットする。だんだん前者は忘れられていくのかな…と思い、ここに記憶を書きとどめておく。まあしかし、このくらい白いと、最上階の天守には、いかにもこの世ならぬあやしく美しいものたちが住んでいそうなのは、大変いいと思う。















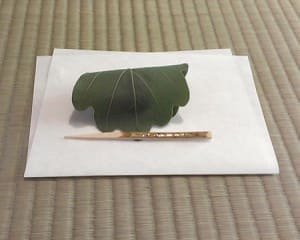


 よくある「週刊〇〇」というスタイルで刊行された薄いムック本である。およそ学習マンガなど描きそうにない、つまり自前の作品がよく売れていて、多くのファンが絵柄を知っているマンガ家、藤原カムイや池上遼一などを執筆陣に迎え入れた意外性に注目した記憶がある。買ったことはなかったのだが、奈良博の『快慶』展を見た後、図録だけでは物足りなくて、一緒に本書を買ってみた。
よくある「週刊〇〇」というスタイルで刊行された薄いムック本である。およそ学習マンガなど描きそうにない、つまり自前の作品がよく売れていて、多くのファンが絵柄を知っているマンガ家、藤原カムイや池上遼一などを執筆陣に迎え入れた意外性に注目した記憶がある。買ったことはなかったのだが、奈良博の『快慶』展を見た後、図録だけでは物足りなくて、一緒に本書を買ってみた。






