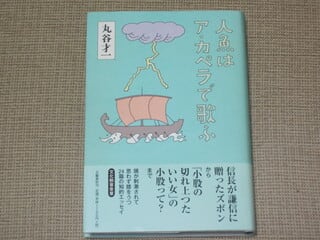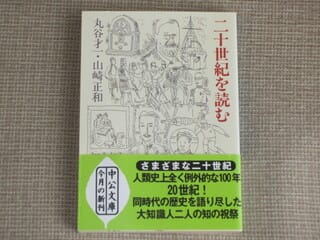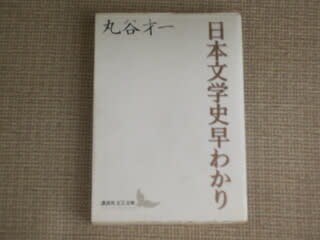これは去年9月の古本まつりで買ったもの、なんか似たようなのあったよなーって思ったんだが、『固い本やわらかい本』ってのが同じ鼎談書評だった。
あっちは1986年の出版なんで、時系列的にはこっちが先かってことになる、媒体は文藝春秋だねえ、あとがきによれば「夕方六時から始まって、休みなくぶっ通しで、九時か九時半までかかる」という座談会だったそうだ。ちなみに座談会ってのは、菊池寛創案で文藝春秋が始めたものだという。
書評といっても座談会なんでむずかしいことなく、おもしろいんだが、私はやっぱ丸谷さんがきびしいこと言うのがお気に入りである。
>丸谷 (略)というふうに、褒めたいことは色々あるんですが、敢えて文句をいうほうに回ります。(笑)
>木村 さあ、どうぞ。(笑)(p.22)
とか、
>丸谷 (略)それと、これだけ褒めたあとだから勘弁してほしいんですけど、もうちょっといい文章だったら、どんなによかったかという感じがします。例えば一五七ページ……。
>山崎 丸谷才一「文章読本」。(笑)(p.68)
とか、
>丸谷 (略)この本がダメなのは、第一、書き方が下等である……。
>木村 もう始まった。(笑)(p.294)
とかって、もう文句のつけかたがひとつの藝になってると言えるんぢゃないかと。
もちろん書評に採りあげる本なんだから全然ダメってことはなく、褒めといてケナすのが藝のみせどころなわけで。
>丸谷 ちょっといいバーの、ちょっといいオツマミを、うんとたくさん食べた時みたいな感じになる本ですね。(p.365)
なんて言い方は、こっちが読んだことない本についてだっておもしろい。
かの薄田泣菫の「茶話」については、
>丸谷 (略)大体、こんなゴシップに夢中になって、しかも、こんなにうまい文章で書けるなんて、人間として少しおかしいんじゃありませんか。(笑)(p.230)
なんて言ってますが、かなわんなあって認めてるってことなんでしょう。
私は丸谷さんファンなんで、どうしても丸谷さんの発言にひかれてしまうんだけど、
>木村 したがって、私は歴史を学校で試験することには、本当をいうと反対です。入試科目からは除いたほうがいい。しかし、にもかかわらず教室で教えなければいけないと思っています。本来、正しい歴史の教科書などありえません。歴史叙述はすべて副読本としての扱いしか出来ないものなんですね。独特の史観、人生観、世界観がそこに反映されてこそ読むに値するからです。(p.248)
って歴史学者なのに言っちゃってる木村さんも、
>山崎 これはかなり深刻な文化論に結びつくんですが、良きにつけ悪しきにつけ、中国の詩は志を述べるものなんです。それに対して日本の詩は「あわれ」を述べる。志に対して「あわれ」ということを言ってしまったが最後、文学は極めて高級になるか、逆にナンセンスになるかどちらかなんですね。(p.204)
って劇作家にして、商品宣伝コピーってのは日本の短詩型芸術の伝統だとか言う山崎さんも、刺激になる発言いっぱいで、読んでておもしろい。
さてさて、それぢゃあ読んでみたくなる本はあったかというと、急にいますぐどうしようって感じになったもんはないんだが、
>山崎 (略)著者は、意図的に一見不愛想な、教科書風、官庁文書風の文体をつくりあげておいて、そこへ突然「泣く子と地頭」とか「腹のすわった大人」といった言葉を投げいれるのです。そこには著者の皮肉な目、悲しみを秘めたユーモアが感じられます。(略)
>木村 これは大変な本ですね。私が日ごろ、日本についていやだなあと思っていることが全部出てくる。「強気を助け弱気を挫く」とか、「虎の威を借る狐」とか「人間万事、色と欲」とか。(笑)(p.90-91)
って評されている、京極純一『日本の政治』とかは興味あるかも、むずかしそうだから、たぶんいかない気がするけど。
あと、
>丸谷 日本の学者が社会に向けて発言すると、以前は、おおむね、抽象的・観念的な説教になるのが普通でした。ところが最近、具体的な提案をするようになってきた。
>(略)いつも具体的に語って、しかもそれが高い識見に支えられている。学者が社会にむかって物を言うときの態度として模範的なものだという感じがしました。(p.257)
と言われてる、芦原義信『街並みの美学』正続二巻ってのも、おもしろそうにみえる。
>山崎 でも私には、海軍の参謀そのものがサービス業だという指摘は発見でしたね。人を動かすのが参謀、ましてや人を死なせるのが参謀。そのためには、まず自分の考えを味方に説得するのが最初の仕事になる。その説得の部分はまさにサービス業で、それはお座敷芸を含む宴会の技術にまでつながっているというんですね。(p.273)
っていう、田辺英蔵『海軍式サービス業発想』ってのも読んだら発見するものありそうとは思わされた。新橋第一ホテルの重役は元海軍の砲術参謀で、ホテルの部屋が狭くて合理的なのが潜水艦の艦内みたいだと思ったら、海軍の発想だったのかって山崎さんの感想がどこまで冗談なのかわからんがおもしろい。
コンテンツは以下のとおり。
草創期の無茶苦茶精神
『星 亨』 有泉貞夫
『明治の東京計画』 藤森照信
『科学者たちの自由な楽園』 宮田親平
人間と性と芸術と
『斎藤茂吉私論』 中村稔
『結婚の起源』 ヘレン・E・フィッシャー
『私のピカソ 私のゴッホ』 池田満寿夫
都市の“下半身”を診断すれば
『水道の文化』 鯖田豊之
『ある明治人の生活史』 小木新造
『地球ドライブ27万キロ』 大内三郎
モーレツなる曲り角の時代
『日本の政治』 京極純一
『見栄講座』 ホイチョイ・プロダクション
『グルマン』 山本益博・見田盛夫
天才ジャーナリストの時代
『「ニューズウィーク」の世界』 オズボーン・エリオット
『破獄』 吉村昭
『人類の長い旅』 キム・マーシャル
“失われた生活”をめぐって
『死と歴史』 フィリップ・アリエス
『アメリカの男たちは、いま』 下村満子
『木村伊兵衛写真全集昭和時代』
“辛口の読書”のすすめ
『読書人 読むべし』 百目鬼恭三郎
『文楽三代 竹本津太夫聞書』
『糸井重里の萬流コピー塾』
英国で「資本論」が書かれたわけ
『クラース』 ジリー・クーパー
『完本茶話』 薄田泣菫
『いいもの ほしいもの』 秋岡芳夫
公教育から「歴史」を廃止せよ!
『戦争の教え方』 別技篤彦
『続・街並みの美学』 芦原義信
『海軍式サービス業発想』 田辺英蔵
西洋的時間と日本的時間
『時計の社会史』 角山榮
『絵巻切断』 NHK取材班
『宮武東洋の写真』
衣食足りて、礼楽の再発見
『御進講録』 狩野直喜
『ハーバード通信』 板坂元
『賭博師ファロン』 ルイス・ラムーア
日本は英国病にかからない
『ジャパニーズ・マインド』 R・C・クリストファー
『橋と日本人』 上田篤
『さよなら、大衆。』 藤岡和賀夫