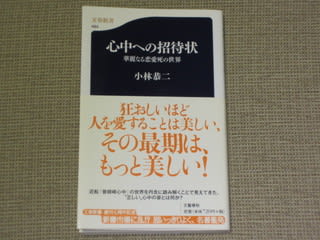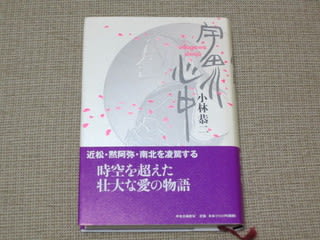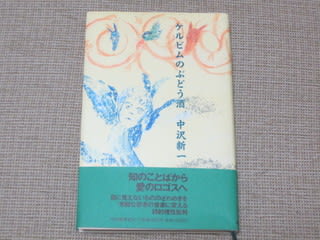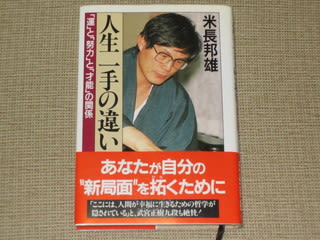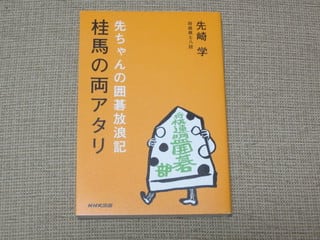小林恭二 2005年 文春新書
きのうのつづき。『宇田川心中』のすぐあとに出た新書。
サブタイトルは「華麗なる恋愛死の世界」。
自分でも心中もの書いた作家なんで、もちろん自殺系サイトへの勧誘なんかぢゃなくて、「原心中」とは何かがテーマ。
そこらへんにゴロゴロ心中があふれてきたせいで見えにくくなっちゃった、心中の本質とは何かの考察。
それを探るために「曽根崎心中」を読み説いている。日本文学というか文化史上においても、最重要ともいえる作品だと。
もっとも私は、曽根崎心中を観たことない。文楽も歌舞伎も知らないし、本も読んだことない。
だから、著者の気合いの入った解説は、ハァそうですかって素直に読むしかないんだけど。
そもそも、江戸時代から現代にいたるまで、近松の原作どおり上演されてる例のほうが少ないってことも、え?そうなの?ってホントは驚くべきとこなんだろうが、私にはピンとこない。
ほかにも、たとえば、悪役の九平次について、著者は“名作の癌”と断罪してるんだが。
「曽根崎心中」は現実の心中事件から十日やそこらで書かれて、即舞台にかけられ心中の本質を提示するという、天才の仕事なんだけど、その代わりに「ドラマトゥルギーは決定的にスポイルされた」という著者の見解には、もっと目からうろこが落ちなきゃいけないはず、予備知識があったらね。
で、曽根崎心中に見られる、本来の心中とは何かってのは、かなり明快に示されている。
目前の障害に打ちひしがれてするもんぢゃなく、熟慮の結果なされるもの。
人生に窮して消極的に死ぬんぢゃなくて、死後の名声のために死ぬもの。
能動的に死を選んで、死の苦しみを積極的に引き受ける気概のあるもの。(薬や入水ぢゃなく、刃物使って雄雄しく死ねって。)
「恋する二人の究極の約束」が心中であって、「敗者たちの複数自殺」は違うよ、と。
そうやって書きならべてみると、過激だなあ。社会批評や心理分析ぢゃなくて、あくまで文芸評論なんだけど。
そうそう、私は読んだことないけど、近松ってのは名文らしい。
でも、名フレーズの間に気の抜けたようなフレーズがはさまってて、正岡子規あたりに批判されたこともあるそうだけど。
そこんとこを、
>これは作詞をした人ならすぐにわかると思いますけど、呼吸を整えているんです。
と解説してくれてるのは、妙に納得できるし、文学の解説らしいとこではある。
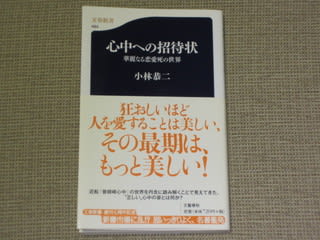
きのうのつづき。『宇田川心中』のすぐあとに出た新書。
サブタイトルは「華麗なる恋愛死の世界」。
自分でも心中もの書いた作家なんで、もちろん自殺系サイトへの勧誘なんかぢゃなくて、「原心中」とは何かがテーマ。
そこらへんにゴロゴロ心中があふれてきたせいで見えにくくなっちゃった、心中の本質とは何かの考察。
それを探るために「曽根崎心中」を読み説いている。日本文学というか文化史上においても、最重要ともいえる作品だと。
もっとも私は、曽根崎心中を観たことない。文楽も歌舞伎も知らないし、本も読んだことない。
だから、著者の気合いの入った解説は、ハァそうですかって素直に読むしかないんだけど。
そもそも、江戸時代から現代にいたるまで、近松の原作どおり上演されてる例のほうが少ないってことも、え?そうなの?ってホントは驚くべきとこなんだろうが、私にはピンとこない。
ほかにも、たとえば、悪役の九平次について、著者は“名作の癌”と断罪してるんだが。
「曽根崎心中」は現実の心中事件から十日やそこらで書かれて、即舞台にかけられ心中の本質を提示するという、天才の仕事なんだけど、その代わりに「ドラマトゥルギーは決定的にスポイルされた」という著者の見解には、もっと目からうろこが落ちなきゃいけないはず、予備知識があったらね。
で、曽根崎心中に見られる、本来の心中とは何かってのは、かなり明快に示されている。
目前の障害に打ちひしがれてするもんぢゃなく、熟慮の結果なされるもの。
人生に窮して消極的に死ぬんぢゃなくて、死後の名声のために死ぬもの。
能動的に死を選んで、死の苦しみを積極的に引き受ける気概のあるもの。(薬や入水ぢゃなく、刃物使って雄雄しく死ねって。)
「恋する二人の究極の約束」が心中であって、「敗者たちの複数自殺」は違うよ、と。
そうやって書きならべてみると、過激だなあ。社会批評や心理分析ぢゃなくて、あくまで文芸評論なんだけど。
そうそう、私は読んだことないけど、近松ってのは名文らしい。
でも、名フレーズの間に気の抜けたようなフレーズがはさまってて、正岡子規あたりに批判されたこともあるそうだけど。
そこんとこを、
>これは作詞をした人ならすぐにわかると思いますけど、呼吸を整えているんです。
と解説してくれてるのは、妙に納得できるし、文学の解説らしいとこではある。