エマニュエル・トッド/大野舞訳 2020年 筑摩書房
これはつい近ごろ、書店へ行ったときに積んであって、なんとなく気になって買ってみたもの。
著者名をぼんやりとおぼえていたのは、なにかテレビ番組のインタビューでおもしろいこと言っていたのを見たからだろうと思ったわけで。
(それって、グローバリゼーションの弊害だか限界だかとか、保護主義のパラドックスとか、そんな感じのこと。)
紹介によれば、著者はフランスの歴史人口学者で、ソ連崩壊やイギリスのEU離脱などを予測させてきたひと。
そのツールは人口に関する統計とかで、ソ連崩壊の決め手は乳児死亡率の高さだったという、いいねえ、統計による冷静な事実って。
でも、読んでくうちに失敗したと思った、そういうったこれまでの研究に関する著作を読んでないのに、いきなり本書を読んでも何の話をされてるか、ちょっとピンとこないから。
どうやら得意分野のひとつは家族構成に関することらしくて、現在の新型コロナウイルスへの対応にしても、ドイツ、日本、中国、韓国といった国は比較的うまくやっているんだけど、これらは直系家族の国だとか、そういう視点があるらしい。
ただ、これまでの業績に関してもけっこう批判があるらしく、詳しい事情は知らないが、
>私がめちゃくちゃなことばかり言うから学術界からは排除されてしまいましたが(略)(p.124)
なんて言ってる、でも活躍しているようだから、これは皮肉なんだろうか。
でも、そういう周囲の批判に対しても、
>(略)大学とそこに属する人々は、私の学説が人間の自由への侮辱だということを理由に、事実を見ようとはしませんでした。多くの人が批判を浴びせましたが、肝心なデータの正確性に関してのものは一つもありませんでした。(p.191)
と堂々と言ってのけられるんで、やっぱ統計データによる事実ってのは偉いんだと、私なんかは再認識しちゃう。
どうも伝統的なフランス文化みたいなものとソリがあわないらしく、「フランス哲学は現実から驚くほど切り離されてしまっている」とか、「フランス哲学の抽象的でまったく何が言いたいのかわからない文章」とかって言ってるとこもあり、イギリスの経験主義のほうがはるかに現実を直視してるぢゃないかってスタンスらしい。
タイトルにもなってる、肝心の「思考」ということについては、
>私にとって思考することの本質とは、とある現象と現象の間にある偶然の一致や関係性を見いだすということ――つまり「発見」をするということです。私には、方法論や抽象的な問いよりも、このことのほうが重要なのです。私にとって「発見」とは、」変数間の一致を見いだすことを意味します。(p.89)
というぐあいに、はっきり表明している。
ってことは、やっぱ量的データを処理して、そこにある事実を明らかにする、それが現実、って感じなんだろう、私は好きですね、そういうの。
ただ、経済学とかだとわりとふつうなんだろうが、歴史学でそういう考えとるのって、いままであんまり聞いたことなかった。
そのへん、歴史を学ぶことってことについては、
>(略)未来を見たいと思うのであれば、一歩下がって歴史的な観点から考察するのは必要不可欠なことです。(略)長期的な傾向についての知識を持っているということは、今日の突然で極端な変化をしっかりととらえることにつながるのです。(p.149)
みたいに言ってて、それに尽きるんぢゃないかと、学ばなければ、過去はあっても歴史がないってことになっちゃうしね。
序章 思考の出発点
1入力 脳をデータバンク化せよ
2対象 社会とは人間である
3創造 着想は事実から生まれる
4視点 ルーティンの外に出る
5分析 現実をどう切り取るか
6出力 書くことと話すこと
7倫理 批判にどう対峙するか
8未来 予測とは芸術的な行為である
村上春樹 2001年 文春文庫版
まだ読んだことなかった村上春樹を読むことにするか、と思って古本屋行くと探したりするようにしてんだけど、これは去年夏に地元で買った文庫。
サブタイトルのとおり、『アンダーグラウンド』の続編、単行本は1998年。
出版当時に出たこと知ってたはずだけど手に取らなかったのは、たぶん『アンダーグラウンド』が私にとってはあまり面白くなかったからではないかと。読み直したりしてないしね。
前作は地下鉄サリン事件の被害者へのインタビューなんだけど、こちらはオウム真理教の信者(元信者)へのインタビュー、もしかしたら、それも私があまり興味をもたなかった理由かもしれない。
で、読んでみたんだけど、やっぱ、ちょっと、何言ってんだかみたいに感じるとこあって、正直それほどおもしろくない。
でも、巻末に河合隼雄氏との対談があって、そこで河合さんの言ってるの読むことで、なんか救われた感があった。
>河合 それでね、インタビューの中にオウムに入ってちょっとやっているうちに身体の調子がぱっと良くなったという人がいたでしょう。あれ、僕はようわかるんです。僕らのとこにもそういう人が訪ねてこられます。で、会って話していてこう思うんです。こういう人はたとえばオウムみたいなところに行ったらいっぺんでぱっととれるやろなと。それは村上さん流に言うたらひとつの箱の中にぽこっと入ることなんです。だからいっぺん入ったら、ぱっと治ってしまいます。(略)
>ところがいったん入ってしまったら、今度は箱をどうするかというものすごい大きい問題を抱えることになります。だから僕らはそういう人を箱に入れずに治ってもらおうとします。(p.301-302)
とかって、治そうとか、しかも早く治そうとかって考えをとらず、さらに続けて、
>河合 (略)絶対帰依です。これは楽といえば楽でいいです。この人たちを見ていると、世界に対して「これはなんか変だ」と疑問を持っているわけです、みんなで、その「何か変だ」というのは、箱の中に入ると、「これはカルマだ」ということで全部きれいに説明がついてしまうわけです。(略)
>でもね、全部説明がつく論理なんてものは絶対だめなんです。僕らにいわせたらそうなります。そやけど、普通の人は全部説明できるものが好きなんですよ。
と言って、簡単そうな解決を性急に求めないことの重要性を説いてくれるんで、安心する。うーむ。
コンテンツは以下のとおり。
インタビュー
狩野浩之「ひょっとしてこれは本当にオウムがやったのかもしれない」
波村秋生「ノストラダムスの大予言にあわせて人生のスケジュールを組んでいます」
寺畑多聞「僕にとって尊師は、疑問を最終的に解いてくれるはずの人でした」
増谷始「これはもう人体実験に近かったですね」
神田美由紀「実を言いますと、私の前世は男性だったんです」
細井真一「ここに残っていたら絶対に死ぬなと、そのとき思いました」
岩倉晴美「麻原さんに性的な関係を迫られたことがあります」
高橋英利「裁判で麻原の言動を見ていると、吐き気がしてきます」
河合隼雄氏との対話
『アンダーグラウンド』をめぐって
「悪」を抱えて生きる
星野之宣 1981年 集英社ヤングジャンプ・コミックス 全2巻
去年の夏に特集のムックを手に取るときにはたぶん諸星大二郎が目当てだったんだけど。
そこで作品紹介されてるのをいろいろみるうちに、あれもこれも読んでみたくなった。危険だ。
そのなかでも、特に強い興味もった本作品なんだが、去年秋に古本を探しに行ったとき運よく2冊揃いで手に入れることができた。(値段がお買い得だった。)
伝説に登場する女性を題材にしたオムニバス短編集。
たとえばクレオパトラが、いったん死ぬが、エジプトの秘法により生まれ変わる、それがサロメだとか、ドキドキの設定。
それでも私がいちばん見たかったのは、「ファンが選んだ星野之宣作品の名シーン」という企画で支持を集めた、「月夢」のひとこま。
日本人初の月面着陸宇宙飛行士が、月に降り立ったとたんに走り出す、その先にあったのはかぐや姫の御殿だった、っていう圧倒的な光景、すごいな。よくこんな絵が思い浮かぶものだ。
第1巻
第1話 ローレライの歌
第2話 月夢
第3話 メドゥサの首
第4話 蜃気楼ファタ・モルガーナ
第5話 日高川
第2巻
第1話 カーミラの永い眠り
第2話 砂漠の女王
丸谷才一 2011年 中公文庫版
これは2019年4月に地元の古本屋で買ったもので、不幸なことに長い間読まずに放っておかれたもの。
もっとも単行本は一九八五年刊行だっていうんで、遠い昭和の話だ、5年くらい読むのが遅れたって何でもないような気もしないでもない。
おさめられている対談の初出はいろいろ雑誌だけど、古いのは昭和47年、新しくても昭和58年だしねえ。
対談集っておもしろいんだが、丸谷さん本人が本書のなかで、
>最近の本ではシンポジウムというのがはやってまして、序文に、われわれ三人があるホテルに籠って、じつに三日間の長きにわたって討論した内容がこの本であると書いてあるのですね。三日間の長きにわたってといえば、当人は長いと思ったかもしれないが、一冊の本が三日でできるわけじゃありませんか。おかしいですよ。(略)
>シンポジウム形式、対話形式の本というのは一切書評しないのが正しいだろうとかねがね思っているのですけど。(p.43)
なんて言って、手っ取り早く本をつくるために、しゃべりとばしたものを文字にしただけってのはいかがなものかと。
そんなこと言ってる対談は、本をつくろうとしてんぢゃなくて、雑誌の一コーナーの企画であるからいいんだろうが。
ちなみに雑誌ってものについて、昭和47年時点での話ではあるが、丸谷さんは、
>そういう、本と雑誌の関係が、日本ではいままで逆転していましたね。雑誌が一番立派なもので、本はその次に来る何かもっと低いものという具合だった。(略)
>本と雑誌が両方あって、雑誌が本に勢いをつける、刺戟を与えるようになるのが非常に望ましいと、ぼくは考えているんですよ。(p.12)
なんて言っていて、雑誌第一とする出版事情がおかしかったといい、文芸雑誌はもっと批評を載せるようになるべきと言っている。
おもしろいのは、その対談相手の吉田健一の意見で、
>そうよ。話はちょっと高級になるけど、ご馳走ってものがあるでしょう。本式に食べるとなると大変なもので、西洋なら、前菜に始まり、コーヒー、コニャックまでいく。それじゃ大変だから、前菜とスープだけの店はないものかと思うんだよ。これは実に気の利いた店でしょう。雑誌って本来そういうものじゃないかしら。(p.13)
っていうんだが、さすが食通だ、そういう例えでくるか。
吉田健一のことについては別の対談でとりあげてるけど、年をとってからは食べなくなったそうで、金沢に行ったときの話として、
>吉田さんはあれだけ召し上らないくせに、目の前には料理がたくさん並んでないといけないんですね。
>(略)招待側が金沢中の料理屋に、東京から美食家の偉い先生がお見えになるからと言って、お二人を案内した。ところが、飲んでばかりいて、ちっとも食べない。(略)困ってしまって、どうぞ箸をおつけ下さいとお願いすると、二人で叱るんだそうです。しかし何しろ料理屋の女将に言った手前もあるから、無理にまた催促したら、吉田さんが「料理の味は目で見ればわかります」(笑)。ぼくは中島敦の『名人伝』を思い出しましたね。弓の名人が修業を積んで、とうとう飛んでいる鳥を目で見るだけで落としてしまったという、あの境地に達している(笑)。(p.132-133)
なんてエピソードがあって、妙におかしいったらない。
酒といえば、最後の最後にあとがきのとこで本書のタイトルに触れ、
>『文学ときどき酒』といふ題なのに、どこでどういふ具合に酒を飲んでゐるかを示してゐないのは心残りだが、(笑)と書くのと同じ呼吸で(酒)と途中に入れるのはやはりをかしいだらう。第一、吉田健一さんの場合なんか、とてもその煩に堪へないのである。
って、また吉田健一さんを担ぎ出しているんだが、それにしても対談を活字にしたとき「(酒)」は、あってもいいような気がしてくる。
読んだなかでは、毎度おなじみのとおり源氏物語とか王朝和歌について語られてるものもいいんだけど、丸谷さんが自身の小説について言ってる一節がとても気になった。
『たった一人の反乱』が、意外なことが絶えず起きておもしろいとホメられたところで、
>ああいう小説は、自分では非常に論じにくい小説で、というのは、実用性が非常にないのですね、あの小説は。日本の文壇で最も受け入れられない小説ですね。あの小説読んだからどうだということはべつに何にもないわけですから。そういう実用性の乏しさというものが退けられてきたのが日本文学の明治以後の伝統ですね。明治以前の日本文学というものは、もちろん実用性というものを非常に排除して、(略)夏炉冬扇のごとしというのが文学の理想だったわけでしょう。ところが明治以後の文学は、夏の冷房装置、冬のセントラル・ヒーティングのごときものになってきてるでしょう。私はそういう実用性をなるべく排除した形の小説を書きたい。(p.24-25)
なんて言ってる、これまた昭和47年での話だが、そういう意見表明はちょっとめずらしいんぢゃないかと思った。
コンテンツは以下のとおり。
読むこと書くこと 吉田健一
小説のなかのユーモア 河盛好蔵
本と現実 石川淳
倚松庵日常 谷崎松子
いろんなことをするから人生 里見弴
吉田健一の生き方 河上徹太郎
『源氏物語』を読む 円地文子
花・ほととぎす・月・紅葉・雪 大岡信
エズラ・バウンドの復権 篠田一士、ドナルド・キーン
ジョイス・言葉・現代文学 清水徹、高橋康也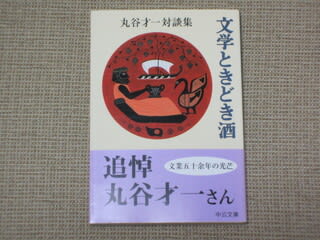
柚月裕子 2017年 中央公論新社
丸谷才一さんの書評の影響などから、ひと月に一冊ぐらいはミステリーも読もうとはしているのだが。
イギリスの古典とかばかりぢゃなくて、めずらしく日本の最近のものを読んでみることにしたのが、これ。
去年9月くらいだったかな、文庫版が出たって何かでみて、ぢゃあ買ってみるかと思ったのはいいが。
笑っちゃうことに、よせばいいのにネットこそこそ検索すると、文庫二分冊より単行本の古本のほうが安いじゃん、とかヘンなことに気づいて買ってしまった。
だからー、もう置くとこないんだから大きい本は買うのやめようって自分で決めたばっかじゃーん、と。
私の買い物動向はいいとして、ミステリーとりあげるときは、謎とされてる部分を抜き書きして、それに対する感想なんかを書いてしまっては味消しだから、書きかたむずかしいんだが。
帯にでっかく「実業界の寵児で天才棋士。本当にお前が殺人犯なのか?」なんて書いてしまってあるんで、そういう話だと言ってしまうのはかまわないらしい。
序章で二人の刑事が山形県天童でやってるタイトル戦の会場に乗り込んでくるんだけど、それは容疑者の目星がついてて来てるってことなんで、なんでそうなってんのかってのを以下さかのぼってからの物語を読むことになる。
事件は埼玉県の山中でみつかった白骨死体、殺されてから埋められたのではないかということ。
現場には、遺留品というか、名工の作による駒一式が、死体の胸のあたりに置かれて一緒に埋められていた。
犯人だれなのかっていうより、死体の身元は誰なのか、なんで数百万の価格がつく駒が埋められてたのか、そっちのほうが解かれるべき謎で、それがだんだん明かされていく。
事件発生は平成6年の話で主役は二人の刑事、もうひとつのそこに至るストーリーは昭和46年に小学三年生だった少年のとこから始まって、少年の成長を追っかけてくと平成6年現在に追いつくんだが。
将棋の知識は、ストーリーの場面場面読んでくなかでも、謎を解くうえでも、まったく必要ない。
知ってると人物のモデルが、ああ、これは羽生さんねとか、これは小池重明なんでしょとか思い当たるだけ。
(小池重明氏については『真剣師小池重明』のほうがおもしろい。)
わかんないのは、タイトルにある、なにがヒマワリなんだってことだったんだけど、最後のほうになって、なるほどそういうことって感じで出てくる。
そういう使い方するかあ、って気もして、なんか特に感心するものでもなかった。
っつーか、ヒマワリ関係のシークエンスは浮いてるようで、なんかピースがピタッとはまった感がしなかったんだよね。
















