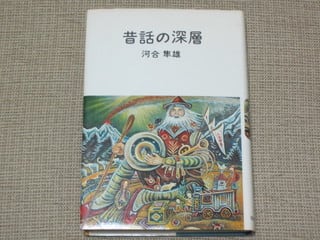ビートたけし 2017年 新潮新書
前回の志らくの文庫と近くにあって目についたんで買ってみた、とかく一冊だけでは買い物が済まないのは昔から変わらない。
最近、どうも新書って形式のものは、なんかうすっぺらいような気がして敬遠してたんだけどね、私。
しかし、売れてるみたいだねえ、昨年10月20日の発行で、12月20日付で7刷を重ねている。
たけしの本なんて、読むのひさしぶりだな、昔のアレ何ていったっけと思ったら、「はじめに」のところに書いてあった、『ツービートのわッ毒ガスだ』、それだそれ確か、自分で買ったんぢゃないけど、誰かの見せてもらったやつ。
で、これは漫才やコントのネタぢゃなくて、冒頭から「昔からバカにはうるさい」と宣言してる著者の、バカにバカと言いまくってる本。
特にマスコミなんかにも厳しくて、言い訳のテロップ出しながら放送してんのにバカと言ったりしてんだけど、一方でその原因となる変なクレームつけてくる視聴者もバカだと言うのも忘れない。
若い芸人とかについても、芸を見せてるんぢゃなくておかしな格好してるだけの奴は、笑わせてるんぢゃなくて笑われてんだよと、バカと通告する。
政治関連では時短とか働き方改革とかいっても、芸能界の長時間で過酷な現場のことは無視してる点について、「いまだに江戸時代と変わらない」という指摘詩的(2022年4月16日誤字修正)は鋭いと思う。ま、政策唱えてる側は、そこまで深く意識してないで、票になる層狙ってるだけだろうけど。
インタビューのバカな質問はたくさんあげられてるけど、なかでいちばん同意するのが、次のようなやつ。
>―「今度の映画をひとことで言うと、どんな映画ですか?」
>どんな映画か、ひとことで言えるようだったら、そもそも映画なんて撮るわけないだろう。「これを見ている視聴者にどんな映画か説明してください」とか言うけど、映画を観ろ、映画を。(p.159)
まったく「ひとことで」ってのは、おちいりやすい病のようなものって気がする。考えんのがヤなんだろうね、きっと。それと自分で見たり考えたりしないで、伝聞の評価で終わらせたがるひと多過ぎのような気もする。
でも、あまり賛成できないのもあって、たとえばテレビのお笑い番組を批判されたりしたときは、「じゃあ、お前がやってみろ」と言うそうなんだが、私はそれ言わないのがプロってもんぢゃないかと思うもんで。
コンテンツは以下のとおり。
はじめに―バカは死んでも治らない
第一章 バカなことを聞くんじゃない
第二章 バカ言ってんじゃない
第三章 渡る世間はバカばかり
第四章 バカがテレビを語っている
第五章 こんなバカが好きなんだ
第六章 たまにはバカな質問に答えようか
おわりに―バカな言い訳
立川志らく 2018年1月 PHP文庫版
最近書店で見かけて買って読んだ、新しい文庫。
うしろのほう見たら、2010年12月の『立川流鎖国論』を改題、加筆・修正したものだっていう。
そういわれると、なんとなく察し、というか邪推かもしんないけど、がつく。
いまや志らくはテレビ番組のコメンテーターとして名を馳せてるからねえ(実は私は見たことないんだが)、そういうタイトルのほうが売れそうだ。
立川流鎖国論ぢゃあ、立川流マニアしか読まないもん、きっとw
ってことで、本書はタイトルから世間が想像するかもしれない、志らくが世相を斬るとかそういうんぢゃなくて、立川流とは何かという、イズムのようなものの披露。
もっとも、本文中には、
>(略)最近の芸能人のなにがいやかというと、テレがない輩のなんと多いことか。
>まあ芸能人と呼ばれている大半は電波芸者であり、世間様にさからわず、ただ煽るだけ。(略)
>ワイドショーのコメンテーターの「長いものにはまかれろ」的態度は、人間らしいと言えばたしかにそうだが、品がないことおびただしい。(p.164)
なんて阿諛追従のやからへの毒が含まれてたりするんで、油断ならない。
全編おもしろくて一気に読んでしまったようなとこあるんだが、なかでも談春に関して語ってるとこがいちばんおかしい、つい笑ってしまう。
談春と志らくといえば、談春が前座時代に家元の命で魚河岸に修行に行ってたときに、志らくはイヤですと言って魚河岸にはとうとう行かなかった、談春をして立川流の闇とまで言わせた因縁があるんだが。
志らくは兄弟子に気ぃつかってんのか、ポスト志ん朝の座におさまったのは談春なんて、持ち上げるようなことも以前の著書には書いてたりするんだけど。
本書でも、随所に兄弟子を敬愛してるようなんだけど、そのわりには言うことやることムチャだなってことが多くあって、それがおかしい。
たとえば、あるとき二人で高校に落語やりいった、二人で一時間の持ち時間の予定。
ところが、客席の高校生はだれきってて態度がなっちゃいない、先にあがった志らくは頭きて5分でやめちゃう。
で、談春は、いきなり出番ふられて、まるまる時間も残されてるから、あわてて、怒って、高座に上がる。そこで、
>で、きちんと古典落語を五十五分演じておりました。さすがは平成の名人だ。(p.170)
というのが爆笑もの、ひどいパスだしといて、名人だで済ますことはないでしょ。
まあ、兄弟弟子の絆はどんなもんだかともかく、本書には師弟関係について多くが語られている。
談志家元の弟子たちの話はこれまでも聞いたり読んだりしたことあるんだけど、志らくも自分の弟子に苦労してることを書いている。
師匠が思うように弟子はなんないんだけど、そこはビシッとやるところはやる。
>立川流における師弟の定義は「情」ではなく「価値観」。(p.250)
って言葉に、多くは言い表されているなあ。
コンテンツは以下のとおり。
序章 「立川流」とはなんなのか
第一章 継承される「談志イズム」
第二章 談志への愛、演劇への愛
第三章 立川談春伝説
第四章 個性なのか、ぶざまなのか
第五章 立川志らく伝説
第六章 談志の価値観、一門の了見
第七章 立川談志伝説の真相
終章 立川流はどこへ行くのか
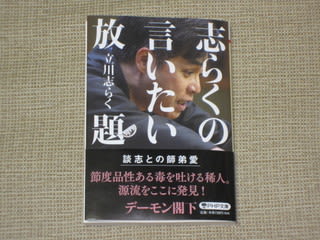
最近書店で見かけて買って読んだ、新しい文庫。
うしろのほう見たら、2010年12月の『立川流鎖国論』を改題、加筆・修正したものだっていう。
そういわれると、なんとなく察し、というか邪推かもしんないけど、がつく。
いまや志らくはテレビ番組のコメンテーターとして名を馳せてるからねえ(実は私は見たことないんだが)、そういうタイトルのほうが売れそうだ。
立川流鎖国論ぢゃあ、立川流マニアしか読まないもん、きっとw
ってことで、本書はタイトルから世間が想像するかもしれない、志らくが世相を斬るとかそういうんぢゃなくて、立川流とは何かという、イズムのようなものの披露。
もっとも、本文中には、
>(略)最近の芸能人のなにがいやかというと、テレがない輩のなんと多いことか。
>まあ芸能人と呼ばれている大半は電波芸者であり、世間様にさからわず、ただ煽るだけ。(略)
>ワイドショーのコメンテーターの「長いものにはまかれろ」的態度は、人間らしいと言えばたしかにそうだが、品がないことおびただしい。(p.164)
なんて阿諛追従のやからへの毒が含まれてたりするんで、油断ならない。
全編おもしろくて一気に読んでしまったようなとこあるんだが、なかでも談春に関して語ってるとこがいちばんおかしい、つい笑ってしまう。
談春と志らくといえば、談春が前座時代に家元の命で魚河岸に修行に行ってたときに、志らくはイヤですと言って魚河岸にはとうとう行かなかった、談春をして立川流の闇とまで言わせた因縁があるんだが。
志らくは兄弟子に気ぃつかってんのか、ポスト志ん朝の座におさまったのは談春なんて、持ち上げるようなことも以前の著書には書いてたりするんだけど。
本書でも、随所に兄弟子を敬愛してるようなんだけど、そのわりには言うことやることムチャだなってことが多くあって、それがおかしい。
たとえば、あるとき二人で高校に落語やりいった、二人で一時間の持ち時間の予定。
ところが、客席の高校生はだれきってて態度がなっちゃいない、先にあがった志らくは頭きて5分でやめちゃう。
で、談春は、いきなり出番ふられて、まるまる時間も残されてるから、あわてて、怒って、高座に上がる。そこで、
>で、きちんと古典落語を五十五分演じておりました。さすがは平成の名人だ。(p.170)
というのが爆笑もの、ひどいパスだしといて、名人だで済ますことはないでしょ。
まあ、兄弟弟子の絆はどんなもんだかともかく、本書には師弟関係について多くが語られている。
談志家元の弟子たちの話はこれまでも聞いたり読んだりしたことあるんだけど、志らくも自分の弟子に苦労してることを書いている。
師匠が思うように弟子はなんないんだけど、そこはビシッとやるところはやる。
>立川流における師弟の定義は「情」ではなく「価値観」。(p.250)
って言葉に、多くは言い表されているなあ。
コンテンツは以下のとおり。
序章 「立川流」とはなんなのか
第一章 継承される「談志イズム」
第二章 談志への愛、演劇への愛
第三章 立川談春伝説
第四章 個性なのか、ぶざまなのか
第五章 立川志らく伝説
第六章 談志の価値観、一門の了見
第七章 立川談志伝説の真相
終章 立川流はどこへ行くのか
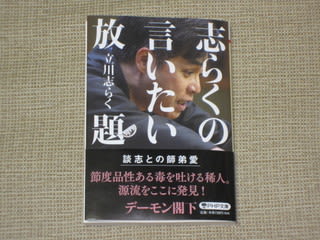
柳澤健 2017年 文藝春秋
去年の秋に、書店でなんだかUWF関係とみられる本がたくさん並んでて。
けっこう興味あって、どれがどんなんだか、ちょっと見にはわかりそうもないし。
しばし検討した結果、読めるだけ読んでみるか、って勢いで、そのちょっと後に何冊かまとめて買ってみた。
暮れ正月の休みにでも読めば退屈するまいと、しばらく積んでおいたんだが、なかなか読まなくて、いまごろになってボツボツとりかかっている。
なるべく出た順に読んでみるかと思って、最初にとりかかったのがこれ。
1984年のUWF創設とその前段、そのあとの佐山が抜けたり新日のリングに戻ったり、また新生UWF起ち上げたけど、バラバラになっていく、そんな時代の詳しい解説。
当時は何が起きてんのかわかんなかったけど、なるほどいろいろあったのね。
結局、UWFはプロレスだったと。
>佐山聡が新格闘技づくりに邁進したこと。藤原がゴッチの関節技を学ぶためにフロリダに行ったこと。前田と高田が藤原との厳しいスパーリングに挑み続けたこと。
>それらすべては「プロレスが真剣勝負ではない」ということへのコンプレックスから始まっている。(p.138)
というところに、UWFのホントのとこが言い表されてるような気がするなあ。
キーマンは佐山で。佐山だけが、ルールがあって、打・投・極のミックスされた格闘技をつくって、選手を育てて試合してこうと考えていて、UWFを最初はプロレスでも将来には格闘技の場にしようというプランを持ってたんだが、それは実現できなかったと。
1981年にむりやりタイガーマスクにさせられて、人気絶頂だったけど、6月に猪木がホーガンにKO負けした1983年の8月に契約解除通告書をつきつけて新日を離れる。
契約を無視してもうけは猪木の関連会社に流用するし、結婚式は海外で新日幹部だけが出席してやれとか言われるしで、ブチ切れた。
詳しいことは知らなかったんだけど、プロレスラーって社員ぢゃなくて、契約している個人事業主だったのね、それでプライベートの一大行事の指図されたら腹立つわな。
かくして新日はスター失って役員退陣してガタガタになるが、そこからややこしいことに、佐山とトラブったはずのフロントの仕掛け人が、佐山をニューヨークのリングで復活させようとプランをすすめる。
ところがテレビ局との契約も巻き込んだゴタゴタに発展して、結局、佐山は参加せず。UWFとしての日本での旗揚げ公演日も決まってたが、エース不在。
そこで表舞台に立てられたのが、猪木も佐山も来るからと言われて参加してた前田。急遽MSGのリングで無名の選手と試合して、勝ってチャンピオンベルトを手にしてしまって、日本に帰ったらメインイベンターになることが決定。
前田の初戦の相手は、なんとジャイアント馬場からテリー・ファンクつながりで、このギャラで来られるならと誰でもいい状態で呼ばれた外国人、ロサンジェルスから成田に午後着いてその夜に試合だって、いいかげんだなあ。
前田の試合は当時の観客にもあんまりウケなかったらしいし、ときにデンジャラスな技炸裂してしまうんで相手のプロレスラーにも不評。でも、
>前田は甘いマスクと立派な体格の持ち主だが、アントニオ猪木のような天性のショーマンシップも、佐山聡のような天才的な運動神経も持ちあわせていなかった。
>しかし、前田日明は心に響く言葉を持っていた。
>率直で温かい心の持ち主は、いま自分が置かれている状況を客観的に見ることのできる知性をも兼ね備えていた。(p.113)
ってのは言えてると思うねえ。
で、興行的に不振で、早くも新日本に帰るかみたいな方向でUWFは無くすプランが持ち上がるんだけど、そういうこと言う選手から信頼のない仕掛け人を退場させて、新たなブレインを加えて、週刊プロレスを味方につけて、存続してく。
その段階で加わったのが、藤原と高田。1984年6月の記者会見で初めての晴れ舞台の主役になった藤原は、ウィスキーをラッパ飲みしてアルコールの力で乗りきったらしい、おいおい。
さらに、そこへ、新格闘技に向けてジムをつくって活動していた佐山が合流。
>佐山にとってのUWFは、新格闘技を実験するための研究室であり、新格闘技を運営するための収入源であり、新格闘技を宣伝するためのメディアであった。(p.153)
っていうんだけど、それはしかたない。
かくして、「真剣勝負に見えるプロレス」で、ものすごく盛り上がる。
しかし、佐山の元マネージャーとのゴタゴタから社長が逮捕とか、スポンサーとしてついてくれたのが豊田商事の子会社だったりとか、よろしくない状況に陥ってメジャーになりきれない。
一方で、UWF起ち上げの苦しいときからがんばってて、道場で皆と汗を流して慕われる前田と、道場には来なくて新格闘技がいちばん大事な佐山のあいだで、溝が生まれ始めたらしい。
結局、シューティング・ルールという画期的なものつくった直後に、佐山は退団、プロレス界から去る。
そのあと、UWFは経営危機になり、前田たちは新日本プロレスのリングに復帰。
>結局のところ、彼らは、プロレスラー以外の何者でもなかった。
>UWFの思想は、佐山聡ひとりの中だけに存在したのだ。(p.242)
ってことになるらしいけど、厳しいね。
そのあとにも、新日で暴れすぎて解雇されちゃった前田を中心にして、新生UWFが起ちあがるんだが、その試合のスタイルは、佐山が作ってったシューティング・ルールと、レガースとシューズを着用って、前回自分たちが否定したはずのものになったことについて、
>「新生UWFのレスラーたちに思想などなかった」
>と語るのはターザン山本である。
>「前田たちは典型的なプロレスラー。金と女とクルマにしか興味のない人間。UWFとは何か、UWFがどうあるべきか、UWFはどうあらねばならないか。そんなことを真剣に考えている人間は、新生UWFにはひとりもいなかった。(略)
>ファンはUWFの幻想を心から信じている。UWFのレスラーは誰も何も信じていないのに。ギャグですよ」(ターザン山本)(p.283)
と手厳しい内容を、元は味方にたってくれてたひとの言葉として語らせているんだが。
ま、思想はなかったかもしれないけど、そのあとの総合格闘技のムーブメントのなかに、いろんな人材を生み出していったプロレスってのは、悪いもんぢゃなかったんぢゃないかと。
章立ては以下のとおり。最初と最後に、中井祐樹さんがとりあげられてるのが、なんともいい。
序章 北海道の少年
第1章 リアルワン
第2章 佐山聡
第3章 タイガーマスク
第4章 ユニバーサル
第5章 無限大記念日
第6章 シューティング
第7章 訣別
第8章 新・格闘王
第9章 新生UWF
第10章 分裂
終章 バーリ・トゥード
あとがきにかえて~VTJ95以後の中井祐樹
[特別付録]1981年のタイガーマスク
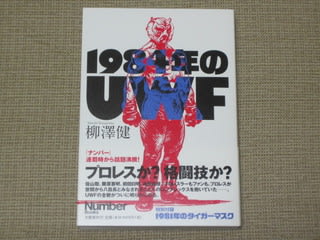
去年の秋に、書店でなんだかUWF関係とみられる本がたくさん並んでて。
けっこう興味あって、どれがどんなんだか、ちょっと見にはわかりそうもないし。
しばし検討した結果、読めるだけ読んでみるか、って勢いで、そのちょっと後に何冊かまとめて買ってみた。
暮れ正月の休みにでも読めば退屈するまいと、しばらく積んでおいたんだが、なかなか読まなくて、いまごろになってボツボツとりかかっている。
なるべく出た順に読んでみるかと思って、最初にとりかかったのがこれ。
1984年のUWF創設とその前段、そのあとの佐山が抜けたり新日のリングに戻ったり、また新生UWF起ち上げたけど、バラバラになっていく、そんな時代の詳しい解説。
当時は何が起きてんのかわかんなかったけど、なるほどいろいろあったのね。
結局、UWFはプロレスだったと。
>佐山聡が新格闘技づくりに邁進したこと。藤原がゴッチの関節技を学ぶためにフロリダに行ったこと。前田と高田が藤原との厳しいスパーリングに挑み続けたこと。
>それらすべては「プロレスが真剣勝負ではない」ということへのコンプレックスから始まっている。(p.138)
というところに、UWFのホントのとこが言い表されてるような気がするなあ。
キーマンは佐山で。佐山だけが、ルールがあって、打・投・極のミックスされた格闘技をつくって、選手を育てて試合してこうと考えていて、UWFを最初はプロレスでも将来には格闘技の場にしようというプランを持ってたんだが、それは実現できなかったと。
1981年にむりやりタイガーマスクにさせられて、人気絶頂だったけど、6月に猪木がホーガンにKO負けした1983年の8月に契約解除通告書をつきつけて新日を離れる。
契約を無視してもうけは猪木の関連会社に流用するし、結婚式は海外で新日幹部だけが出席してやれとか言われるしで、ブチ切れた。
詳しいことは知らなかったんだけど、プロレスラーって社員ぢゃなくて、契約している個人事業主だったのね、それでプライベートの一大行事の指図されたら腹立つわな。
かくして新日はスター失って役員退陣してガタガタになるが、そこからややこしいことに、佐山とトラブったはずのフロントの仕掛け人が、佐山をニューヨークのリングで復活させようとプランをすすめる。
ところがテレビ局との契約も巻き込んだゴタゴタに発展して、結局、佐山は参加せず。UWFとしての日本での旗揚げ公演日も決まってたが、エース不在。
そこで表舞台に立てられたのが、猪木も佐山も来るからと言われて参加してた前田。急遽MSGのリングで無名の選手と試合して、勝ってチャンピオンベルトを手にしてしまって、日本に帰ったらメインイベンターになることが決定。
前田の初戦の相手は、なんとジャイアント馬場からテリー・ファンクつながりで、このギャラで来られるならと誰でもいい状態で呼ばれた外国人、ロサンジェルスから成田に午後着いてその夜に試合だって、いいかげんだなあ。
前田の試合は当時の観客にもあんまりウケなかったらしいし、ときにデンジャラスな技炸裂してしまうんで相手のプロレスラーにも不評。でも、
>前田は甘いマスクと立派な体格の持ち主だが、アントニオ猪木のような天性のショーマンシップも、佐山聡のような天才的な運動神経も持ちあわせていなかった。
>しかし、前田日明は心に響く言葉を持っていた。
>率直で温かい心の持ち主は、いま自分が置かれている状況を客観的に見ることのできる知性をも兼ね備えていた。(p.113)
ってのは言えてると思うねえ。
で、興行的に不振で、早くも新日本に帰るかみたいな方向でUWFは無くすプランが持ち上がるんだけど、そういうこと言う選手から信頼のない仕掛け人を退場させて、新たなブレインを加えて、週刊プロレスを味方につけて、存続してく。
その段階で加わったのが、藤原と高田。1984年6月の記者会見で初めての晴れ舞台の主役になった藤原は、ウィスキーをラッパ飲みしてアルコールの力で乗りきったらしい、おいおい。
さらに、そこへ、新格闘技に向けてジムをつくって活動していた佐山が合流。
>佐山にとってのUWFは、新格闘技を実験するための研究室であり、新格闘技を運営するための収入源であり、新格闘技を宣伝するためのメディアであった。(p.153)
っていうんだけど、それはしかたない。
かくして、「真剣勝負に見えるプロレス」で、ものすごく盛り上がる。
しかし、佐山の元マネージャーとのゴタゴタから社長が逮捕とか、スポンサーとしてついてくれたのが豊田商事の子会社だったりとか、よろしくない状況に陥ってメジャーになりきれない。
一方で、UWF起ち上げの苦しいときからがんばってて、道場で皆と汗を流して慕われる前田と、道場には来なくて新格闘技がいちばん大事な佐山のあいだで、溝が生まれ始めたらしい。
結局、シューティング・ルールという画期的なものつくった直後に、佐山は退団、プロレス界から去る。
そのあと、UWFは経営危機になり、前田たちは新日本プロレスのリングに復帰。
>結局のところ、彼らは、プロレスラー以外の何者でもなかった。
>UWFの思想は、佐山聡ひとりの中だけに存在したのだ。(p.242)
ってことになるらしいけど、厳しいね。
そのあとにも、新日で暴れすぎて解雇されちゃった前田を中心にして、新生UWFが起ちあがるんだが、その試合のスタイルは、佐山が作ってったシューティング・ルールと、レガースとシューズを着用って、前回自分たちが否定したはずのものになったことについて、
>「新生UWFのレスラーたちに思想などなかった」
>と語るのはターザン山本である。
>「前田たちは典型的なプロレスラー。金と女とクルマにしか興味のない人間。UWFとは何か、UWFがどうあるべきか、UWFはどうあらねばならないか。そんなことを真剣に考えている人間は、新生UWFにはひとりもいなかった。(略)
>ファンはUWFの幻想を心から信じている。UWFのレスラーは誰も何も信じていないのに。ギャグですよ」(ターザン山本)(p.283)
と手厳しい内容を、元は味方にたってくれてたひとの言葉として語らせているんだが。
ま、思想はなかったかもしれないけど、そのあとの総合格闘技のムーブメントのなかに、いろんな人材を生み出していったプロレスってのは、悪いもんぢゃなかったんぢゃないかと。
章立ては以下のとおり。最初と最後に、中井祐樹さんがとりあげられてるのが、なんともいい。
序章 北海道の少年
第1章 リアルワン
第2章 佐山聡
第3章 タイガーマスク
第4章 ユニバーサル
第5章 無限大記念日
第6章 シューティング
第7章 訣別
第8章 新・格闘王
第9章 新生UWF
第10章 分裂
終章 バーリ・トゥード
あとがきにかえて~VTJ95以後の中井祐樹
[特別付録]1981年のタイガーマスク
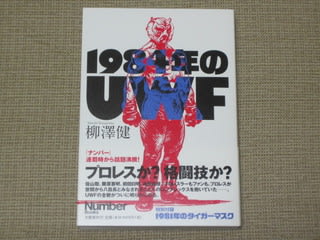
筒井康隆 昭和58年 新潮社
筒井康隆の初期作品「東海道戦争」というのはおもしろいらしいと聞いて、読んでみたくて古本を買った。
そしたら、短編小説だったというのは、目次あけるまで知らなかった。
なんせ、この本、短編が49篇入ってるんで、その最後に配置されてる肝心のお目当てにたどりつくまで時間かかってしまった。
でも、期待してたのにたがわず、短編のなかでは秀逸だとは思えた。
物語は、ある日突然、東京と大阪の戦争が始まって、市民もみんな参加して戦闘が繰り広げられるんだが。
なんでそんな戦争が始まったのかは謎だが、けっこうみんなエキサイトしてて、はっきりいって楽しそう。
そのへんを登場人物のセリフを借りて、
>戦争を起したのも、それを楽しむのも大衆だ。マス・メディアは、戦争を大衆に楽しませるためにあるんだ。もっとも、この戦争が、報道あるいは再現メディアにつごうのいいように仕組まれ、準備され、そして発生したことも確かだがね
とか、
>この戦争はあきらかに、贋造の出来事だ。マスコミの世界では、贋造の出来事が本物の出来事を追いやってしまう。グレシャムの法則だ。だからこの戦争は、取材されるための戦争だ。製造されたニュースだ
なんて言うところが、けっこうおもしろい。
それにしても、あらためてまとめて読んでみると、筒井康隆の小説は、心理学の素養がないとむずかしいのかなって気がした、前意識とかって何のことだか私にはわからないし。
この本には、ほかに長編ひとつとエッセイ3篇が収録されてるけど、エッセイの「精神病院ルポ」ってのが、なかではいちばんおもしろかったりする。
ところで、なんで、そろえる気もないくせに全集になってるものを買ったかっていうと、アルコール入った状態で古本まつりへ行くもんぢゃねえな、ってことで、ただの勢いである。
(なんか重いのいくつも買って、ウチに着くころくたびれた記憶はある。)
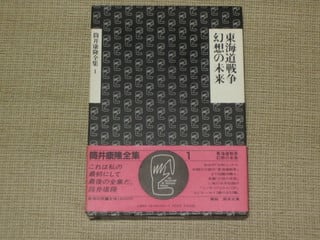
筒井康隆の初期作品「東海道戦争」というのはおもしろいらしいと聞いて、読んでみたくて古本を買った。
そしたら、短編小説だったというのは、目次あけるまで知らなかった。
なんせ、この本、短編が49篇入ってるんで、その最後に配置されてる肝心のお目当てにたどりつくまで時間かかってしまった。
でも、期待してたのにたがわず、短編のなかでは秀逸だとは思えた。
物語は、ある日突然、東京と大阪の戦争が始まって、市民もみんな参加して戦闘が繰り広げられるんだが。
なんでそんな戦争が始まったのかは謎だが、けっこうみんなエキサイトしてて、はっきりいって楽しそう。
そのへんを登場人物のセリフを借りて、
>戦争を起したのも、それを楽しむのも大衆だ。マス・メディアは、戦争を大衆に楽しませるためにあるんだ。もっとも、この戦争が、報道あるいは再現メディアにつごうのいいように仕組まれ、準備され、そして発生したことも確かだがね
とか、
>この戦争はあきらかに、贋造の出来事だ。マスコミの世界では、贋造の出来事が本物の出来事を追いやってしまう。グレシャムの法則だ。だからこの戦争は、取材されるための戦争だ。製造されたニュースだ
なんて言うところが、けっこうおもしろい。
それにしても、あらためてまとめて読んでみると、筒井康隆の小説は、心理学の素養がないとむずかしいのかなって気がした、前意識とかって何のことだか私にはわからないし。
この本には、ほかに長編ひとつとエッセイ3篇が収録されてるけど、エッセイの「精神病院ルポ」ってのが、なかではいちばんおもしろかったりする。
ところで、なんで、そろえる気もないくせに全集になってるものを買ったかっていうと、アルコール入った状態で古本まつりへ行くもんぢゃねえな、ってことで、ただの勢いである。
(なんか重いのいくつも買って、ウチに着くころくたびれた記憶はある。)
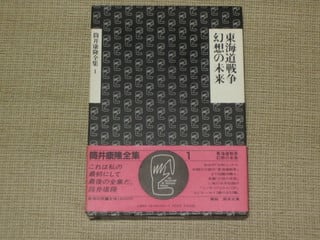
河合隼雄 1977年 福音館書店
去年9月に買った古本、著者名から心理学関係だろうなとは思ったけど、昔話ってのがそこんとこどうなってるのか気になったもんで。
(諸星大二郎ファンなものだから、伝説とか民俗文化とかってのはけっこう興味ある。)
ユングの心理学なんてまったく知らないんだけど、たとえば鬼退治とか物語の詳細はなんでもいいが、洋の東西を問わず、成人をしのぐ活躍をする昔話があれこれあることは、「人類はこのような超人的な子どもの話を好む」「全人類に共通に、このような超能力をそなえた子どもという表象を産出する可能性が無意識内に存在する」(p.16)って解説されちゃうと、そうか集合的無意識ってそういうこと、と初めてわかった気がした。
あるところに二人の兄弟がおりました、で始まり、二人の性格や行動の対比で進められる昔話は世界中にあって、古い例では紀元前1300年頃のエジプトに既にあったというんだが、それって「このようなテーマがいかに人間の心の在り方と深く結びついているかを示すものである(p.93)」と言われちゃうと、そうか人の心理のなかには普遍性のあるものあるんだと納得せざるをえない。
主にグリムに題材をとっているんだが、なんとなく通り過ぎていた昔話に秘められている意味を明るみにされちゃうと、そこまで深読みできるものだったんだと驚く。
たとえば、昔々あるところに王様と三人の息子がいて、王様は死にあたって息子のなかで最もものぐさな者に王位を継承させようとしました、なんて話について、まず王妃が登場しない男性ばかりの世界であることに注目。
>自分に対してふりかかってくる運命に対して積極的に戦ってゆくこと、これは男性の原理である。これに対して、運命を受け容れること、これは女性原理である。(略)おそらく理想としては、この両立し難い原理が一人の人格のなかに統合的に存在することであろう。
>ところで、この話のなかで王さまが死に瀕しているが、これはなにを意味するのだろうか。これは男性の原理のみによって成立していたこの王国の規範性が、今やひとつの危険に臨んでいること示している。(略)(p.82-83「怠けと創造」)
という具合で、意識と無意識とのバランスの乱れみたいなことを指摘するんだが、そこでなんで怠けが評価されるかっていうと、
>常識の世界に忙しく働いている人は、天の声を聞くことができない。怠け者の耳は天啓に対して開かれている。このように言うと、私の心には現代の多くの「仕事に向かって逃避」している人たちのことが思い浮かんでくる。これらの人は仕事を熱心にし、忙しくするという口実のものに、自分の内面の声を聞くことを拒否しているのである。(p.85)
ってことで、意識的な努力の評価に対するアンチテーゼとしての無為の重要性だってことで、現代人の心理療法にまで結び付けられちゃう。
(どうでもいいけど、運命に対する男性原理と女性原理の立ち位置のちがいは、ホリイ氏の『恋するディズニー 別れるディズニー」で学んだのと同じことだ。)
ほかにも、白雪姫の母親とか、いばら姫の悪い魔法使いとかってのは「母性の否定的な面を表わすことは明らか」ということで。
母親に否定的なコンプレックスをもつと、娘は自らの女性性を否定しようとして、現代の臨床像としてそれは思春期拒食症になるとか、ガラスの棺にはいった乙女の像は離人症の症状を連想させるとかって見解を披露されて、
>このように、女性の思春期の発達と関連づけてみると、いばら姫は案外すべての正常な女性の心理的発達の過程を描いているのかも知れぬと思われる。(p.128-129「思春期」)
だなんて想像もしたこともなかったとこに着地させてくれる。
父性原理と母性原理というのはポイントになる考え方らしくて、
>母なるものの、すべてのものを区別することなく包みこむ機能と、父なるものの善悪などを区別する機能との間に適切なバランスが保たれてこそ、人間の生活が円滑に行われる(p159「父と息子」)
という観点から、王と息子とか、王と姫とか、物語におけるいろんな対立の場面を、これはこういう状態を反映しているみたいに意味解説してくれるんで、なかなかおもしろい。
“昔々あるところに王がいて、庭のりんごの木の実の数は毎日数えさせていましたが、あくる朝になると実がひとつずつ無くなっていることが報告されました”で始まる物語があるんだけど、これって、りんごの数を数えてるのは規範性の尊重を示すものなんだという。
で、りんごが盗まれるのは、規範に対する挑戦で、規範性の体現者としての王は何らかの意味で危機に陥っていて、規範を改善し危機を救うものとして、新たな男性性の動きが必要とされると、例えば王の息子たちがりんごの見張り役として登場してくることになるってのが物語のつくりだそうだ。
>りんごが盗まれるということは、意識から無意識への心的エネルギーの流れが生じたことを意味すると述べた。それが王の知らぬ間に盗まれるとは、自我のあずかり知らぬ間に退行が生じていることを示す。これは一種のノイローゼ的な状態である。(p.168「父と息子」)
という調子で、まさか黄金の鳥がりんごをついばみに来る昔話が、ひとのノイローゼのことを表しているとは想像したこともなかった。
そのへんとても刺激的で、けっこうおもしろく読めた本だった。うーむ、グリム童話いっぺんちゃんと読んでみようかなと思わされている。
章立ては以下のとおり。諸星ファンとしては、いきなり登場したのが「トルーデさん」ってのは気になるところ。
第一章 昔話と心の構造
第二章 グレートマザー(太母) トルーデさん
第三章 母からの自立 ヘンゼルとグレーテル
第四章 怠けと創造 ものぐさ三人息子
第五章 影の自覚 二人兄弟
第六章 思春期 いばら姫
第七章 トリックスターのはたらき 忠臣ヨハネス
第八章 父と息子 黄金の鳥
第九章 男性の心の中の女性 なぞ
第十章 女性の心の中の男性 つぐみの髯の王さま
第十一章 自己実現の過程 三枚の鳥の羽
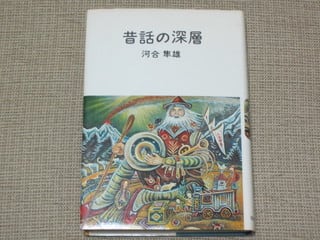
去年9月に買った古本、著者名から心理学関係だろうなとは思ったけど、昔話ってのがそこんとこどうなってるのか気になったもんで。
(諸星大二郎ファンなものだから、伝説とか民俗文化とかってのはけっこう興味ある。)
ユングの心理学なんてまったく知らないんだけど、たとえば鬼退治とか物語の詳細はなんでもいいが、洋の東西を問わず、成人をしのぐ活躍をする昔話があれこれあることは、「人類はこのような超人的な子どもの話を好む」「全人類に共通に、このような超能力をそなえた子どもという表象を産出する可能性が無意識内に存在する」(p.16)って解説されちゃうと、そうか集合的無意識ってそういうこと、と初めてわかった気がした。
あるところに二人の兄弟がおりました、で始まり、二人の性格や行動の対比で進められる昔話は世界中にあって、古い例では紀元前1300年頃のエジプトに既にあったというんだが、それって「このようなテーマがいかに人間の心の在り方と深く結びついているかを示すものである(p.93)」と言われちゃうと、そうか人の心理のなかには普遍性のあるものあるんだと納得せざるをえない。
主にグリムに題材をとっているんだが、なんとなく通り過ぎていた昔話に秘められている意味を明るみにされちゃうと、そこまで深読みできるものだったんだと驚く。
たとえば、昔々あるところに王様と三人の息子がいて、王様は死にあたって息子のなかで最もものぐさな者に王位を継承させようとしました、なんて話について、まず王妃が登場しない男性ばかりの世界であることに注目。
>自分に対してふりかかってくる運命に対して積極的に戦ってゆくこと、これは男性の原理である。これに対して、運命を受け容れること、これは女性原理である。(略)おそらく理想としては、この両立し難い原理が一人の人格のなかに統合的に存在することであろう。
>ところで、この話のなかで王さまが死に瀕しているが、これはなにを意味するのだろうか。これは男性の原理のみによって成立していたこの王国の規範性が、今やひとつの危険に臨んでいること示している。(略)(p.82-83「怠けと創造」)
という具合で、意識と無意識とのバランスの乱れみたいなことを指摘するんだが、そこでなんで怠けが評価されるかっていうと、
>常識の世界に忙しく働いている人は、天の声を聞くことができない。怠け者の耳は天啓に対して開かれている。このように言うと、私の心には現代の多くの「仕事に向かって逃避」している人たちのことが思い浮かんでくる。これらの人は仕事を熱心にし、忙しくするという口実のものに、自分の内面の声を聞くことを拒否しているのである。(p.85)
ってことで、意識的な努力の評価に対するアンチテーゼとしての無為の重要性だってことで、現代人の心理療法にまで結び付けられちゃう。
(どうでもいいけど、運命に対する男性原理と女性原理の立ち位置のちがいは、ホリイ氏の『恋するディズニー 別れるディズニー」で学んだのと同じことだ。)
ほかにも、白雪姫の母親とか、いばら姫の悪い魔法使いとかってのは「母性の否定的な面を表わすことは明らか」ということで。
母親に否定的なコンプレックスをもつと、娘は自らの女性性を否定しようとして、現代の臨床像としてそれは思春期拒食症になるとか、ガラスの棺にはいった乙女の像は離人症の症状を連想させるとかって見解を披露されて、
>このように、女性の思春期の発達と関連づけてみると、いばら姫は案外すべての正常な女性の心理的発達の過程を描いているのかも知れぬと思われる。(p.128-129「思春期」)
だなんて想像もしたこともなかったとこに着地させてくれる。
父性原理と母性原理というのはポイントになる考え方らしくて、
>母なるものの、すべてのものを区別することなく包みこむ機能と、父なるものの善悪などを区別する機能との間に適切なバランスが保たれてこそ、人間の生活が円滑に行われる(p159「父と息子」)
という観点から、王と息子とか、王と姫とか、物語におけるいろんな対立の場面を、これはこういう状態を反映しているみたいに意味解説してくれるんで、なかなかおもしろい。
“昔々あるところに王がいて、庭のりんごの木の実の数は毎日数えさせていましたが、あくる朝になると実がひとつずつ無くなっていることが報告されました”で始まる物語があるんだけど、これって、りんごの数を数えてるのは規範性の尊重を示すものなんだという。
で、りんごが盗まれるのは、規範に対する挑戦で、規範性の体現者としての王は何らかの意味で危機に陥っていて、規範を改善し危機を救うものとして、新たな男性性の動きが必要とされると、例えば王の息子たちがりんごの見張り役として登場してくることになるってのが物語のつくりだそうだ。
>りんごが盗まれるということは、意識から無意識への心的エネルギーの流れが生じたことを意味すると述べた。それが王の知らぬ間に盗まれるとは、自我のあずかり知らぬ間に退行が生じていることを示す。これは一種のノイローゼ的な状態である。(p.168「父と息子」)
という調子で、まさか黄金の鳥がりんごをついばみに来る昔話が、ひとのノイローゼのことを表しているとは想像したこともなかった。
そのへんとても刺激的で、けっこうおもしろく読めた本だった。うーむ、グリム童話いっぺんちゃんと読んでみようかなと思わされている。
章立ては以下のとおり。諸星ファンとしては、いきなり登場したのが「トルーデさん」ってのは気になるところ。
第一章 昔話と心の構造
第二章 グレートマザー(太母) トルーデさん
第三章 母からの自立 ヘンゼルとグレーテル
第四章 怠けと創造 ものぐさ三人息子
第五章 影の自覚 二人兄弟
第六章 思春期 いばら姫
第七章 トリックスターのはたらき 忠臣ヨハネス
第八章 父と息子 黄金の鳥
第九章 男性の心の中の女性 なぞ
第十章 女性の心の中の男性 つぐみの髯の王さま
第十一章 自己実現の過程 三枚の鳥の羽