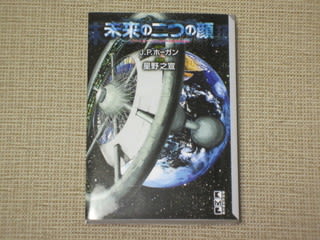高野文子 昭和62年 小学館プチフラワーコミックスセレクト版
ことし9月の古本まつりで見つけて、思わず買ってしまったマンガ。
特別好きというわけでもないんだけどね、著者の描くマンガ、興味はある。
タイトルのラッキーというのは、ヒロインの名前、ミス ラッキー=ランタンタン。
お屋敷でメイドをしてたんだけど、デパートにおつかいに行って、ダリヤ=ポポーンズお嬢様の名をかたって、オムライスを食べたのがバレて、クビになる。
でも、昼間デパートで支配人にスカウトされてたから、めでたくリッチデパートの店員という新しい仕事につくことにする。
寝る場所もないので、閉まったデパートに潜り込んで一夜を明かそうとするんだが、そこへ三人組の強盗が入ってきて、なぜかそこに居合わせたドレス売場担当の男性店員タンチー=オルタンスとともにトラブルに巻き込まれる。
かくして、翌日からのラッキーの仕事は、ただの売り子ぢゃなくて、お客のふりして極秘文書を受け取りにくる使者への対応という特殊任務になる。
最初言われたときは、デパートの新築設計図みたいな話だったのに、やがて事態が進んでいくと、国家間の陰謀だと明かされる。
かくして、ヘンなスタイルの帽子をめぐって、15周年記念イベントでごったがえすデパート店内で活劇が繰り広げられるわけだが。
ほかの作品読んだときも思ったけど、不思議な構図、不思議な動きの描写で、慣れない私なんかはときどきクラクラする、そこが魅力ではあるんだけど。

ことし9月の古本まつりで見つけて、思わず買ってしまったマンガ。
特別好きというわけでもないんだけどね、著者の描くマンガ、興味はある。
タイトルのラッキーというのは、ヒロインの名前、ミス ラッキー=ランタンタン。
お屋敷でメイドをしてたんだけど、デパートにおつかいに行って、ダリヤ=ポポーンズお嬢様の名をかたって、オムライスを食べたのがバレて、クビになる。
でも、昼間デパートで支配人にスカウトされてたから、めでたくリッチデパートの店員という新しい仕事につくことにする。
寝る場所もないので、閉まったデパートに潜り込んで一夜を明かそうとするんだが、そこへ三人組の強盗が入ってきて、なぜかそこに居合わせたドレス売場担当の男性店員タンチー=オルタンスとともにトラブルに巻き込まれる。
かくして、翌日からのラッキーの仕事は、ただの売り子ぢゃなくて、お客のふりして極秘文書を受け取りにくる使者への対応という特殊任務になる。
最初言われたときは、デパートの新築設計図みたいな話だったのに、やがて事態が進んでいくと、国家間の陰謀だと明かされる。
かくして、ヘンなスタイルの帽子をめぐって、15周年記念イベントでごったがえすデパート店内で活劇が繰り広げられるわけだが。
ほかの作品読んだときも思ったけど、不思議な構図、不思議な動きの描写で、慣れない私なんかはときどきクラクラする、そこが魅力ではあるんだけど。