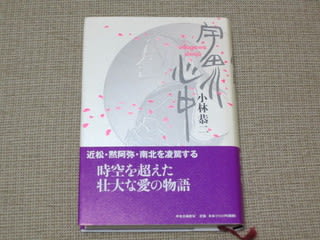ゼウスガーデン衰亡史決定版 1999年 ハルキ文庫
んー、東京オリンピックやってんのをテレビでみてたら、なんか「ゼウスガーデンの秋」を読みたくなったので読んだ。
「ゼウスガーデンの秋」はハルキ文庫版に収録されている、「ゼウスガーデン衰亡史」の番外編で、「I」と「II」があるんだが、今回読みたかったのは「野生時代」1989年1月号初出の「I」のほう。
物語の舞台のときは、はっきりしないが、2047年から2050年くらいのどこか。
主要登場人物は、ゼウスガーデンの快楽学府に学ぶ学生たち、ドミトリーのルームメイトである、僕こと藤島と、快楽学府の二大秀才のひとりと呼ばれる高尾と、これまた才能あってとびきりの美貌のゼルダと、一風変わった少女である花散る午後。
ある朝、高尾が言い出す。
>「オレ思うんだけどさ、裏オリンピックってのがあれば面白いんじゃないか」(略)
>「ああ、薬も使い放題、審判も抱き込み放題、観客乱入も大歓迎なら、競技妨害や裏取引も大あり、つまり今までオリンピックが弾圧してきたものをすべて前面にだすんだ。これはウケるぜ」(略)
>「ウケるさ。百メートルなんて脅威的な記録が続出するぜ、八秒台も夢じゃないさ。そうなったら清く正しくのオリンピックなんて一遍に色あせるさ」(略)
>「それがどうだってんだよ。オリンピックに出るくらいの選手はみんな寿命縮めてスポーツやってんだぜ。カネと名誉と快楽のためなら、健康のひとつやふたつ誰だって売りとばすさ」(P.407-408)
という思いつきなんだが、バカ言ってんぢゃないよとルームメイトも相手にしない。
しかし、高尾はゼウスガーデンの幹部に直談判の売り込みして、全面的支援をとりつける。
「人類がいかに自分の肉体をおもちゃにしてきたかという歴史」や「自分の肉体をいじくることへのタブー意識」を調べた結果、高尾はサイバーオリンピックは実現可能という結論に至る。
>「でもそれで薬も手術もやってない選手が勝っちゃったら、普通の競技会と変わらなくなるぜ。そうしたらサイバーオリンピック面目まるつぶれ」
>「だから優勝賞金を天文学的な額にする」
>「そんなことしたら、ますます世界中のノーマルな一流選手を呼び寄せることになるわよ」
>「それでいいのさ。アブノーマルな連中がノーマルな一流選手を破ってこそサイバーオリンピックの価値がある」(P.429)
という確信のもと、高尾はルームメイトの協力もえて、大会実施に向けて働きだす。
全競技だと大変なので、まずは陸上と水泳あたりにしぼってプレ・サイバーオリンピックをやろうとすると、スポーツ界の関係者は、ほとんどこの企画に賛成し、
>何にもまして劇的だったのが、選手たちの反応である。彼らは、長年の間、スポーツのことなどこれっぽっちも分かっていないオリンピック委員会から発せられた「スポーツマンはかくあるべき」という妄想じみた布告に苦しめられていたから、僕たちの提案をほとんど救世主として受け入れてくれた。彼らは争ってプレ・サイバーオリンピックへの参加を申し込んだ。(P.436)
ということになり、殺人的な忙しさのなか大会準備はすすむ。
マスコミはだいたい批判的ではいるものの、世論の動向を様子見する状態でいるが(このころSNSとか存在しなかったんだねえ)、次第に世界中の目がプレ・サイバーオリンピックの成否に向けられていく。
世界をとびまわって、いろんな選手と接触してる高尾は、脳をいじくった者を多く目にしていて、「人間てどこからどこまでが人間なんだろうね?」なんて疑問を抱くようになるが。
そして、いよいよ開幕、オープニングパレードは競技場ではなくゼウスガーデンのメインストリートで行われた。
選手団が入場する。
>この瞬間、おそらくゼウスガーデンはじまって以来の拍手と喝采がわきおこった。
>ついに肉体の封印がとかれる時がきたのだ。
>これまで人類は、足の代用品は作っても足そのものをいじることはなかった。脳の代用品を作っても脳そのものをいじることはなかった。それは肉体の禁忌にふれるとされてきたのだ。
>無論、肉体の禁忌に挑戦するものもいないではなかった。彼らは自らの肉体に筋肉増強剤やら男性ホルモンやら興奮剤やらを多量に投与することで肉体の限界を超えようとした。
>しかし、それら英雄的な試みは、ことごとく旧態依然とした肉体信仰の前に異端の烙印をおされて葬り去られていった。
>それが今、陽光のもとにさらされようとしているのだ。(P.443)
という期待に反して、観客が目にすることになったのは世にも醜悪な光景だった。
っていう話だが、血気盛んな若者の行動だけぢゃなくて、この一件の評価にゼウスガーデン稀代のアトラクション・アーティスト真原合歓矢(まはらねむや)がからんでくるところがいい。
小林恭二 2008年 集英社新書
『悪への招待状』『心中への招待状』に次ぐ、小林恭二の新書。
四谷怪談の主人公であるお岩さまに関する考察、何がお岩さまを強力な怨霊としたのか、その背負ってる怨念の対象は何なのかといったことを考えるのがテーマ。
著者得意の歌舞伎の筋書きをたどって、丁寧に四谷怪談の解説がなされていきます。
文化文政の時期の御家人は、非常に苦しい生活を強いられていて、そこの女性たちには(現実には苦しい家計を切り盛りしたといわれる)お岩さまが信仰の対象になったとか、そういう時代背景は、言われてみなけりゃ確かにわかりません。
「お岩さまの霊力の裏には困窮する御家人の内儀たちの怨嗟の声がある」ってことだそうです。
そして、お岩さまについては、ただただ単発にこの怪談のストーリーの登場人物ってんぢゃなくて、「日本におけるあらゆる怨霊、妖怪の伝統を一気に引き受けたような存在」「日本の歴史すべてから材料を得たサイボーグ」「極言すれば一種の装置であり、個人的感情を超越した存在」だってことを解き明かしてくれてます。
ふつうだったら、自分が亡き後に後妻になった女あたりにたたりそうなところを、ダイレクトに男を攻撃したりするとこが、それまでの日本の幽霊にはなかったところ、ってのも言われてみれば、ハタと目からうろこが落ちる。
ちなみに、幽霊ってのは、ボヤっとした存在(不在?)で、気の迷いのせいみたいなとこもあるけど、お岩さまは、喉笛にかみつくとか、物理的に攻撃をすることのできる存在・怪物ってことで、幽霊とは一線を画してるっつーか、違う存在だってことも解説されてる。
まあ、怪談を題材にして、書きようによっては、暗くて救いがなくなるんだけど、そこんとこらへんを、「子年の人間が怨霊になるたびに鼠が総動員されるとすれば、鼠だって忙しくてやりきれないでしょう」ってユーモアはさんだりとか、論陣を張ってる合間に「まだ話は終りではありません」とか一文を入れて呼吸を整えたりとか、そういう書き方がされてるんで、読んでて楽しい一冊ではあります。
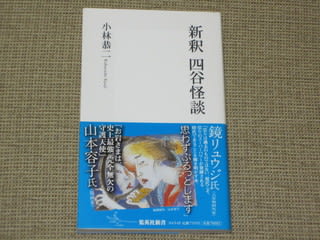
『悪への招待状』『心中への招待状』に次ぐ、小林恭二の新書。
四谷怪談の主人公であるお岩さまに関する考察、何がお岩さまを強力な怨霊としたのか、その背負ってる怨念の対象は何なのかといったことを考えるのがテーマ。
著者得意の歌舞伎の筋書きをたどって、丁寧に四谷怪談の解説がなされていきます。
文化文政の時期の御家人は、非常に苦しい生活を強いられていて、そこの女性たちには(現実には苦しい家計を切り盛りしたといわれる)お岩さまが信仰の対象になったとか、そういう時代背景は、言われてみなけりゃ確かにわかりません。
「お岩さまの霊力の裏には困窮する御家人の内儀たちの怨嗟の声がある」ってことだそうです。
そして、お岩さまについては、ただただ単発にこの怪談のストーリーの登場人物ってんぢゃなくて、「日本におけるあらゆる怨霊、妖怪の伝統を一気に引き受けたような存在」「日本の歴史すべてから材料を得たサイボーグ」「極言すれば一種の装置であり、個人的感情を超越した存在」だってことを解き明かしてくれてます。
ふつうだったら、自分が亡き後に後妻になった女あたりにたたりそうなところを、ダイレクトに男を攻撃したりするとこが、それまでの日本の幽霊にはなかったところ、ってのも言われてみれば、ハタと目からうろこが落ちる。
ちなみに、幽霊ってのは、ボヤっとした存在(不在?)で、気の迷いのせいみたいなとこもあるけど、お岩さまは、喉笛にかみつくとか、物理的に攻撃をすることのできる存在・怪物ってことで、幽霊とは一線を画してるっつーか、違う存在だってことも解説されてる。
まあ、怪談を題材にして、書きようによっては、暗くて救いがなくなるんだけど、そこんとこらへんを、「子年の人間が怨霊になるたびに鼠が総動員されるとすれば、鼠だって忙しくてやりきれないでしょう」ってユーモアはさんだりとか、論陣を張ってる合間に「まだ話は終りではありません」とか一文を入れて呼吸を整えたりとか、そういう書き方がされてるんで、読んでて楽しい一冊ではあります。
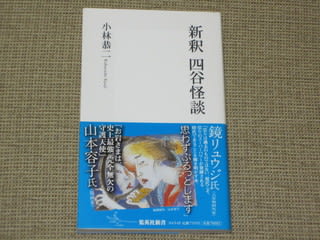
小林恭二 1999年 集英社新書
副題は「幕末・黙阿弥歌舞伎への愉しみ」
こないだの「心中への招待状」と順番は前後しちゃったけど、ここへリストアップするのもあとわずかになった、私のフェイバリットの作家・小林恭二の、新書。
著者の新書ったら、「俳句という遊び」とか「短歌パラダイス」とか、大傑作ばかりだったんで、書店で見かけた瞬間、すぐ手にとったんだけど、本書は俳句・短歌とはちょっと違ったね。
「カブキの日」のすぐあとだったし、カバー折り返しにいわく“著者入魂の新しい歌舞伎論”ってあるんだが、今回ひととおり読み返してみたら、最後あとがきに「自分なりの江戸像をつくってみたかった」と書いてあって、江戸論ですね、テーマは、たぶん。
水先案内人の役としてとりあげられてるのは、幕末に黙阿弥が書いた(黙阿弥って幕末のひと(っていうか明治まで生きた)って、私は知らなかったんだけど)歌舞伎の「三人吉三」で、その物語進行に沿って、いろんなことが書かれてます。
タイトルにある“悪”が刺激的なんだけど、
>黙阿弥が描きたかった悪は、個人の区々たる悪ではないのです。巨大な運命に導かれた抗しがたい悪なのです
なんて言い方で、さらにその背景にある、風雲急を告げてる幕末という時代の、価値観の深刻な紊乱を説くことがテーマです。
例の「因果の闇」についても、わかりやすく示していて、武家のもつような忠義なんかを中心とした倫理が根本から消滅して、私的な盟友関係とかのほうが重要になってくるし、倫理的に混乱が生じてんだけど、だからって神仏に救いを求めるほど、江戸人の精神構造は前近代的ではないっていいます。
>因果の闇という思想にこそ、幕末という時代の大特徴があり、ひいては明治維新という未曽有の革命を、ほとんど無血で行った下地になっているように思える
まで大きいこといわれると、ただ単に幕末にヒットした芝居の解説ではなくなりますね、たしかに。

副題は「幕末・黙阿弥歌舞伎への愉しみ」
こないだの「心中への招待状」と順番は前後しちゃったけど、ここへリストアップするのもあとわずかになった、私のフェイバリットの作家・小林恭二の、新書。
著者の新書ったら、「俳句という遊び」とか「短歌パラダイス」とか、大傑作ばかりだったんで、書店で見かけた瞬間、すぐ手にとったんだけど、本書は俳句・短歌とはちょっと違ったね。
「カブキの日」のすぐあとだったし、カバー折り返しにいわく“著者入魂の新しい歌舞伎論”ってあるんだが、今回ひととおり読み返してみたら、最後あとがきに「自分なりの江戸像をつくってみたかった」と書いてあって、江戸論ですね、テーマは、たぶん。
水先案内人の役としてとりあげられてるのは、幕末に黙阿弥が書いた(黙阿弥って幕末のひと(っていうか明治まで生きた)って、私は知らなかったんだけど)歌舞伎の「三人吉三」で、その物語進行に沿って、いろんなことが書かれてます。
タイトルにある“悪”が刺激的なんだけど、
>黙阿弥が描きたかった悪は、個人の区々たる悪ではないのです。巨大な運命に導かれた抗しがたい悪なのです
なんて言い方で、さらにその背景にある、風雲急を告げてる幕末という時代の、価値観の深刻な紊乱を説くことがテーマです。
例の「因果の闇」についても、わかりやすく示していて、武家のもつような忠義なんかを中心とした倫理が根本から消滅して、私的な盟友関係とかのほうが重要になってくるし、倫理的に混乱が生じてんだけど、だからって神仏に救いを求めるほど、江戸人の精神構造は前近代的ではないっていいます。
>因果の闇という思想にこそ、幕末という時代の大特徴があり、ひいては明治維新という未曽有の革命を、ほとんど無血で行った下地になっているように思える
まで大きいこといわれると、ただ単に幕末にヒットした芝居の解説ではなくなりますね、たしかに。

小林恭二 2005年 文春新書
きのうのつづき。『宇田川心中』のすぐあとに出た新書。
サブタイトルは「華麗なる恋愛死の世界」。
自分でも心中もの書いた作家なんで、もちろん自殺系サイトへの勧誘なんかぢゃなくて、「原心中」とは何かがテーマ。
そこらへんにゴロゴロ心中があふれてきたせいで見えにくくなっちゃった、心中の本質とは何かの考察。
それを探るために「曽根崎心中」を読み説いている。日本文学というか文化史上においても、最重要ともいえる作品だと。
もっとも私は、曽根崎心中を観たことない。文楽も歌舞伎も知らないし、本も読んだことない。
だから、著者の気合いの入った解説は、ハァそうですかって素直に読むしかないんだけど。
そもそも、江戸時代から現代にいたるまで、近松の原作どおり上演されてる例のほうが少ないってことも、え?そうなの?ってホントは驚くべきとこなんだろうが、私にはピンとこない。
ほかにも、たとえば、悪役の九平次について、著者は“名作の癌”と断罪してるんだが。
「曽根崎心中」は現実の心中事件から十日やそこらで書かれて、即舞台にかけられ心中の本質を提示するという、天才の仕事なんだけど、その代わりに「ドラマトゥルギーは決定的にスポイルされた」という著者の見解には、もっと目からうろこが落ちなきゃいけないはず、予備知識があったらね。
で、曽根崎心中に見られる、本来の心中とは何かってのは、かなり明快に示されている。
目前の障害に打ちひしがれてするもんぢゃなく、熟慮の結果なされるもの。
人生に窮して消極的に死ぬんぢゃなくて、死後の名声のために死ぬもの。
能動的に死を選んで、死の苦しみを積極的に引き受ける気概のあるもの。(薬や入水ぢゃなく、刃物使って雄雄しく死ねって。)
「恋する二人の究極の約束」が心中であって、「敗者たちの複数自殺」は違うよ、と。
そうやって書きならべてみると、過激だなあ。社会批評や心理分析ぢゃなくて、あくまで文芸評論なんだけど。
そうそう、私は読んだことないけど、近松ってのは名文らしい。
でも、名フレーズの間に気の抜けたようなフレーズがはさまってて、正岡子規あたりに批判されたこともあるそうだけど。
そこんとこを、
>これは作詞をした人ならすぐにわかると思いますけど、呼吸を整えているんです。
と解説してくれてるのは、妙に納得できるし、文学の解説らしいとこではある。
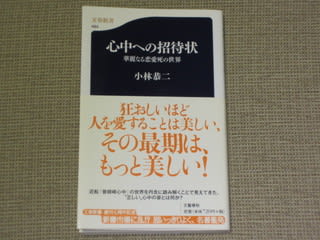
きのうのつづき。『宇田川心中』のすぐあとに出た新書。
サブタイトルは「華麗なる恋愛死の世界」。
自分でも心中もの書いた作家なんで、もちろん自殺系サイトへの勧誘なんかぢゃなくて、「原心中」とは何かがテーマ。
そこらへんにゴロゴロ心中があふれてきたせいで見えにくくなっちゃった、心中の本質とは何かの考察。
それを探るために「曽根崎心中」を読み説いている。日本文学というか文化史上においても、最重要ともいえる作品だと。
もっとも私は、曽根崎心中を観たことない。文楽も歌舞伎も知らないし、本も読んだことない。
だから、著者の気合いの入った解説は、ハァそうですかって素直に読むしかないんだけど。
そもそも、江戸時代から現代にいたるまで、近松の原作どおり上演されてる例のほうが少ないってことも、え?そうなの?ってホントは驚くべきとこなんだろうが、私にはピンとこない。
ほかにも、たとえば、悪役の九平次について、著者は“名作の癌”と断罪してるんだが。
「曽根崎心中」は現実の心中事件から十日やそこらで書かれて、即舞台にかけられ心中の本質を提示するという、天才の仕事なんだけど、その代わりに「ドラマトゥルギーは決定的にスポイルされた」という著者の見解には、もっと目からうろこが落ちなきゃいけないはず、予備知識があったらね。
で、曽根崎心中に見られる、本来の心中とは何かってのは、かなり明快に示されている。
目前の障害に打ちひしがれてするもんぢゃなく、熟慮の結果なされるもの。
人生に窮して消極的に死ぬんぢゃなくて、死後の名声のために死ぬもの。
能動的に死を選んで、死の苦しみを積極的に引き受ける気概のあるもの。(薬や入水ぢゃなく、刃物使って雄雄しく死ねって。)
「恋する二人の究極の約束」が心中であって、「敗者たちの複数自殺」は違うよ、と。
そうやって書きならべてみると、過激だなあ。社会批評や心理分析ぢゃなくて、あくまで文芸評論なんだけど。
そうそう、私は読んだことないけど、近松ってのは名文らしい。
でも、名フレーズの間に気の抜けたようなフレーズがはさまってて、正岡子規あたりに批判されたこともあるそうだけど。
そこんとこを、
>これは作詞をした人ならすぐにわかると思いますけど、呼吸を整えているんです。
と解説してくれてるのは、妙に納得できるし、文学の解説らしいとこではある。
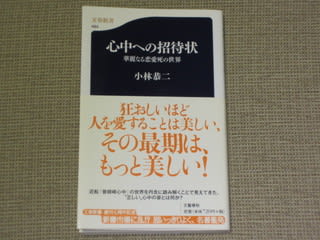
小林恭二 2004年 中央公論新社
(小林恭二のリストアップもあと少しのところだなあ。)
長編小説っていうか、戯曲に近い感じの物語。
宇田川は、舞台の地名。いまの渋谷のど真ん中。
時代は今から150年前の安政年間。
当時の渋谷は、江戸からみたら外れに位置し、文字どおり谷のある地形で、谷の底には宇田川が流れてた。
そのへんで出会った、小間物問屋の娘で渋谷小町と呼ばれる「はつ」と、僧の「昭円」の恋物語。
昭円がつとめる道玄寺は、もちろん道玄坂にある。
道玄坂の名前の由来は、鎌倉時代の元は武士、山賊をはたらいたという大和田道元なる者に由来する。
で、そのころからの因果がめぐりめぐって、はつと昭円の運命にまで係わってくる。
因果の闇は、近松だか黙阿弥だか忘れたけど、そのへんの基本だからねえ。
どんな話か今回ひさしぶりに読み返すまですっかり忘れてたんだけど、いやーおもしろい。
ハードカバー440ページくらいあるんだけど、読み出したらアッという間だった。
全編セリフまわしでサクサクと物語が進んでくからかね。
心中が主題だからもちろん悲劇なんだけど、最終章があるのが救いになってる。
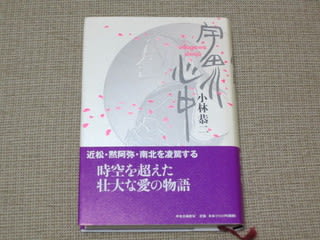
(小林恭二のリストアップもあと少しのところだなあ。)
長編小説っていうか、戯曲に近い感じの物語。
宇田川は、舞台の地名。いまの渋谷のど真ん中。
時代は今から150年前の安政年間。
当時の渋谷は、江戸からみたら外れに位置し、文字どおり谷のある地形で、谷の底には宇田川が流れてた。
そのへんで出会った、小間物問屋の娘で渋谷小町と呼ばれる「はつ」と、僧の「昭円」の恋物語。
昭円がつとめる道玄寺は、もちろん道玄坂にある。
道玄坂の名前の由来は、鎌倉時代の元は武士、山賊をはたらいたという大和田道元なる者に由来する。
で、そのころからの因果がめぐりめぐって、はつと昭円の運命にまで係わってくる。
因果の闇は、近松だか黙阿弥だか忘れたけど、そのへんの基本だからねえ。
どんな話か今回ひさしぶりに読み返すまですっかり忘れてたんだけど、いやーおもしろい。
ハードカバー440ページくらいあるんだけど、読み出したらアッという間だった。
全編セリフまわしでサクサクと物語が進んでくからかね。
心中が主題だからもちろん悲劇なんだけど、最終章があるのが救いになってる。