町山智浩 2019年10月 集英社文庫版
こないだ、ようやくマイケル・ムーアの『ボウリング・フォー・コロンバイン』をCSで観た、ついでに『華氏119』って新しめのも観た。
町山さんの映画についての本でも読もうかと思い、最近文庫になったという本書を買ってみた、単行本は2016年だそうです。
ドナルド・トランプのやることは、1992年の『ボブ★ロバーツ』って映画にそっくりで、でもその『ボブ★ロバーツ』のもとには1957年の『群衆の中の一つの顔』って映画があるって導入から、
>アメリカ映画では昔から、(略)差別や不正と戦う姿を通して自由、平等、進歩、ヒューマニズムが謳歌されてきた。
>だが、それはいわば「よそゆき」の顔。その陰には、差別的で狂暴で愚かなアメリカの素顔を暴いた映画もあった。(p.13「はじめに」)
という映画史の講義をしてくれる本。
知らない映画ばっかりだけどね、観たことあるのは『バック・トゥ・ザ・フューチャー』と『フォレスト・ガンプ』くらい。
でも、この2つにしても、60年代はなかったことにしたいとか、60年代のうちでも反戦運動とか公民権運動を肯定しないとか、そういう政治的なもんだと言われると、けっこう驚かされる。
個人的には、近頃観たなかではお気に入りの『ドリーム』のあとに、『デトロイト』とか『ゲット・アウト』とかをたまたま観たりしたもんで、うーん、映画の世界では人種差別の問題を振り返るのが近年のテーマになってんのかな、って漠然とした印象を持ってたんだが。
アカデミー賞なんかでも、なんかっつーと人種のこと問題にしてるみたいだし。
あと、本書には、
>クエンティン・タランティーノは自作『ジャンゴ 繋がれざる者』のインタビューで、アメリカ映画が今までほとんど奴隷制度を描いてこなかった事実について「奴隷制度はアメリカの汚点だからだ。どの国にも触れたくない歴史の恥部はある」と答えた。「でも、そこにこそ、最もエキサイティングな物語の可能性が眠っている」(p.51)
なんて紹介されてるところもあり、そーかー闇歴史に直面する作品をつくろうとするのがもしかしてトレンドのひとつだったりするのかもー、なんて思ったりもしたけど。
だってねえ、そういうのもあったりしないと、中国輸出向けのドッカンドッカンSFX炸裂させるアクションばっかりになっちゃうんでしょ、って気もするし。
あと、教わって、とても興味もったのは、「アメリカ人の「普通の男」信仰」(p.214)ってやつ、それが度重ねて映画のテーマになってたりする、昔もいまも、Common Man。
「普通の人間」を政治的に利用して英雄にしてって、民衆はそれにのっかって熱狂的に支持してく、って展開。
あまり、上品な出身であったり、物を知ってたり頭がよかったりする必要はない、でも単純な言葉に庶民たちはよくぞ言ったとついていく、ってタイプ。
あからさまに政治的主張をうたうより、一見はサクセスストーリーのようにみえるから怖いんだけど、そのウラには必ずそれ使って支配力を増そうとする存在もいると。
そうそう、なんかっつーと、資本主義国家では自由ってものが称えられるようにみえるんだけど、なんでもかんでも自由万歳ってわけぢゃないのは、
>マッカーシーは「共産主義から自由を守るんだ」と言いながら、アメリカを共産主義と同じような、思想の自由のない監視社会にしてしまった。(p.243)
みたいなことあるからで、意外と多様性への寛容ないからね、あの国は。80年代くらいからか、リベラルだ、って言われちゃうと負け、みたいな雰囲気できてきたみたいだし。
それはそうと、私がいちばん印象に残った映画の技術(?)の用語が、「マジカル・ニグロ」、これにはおどろいた。
>マジカル・ニグロとは2001年に黒人監督スパイク・リーが言い出した言葉で、ハリウッド映画において、白人の都合のいいように作られた黒人キャラクターをいう。白人の主人公は劇中のひとりの黒人と仲良くすることで、人種にこだわらない善人に見える。その黒人は主人公の窮地を救い、多くの場合、死んでいく。
>(略)なぜ主人公と友情を結び、彼のために尽くすのかといえば、そのためだけに作られたキャラクターだからだ。つまりマジカル・ニグロとはストーリーテリングのための奴隷である。(p.326-327)
って解説されると、ええっ!?と思う、知らんかった。
…って、もしかして、現在の新しいスター・ウォーズシリーズのあのひとなんかもそう? とか思っちゃったりするんである。
章立ては以下のとおり。各章のタイトルがわかりやすくていい。
第1章 KKKを蘇らせた「史上最悪の名画」 『國民の創生』
第2章 先住民の視点を描いた知られざるサイレント大作 『滅び行く民族』
第3章 ディズニー・アニメが東京大空襲を招いた? 『空軍力による勝利』
第4章 封印されたジョン・ヒューストンのPTSD映画 『光あれ』
第5章 スプラッシュ・マウンテンの「原作」は、禁じられたディズニー映画 『クーンスキン』『南部の唄』
第6章 ブラックフェイスはなぜタブーなのか 『バンブーズルト』『ディキシー』
第7章 黒人教会爆破事件から始まった大行進 『4リトル・ガールズ』
第8章 石油ビジネスとラジオ伝道師 『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』『エルマー・カントリー 魅せられた男』
第9章 金はやるから、これを絶対に映画化しないでくれ! 『何がサミーを走らせるのか?』
第10章 ポピュリズムの作り方 『群衆』
第11章 リバタリアンたちは今日も「アイン・ランド」を読む 『摩天楼』
第12章 「普通の男(コモン・マン)」から生まれるファシズム 『群衆の中の一つの顔』
第13章 マッカーシズムのパラノイア 『影なき狙撃者』
第14章 アメリカの王になろうとした男ヒューイ・ロング 『オール・ザ・キングスメン』
第15章 インディの帝王が命懸けで撮った「最も危険な映画」
第16章 なぜ60年代をアメリカの歴史から抹殺したのか 『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『フォレスト・ガンプ』
堀井憲一郎 二〇一九年 本の雑誌社
私の好きなライター、ホリイ氏のあたらしい本が出たと知ったので、さっそく読んでみた。
サブタイトルは、「ホリイのゆるーく調査」、なんでも『本の雑誌』という雑誌にそういうタイトルの連載をもっているそうで、そこの調査記事から50編がまとめられたのが本書。
「ゆるーく」ってのは、帯にあるように「役に立たないこと」が対象だし、ガチガチに統計固めようとしてないで手近にあったもの調べるだけで済ましてることを言ってる。
いーねー、私そーゆーの好きなんです。
オープニングは、書名のとおり、文庫本を積んでって何冊までいけるかの調査、ゆるーくなんで同じ本を積んだり、厚さそろえた材料つかったりはしません、そこにあるもので適当に。
でも実験場の編集部には出版社べつに文庫がおいてあるんで、岩波、講談社、集英社、光文社、新潮に分けて記録をとってたりします、最後に「各社連合」って混ぜたのやるとこがおもしろい。
今回の結論は、新潮文庫は積み上げに強い、ってことになったんだけど、ゆるーくなんで繰り返しの検証とかするはずもないから、それが不変の真理かどうかはわからない、どうでもいいからいいんだけど。
しかし、ふと思ったんだが、前に著者の書いたもので、「エスカレーターとエレベーターのどちらがはやい」みたいなタイトルはダメだって話があったとおもうんだけど、その伝でいくなら「文庫は40冊を超えて積むな」みたいなタイトルにしないのかな、って気がした。
ほかにも、しょうもない計測がいろいろあって、文庫の高さって微妙に違うなとは私も思ってたんだけど、実際計ってみて講談社は148.3mmなのに一番高いハヤカワは157.4mmとか。
文庫本のカバーの長さをはかったついでに、背幅をはかって、川端康成の「掌の小説」は背幅19mmで本体価格840円だから背1mmあたり44.2円で、「名人」の同57.1円よりオトクとか。
本屋大賞の歴代の受賞作をならべて、重さはかって、「鹿の王」の上巻がいちばん重くて560グラム、100グラムあたり285.7円だとか、そこ1ミリあたりとか100グラムあたりで計算しなくていいでしょってとこを計算して並べてるのがおもしろい。
本の外見ばかりで、読んでないのかっていうと、もちろんそんなことはなく。
ロシアの小説の一段落って長いよなってことで、「カラマーゾフの兄弟」の第一部の第一編は62ページあるけど25段落なんで、1ページあたりのおよその段落数は0.4段落という調査結果をえて、それを「罪と罰」とか「戦争と平和」とか、ぢゃあフランスの「赤と黒」はどうか、イギリスの「ジェーン・エア」はどうなんだと比べたりしてます。
明治の小説は漢字が多いよなってことで、夏目漱石の「吾輩は猫である」の冒頭から約5ページ、二千文字くらいまでを採取して、2073文字中に漢字は779文字だから、漢字率は3割7分5厘という結果をえて、それを漱石が1867年生まれだから、その50年後の1917年生まれの作家と、100年後の1967年生まれの作家をとりあげて比較してます。結論として、やっぱ漢字率は落ちるんですねえ。
それだって文章の外見のことだけじゃんっていうひともいるかもしれないが、ときどき出版界の現状にも切り込んでる。
新潮文庫の解説目録の2000年と2015年のを比べて、海外の作家がどんなに切られているか調査、アガサ・クリスティの10冊全部とか、パスカルの「パンセ」、ロマン・ロランの「ジャン・クリストフ」なんかでも、売れないものはバッサリ切られて無くなっていると。
べつの章では、新潮文庫のフランソワーズ・サガンは1979年に16冊あったのに、2000年には9冊に減って、読者層がついていかなくなったんだろうな、とか。
若いひとは本を読まないからねえって話になると、「ぼくは本が読めないのです」という大学生について、
>病気だね。病気だ。受け身でぼんやりしている私を楽しませてくれないものはつまんないぞ病だね。(p.86)
とバッサリ。
そうそう、読者だけぢゃなくて、最近の文庫の解説はあらすじの紹介だけってのが多いことについて、
>文庫の編集者に、これでいいの、と聞いたところ「だめです、とは言えないんです」と苦しげに答えてくれていた。そりゃだめですわね。(p.39)
と厳しい。
新潮文庫の「細雪」上中下3巻を読んだところ、本文が全1101ページなのに「注」が861個もあると。なかには「え、なんでこれに注つける?」って思うものもあって、
>なんか注釈者が他社の物語として読んでるのがわかってきますね。(略)この小説の登場人物たちは、自分たちと違って金に困らない身分の人であるという解説を繰り返していて(略)(p.211)
として、これは注ぢゃなくて副音声解説だろと指摘している、1.28ページことに1注つけるかあ、と。
どうでもいいけど、私が興味ひかれたのは、本を買うだけ買って読まないでいることについて、
>本は腐ります。
>物理的にではなく、気分的に腐っていきます。(略)
>読みたいとおもって買った本は、ひとつきも手に触れないと、なんか腐っていきますね。本自身がすねてきて、「もう、読んでくれなくてもいいよ」という気配を出し始める。(略)(p.32)
って表現をして、そのあとの別の章で「未読の悪魔はどれくらいで取り憑くか」と題して、自分の机にすぐ読むつもりで積んであるけど読んでない本を分析してる。
見えない何かが取り憑いて、本を開くことができなくなる、日にちが経てばたつほどそれは強くなって、
>21日過ぎたら危険ゾーンに突入、30日越えたらほぼアウト、という結論をとりあえず出しておきます。(p.49)
っていうんだけど、日数は個人差あるだろうが、私も気をつけなきゃいけない、って思うんだけど、逆に、誰でもそういうもんなんだって安心する面もあったりして。
穂村弘 2016年 KADOKAWA
こないだ、このシリーズの「双子でも片方はなく夜もある篇」を読んだんだけど、それより前に刊行されてたこの第3弾を読んでなかったんで、先月買って、さっそく読んでみた。
「ダ・ヴィンチ」の連載(実を言うと私は読んだことないんだけどね)の第61回から90回までをまとめたものだとのこと、2013年5月から2015年10月だって。
毎回お題が決められてる募集テーマ投稿と、いつでも募集中の自由詠があって、テーマ決まってるほうが人それぞれでとりあげる角度のちがいとかあるんで私にはおもしろい。
それにしても、読んでて思ったんだけど、これやっぱ穂村さんの解説があるからいいんではないかと。
ひとつの作品につき、2,3行だけの短いものだけど穂村さんの評がついてて、もしそれ無くて歌だけがズラっと並んでたら、たぶん私は飽きる、っていうか読んでて意味わかんないと思う。
「触感的なオノマトペがいい」とか「サ行音の連鎖が意識されています」とかって音のテクニックのこともあれば。
「どきっとしますね」とか「妙なリアリティがある」とか「突き刺さる説得力」とかって斬新な表現への共感のようなもののこともある。
そんななかで私がひかれるのは、
>世界には見える法則と見えない法則があるみたいですね。自然科学が前者の担当で、詩歌は後者の担当。(p.205)
みたいに、さらっと語られる短歌論のようなもの。
ちなみに、これは「信号がかつてないほど連続の青でほどけたままの靴ひも」という歌、靴ひも直したいときに限って止まるタイミングがないってことを切り取ったことへの評。うーむ。
特に短歌のよしあしがわかるわけぢゃない私が、今回一読したなかで気に入った歌のいくつかを以下に引用。
(価値観が確立されてないので、こういうの何が自分のどこかにひっかかるのかは体調次第だったりする。)
「ウィンカー出さずにキミが曲がるたび世界に二人だけの気がした」(p.114自由題)
「七月に君が眼鏡をかけて以後好きです以前は覚えてません」(p.119眼鏡)
「鳴きまねににゃーと応えてくれたけど私は猫語でなんて言ったの」(p.194猫)
丸谷才一 1976年 文春文庫版
これはちょっと前にネットで何冊かまとめて買った古本のうちのひとつ。
後年編まれたエッセイ傑作選の文庫『腹を抱へる』に何篇かが収録されてたんだが、それによると、
>「女性対男性」は、「週刊女性」一九六五年十一月から一九七〇年三月まで、足掛け六年(計二百六回)にわたり連載された。そのうち、五十篇が、一九七〇年「女性対男性 会話のおしゃれ読本」として文藝春秋より刊行され、ベストセラーとなった。いわば、丸谷さんの「雑文」の原点である。
ということらしい、そういわれちゃうと読んでないのはあるまじきことという気がしてきたので手に入れた。
それにしても、芥川賞とったのが1968年だから、そのころだし古い話だ。本文中にも、ハガキが5円から7円に値上げになった、なんて話題が出てくるけど。
副題の「会話のおしゃれ読本」というのにあるとおり、「ぼく」と「女友達」の会話という形をとっている。
だいたい昔も今も変わらないことのように、想像どおり女性が自由奔放な話し方をして男性がモノゴトに理屈をつけて賢くみられようとするみたいなやりとりが多い。
>一体、女性の話というのは、こんなふうに、時間的・空間的制約を無視して思いがけない方角へゆくことがしょっちゅうなのである。(p.211)
というふうに感じられる女性に対して、
>(略)ぼくはもうすこし説得力のある論理を展開しなければならないと考えて(略)(p.140)
みたいなスタンスで対応するパターンが基本のようだけど、それでも、
>(略)しかしぼくという男は、女性に対してはなんと親切な男であろうか、頭をしぼって彼女のリクツに都合のいいような例をいっしょうけんめい探していたのである。(p.215)
というように、女友達の話に同調してあげようとするやさしさがある「ぼく」なのである。
女友達の性格の設定も、そんなミーハーなだけというわけではなく、
>(略)女友達は食べ物の話になるとコーフンする癖があるということを(略)(p.288)
ってのは、まあ普通だけれど、意外なことに、
>(略)わざとむずかしいことばを使った。彼女は、むずかしいことばを使われると、何となくコーフンするくせがあるのだ。(p.205)
なんていう一面も持ってたりすることになってる。
男のほうもやさしいだけぢゃなく、
>一体、男には、女の人に悪趣味な話を聞かせて喜ぶという傾向があるものです。(p.130)
ということを自ら承知しつつ、失礼のないように、適度な距離感をもって、いろんな話題を提供している。
それぞれの章にはタイトルはついてなくて、最初の一文にその回の内容が紹介されている形式になっている。なんのことだか読んでみたくなるひとつの技法といえるでしょう。
目次を全部並べるのは量おおいからやめとくけど、いくつか例をあげると以下のとおり。
・マッチの話からシャネルの5番の話になりました
・縁日の話からノーベル賞の話になりました
・千円札の話から華族の話になりました
・テレビ選挙の話から豚肉の話になりました
・欲求不満の話から飛行機の話になりました
・将棋の話からてんぷらの話になりました
京極夏彦 2006年 講談社文庫版
ひさしぶりに、自分はまだ読んだことのない京極堂シリーズを読むことにしてみた。
『塗仏の宴』だっけ、あれ読んで、もういいか、みたいに思ったのが、いま調べたら2010年のことだから、それ以来か、つづきの長編読むのは。
タイトル、「おんもらき」は例によって妖怪のたぐいで、鳥のカッコ、鶴に似てて色が真っ黒で目がランランと光ってるという、知らないな、聞いたこともない。
語り部の「私」ってのが、気がつくと三人いることになってる。
ひとりは、毎度おなじみの小説家の関口巽、京極堂のおなかまのひとり、京極堂は友人ではなく知人だとか意地悪言うけど。
このひとは、例によって、かかわりたくもないのに怪事件に巻き込まれて、精神がこわれるような目になってしまう。
いまひとりは、白樺湖畔の大きな屋敷の主の由良昂允伯爵、このひとが本書の中心人物なんでしょう。
昭和28年の話だから、もう伯爵とかって制度はないんだけど、代々家を継ぐ人は伯爵位を継いだんで、それにならって伯爵と呼ばれている。
トシは50歳で、死んだ両親の財産がいっぱいあるんで、経済的にはなんも苦労をしていないが、生まれたときからその屋敷の外に出たことない、家のなかにある本で自らすべてを学んだという普通ぢゃないひと。
家柄はもともと儒学かなんかの家系らしいが、伯爵の父は博物学者で、邸内にはつくらせた鳥の剥製が並んでるから鳥の城とまで呼ばれてる、出たね鳥、どっかに陰摩羅鬼がいるとみた。
で、事件は、由良家花嫁連続殺人である。連続ったって、最初は23年前の昭和5年のことだが、とにかく23年前、19年前、15年前、8年前の四度にわたって、伯爵が婚礼をあげると、その翌朝その屋敷内で花嫁が死んでいるのが見つかった。
関口に言わせると、「動機もなく、理由もなく意味もなく、トリックもなく方法もなく、ただ、伯爵を傷付けるためだけに繰り返し行われる殺人(p.712)」。
それで今般五度目の婚礼があるんだが、殺人をふせぐべく呼ばれたのが、旧華族の家系の探偵、榎木津礼二郎だ、かーっこいい。
ところが榎木津探偵は、信州まで出かけてったところで諏訪あたりで高熱を出し、目が見えなくなってしまったという、そこで頼まれて関口がいやいや同行することになったという展開。
視力を失ったというのに、ひとの記憶がみえるという特殊能力は活きている榎木津探偵は、関係者一同が集まった場に初登場するなり、こう言った。
「おお! そこに人殺しが居る!」
カッコイイです、文庫で1200ページからあるのに、わずか95ページでもう解決してるぢゃないですか。
伯爵の親戚筋に、呪われた因縁を断ち切ってくれと言われた探偵は、
「探偵はただ真実を云い中てるためだけに居るのです! 捕まえるのは警察、裁くのは法律、呪いを解くのは拝み屋だ。序でに云うなら話を聞くのは下僕の仕事です」(p.388)
と言って、呪いを解くのは仕事ぢゃない、いったい自分に何を依頼したいんだと憤慨する、花嫁を守るんなら夫婦の部屋のなかにいさせろとか極めてまっとうな意見も言う。
さてさて、もうひとり「私」って語り部役をしてるのが、元刑事の伊庭というひと、出羽の事件で中禅寺とどうこうと書いてあるんで、そういや最近読んだ『今昔続百鬼―雲』に出てきてたなと思い出したが。
このひとは長野の出身で、過去の花嫁殺人事件の捜査もしているんだが未解決なのがもやもやしてる、それでひょんなことから今回五度目があると聞いて、京極堂のところに相談にくる。
「俺の肚の中にずっと棲んでる鬼魅の悪い鳥がな、古疵を突くんだ(p.906)」と言って、憑物落としの依頼者となるのはこのひと。
かくして、京極堂は、伊庭元刑事にいわせると「艦隊を全滅させた海軍指揮官のような不機嫌な顔をして(p.814)」長野まで出かけていくことになる。
現場に行く前から、京極堂は事件の真相を見通していたようで、
「伊庭さん、真相などと云うものは幾つも幾つもあるんですよ。謎を解明すると云うのは、要するに幾つもある真相の中から一番都合の良いものを選び取ると云うことなんです。(p.862)」
なんて言って、真相が明らかになるのは哀しいことになるとわかっていて乗り込んでいく。
それよりずっと前、伊庭から伯爵家の話を聞く前に、京極堂は自宅を訪ねてきた大学院生と議論してるときに、
「仮令全く同じ言説であっても、時と場合によっては全然別の解釈が出来るのだと云うことを忘れてはいけない。正しい正しくないと云うのは、その思想なり言説がどんな器に入っているかで変わってしまう、と云うことだ」(p.501)
なんて、おんなじような感じのことを言ってるとこがあって、そういうのはわりと印象に残った。
その大学院生との会話は、林羅山とか儒学のことで、過去に読んだ作品で、禅とか、真言立川流とキリスト教とか、御筥さまとか、いろんなもん相手にまわしてきたけど、今回は儒教を相手に憑物落としかいと期待させるものがあった。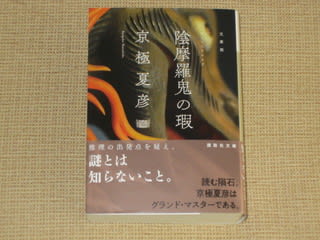
95















